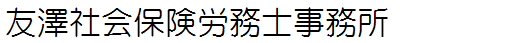| (1)本法はどのような趣旨・目的で設けられたのでしょうか |
| 近年、働き方の多様化が進展する中、個人が、それぞれのニーズに応じた |
| 働き方を柔軟に選択できる環境を整備することが重要となってきており、 |
| フリーランスという働き方もその選択肢の一つです。「自分の仕事のスタ |
| イルで働きたい」、「働く時間や場所を自由にしたい」といった理由から |
| フリーランスとして働くことを積極的に選択する方も多くいますが、育児 |
| や介護のほか、様々な事情によりフリーランスという働き方を選択する方 |
| もいます。 |
| こうした中、発注事業者と業務委託を受けるフリーランスの方の取引にお |
| いて、 |
| ・「一方的に発注が取り消された」 |
| ・「発注事業者からの報酬が支払期日までに支払われなかった」 |
| ・「発注事業者からハラスメントを受けた」 |
| などの取引上のトラブルが生じている実態があります。 |
| この背景には、一人の「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、 |
| 「組織」として業務委託を行う発注事業者との間には、交渉力やその前提と |
| なる情報収集力の格差が生じやすいことがあると考えられます。 |
| こうした状況を改善し、フリーランスの方が安定的に働くことができる環境 |
| を整備するため、令和5年5月12日に、この「特定受託事業者に係る取引 |
| の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が公 |
| 布され、令和6年11月1日に施行されることとなっています。 |
| 本法では、 |
| ①取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託を |
| した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止す |
| るとともに、 |
| ②就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護 |
| 等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けてい |
| ます。 |
| (5)契約上はフリーランスとして業務委託を受けていることと |
| なっていますが、働き方の実態は労働者である場合、本法は適 |
| 用れるのでしょうか。 |
| 形式的には雇用契約を締結せず、請負契約や準委任契約などの契約で仕事を |
| する場合であっても、労働関係法令の適用に当たっては、契約の形式や名称 |
| にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて、各法令における「労働者」 |
| に該当するかどうかが判断されることになります。 |
| 発注事業者との関係で、受注事業者が労働基準法等における「労働者」と認 |
| められる場合は、本法の「特定受託事業者」には該当しません。この場合、 |
| 当該発注事業者との関係では、労働基準法等の個別的労働関係法令(※)が |
| 適用され、本法は適用されません。 |
| なお、発注事業者との関係で、受注事業者が本法の「特定受託事業者」に該 |
| 当する者であっても、労働組合法(昭和24年法律第174号)における |
| 「労働者」と認められる場合があります。この場合、当該発注事業者との関 |
| 係では、本法が適用されるほか、団体交渉等について同法による保護を受け |
| ることができます。 |
| (※)労働契約法(平成19年法律第128号)、育児休業、介護休業等育 |
| 児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号) |
| 、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律( |
| 昭和47年法律第113号)等 |
| (9)業務委託の時点では、発注事業者が「従業員を使用」して |
| いませんでしたが、その後「従業員を使用」するようになった |
| 場合、当該業務委託について、発注事業者は「特定業務委託事 |
| 業者」としての本法上の義務を負うのでしょうか。 |
| 例えば、 |
| ・業務委託時点で、発注事業者が「従業員を使用」しておらず、「特定業務 |
| 委託事業者」に該当しない場合、 |
| ・業務委託の後で発注事業者が「従業員を使用」することとなり、「特定業 |
| 務委託事業者」としての要件を満たすようになった場合には、当該発注事業 |
| 者は「特定業務委託事業者」としての義務を負いません。 |
| なお、「従業員を使用」していない発注事業者であっても「業務委託事業者」 |
| として3条通知(本法第3条に基づき、明示すべき事項を、書面又は電磁的 |
| 方法により特定受託事業者に対し明示することをいう。以下同じ。)による |
| 明示を行う必要があります。 |
| (10)複数の事業を営んでいる受注事業者は、ある事業では従 |
| 業員を使用しているものの、その他の事業では従業員を使用 |
| していません。発注事業者が、当該受注事業者に対し、従業 |
| 員を使用していない事業について業務委託を行う場合には、 |
| 当該業務委託は本法の適用対象となるのでしょうか。 |
| 従業員を使用」しているか否かについては、個別の業務委託や事業に 関し |
| て従業員を使用しているか否かではなく、受注事業者が個人又は法人として |
| 従業員を使用しているか否かで判断されます。 |
| 上記の事例において、複数の事業を営んでいる受注事業者が、ある事業にお |
| いて従業員を使用している場合、受託する業務の属する事業における「従業 |
| 員」の使用の有無にかかわらず、当該受注事業者は「従業員を使用」してい |
| ると判断され、「特定受託事業者」には該当しません。したがって、発注事 |
| 業者が当該受注事業者に対して、従業員を使用していない事業に関する業務 |
| 委託をする場合であっても、当該業務委託は本法の適用対象とはなりません。 |