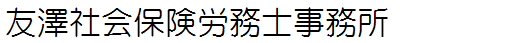 |
松山市余戸西3丁目12-25 |
| |
電話受付:089-989-0178 |
| 平日 9:00~17:30 | |
| HOME>>今月の特集>>2023>>12月 |
| 2023年12月の特集 |
| 育児・介護休業等に関する規定例17 |
| (令和4年4月1日、10 月1日施行対応版) |
| ※厚生労働省HPより |
| 第9章 所定労働時間の短縮措置等 |
|
(育児短時間勤務)
第 19 条
13歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯
条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。所定労働時
間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの
1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に
別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。
2本条第1項にかかわらず、日雇従業員及び1日の所定労働時間が6時間以下で
ある従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
3申出をしようとする者は1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短
縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則
として、短縮開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申出書(社内様式11
)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、
会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書(社内様式13)を交
付する。
その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第
2項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
4本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労
務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給
する。
5賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合
においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
6定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常
の勤務をしているものとみなす
|
|
《労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》
2本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間
勤務の申出は拒むことができる。
一 日雇従業員
二 1日の所定労働時間が6時間以下である従業員
三 労使協定によって除外された次の従業員
(ア)入社 1 年未満の従業員
(イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3~6 (略)
|
| 【ポイント】 |
| ①事業主は、3歳までの子を養育する労働者であって現に育児休業(出生時 |
| 育児休業含む)をしていないものに関して、1日の所定労働時間を原則とし |
| て6時間とする措置を含む所定労働時間の短縮措置を講じなければなりませ |
| ん(法第23条第1項及び則第74条第1項)。ただし。1日の所定労働時間が |
| 6時間以下の労働者(変形労働時間制の適用される労働者については、すべ |
| ての労働日における所定労働時間が6時間以下の労働者)は除きます(則第 |
| 72条)。また、勤続1年未満の労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働 |
| 者及び業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を |
| 講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者については、労使協定 |
| の締結により対象外とすることができます(法第23条第1項、則第73条)。 |
| ②また、以下の労働者の区分に応じて定める制度又は措置に準じて、必要な |
| いずれかの措置を講じることが事業主の努力義務となっています(法第24条 |
| 第1項)。1の「3歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子 |
| 」とすることで努力義務を満たすことができます。 |
| (1)1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないもの |
| 始業時刻変更等の措置(※) |
| (※)〔1〕フレックスタイム制、〔2〕始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ |
| 〔3〕保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与のうちいずれかの |
| 措置をいいます。 |
| (2)1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者 |
| 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置 |
| なお、1歳6か月までの育児休業ができる場合には、1歳を1歳6か月とし |
| て、1歳6か月以降の育児休業ができる場合には、1歳6か月を2歳として |
| 考える必要があります。 |
| (3)3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 |
| 育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短 |
| 縮措置又は始業時刻変更等の措置 |
| ③4の給与については、次のような規定も考えられます。(所定労働時間8 |
| 時間を2時間短縮して6時間とする場合) |
| ・本制度の適用を受ける間の給与については、給与規定に基づく基本給から |
| 25%を減額した額と諸手当の全額を支給する。 |
| ・本制度の適用を受ける間の給与については、給与規定に基づく基本給及び |
| ○○手当からその25%を減額した額と○○手当を除く諸手当の全額を支給す |
| る。 |
| ④5の賞与については、次のような規定も考えられます。 |
| ・賞与は、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合におい |
| ては、前項に基づき支給される給与を基礎として算定する。(※給与が勤務 |
| 時間比例で減額されている場合、賞与はその給与を基礎として通常の算定方 |
| 法で算定すれば勤務時間比例で減額されていることとなる場合が多い。) |
| ・賞与は、本制度の適用を理由に減額することはしない。(※成果に基づく |
| 賞与の場合、時間比例で減額する必要はない場合も考えられる。) |
| ⑤4~6については、育児休業に関する労働条件の取扱いと同様、様々な内 |
| 容が考えられます。 |
| ⑥《労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》については、就業規 |
| 則等に除外する旨を明記していたとしても、実際に労使協定を締結していな |
| い場合は、締結するまでは除外できないため、申出があれば当該従業員は対 |
| 象となります。 |
| 《労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》のほか、実際に所定労 |
| 働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、そ |
| の業務に従事する従業員がいる場合には、労使協定を締結することにより、 |
| 対象から除外することができます。 |
| 対象から除外される従業員について、事業主は、代替措置として、(1)育児休 |
| 業、(2)フレックスタイム制、(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、(4)保育 |
| 施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与、のうちのいずれかの措置を |
| 講じなければなりません(法第23条第2項、則第74条第2項)。 |
| お問い合わせ |
| (住所) |
| 〒790-0046 |
| 松山市余戸西3-12-25 |
| 友澤社会保険労務士事務所 |
| (電話/FAX) |
| 089-989-0178 |
| (営業時間) |
| 平日:9:00~17:30 |
| 休日:土曜日・日曜日・祭日 |
| 『メール』でのお問い合わせは、ここをクリックしてください! |



