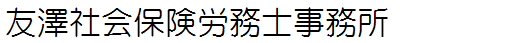 |
松山市余戸西3丁目12-25 |
| |
電話受付:089-989-0178 |
| 平日 9:00~17:30 | |
| HOME>>質問広場>>2024>>03 |
| 2024年03月のQ&A |
| 【Q】 |
| 第2種計画認定について教えてください。 |
| 【A】 |
| 原則として、定年後引き続き雇用される有期労働契約者(自社定年後の嘱託 |
| 社員等)についても、無期転換ルール※は適用されます。ただし、適切な雇 |
| 用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局の認定(第二種計画認定)を |
| 受けた場合には、無期転換ルールの特例として、その事業主の下で、定年後 |
| に引き続き雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。(専門的知 |
| 識等を有する有期雇用労働者に関する特別措置法) |
| 第2種認定計画の効力は、無期労働契約で定年を迎えた労働者を定年後に再 |
| 雇用する場合に及びます。(自社定年後の嘱託社員等) |
| 【注意】 有期労働契約で定年年齢を迎えた労働者や他社(特殊関係事業主 |
| 等除く)で定年を迎えた労働者は対象になりません。 |
| 対象となる労働者には、有期労働契約の締結・更新時に、無期転換ルールの |
| 特例が適用されていることを書面で明示しなければなりません。 |
| 用語解説【無期転換ルールとは】 |
| 同一の使用との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期労 |
| 働者(契約社員、アルバイト等)からの申込により、期間の定めのない労働 |
| 契約に転換されるルールのことです。有期労働契約者が使用者(企業)対し |
| て無期転換の申し込みをした場合、無期労働契約が成立します。(使用者は |
| 断ることができません。) |
| 【注意】無契約期間が6ヶ月以上(契約期間が1年未満の場合は、契約期間の |
| 半分)であれば、それ以前の期間は通算対象期間から除外される。 |
| (2)契約締結時の労働条件明示ルールの改正(2024年4月1日以降) |
| 無期転換申込権が発生する有期労働契約更新時の明示義務 |
| ■無期転換申込権を行使しない労働者にも明示が必要 |
| 同一の使用者との間で、通算5年を超えて有期労働契約が更新されたとき、 |
| 有期契約労働者には、本人の申し込みにより期間の定めのない労働契約に転 |
| 換できる権利(無期転換申込権)が発生する。有期契約労働者の雇用の安定 |
| を図る目的で、平成25年に導入された制度(労働契約法第18条、無期転 |
| 換ルール)だ。 |
| 2024年4月1日から、無期転換申込権が発生する労働者に対し、①無期転換 |
| を申込できる旨(無期転換の申込機会)と、②無期転換後の労働条件を書面 |
| で明示しなければならない。 |
| 加えて②に関しては、労働条件を決定するにあたって、他の通常の労働者( |
| 正社員等の無期フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項の説明に努める |
| ことも求められる。 |
| 労働者が無期転換申込権を行使せずに契約が満了し、有期労働契約を更新す |
| る場合は、契約更新時に改めて上記明示及び説明が必要だ。仮に権利を行使 |
| しないと表明している労働者であっても、明示を行う義務等に変わりはない。 |
| 但し、第二種計画認定を各都道府県労働局に申請し受理されているならば、 |
| 自社定年退職後の嘱託社員等との労働条件通知書に、「第二種計画認定が受 |
| 理されているため、無期転換申込権は発生しない。」と明記する。 |
| 用語解説【契約締結時の労働条件明示ルールの改正】 |
| ●労働条件明示等に関する改正事項 |
| 新ルールの対象となる労働契約 2024年4月1日以降締結した労働契約(有 |
| 期労働契約の更新を含む。) |
| 【改正される労働条件明示事項】 |
| すべての労働契約の締結時 |
| ●雇入れ直後の就業場所及び従事すべき業務内容に加え、就業場所及び業務 |
| の「変更の範囲」 |
| 有期労働契約の締結時(契約更新を含む)など |
| ●更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)がある場 |
| 合はその内容 |
| ※更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ説明する。 |
| 無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時 |
| ●無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会) |
| ●無期転換後の労働条件 |
| ※無期転換の労働条件決定にあたって、他の労働者(正社員等)との均衡を |
| 考慮した事項の説明に努める。 |
| (3)申請様式・記入例 |
| ■第二種計画認定申請書(厚生労働省 愛媛労働局リンク) |
| ■第二種計画認定記入例(厚生労働省 大阪労働局リンク) |
| ■第二種計画認定提出書類一覧 |
| 提出先 各都道府県労働局 |
| 申請書・添付書類は「正」「副」合計2部を提出してください。(写しは認定 |
| 通知書等の交付時に返却) |
| ①第二種計画認定・変更申請書 |
| ②申請書2でチェックした措置を実施することを明らかにするもの |
| 高年齢者雇用推進者の選任を確認する書類 |
| □高年齢雇用状況報告書(ハローワークに提出したもの) |
| □辞令・専任のお知らせ 等社内文章の写し |
| 上記以外の措置を実施する場合の確認資料 |
| □就業規則 □労働契約書のひな型 |
| □職業訓練計画書 □改善計画報告書 等 |
| ●事業主の署名または記名押印があり、実施する措置の内容が確認できる書類 |
| など |
| ③申請書3でチェックした高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明ら |
| かにするもの |
| 就業規則の下記該当部分 |
| □監督署へ届け出た際の受付印(就業規則の表紙、変更届等) |
| □定年制度と継続雇用制度の規定、継続雇用労働者に適用する規定等 |
| 10人未満の事業場で就業規則を作成していない場合 |
| □定年制度や継続雇用制度を社内周知していることが明らかとなる書類等、就 |
| 業規則に準じるもの |
| 【注意点】 |
| 高年齢雇用安定法による雇用確保措置を遵守していますか? |
| 法違反や就業規則と雇用実態に相違等がある場合は、指導を行い、訂正後に再 |
| 提出をお願いする場合があります。 |
| ④経過措置に基づく労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を利用す |
| る場合にチェックした場合 |
| □当該基準を定めた労使協定 |
| (高年法改正前の平成25年3月31日以前に締結したもの) |
| ⑤処分結果(認定・不認定通知書)の交付を郵送で希望する場合 |
| 申請事業場宛の返信用封筒 |
| □簡易書留 □配達証明 □レターパックプラス |
| (封筒の重さ+書類(副本)の重さ+認定書等の重さ(A4サイズ2枚程度)の |
| 切手代+簡易書留の場合(310円)・・・変更がないか郵便局で確認すること |
| 上記の合計切手を返信用封筒に貼ってください。 |
| ⑥認定された計画申請の場合 |
| □変更申請書及び添付書類(原本と写しの2部) |
| □既に認定された計画書及び認定通知書(写しを各2部) |
| 問い合わせ先 |
| 各都道府県労働局 雇用環境・均等室 |
| お問い合わせ |
| (住所) |
| 〒790-0046 |
| 松山市余戸西3-12-25 |
| 友澤社会保険労務士事務所 |
| (電話/FAX) |
| 089-989-0178 |
| (営業時間) |
| 平日:9:00~17:30 |
| 休日:土曜日・日曜日・祭日 |
| 『メール』でのお問い合わせは、ここをクリックしてください! |