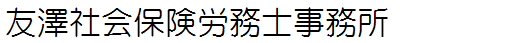 |
松山市余戸西3丁目12-25 |
| |
電話受付:089-989-0178 |
| 平日 9:00~17:30 | |
| HOME>>質問広場>>2023>>03月 |
| 2023年03月のQ&A |
| 【Q】 |
| 兼業・副業における労災のポイントを教えてください。 |
| 【A】 |
| 兼業・副業であっても、各会社(法人)における労働者の労災保険への加入は必 |
| 須です。労働者が会社Aでの仕事と会社Bでの仕事を兼業しているのであれば、会 |
| 社Aでも会社Bでもそれぞれ、労災保険に加入することになります。労災保険へ労 |
| 働者を加入させる義務は、事業主にあるため、会社側が手続きを行うのが一般的 |
| です。保険料もそれぞれの事業主が全額払います。そのため、それぞれの会社で |
| 得る賃金や業種によって、会社Aの事業主が支払う労災保険料と会社Bの事業主が |
| 支払う保険料額には金額の違いが生じます。 |
| フリーランスは対象外 |
| 会社に雇用されていればそれぞれの会社で労災保険に加入できます。しかし、労 |
| 災保険の対象は雇用されている賃金を受けとっている「労働者」であり、フリー |
| ランスや自営業者は対象になりません。ただし、一部のフリーランス・自営業者 |
| (一人親方等)に対しては、特別加入としての労災保険加入が認められており、 |
| 今後その枠の拡大が検討されています。 |
| 【用語解説】 |
| 特別加入者の範囲 |
| 労働者を使用しないで次の①~⑭の事業を行うことを常態とする一人親方その |
| 他の自営業者及びその事業に従事する人が特別加入できます。 |
| ①自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送事業又は原動機付き自転車若し |
| くは自転車を使用して行う貨物運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業 |
| 等) |
| ②ITフリーランス(ITコンサルタント、プロジェクトマネージャー、プログラマ、 |
| システムエンジニア、Webデザイナー等) |
| ③土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、 |
| 破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など) |
| ④漁船による水産動植物の採捕の事業(⑧に該当する事業を除く) |
| ⑤林業の事業 |
| ⑥医薬品の配置販売の事業 |
| ⑦再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 |
| ⑧船員法第1条に規定する船員が行う事業 |
| ⑨柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業 |
| ⑩改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、 |
| 同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する |
| 事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づい |
| て高年齢者が行う事業 |
| ⑪あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づくあん摩マッ |
| サージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業 |
| ⑫歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業 |
| ⑬芸能関係作業従事者 (労働者以外の方:芸実演家、芸政策作業従事者) |
| ⑭アニメーション制作作業従事者(労働者以外の方 声優の方除く) |
| 2.兼業・副業の労災の問題点 |
| ■給付金額の算定方法変更 |
| 2020年9月の労災保険法改正前における、兼業・副業している人の労災保険に関す |
| る問題は、「労災に遭うと、労災が起こった会社での労災保険しか適用されない点 |
| にありました。 |
| 例)A社とB社で兼業・副業し、どちらかの会社でも労災保険加入している人が、B |
| 社での業務中に労災にあった場合には、労災の給付はB社での契約分のみ適用され |
| ていました。給付額はB社からの賃金に対する額のみとなり、労働者の収入は激減 |
| してしまいます。 |
| このような問題を解決するために、労災保険法の改正(2020年9月)が行われまし |
| た。兼業・副業を行う労働者に対する労災給付は、「すべての就業先の賃金を合算 |
| した額」をベースとすることになりました。 |
| ■複数業務要因災害も労災保険の対象に |
| 業務災害のうち職業病(腰痛、頸肩腕障害等)、脳・心臓疾患(いわゆる過労死)、 |
| 精神疾患等が業務に起因して発生したものであるかどうかは、業務上の負荷が作用 |
| したものであるかどうかが基準になります。これまでは、複数の会社で働いている |
| 場合であっても、それぞれの会社での負荷を個別に評価していました。しかしこの |
| 方法では、複数の会社で働いている場合の総労働時間やストレス等を評価できず、 |
| 労使認定を受けることができないケースもありました。 |
| そこで、改正労災保険法(改正2020年9月)では、副業している場合には、複数の |
| 事業場における負荷を総合的に評価して労災認定を行うことになりました。 |
| このように複数の事業場での業務を要因とする労災のことを「複数業務要因災害」 |
| といいます。複数業務要因災害の対象となる労災は、脳・心臓疾患や精神障害等で |
| す。以下の労災給付が新たに設けられました。 |
| ・複数事業労働者休業給付 |
| ・複数事業労働者療養給付 |
| ・複数事業労働者障害給付 |
| ・複数事業労働者遺族給付 |
| ・複数事業労働者葬祭給付 |
| ・複数事業労働者傷病年金 |
| ・複数事業労働者介護給付 |
| ■複数業務要因災害については、いずれかの労働基準監督署に提出 |
| 通常の業務災害の場合には、各事業場を管轄する労働基準監督署のいずれかに申請 |
| すれば足りることになりますが、複数業務要因災害の場合には、各事業場を管轄す |
| る労働基準監督署のいずれかに申請すればよいです。 |
| ■労災の申請方法 |
| 労災保険給付の請求を行うのは、原則として労働者本人です。しかし、実際は事業 |
| 主の証明が必要になる等の理由から会社が労働者に代わって記入し、申請している |
| ことが多いです。但し、会社で副業を把握していない場合には、労働者自身が適切 |
| に記入を行わなければ複数事業労働者とはみなされず、労災保険給付額で不利な扱 |
| いを受けることになります。 |
| 副業をしている方が自身で労災申請する場合には以下の記入が必要です。 |
| ・複数就業先有無 |
| ・複数就業先の事業場数 |
| ・労働保険番号(特別加入) |
| ・特別加入の状況 |
| また、複数の就業先で働いている場合には、複数の就業先での賃金額を証明するた |
| めに、就業先毎に別紙を作成して事業主の証明を受ける必要があります。 |
| お問い合わせ |
| (住所) |
| 〒790-0046 |
| 松山市余戸西3-12-25 |
| 友澤社会保険労務士事務所 |
| (電話/FAX) |
| 089-989-0178 |
| (営業時間) |
| 平日:9:00~17:30 |
| 休日:土曜日・日曜日・祭日 |
| 『メール』でのお問い合わせは、ここをクリックしてください! |