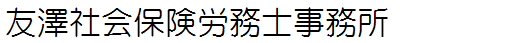| 【A】 |
| 労基法は、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業または事業所・・・に使用 |
| される者で、賃金を支払われる者」と定義しています(9条)。言い換えると、労 |
| 基法上の「労働者」とは、使用者の指揮命令を受けて労働し、かつ賃金を支払わ |
| れている者です。 |
| これは労基法の適用を受ける「労働者」の定義ですが、労基法から派生した労働 |
| 者安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法などの適用範囲も労基法と一 |
| 致します。また、男女雇用機会均等法や育児介護休業法などの労働法規も、労基 |
| 法と共通の「労働者」概念を採用としているものと理解されています。さらに、 |
| 労働契約法も「この法律で『労働者』とは、使用者に使用されて労働し、賃金を |
| 支払われる者をいう」(同法2条1項)と定め、労基法と基本的に同じ「労働者」 |
| の定義を採用しています。したがって、労基法上の「労働者」は原則として労働 |
| 契約の当事者たる「労働者」であり、労働契約法および判例により形成された労 |
| 働契約法理(配転法理など)の適用を受けます。 |
| すなわち、労基法9条の定める「労働者」概念は、個別的労働関係法全体の適用対 |
| 象となる「労働者」の範囲を定めるものだといえます(ただし、適用除外の範囲 |
| は法律により異なるので、注意が必要です)。 |
| 判例【横浜南労基署長(旭紙業)事件 最高裁 平成8年11月28日】 |
| 本件は自己の所有するトラックをA(会社)に持ち込み、専属的にAの製品の運送 |
| 業務に従事していた原告側労働者(運転手)Xが、積み込み作業中に傷害を負った |
| ことから、労災保険法所定の療養・休業補償給付を請求したところ、「労働者」で |
| はないとして不支給決定を受けたため、提訴した事案である。Xの報酬は出来高払 |
| いで、トラックの購入代金、ガソリン代、修理費、運送の際の高速道路料金等はX |
| が負担していた。また、Xに対する報酬の支払いにあたっては、所得税の源泉徴収 |
| 及び社会保険・雇用保険の保険料の控除はなされず、Xはこの報酬を事業所得とし |
| て申告していた。 |
| 判決の内容 労働者側敗訴 |
| 本件事実関係の下においては、Xは、トラックを所有し、自己の危険と計算の下に |
| 運送業務に従事していたものである。Aは、運送という業務の性質上当然に必要と |
| される運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、Xの業務の遂行 |
| に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえない。時間的、場所的な拘束の程度 |
| も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、XがA社の指揮監督の下で労 |
| 務を提供していたと評価するには足りない。報酬の支払方法、租税及び各種保険 |
| 料の負担等についてみても、Xが労基法上の労働者にあたるとすべき事情はない。 |
| であれば、Xは、専属的にAの製品の運送業務に携わっており、Aの運送係の指示を |
| そう拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻はAの運送係の指 |
| 示内容によって事実上決定されることなどを考慮しても、Xは労基法及び労災保険 |
| 法上の労働者にはあたらない。 |
| 2.「労働者」性の判断基準 |
| 労基法上の「労働者」性は就労の実態に即して客観的に判断されます。契約の形式 |
| が請負や委任となっていても、実態において「使用者の指揮命令を受けて労働し、 |
| かつ賃金を支払われている者」の基準を満たしていれば「労働者」に当たります。 |
| 判例は、具体的な判断要素として、①仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自 |
| 由の有無、②業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無、③勤務場所・時間 |
| についての指定・管理の有無、④労務提供の代替可能性の有無、⑤報酬の労働対償 |
| 性、⑥事業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など)、⑦専属性 |
| の程度、⑧公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無)を総合的に考慮 |
| し、「労働者」に当たるか否かを判断しています。 |
| 労働者性が問題となる者の類型としては、従業員兼取締役、裁量性の高い職種や特 |
| 殊な職種の者、零細下請業者などがあり、最近は雇用形態の多様化により判断が難 |
| しいケースが増えています。近年の判例としては、映画撮影技師を労働者と認めた |
| 新宿労基署長(映画撮影技師)事件や、私立大学病院の研修医の労働者性を肯定し |
| た関西医科大学研修医(未払賃金)事件、NHK集金人の労働者性を否定した日本放 |
| 送協会事件などがあります。 |
| 上記判例は、車持ち込み運転手の労働者性に関する初の最高裁判決です。判決は、 |
| Xが上記①や②について一般の従業員と同程度の拘束を受けていないことを重視し |
| てXの労働者性を否定しています。ただし、車持ち込み運転手がおよそ「労働者」 |
| に当たらないと判断しているわけではない点に注意が必要です。 |
|
| 3.労働組合法上の「労働者」 |
| 労働組合法は、「労働者」を「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ず |
| る収入によって生活する者」と定義しています(3条)。この定義は、労働者の経 |
| 済的従属性に着目し、労働組合を組織し使用者と団体交渉を行う権利を保障すべき |
| 者の範囲を定めたものであり、「使用されること」を要件としていないため、労基 |
| 法や労契法上の「労働者」よりも広い範囲に及びます。 |
| 最近の最高裁判例は、上記の労働者性の判断に当たり、①労務提供者が事業組織に |
| 組み入れられているか、②契約内容(労働条件や提供すべき労務の内容)が相手方 |
| により一方的・定型的に決定されているか、③報酬の労務対償性の有無を基本とし |
| つつ、④業務の依頼に対する諾否の自由の有無、⑤広い意味での指揮命令関係の有 |
| 無を補充的判断要素、⑥顕著な使用者性の有無をも考慮して決するという枠組みを |
| 採用し、会社との業務委託契約により同社製品の修理業務に従事するエンジニアや、 |
| 1年間の出演契約に基づいて公演に出演するオペラ歌手について、労組法上の「労働 |
| 者性」を肯定しています。 |