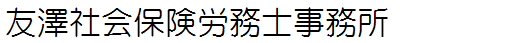| 【A】 |
| 労働契約法は、就業規則の効力のうち、単なる最低基準でなく、労働条件(労働 |
| 契約内容)そのものを決定・変更する効力の発生要件として、使用者が就業規則 |
| の内容(変更時には変更後の就業規則の内容)を労働者に周知させていることを、 |
| 就業規則の内容(もしくは変更)の合理性と共に明記しています(7条、10条)。 |
| このように、就業規則の周知がこれらの効力の発生要件(の一部)とされている |
| のは、下記判例で示された労働契約法制定前の判例法理が労働契約法の条文に取 |
| り入れられたことによります。 |
| 下記判例は、懲戒処分の根拠としての就業規則の効力が問題になった事案におい |
| て、就業規則の効力が認められるためには、その内容を、適用を受ける事業場の |
| 労働者に周知させることが必要との最高裁の立場を明らかにしたものです。具体 |
| 的判断としては、労働者の所属事業場とは別の事業場で労働者代表の意見を聴取 |
| しただけでは周知があるとはいえないとして事件を差し戻しています。 |
| 判例【フジ興産事件 最高裁 平成15年10月10日】 |
| 各種プラントの設計・施工等を業とするY会社(被告・被上告人)のエンジニア |
| リングセンター(大阪府門真市所在)に勤務する従業員であったX(原告・上告 |
| 人)は、平成6年6月15日に、職場秩序を乱したこと等を理由として懲戒解雇処 |
| 分を受けた。 |
| Y会社では、昭和61年に、労働者代表の同意を得た上で就業規則(旧就業規則) |
| を定め、労働基準監督署に届け出ていた。また、平成6年4月からは旧就業規則 |
| を変更した新就業規則を実施することにし、同年6月に労働者代表の同意を得た |
| 上で労働基準監督署に届け出ていた。これらの就業規則には、懲戒処分に関す |
| る規定が置かれている。Xは本件懲戒解雇に先立ち、エンジニアリングセンター |
| の労働者に適用される就業規則について質問したところ、旧就業規則はYの本社 |
| (大阪市西区所在)には存在するものの、エンジニアリングセンターには存在し |
| ないという状況であった。 |
| Xは、本件解雇の根拠となる事実が発生した時点でエンジニアリングセンターの |
| 労働者に適用される就業規則が存在しなかったこと等を理由に本件懲戒解雇の違 |
| 法・無効を主張し、Yらを提訴した。原審である大阪高裁は、本件懲戒解雇の根 |
| 拠となるのは旧就業規則であるとしたうえで、それがエンジニアリングセンター |
| に備え付けられていなかったからといって同センターの労働者に対して効力を有 |
| しないとはいえないとの判断を示した上で、X敗訴の判決を下していた。 |
| 判決 労働者側勝訴(労働者側敗訴の原判決を破棄・差戻し) |
| 使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種類および |
| 事由を定めておくことを要する。 |
| 就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずるためには、 |
| その内容を、適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られているこ |
| とを要する。 |
| 原審は、Yが労働者代表の同意を得て旧就業規則を制定し、労働基準監督署長に |
| 届け出た事実を確定したのみで、その内容をセンターの労働者に周知させる手続 |
| きが採られていることを認定しないまま旧就業規則に法的規範としての効力を肯 |
| 定し、本件懲戒解雇が有効であると判断しているが、この判断には審理不尽の結 |
| 果、法令の適用を誤った違法がある。 |
| 2.周知の意義 |
| 労働基準法は、就業規則を作業場の見やすい場所に掲示するなど同法施行規則の |
| 定める方法により、労働者に周知することを義務づけています(労基法106条1項)。 |
| これに対し、労働契約法7条、10条にいう、労働契約の内容を決定・変更する効力 |
| の発生要件としての「周知」とは、労働基準法および同法施行規則の定める方法 |
| に限らず、実質的に見て就業規則の適用を受ける事業場の従業員が就業規則の内 |
| 容を知ろうと思えば知りうる状態に置くこと(実質的周知)を意味しています。 |
| 具体的には、就業規則が各事業場で管理職員の机の中や書棚に設置され、事業場 |
| の従業員がいつでも閲覧しうる状況にあった場合や、会社設立時に営業開始前の |
| 暫定的就業規則として当時の従業員全員にその内容が示され、その後も新規採用 |
| 者には就業規則が配布されていた場合に周知が肯定されています。 |
| 一方、就業規則による労働条件の不利益変更(労働契約法10条)が問題となる事 |
| 案では、使用者が就業規則の掲示などを行っていても、実質的周知がなされてい |
| ないと評価されることもあります。判例には、就業規則による退職金制度の変更 |
| について、就業規則が掲示されていたとしても、従業員が就業規則を参照しただ |
| けで変更後の退職金額を知ることは困難であり、使用者は説明文書の配布や説明 |
| 会の実施などを行うべきであったとして、周知を否定したものも見られます。 |
| 3.労基法上の義務の違反と就業規則の効力 |
| 労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者に就業規則の作 |
| 成義務を課しており、作成義務を負う使用者については、就業規則に記載すべき |
| 事項、所轄労働基準監督署長への届出義務(以上89条)、事業場の過半数代表者 |
| の意見を聴取する義務(90条)、法所定の方法での周知義務(106条)について |
| 定めています(周知義務については、作成義務を負わない使用者が就業規則を作 |
| 成した場合にも適用があります)。 |
| 使用者が就業規則作成に当たり上記の義務に違反した場合、労働契約法7条・10 |
| 条に基づく就業規則の効力は生じるのでしょうか。まず、周知義務については、 |
| 2.周知の意義のとおり法所定の方法による周知は効力発生要件ではありません。 |
| また、法定の必要的記載事項の記載漏れは作成された部分の効力には影響を及ぼ |
| しません。次に、意見聴取義務および届出義務についてみると、判例はこれらの |
| 義務の違反があっても労働契約内容を決定・変更する就業規則の効力に影響はな |
| いと判断する傾向にあります(シンワ事件、ブイアイエフ事件等)。 |