インド風土記 その5(全5回)
聖なるガンジス河の聖水
沐浴をする風景で有名ですが、今回の駐在期間中には行く機会がありませんでした。
テレビでよく放映される場所は、位置的にはインドの真ん中の北側で、バラナシの町です。
行った人の話ですと、沐浴場所、死体の焼却場などごちゃごちゃしていて、牛の糞も多くて踏まずに川縁までは到達できないし、夏は乾燥したものが空中に舞っていて、ある人は牛の糞で喉をやられたと言っていました。
水質はたいへん悪いので、わざわざ日本語で汚いので入らないでくださいと書いてあります。でも、皆さん興味があるので入る人もいるようです。半焼きの死体が(どこまで焼くかは金額によるのでしょうから)本当に流れていたそうです。
インド人でも信仰心の強い人は年に1度秋に、村ぐるみ、友達、個人とかグループで近くのガンジス河に水を取りに行きます。その水を神としてお祈りをします。時期は毎年夏で、太陰暦で決まり(3週間くらいだったと思います)、行きは自動車等少し楽をして行っても良いのですが、帰りは自分の足で帰って来なくてはいけません。デリー近郊からでも本流まで200kmくらいあり、最盛期には国道沿いに人が列を成して歩いています。信仰の力はさすがで、インドを支えている力を感じます。
基本的に靴は履かないでサンダル履きの人が多いです。歩くのだったらもっと歩き易い方が良いのに、と従業員に聞いてみたら、靴は牛革で作るので履かないとの明解な答えが返って来ました。
村の若者を30〜40人引き連れてトラックの荷台に乗せて、それぞれ200m位を走りながらリレーで帰る方法もあり、見ているとランナーは止まってはいけないようで、一生懸命走っています。
 |
 |
| 交代要員を乗せたトラック ガンジスの水を運ぶ人達 |
ナップサックに入った水を バトンタッチしています |
 |
 |
| 水を運ぶ人 | 水運びの休憩所 |
結構渋滞の原因になりますが、聖なる神様を運んでいるので、誰もクラクションを鳴らすとかアオルような事はせずに横をすり抜けて行きます。
この時期だけは、沿線の企業や金持ちが、休憩所の設置や炊き出しをボランティアで行っています。
地鎮祭や起工式などお祈りの時に、祈とう師が聖水を持ってきて、参加者の体に振り掛けたり、時々そのまま飲めとか言います。
聖水の凄さを物語るエピソードですが、空港でペットボトルの水が検査で引っかかり、捨てろと言われた時に、これはガンガー(ガンジス)の水だよといったらOKだったと、駐在員の若者が自慢げに昼食時に話していました。
タジマハール
タジマハールは、デリーから南東200kmにあるアグラの町にあります。自動車で5時間程かかります。
昔の王様が奥さんの為に建てたお墓ですが、インドを感じる代表的な建物です。
このモデルとなったお墓がデリー市内にあるフマユーン廊で、大きさは小さいのですが、ミニ版でこれも世界遺産に指定されています。
入場料は、地元民は15ルピー、外国人は750ルピーと違っていて、50倍くらいの差があります。外国人でも駐在して居住証明書を持っていれば地元と同じ金額で入場できるのですが、窓口のおじさんは知らないととぼけて、750ルピー取られます。
インドの有名な史跡はほとんどがイスラムの遺跡で、ヒンズーは精神的な支えが残っているような感じです。間違っていたらごめんなさい。説明するより見て凄さを感じて下さい。
紅 茶
 |
| 110ルピーのスーパーに並ぶ紅茶 |
どこに行っても紅茶は出てきます。チャイかブラックティーかと聞かれ、ミルクはと最後に言われます。ここで砂糖はと聞かないところがインド的で、甘いのが好きな国民なのでブラックでも砂糖入りが普通です。砂糖は入れないでねと言っても20%位の確率で入っています。
ギーと呼ばれる羊のミルクをいっぱい入れて飲むのが定番ですが、甘いので砂糖なしのブラックにしています。
紅茶は、化学薬品が入っているペットボトルの水を使うのではなく、自然に近い怪しい水道の水で飲むのが一番美味しいと思います。一度沸騰させるので、雑菌は心配ありません。
アッサム、ダージリン、(隣国)セイロンなどの紅茶の産地ですが、高級品は輸出され、一般国民は残った葉っぱを飲んでいます。でも、全体レベルが高いので三重県の牛肉のように美味しいですね。
空港では高い値段で紅茶を売っていますが、所詮一見客が対象ですので、賞味期限切れとか、棚落ち品が多いので買う時は必要最低限にした方が無難です。市販の3〜5倍の値段で売っています。
ブラックで思い出した余談です。以前、この時はコーヒーでしたが、日本語の話せるスチュワーデスに持ってきてと頼んだら、クロデスカと聞かれ一瞬わからず聞き返しました。ブラックの意味だと理解するのに30秒ほどかかりました。
ターバン
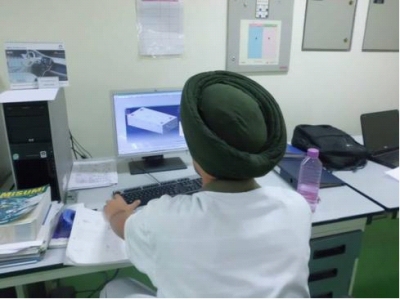 |
| 帽子のようなターバン |
ヒンズー教徒の中の一派で、シーク教徒と呼ばれている人がターバンを巻いています。くるくると巻いているのかと思っていたら、帽子のようにすっぽりかぶるタイプが多く、たいていの人が簡単なのを使っています。
勤勉な人が多く、いろんな分野の中枢を握っているので、ターバンを目にする機会も多いのですが、思っているよりは少ないです。工場内に700人近くインド人が働いていますが、ターバンを巻いている人は3人しかいません。路上生活者にターバンを巻いた人が少ないので、ある意味勤勉である証拠だと思います。先日日本に戻る時の機長さんはターバンを巻いていましたし、インドのシン首相も着用しています。
ヒンズー教の中にもいろいろな宗派があって、喜怒哀楽を表に出さず服も着ないで生活をするジャイナと呼ばれる派があります。時々5〜6人で、それも素っ裸で道を歩いています。丸見えで初めて見た時はびっくりしましたが、周りの人は気にしていない様子でした。男ばかりでしたので、女の場合は?と疑問を抱きながら次のチャンスを待っていたら半年後に遭遇しました。肩から白い布をすっぽり被って歩いていたので、その時は少しガッカリしたのか安心したのか複雑な心境でした。彼らは突然現れるので写真はありません。
人人人
どこに行ってもいっぱい人がいます。 衛生環境が悪いので乳児の死亡率は相当高いと思われますが、それでも凄い率で人口が増えていくとは、元の発生源はどれだけ生産をしているのか想像がつきません。
ある朝サイクリングをしていたら(自転車は貧乏人の乗り物です)通勤時間になってしまい、バスターミナルから続く幅20mの道路を横いっぱいに、車道?歩道?関係なく人が歩いてくるので、自転車に乗る事が出来ずに歩いた事があります。
レジなどで人が並んでも、後ろの人のお腹と前の人の背中が接触しています。それだけ昔から人が多いので前、前と行かないと生きていけなかったのでしょう。
よくバスの屋根に人がいっぱい乗っている写真がありますが、実際乗りすぎてバスが傾きながら走っています。インド的にはまだ横転してないので「まだいいか」です。
インドの人は話をするのが大好きです。結論を出すのではなく、ただいつまでも自分中心に話をしています。相手が何を求めているかは無視するので、「あなたの年はいくつですか」と聞くと、お父さんはどこで生まれてお母さんと結婚した時期とか、住んでいた場所とかを一生懸命10分ほど話します。
話を止めて年だけを言いなさいと注意をしても、またさき程の話を続けます。紙を出して何歳かここに書きなさいと言うと、やっと自分の年を紙に書きます。
単純な質問に10分はかかります。また規則を自分の都合が良くなるように解釈します。ですから一方通行でも少しだけなら問題ないと逆走するのですが、人により少しが1〜2kmにもなります。 「インド人とは」の講習会で教わった基本は、「規則を守らないのがインド人の規則」と教えられました。
日本で30年商売をしているインド人と、先日話をする機会がありました。その人は日本もインドも好きですよと話をしていましたが、インドでは商売はしないそうです。遊びにいくだけで、理由を聞くとストレスが溜まって仕事が進まないとそうです。
日本人は時間を守って、約束事を守るので日本が好きなのだそうです。
 |
 |
| 会社でのダンスパーティー | 路線バスを後ろから |
数学の達人
この項目もよく質問されます。IT分野やインド工科大学には優秀な人もいるようですが、私たちの前に現れた事はまだありません。でも工場レベルのマネージャーでも数字の記憶力はすばらしく、1年前の見積もり金額を突然質問してもちゃんと正しく答えてくれます。また、計算もそこそこで、個々の計算は速いのですが、全体の数字の意味を理解する感覚はありません。小学校1年生が電卓を持って計算が速いだろうと言っている感じです。
50+50=100はすぐ出しますが、20×5と同じ値との連想が出来ないので、在庫を数えても1桁間違えてしまう事があります。今の日本ではその計算もできない人が増えてきたそうですが、日本の九九はインド数学より優れています。
編集後記
日本は海に囲まれているので、外国の事を海外と呼びますが、韓国でもアメリカでもヨーロッパでもインドでも外国とは陸続きなので、多分そのような呼び方はないのではと思います。他国と接しているのが普通ですので周りは敵だらけで、常に自国を守らなければいつ侵略されるか分かりません。
以前中東からの報道テレビで、日本の女性アナウンサーが10才位の男の子に、戦争のない平和な暮らしをしたいですかと質問をしていました。
その子は生まれてからずっと戦争の中で生きてきたので質問の意味を理解できずに分からないと答えていました。なんと勉強不足なアナウンサーだなと少し腹がたち、またその場面がいつまでも頭に残っています。
10年以上海外勤務をして、幸いにも生産工場でしたのでその国の地方にいる事が多かったのですが、それでも仕事や私生活では、自分を失わず、いつだまされるか、襲われるかと緊張感を持って生活する状況でした。
それと比較すると、日本での生活は社会システムが上手に出来すぎていて、それに甘んじて皆が生活するので、自分から何もしないでも物事が終わってしまいます。
平和と呼べば皆が同調すると思っているのは、日本人だけではないでしょうか。情報がすぐ世界を走る時に、日本が外国から取り残されていると感じるのは、私だけではないと思います。
インドでは交差点に乞食が居て、毎日物乞いをします。一度お金をあげると、くれた人は何時に通ってどんな車に乗ってどの位置に座っていたかを覚えていて、翌日からの1週間は今まで以上にしつこく迫ってきます。さすがプロ根性に徹していないと生きて行けないのだと感心しました。これも情報分析ですね。日本円で5円与えただけでしたが、お金で買えない価値のある事を教えてもらいました。
日本ではよく国際化と言われますが、英語を話すだけが国際化ではないと思います。社会の中で皆と協調して自分がどの様に生きていくのか。自分がしっかりとした考えを持って立っていなければ相手からも認めてもらえません。これからはそんな気持ちを子供や孫にしっかりと伝えて行きたいな、と今回のインド風土記を書きながら思いました。
日本向けの食材店とかレストランも増えてきましたので、ダッカの山家さんよりは生活は楽ですし、今は少し慣れてしまって最初の新鮮な気持ちを忘れてしまいました。読んでいてよく理解できない部分もあったかと思いますし、まだまだ書き足りない部分もありますが、どこかで会ったときに続きをお話しします。読んでくれてありがとう。