第4回 ダッカからローマへ、そしてまたダッカへ
11月21日から27日まで、FAO本部で開催された病気の監視(サーベイランス)における情報システムについての国際ワークショップにまねかれてローマに行った。
この2年来、携帯電話とコンピュータ間で情報を直接送受信することができるSMSゲイトウェイ・システムをフィールドにおける動物の病気の監視(サーベイランス)に用いることにより報告に要する時間の短縮化とフィールドからの情報伝達業務の簡便化に大いに貢献していることが注目されたのである。このプログラムのためにバングラデシュの492の行政単位であるウパジラのうち260にそれぞれ3人ずつ、合計780人のコミュニティ・アニマル・ヘルス・ワーカー(CAHW)と、ほぼ3ウパジラにつき1人の割合で獣医師を合計88人雇って配置し、毎日、CAHWたちには村を巡回して一日の終わりにルーティンに報告を行なってもらっている。したがって、毎日780の情報がダッカの疫学センターに寄せられ、月にすると2万3000以上に達することになる。しかるにSMSゲイトウェイを用いる事により情報は自動的にサーバー内のデータベースに蓄積されると同時に異常事態発生の場合には担当の獣医師に警報がこれも自動的に届けられ、確認を要請する指示を出せるので、情報量の多さに圧倒されることはない。
ただしCAHWは地元の事情に精通し、かつ症例定義(ケース・デフィニション)について訓練を受け、どのような状況に遭遇したらHPAIアウトブレークの前兆とみなすかの判断ができなくてはならない。アウトブレークがあきらかになってから報告をする受動的監視(パッシブ・サーベイランス)とちがって、このように前兆を探し当てて報告をする監視態勢を積極的監視(アクティブ・サーベイランス)という。従来、地域の獣医業務で行なわれている養鶏家からの報告にもとづく受動的監視(パッシブ・サーベイランス)に先立って積極的監視(アクティブ・サーベイランス)により報告がなされたのは過去1年のアウトブレーク総数の7割以上、8割近くにのぼる。火災とおなじくボヤの段階で早期に検出ができれば、隣家への類焼・飛び火をまぬかれるのと同じ理屈である。
11月のダッカはまだ暑いさなかであったのでつい季節の移り変わりに無頓着になりがちだったが、ローマはすでに晩秋である。外套をたずさえて飛行機に乗った。今回は朝、普段の出勤時刻に家を出て、9:40ダッカ発の昼間の旅だったので睡眠を犠牲にせずに済んだ。しかも、ちょっと距離があるということで、ビジネスクラスの座席を取ってくれていたため快適な旅だった。ドバイ経由で、ローマまで、6時間と6時間の飛行である。
 |
これはエミレーツ航空のビジネスクラスの機内。この便では座席と足の置き場がゆったりしていて脚をいっぱいに伸ばすことができたほか、エコノミーと大差はなかったが、ドバイで乗り換えた次の便では180度に体を伸ばして横になって休めた。 エミレーツのスチュワーデスは赤い帽子に右頬に白いストールを垂らして首に巻いている。ユニフォームはラクダ色に、よく見ると縦縞が入っている。スラックス姿だったのがなぜか離陸後はスカートに代わった。なにかご用のときはお申し付けください、ミスター・ヤマゲと個体識別してくれるところが、エコノミーと違う。乗り換えの空港で、VIPラウンジをつかえるのはうれしい。 |
日付上は出発と同じ日の夕方、現地時間で18:45にはローマである。イタリアは冬時間で一時間遅らせてあるため、ダッカとの時差は4時間でなく、5時間である。したがって、宵の口には早く眠くなり、ダッカでのいつもの生活習慣上、ローマでは朝は2時には目が覚めてしまう。
ローマの郊外のフィウミチーノ空港から、宿泊予定しているコロッセウム近くのホテルLまでシャトルで30€という。一方、空港からローマテルミニ中央駅まで電車だと14€なのである。迷わず電車でテルミニ駅まで来たところ、そこからホテルLまで乗ったタクシーに40€かかった。
ローマは予期していた通り、深い秋のまっただなかである。熱帯からやって来ると、季節を感じさせてくれるすべてのものが新鮮に思える。天然の冷気、色とりどりのプラタナスの落ち葉。
 |
 |
| ホテル周辺の町並み。 | 石畳の上に茶色や浅黄色の落ち葉にも見とれてしまう。 |
食料品店の軒先には熟した柿が売られていた。
「これはもしかしてパーシモン(柿)?」
と店の者にたずねたら、若い店員からさも当然といった感じで、
「『カキ』や」
と言われた。
「買ったっ!」
カキという名は、すでにイタリア語に定着しているようである。3個買って、ホテルの部屋で皮ごと食べた。熟しきって食べごろだった。
 |
 |
| 柿を店頭に並べて売る店がいくつもあった。栽培しているところを見てみたいものである。 | カキを売っていたカポ・デ・アフリカ通りの食料品店。「カキ」という名前が日本語であることを知っているのかどうか。 |
ホテルLはコロッセウムから歩いて10分、カポ・デ・アフリカ通りにある。FAO本部のあるカラカラ浴場遺跡の周辺には歩いて20分もかからない。 周辺は石畳が多く、修道院などがある。
 |
 |
 |
| ホテルLの外観。 | ホテルL の6階のテラスからはコロッセウムが眺められる。 | コロッセウムのそばの泉。昔、スイスに住んでいた頃、「ハイジの泉」というのを見に行ったら、湖ではなくてこんなチョロチョロ水の出るところだった。 |
ホテルLはFAOの職員や訪問者が好んで泊まる宿として知られている。知人が教えてくれたので迷わず、予約(ブッキング)をしたのである。インターネットでシングルルームを予約しようとしたら満室だとの返事だった。念のために直接、国際電話を入れてシングルルームは?と訊いたら空いていないという同様の返事である。では、どんな部屋なら空いているのか、と訊いたら、ダブルルームをシングルルームとして使用する部屋なら空いている、という。ものは聞きようである。料金は10€程度しか変わらなかった。
 |
 |
| オーナーのK夫人は夕食に加わって客をもてなしてくれる。 | 左端はオーナーの息子さんで、料理を担当する。右手のふたりはFAOで開催された遺伝子資源の会議に出席中のオランダとフィンランドの大学からの研究者。残りのふたり組はFAO関係の他の者とはちがって、リバプールから旅行でローマにやって来た物理学専攻の大学生と、そのガールフレンドらしいフランス語を教えているパリ育ちの女性教師という若いカップルである。 |
部屋は質素で居心地はいいし、清潔で無駄がない。5階の部屋だったが、ひとつ上の階の部屋には広いテラスがついていて眼前にコロッセウムの眺めが見事である。夕食には、オーナーのK夫人が加わって楽しくもてなしてくれるし、食事がすばらしくおいしい。おかげで、滞在中、FAOで懇親会のレセプションがあった一晩をのぞいて、6泊中5回、夕食をすべてホテルLで食べた。料理はフランスとスイスの国境に近いジュネーブに永くレストランを経営していた息子さんが指揮を取っている。この息子さんも食事に加わることが多く、話が話題に豊富で実に面白い。もとの経営者である父上が元FAOの職員であったためか、食糧問題、動物の病気、政治、経済についても蘊蓄(うんちく)がある。今は亡きその父上のもともとのルーツが今はバングラデシュの東端、インドとの国境に近いクミラという町で、しかも今わたしが住んでいるダッカのバリダラ地区とは湖をへだてたグルシャン地区にむかし家があったということから、話が弾んだ。
 |
 |
 |
| FAO本部のこの8階建ての建物はムッソリーニ時代に植民地省に使われていたものを破格の賃貸料で借りているものである。巨大な組織で規模は国連専門機関中、最大であると聞いていたから、どんなものかと思っていたが、米国の国立保健研究所NIHとくらべればこじんまりしている、というのが第一印象である。 |
FAO本部の屋上からの眺め。ローマの中心地でありながら緑が多く、高層ビルがひとつもないところに史跡保存の強い意志が現れている。 |
背後にみえるのはバチカンの南東端にあるカトリック教会の総本山サン・ピエトロ大寺院だろう。FAO本部から歩いて行ける距離だったが訪れる機会を逃した。 |
FAOに出勤する初日の朝も次の日の朝も雨が降ったのでタクシーを呼ばねばならなかった。しかし、それ以外は朝も夕方も歩いて通った。古代ローマの遺跡の中にあるような町である。古い町並みは、永く住んだスイスのベルンも同じだが、ベルンの中世の建物はそのまま形は保存されて残っているものの、砂岩で出来た建物の外壁はたえず修復され新品のままのように見える。昔は新しかったのだから、新しく保つことこそ、原型をとどめることになるという考えなのだろう。そうではなくて、ローマの遺跡群は2000年の時を越えて来た跡が壁に見て取れる。思わず、手で触れてみたくなる。
 |
 |
 |
| これはFAO本部のそばにあるカラカラ浴場遺跡。 |
コロッセウムはFAO本部とホテルLの中間地点にあった。歩いて10分とかからない。感激したふうに写真を撮りまくっている学生風の日本人の若者が自分も映りたいためにカメラのシャッターを押してもらえませんか、と頼んできた。撮ってあげたかわりにわたしもとってくれないかと自分のカメラで撮ってもらった。 |
雨の降らない日はいつもコロッセウムのそばを通って歩いて通った。 |
ワークショップは、世界の各地から40人ほどの参加者があり、つつがなく4日間の会期を終えることができた。
 |
 |
| ワークショップの模様。本部のC棟の5階にあるGerman Roomというホールで開催された。他にPhilippine Roomとか国名の付いたホールがある。Japan Roomというのがあるのかどうかわたしは知らない。 |
アフリカ生まれのスイス人Dr Jはビデオコンファレンスで、わたしたちのバングラデシュでの活動を好意的に評価してくれた。 |
会期中はホテルとFAO本部との往復以外にほとんどどこにも見物に出かける事は出来なかったが、最終日は半日で終ったので、いつも近くながら外からしか見ることのなかったコロッセウムの内部を見る事ができた。これを見た後、カポ・デ・アフリカ通りにあるヴァーチャル・ミュージアム『3Dリワインド・ローマ』という博物館に行ってみたら、西暦310年の古代ローマの3次元再現映像を見せてくれた。また闘技場に上がる昇降機から、天井を見上げると格子越しに獰猛なヒョウが対戦相手の剣闘士(グラディエータ)が現れるのをいまかいまかとしびれをきらして吼えたりうなったりしながら右往左往しているのが見える。すっかり剣闘士(グラディエータ)になったかのような気分である。
 |
 |
 |
| コロッセウムの内側。周囲を観客席で取り囲まれた底の闘技場は、一部手前の部分に復元されているように当時は床で覆われていた。その地下には剣闘士(グラディエータ)や檻に入れたライオンやヒョウなどの猛獣が待機しており、剣闘士(グラディエータ)同士または剣闘士(グラディエータ)と野獣との戦いの出番がくると人力の昇降機(リフト)で舞台に上ってくるのである。 |
これは闘技場の床の下の通路と部屋の名残。 |
コロッセウムの5万人を収容できた観客席の部分。紀元72年に建設された楕円形をした闘技場は現代にサッカー競技場として作られたとしてもおかしくないほどの完成度である。このようなものをじかに見ると過去の遺産でいまも食って行けるだけの先進性というエネルギーがこの国にはかつてはあったんだと素直に思えて来る。 |
ホテルのある界隈を歩くと石畳の坂や露天市や修道院がある。
 |
 |
 |
| コロッセウムの方角からホテルLのあるゆるやかな坂になっているカポ・デ・アフリカ通りをのぼりつめたところにある修道院の西側の外観。 |
ホテルLのK夫人が奨めてくれたので、ある朝訪れてみた修道院。白と薄紅色のシクラメンが可憐に咲いていた。 |
中へはいるとしばらくして尼たちが朝のお勤めのお祈りをしに来た。祈りの最中は写真をとることははばかられたので、おわったあとに撮った教会の内部。 |
このローマへの旅の直前までいろいろと取り込んでいた。そのひとつは炭疽のアウトブレイクだ。
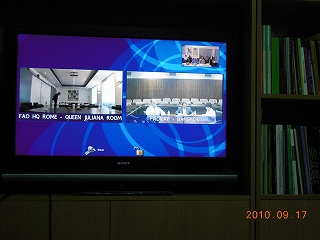 |
これはローマとバンコクとダッカとの三極ビデオ・コンファレンス。FAO本部からの炭疽調査ミッションが訪れる前に、行なわれた。 |
8月にバングラデシュの酪農地帯のひとつシラズゴンジ県(ディストリクト)でひとの感染が起こり、マスメディアに取り上げられて大騒ぎとなった。去年の同じ時期にも発生があったので、記憶があたらしいこともあり、次々とヒトの感染が報道された。炭疽に感染した牛が屠殺され、解体され、食べられたのである。そして、その際、とくに解体にたずさわったひとたちの多くが、皮膚型の炭疽の典型的な症状を現したのである。8月以降で600人以上のヒトの患者が出た。不思議と腸炭疽や肺炭疽は起こっておらず、ひとの死者は出ていないが、動物においては牛を主にヤギも含めて100例以上の死亡または屠殺の報告があった。わたしはヒトにおける発生後さほど日数の経っていないシラズゴンジ県の村に現地視察を行なった。
村の患者たちにはまだ、乾ききっていないブラック・エシュカーとよばれる黒い瘡蓋(かさぶた)ができていた。この仔細はレポートにして、FAO本部その他に提出した。本部からは炭疽の専門家の緊急派遣を必要とするかと打診があった。政府からの正式要請もあり、もちろん、要請した。数百万の牛やヤギが犠牲として食肉処理されるイスラム教徒の宗教的祝祭である11月17日の犠牲祭(イドル・アドハ)に向けて警戒が必要なので、ミッションはできるだけ早くにしてほしい旨を伝えた。ミッションは10月26日から11月3日のあいだバングラデシュを訪問し、データの収集、現地視察、関係機関(WHOや国の研究機関)との協議を行なった。牛肉の消費が落ち込んでいることからダッカの屠場の視察も行なった。宗教的な背景からだろう、大都市にしては驚くほど数の少ない屠場のひとつを早朝の4時に訪れた。屠殺にもイスラム式の流儀があるのである。キブラとよばれる礼拝の方角に頭を向けて頸動脈をどのように切るかとかに細かいルールがある。正しく回教徒(ムスリム)によって屠殺されたかどうかを立ち会って確認する係もいる。そのような手続きをへてはじめて食用に供しうるハラールとなるのである。
炭疽の騒ぎで実際に牛の一日の屠殺数は激減していた。牛肉の消費の落ち込みによる畜産家と、この犠牲祭(イドル・アドハ)の時期に国内の年間のほぼ
40%に相当する皮革を調達するといわれる皮革業者にたいする風評被害が起こりつつあった。ただ、安全であるから安心するようにとむやみに言ってみたところで、逆効果である。わたしは、病気の動物を内々に屠殺解体することは危険であるので、やめること、病気の動物をみつけたらすぐ獣医当局へ連絡すること、死んだ動物を川や湖に投棄しないということを訴えるよう主張した。動物を病気からまもることにより、ヒトへの感染を防げるのだとTVトークショウでも言った。
 |
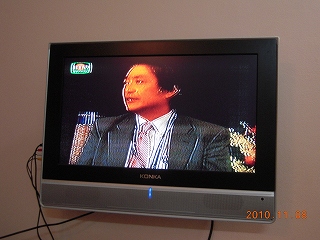 |
| FAO本部からの炭疽調査ミッションとともに11月2日、漁業畜産大臣を表敬訪問した。ワイシャツ姿が大臣で、経歴によると学生時代から学生運動に熱心だったらしい。わたしと2ヶ月しか年が違わない同世代である。 |
バングラデシュにおける炭疽アウトブレイクに関するTVトークショウに招かれて喋ったときのもの。11月8日の夜7:30にバングラデシュテレビジョンBTVから全国放映されたあとも11月17日の犠牲祭(イドル・アドハ)に先立ち繰り返し再放送された。 |
9月5日に出された緊急非常事態宣言(レッドアラート)が10月7日には解除されたこともあって牛肉の消費は回復し、犠牲祭(イドル・アドハ)は平常に祝われた。
 |
 |
| 11月17日の犠牲祭(イドル・アドハ)をまぢかに、ダッカにも多数の牛が続々と連れてこられた。祭りの期間中、バングラデシュ全土で数百万頭の牛とヤギが犠牲に供された。 |
11月17日の犠牲祭(イドル・アドハ)の日、(牛肉でなく)牛を買ったから食べに来てくれというので訪れた畜産普及局の家畜衛生行政の部長B(左端)の家族。ピンクの服の娘さんは医学部に学ぶ2年生である。その横の右端はそのクラスメート。Bの横にいるのは奥さん。 |
6月以来半年以上、バングラデシュでは発生がみられない高病原性鳥インフルエンザH5N1のぶり返しを警戒しなければならないシーズンを前に、インターナショナルとナショナルのいずれのスタッフも拡充することができた。
 |
あたらしく加わったスタッフを夕食に招いて歓迎をすることにしている。去年のいま頃、わたしがしてもらったことである。インターナショナルスタッフとしてニュージーランド国籍のイギリス人R (左からふたり目)、ドイツ人のF (左端)、それにアメリカ国籍のエリトリア人T (右上)らを採用した。三人とも国際経験豊富な獣医師である。 |
バングラデシュに来て一年になりながら、いまだに休暇をとったことがないし、仕事ついでに何かを見る機会にめぐまれるときを除いて、観光を目的にどこか名所を巡る機会はもたずじまいである。しかし、そんな機会以外にも、見て面白く、楽しいものが無いわけではない。
ジュートはバングラデシュの主要産物である。ジュートというとコーヒー豆のジュート袋や強靭な縄をその独特の匂いとともに思い出すが、ジュートの製品がすべて手触りの粗いものというわけではない。手触り、足触りの良い絨毯を買った。テーブルに敷くマットも気にいっている。
 |
 |
| この絨毯はジュート製。この肌触りとデザインがとても気に入っている。 | これは刈り取ったジュートの生茎を乾燥させているところ。ジュートはバングラデシュの主要産物である。 |
 |
 |
| 乾燥させたジュートの生茎をその後1〜2週間位、池の水に漬け発酵(浸水醗酵)させたのち、手で1本ずつ靱皮(じんぴ)繊維を剥離する。これは茎の形成層の外側にできた篩部(しぶ)で、これが紡ぎ糸(ヤーン)の原料となる。 | 紡ぎ糸(ヤーン)のもとは乾燥させられてから、売られる。 |
 |
 |
| これはジュートの紡ぎ糸(ヤーン)から作られた絨毯。モダーンなものから伝統的なデザインのものがいろいろある。 | ダッカのエレファント通りには観光客にはあまり知られていないジュート製のカーペットの専門店がある。 |
バングラデシュの東部にある港町、チッタゴンに学会の用事で行ったときには、かねて見てみたいと思っていた老朽船舶の解体場を訪れた。飛行機からも見える。遠浅の海岸に巨大な船が砂浜に乗り上げて、なかば解体されて、それでも立ち尽くしている。いずれも船首を陸地に向けているのは、できるだけ岸に近づけるため満ち潮のときに陸に向かって全速力で陸地に乗り上げさせるからであろう。
 |
 |
 |
| チッタゴンにある老朽船舶の解体場は解体数では世界で三番目の規模らしい。少年をふくむ2万人の労働者が低賃金で危険な作業に従事しているという。未洗浄のため油槽内からは油槽に残っていた油が海洋へそのまま流出してゆくので環境汚染の問題もある。 |
これは解体された船舶から回収された備品を売る店。 |
ダッカのアンティックの店で買うよりも安く買える。真鍮製の鐘や望遠鏡、寒暖計、コンパスなどがワンサカとあって、見るだけでも楽しい。 |
車の部品に興味のある友人が来たので、ダッカで同じような店がいっぱい集まっている部品屋街に行ってみた。ダッカの市内の道路は、ま新しい高級車と日本でならほとんど法律で一般道を走行することが禁止されてしまうであろうようなポンコツ車両が、どちらも同じように渋滞のためににっちもさっちもできずに立ち往生する光景が日常的である。そのあるかないかわからないような隙間を縫って、リキシャが走り回っている。CNGと呼ばれ、緑色をしたのはCNG(圧縮天然ガス)エンジンを搭載した三輪自動車でオート・リキシャともよばれる。そのようさまざまな車が実用に堪えうるのも、このようななんでも揃う部品屋があるおかげであろう。
薬屋も目を引くひとつである。ダッカではやたらとあちこちで見かける。ドイツやスイスの製薬会社は、ライン川で栄えた染料産業を基盤にして発達した。バングラデシュもヒマラヤから流れてくるガンジス川の下流だから、同じような発展過程を経たのだろうかと思ってしまう。
果物も豊富だが、野菜も豊富である。それは市場を訪れればよくわかる。わたしは、バングラデシュでは料理を作ってくれるメードもやとわず、ひとり暮らしをしている。いろいろな野菜を買ってきては自分で簡単な料理をする。ときどきサラミを買いに行く「ドイツの肉屋(ジャーマンブッチャー)」という店のオーナーのアジア系の女性は日本料理を作るのが上手な家政婦(夫)はいくらでもいるから紹介しますよ、と親身になってリストまで見せてすすめてくれるが、食欲というのはやはり本能のひとつだから、いつも食べるものに関して人まかせにすることにどうも抵抗があってならない。和食の料理本はいくつも買ってあるが、あまり活用しておらず、上手とは言えないが、上手になろうにも日本食の食材がまったくと言っていいほどに入手できないのには困っている。味噌もない。醤油はキッコーマン製のものをスーパーマーケットで見つけたが、回教国向けに成分調整されているためか味が日本のとは異なる。味覚ほど保守的なものはないというのはわたしの持論である。たいていのものには慣れることができるが味覚は馴化させることが難しい。もちろん味覚が変わるという例外的状況はある。たとえば、ある種の寄生虫感染症では土や変なものを食べたくなってくる異味症(アロトリオファギー)があるし、犬などではときどきウンチを食べる食糞症(コプロファギー)というのがある。
 |
 |
 |
| これはダッカの車の部品屋街にある店のひとつ。このマニアックなところが、最近はすっかりこぎれいになって少なくなってしまった秋葉原の電気屋街を思い出させる。 |
なぜかダッカには薬屋が多いし、品揃えが豊富である。抗生物質も処方箋なしで入手できるらしい。製薬会社もたくさんある。 |
市場の野菜屋。野菜は年中豊富で安く買える。 |
パリで聞いてきた藍藻スピルリナの栽培場がバングラデシュにもあるはずだと探しまわってショナルガオンという町に見つけて、見にいってきたのが下の写真である。担当者には家にきてもらって、いろいろ説明を受けた。栽培には水の管理が難しいらしく、水質のよい土地で行なうのがキーらしい。土地は少ないが、池や湖や川なら多いバングラデシュの農村地帯のコミュニティで栽培用のプールを管理して農村の婦人たちが収穫して、鶏や牛などの栄養補給に使えないかと打診したが、スピルリナの培養は難しく、コストもかかるし、地域のひとたちにまかせることはできないと、平行線をたどった。もともとはアフリカのチャド湖で自生しているものを現地のひとたちが収穫して乾燥物にして売っていたものだから、それほど高度な培養技術を要求されるものではないはずなのだが。(自分で試してみるから)生のスピルリナを少量分けてくれないかともちかけたが、断られた。かわりに錠剤になった製品をひと瓶、それに中国産とバングラデシュ産のスピルリナの粉末を試供品として1キロずつ貰った。錠剤は毎日服用して、抵抗がないので、なくなると自分でも薬局で買って続けた。しかし、粉末は湯に溶かして飲もうとしたが、まずくて飲めなかった。砂糖をいれれば飲めるのかもしれないがそこまでして飲むものではないだろう。
 |
 |
 |
| これはパリで7月、Sから聞いた藍藻スピルリナの栽培場。探し回って、バングラデシュにもあることがわかったので訪問した。比較的水質が良いと言われるショナルガオンという町にあった。 |
メッシュで掬(すく)って収穫でき、乾燥ののちフレーク状になったものを、そのまま破砕機にかけ粉末にする。 |
粉末にされたものをこの機械で圧搾加工すると、そのまま栄養補助食品として売られる錠剤となる。粉末の状態では水に溶かせても、そのままではまずくて食べる気はしない。しかし、錠剤の形でなら抵抗なく摂取できる。 |
下の写真は日本から送ってもらった食料がネズミに食われてしまった図。日本では郵便を送れば宛先に届くのが当然とされている。あまりに当たり前なので、その郵便制度の価値を忘れがちである。ものは無くなってみてはじめてその価値がわかる。空気も同じ。水も然り。モンゴルでは郵便局へ自分宛の郵便を取りに行くのである。遊牧しているひとには住所がなく、名字が無い国なので、名だけがたよりである。それで結構、問題もなく済んでいる。バングラデシュの郵便制度は中央郵便局でさえ、こんなネズミ事件が起こる。今度はDHLで送ってもらおう。
 |
 |
 |
| 家内に日本からEMSで送ってもらった小包に入っていた食料はダッカの中央郵便局で保管されているあいだに、ネズミに食われてしまった。 |
新潟産コシヒカリ、茨城産コシヒカリの味がわかるネズミらしい。ネズミの糞がいっぱい残されていた。一匹の仕業ではなく、一族郎党を引き連れての大盤振る舞いをしたのかも。 |
楽しみにしていたひやむぎもねずみたちの饗宴に供されてしまった。こういうことはごく日常的なことだと聞いてまた仰天してしまった。 |
ローマから帰ってからの或る週末、こちらは金曜日であるが、のんびり家でくつろごうと思っていたら朝の9時前に畜産普及局の局長のオフィスから緊急電話が入り、政府のヤギ牧場で原因不明の大量死が起こったので至急、調査に加わって欲しいと連絡があった。こういうことは毎度のことなので、慣れている。こういう緊急の際は無理も通り、週末でも気兼ねなく公用車、運転手の手配ができ、普段なら取得に1日かかる国連安全保安部UNDSSからの保安許可(セキュリティクリアランス)も即座に難なく下りる。フィールドに出るときはいつもUNDSSがスタッフ追跡システムで24時間、居所をチェックし、必要なときには誘導しリスクを避けてくれるのである。
アウトブレイクのあったのはインドとの国境に近いラシャヒという町で、片道、車で6時間かかった。朝の11時には同行の畜産普及局の局長と中央疾病研究所の上級研究員とダッカを出発したが、現地に着いたのはすでに夕方だった。
10時すぎまで牧場施設の調査と検死解剖(ポストモルテム)と地域獣医官たちとの意見交換をして、夕食後、宿泊に選ばれたのは「シュガーミル(砂糖精製工場)」という名の、政府の役人専用の宿泊所だった。翌朝、出発するとき、砂糖精製工場というからには本当に工場があるのかいな、と訊いたら隣に下の写真のような政府の工場があって、すみずみまですべて見せてくれた。早朝からトラックで大量にサトウキビが運びこまれると思えば、また自転車で農民によって一抱えのサトウキビが運び込まれている。破砕のための巨大な回転刃、ベルトコンベアー、搾汁装置、ボイラーなどが、天井は高いがさほど広くはない工場内にひとつひとつつながって、こってりした琥珀色の水飴のような砂糖が、最後にさらさらの白砂糖にまで精製されて袋詰めされてくる。「モダーンタイムズ」のチャーリーチャップリンか「千と千尋の神隠し」の「釜爺」が出てきそうなシュールな風景である。ちなみに従業員数1000人、生産量は月に10,000トンで24時間操業らしい。
 |
 |
 |
 |
| トラックで陸続と運び込まれるサトウキビ。 |
自転車ででも運び込まれる。 |
後方のトラックに積まれたサトウキビは手前の回転刃で短く切断される。 | サトウキビ破砕機。 |
 |
 |
 |
 |
| サトウキビをさらにこまかく粉砕。 | 蒸気機関車のようにも見える。 | ボイラーの窓。焚かれているのはサトウキビの搾りかす。この火力で搾り汁の上澄みを煮詰めて結晶化するのだろう | 濃縮の過程だろう。 |
 |
 |
 |
 |
| ベルトコンベアで結晶化された砂糖が運ばれて行く。 | 畜産普及局の局長のうしろの口から精製砂糖が袋詰めされる。 | 袋詰めされた砂糖。 | このサトウキビの絞りかすは燃料として使えるらしい。ボイラーで焚かれているのは石炭ではなく、この絞りかすと言っていた。 |
今後はバングラデシュの名所・旧跡なども訪れたいと思う。