第3回 ダッカからパリへ
18日まで、パリに行ってきた。14日は、巴里祭だった。ジェット機の編隊が、青・白・赤の三色の煙を吐きながらシャンゼリゼ上空に超低空で飛来し、戦車のパレードがキャタピラの音をとどろかせ、夜にはエッフェル塔の近くのシャン・ド・マルス公園で盛大に花火も上がったはずである。はず、というのは、それを見にいったのではなく、それと知らずに過ごして帰ってきたからである。
そうだったのだろうなと思ったのはバングラデシュに帰ってきてからだった。仁和寺の法師ではないが、なにごとにも先達はあらまほしけれ。しかし、戦車を見れば反戦の言葉が自然と出て来る場合が多い世代に属する者にはわだかまることなしに酒を飲んで浮かれるというわけにはいかなかったろう。7月中旬からは休暇のシーズンで、パリを逃れて大挙して南の地方をめざす人びとの車で渋滞の列が続いているという報道があったから、パリは暑いことを承知で行ったが、ダッカから来てみると驚くほどの涼しさである。朝方で気温摂氏20度、日中でも23度。ダッカよりは10度は低いだろう。オペラ座界隈の日本食レストランを探し求めてさんざん歩き回ったあげく、どこも12時にならないと開かないことが分かってあきらめてから、パリ近郊の閑静な、住宅街といった感じのヌイユ=シュール=セーヌにあるMというホテルにチェックインした。
 |
 |
| 14日の巴里祭にはこのエッフェル塔のふもとの公園から花火が揚げられたのだろう。 | ホテルは閑静な住宅街にあるうえに、窓の作りがいいせいか、外の騒音が内ではまったく聞こえない。おかげで、パリ祭の騒ぎも知らないで過ごした。 |
シャルルドゴール空港からメトロに乗ってシャトレ・レ・アルで乗り換えて、オペラ、そこから3番のメトロ終点のひとつ手前のアナトールフランスという駅で降りて歩いて7分の、ブルバールヴィクトルユーゴという通りにある。フランスではいつも値のわりには古すぎたり、シャワーしかなかったりのホテルに泊まった記憶しかなく、期待はしていなかったが、このMは値も張るが、住み心地もよく、4泊した。落ち着いた住宅地でだけあって、旅行者はあまり来そうにないところである。
ほとんどの人が地域に住み着いているような感じである。邸宅というのはなく、たいていがしっかりした重量感のある石造りのアパートで、親近感のわく町である。あちこち近所を歩いているうちに迷って、中学1年生くらいのふたりの息子をおもちゃのように小さいプジョーの後部座席に乗せた若い母親らしい女性にホテルのカードを見せて道をたずねた。「あ、Mホテルはすごくいいホテルよ。連れてってあげるから、乗んなさい」と右助手席に乗せてくれた。エアフランスに勤めていて、空港まで通っているといっていた。スチュワーデスというよりも地上勤務といった感じだ。「どこから来たの?」と好奇心旺盛である。「バングラデシュのダッカから来た」というと、驚いたような表情をして、おもしろがる。「お仕事は何?」「国際連合の仕事をしている」というと、フムフムとうなずき、「でも日本人なんですよ」というと、「で、ここに何をしにきたの?」「ホピタルアメリカンに来た」というと、「あ、ドクターなんだ?」という。「ドクターだけど、動物の医者です」というとまた、珍しがっていた。「息子たちは日本に憧れていて、とても行きたがっている」という。この近くに住んでいるというので、「静かで住み心地がよさそうで、良いところのようですね」というと、よくぞ言ってくれたといわんばかりに、「そうなのよ、このあたりはすごくいいところ、治安もいいし」と、嬉しそうにしていた。地域に誇りを持っているのだ。
 |
 |
| 朝、近所を散歩していたら小雨に降られたので避難したアナトールフランス駅近くのカフェ。ホテルの外で何か食べようとしたら、レストランは開いていなくともこういうカフェは開いている。クロワッサンにエスプレッソを注文すると、いつもクリームが付かずにでてくる。あとで、空港のカフェで、エスプ レッソにちょっとミルクをいれて飲むコーヒーはカフェ・ノワゼットというのだ、と売り子が教えてくれた。 | ホテルから歩いて7分のメトロの駅アナトールフランスへの途中にある食料品店。この右手上の大きな深紅色のサクランボと手前の扁平桃がおいしかったので、ホテルに持ち帰ってよく食べた。こんな形の桃ははじめてだったが、日本では蟠桃、英語でDoughnut Peachとして知られているらしい。 |
ダッカを発ったのは月曜日の夜、予定より1時間以上遅れて9時すぎ、ペルシャ湾のバーレンという国の名で呼ばれる空港で深夜に乗り換え、パリに翌朝の7時半に着いた。その日の4時20分にホピタルアメリカンという私立病院のDr Rの診察を受けに行ったのである。
 |
 |
| オピタルアメリカンの正面。内部は病院特有のにおいがまったくしない。 | Dr Rの執務デスク。 |
どこに行くにも早すぎる時間なので、20年ぶりに旧知のSに空港から電話を入れると驚いたことに昔と同じ電話番号で通じた。田舎に住んでいる年老いた両親を訪れるところなので、夜遅く、9時か10時ころ帰ってきたときにまた電話してほしいという。
|
それに2日先立つ土曜日、ダッカのアパートの西の窓からグルシャン湖をへだてて居間、台所、寝室の窓とテラスから眺められるUホスピタルという7階建ての近代的で大きな病院の外来医師のDr
Sに舌を診てもらったら、デスク越しに身を乗り出して、「友人として言いますが、これは容易くはありませんよ」とギョロっと目を見開いて言う。
先月の30日に、舌に出来ていた腫れが歯に当たって傷ついてひどく出血した。翌朝、起きたら、舌の表面を厚い血餅が覆っていた。出血は止まったものの、その後、跡が潰瘍になった。ベタジンで手当てし、病院を訪れたのはたて混んでいた仕事も片付いた10日後で、傷は治まりかけていた。「すぐにバイオプシーをすることをお勧めします」と言う。舌先の先端から三分の一の位置の真ん中より左寄りの表面に薄い小豆大のふくらみがあるのには気づいていた。記憶をたどると去年の暮れ日本にいたときに小魚の骨が刺さったのをそのままにしていたことが思い出される。しかし記憶というものははかないものである。そんなこともあったような気がする、というところまで、記憶が退行していた。それが最近になってすこしふくらみかけていたところ、食事中に上顎の前歯が接触して、出血したのである。
Dr
Sは外科医のDr
Jにすぐ予約をとって見てもらうようにと指示した。翌日の4時半に病院にふたたび来てみると予約は取れておらず水曜日、14日にならないと会えないという。手術の可能性がありそうなので、それならバイオプシーの段階からヨーロッパかアメリカか日本の病院に行こうという考えが起こった。その旨を上司のS氏に伝えると大変な驚きようだった。シンガポールで心臓のバイパス手術を受けたことのあるS氏はすぐバンコクのN氏と連絡をとってアドヴァイスを求めるように、そして国外の病院で見てもらうことには大賛成だから
パリのアメリカンホスピタル(「オピタルアメリカン」という)は、個人の寄付で非営利団体として創設されて今年2010年で100年になる、ヨーロッパで唯一、アメリカの医療施設評価合同委員会JCAHAO基準をみたす私立総合病院で、日本人医師、通訳もいるという。診療費は高いらしいが保険が使える。月曜日、電話をいれると翌日の4時20分にRoom
6に来てください、Dr Rが診ます、という。仕事を早く切り上げ、Uホスピタルにフランスに行くことを伝え、medical recordの写しをもらうためにDr
Sに会いに行った。「検査をした訳でもないのだからね、(診断書を)あまり深刻にとらないでね」と、前回とは打って変わって言い訳めいてずいぶん弱気である。もっと自分の診立てに自信を持ってもらいたいのに。
そのあと、旅行代理店に行き、バーレン経由、パリ行きのガルフエアーの往復チケットを買い、家に寄って4日分の着替え、夜間飛行の無聊のなぐさめに村上春樹の『1Q84
Book3』と、
マーシー・シャイモフ『「脳にいいこと」だけをやりなさい』の2冊を旅行かばんに入れて車で20分の空港へ直行した。本は日本出発前の昨年暮れに買ってバングラデシュに送る荷物の中に入れておいたものだ。スミレ色のヴェールのついた青い帽子が印象的なスチュワーデスのガルフエアーの機内ビデオには、ウォルトディズニーの新作、ティム・バートンの“Alice
in
Wanderland”があったので、観ながら1Q84を読んだ。パリに着くまでに、読み終わっていた。実写映像とデジタル技術を駆使(モーションキャプチャーといらしい)して描かれた架空のキャラクターたちが同じリアリティをもって存在するのがめちゃくちゃ愉快だった。
指定された時間よりかなり早くオピタルアメリカンに行き、玄関ホールのつきあたりにある清潔で、座り心地のよいソファーもあり、長居をしても気詰まりにならないカフェで『「脳にいいこと」だけをやりなさい』を読んで過ごした。添付されていた欠乏の度合いをチェックする自己診断テストというのを手慰みにやってみたら、セロトニン、GABA、カテコルアミン、エンドルフィンのいずれも不足の傾向まったくなし、という結果だった。ということは気分が落ち着いており(セロトニン)、興奮はクールダウンされており(GABA)、やる気まんまん(カテコールアミン)、ストレスへの抵抗力が高い(エンドルフィン)ということらしい。
Room
6というのは、反時計周りにぐるりと廊下をまわって日本セクションの4を通りすぎたところにある。その途中にある売店で爪切りを買ったとき、向かいにあるATMでVISAカードを使ってEuro(€)のキャッシュを下ろす事が出来ることを知った。ホテルで高い手数料を払ってドルからユーロに換金する必要はなかった。良心的なMホテルのレセプションはうちで換金すると400ドルだと€70の手数料がかかるので、両替はパリで唯一、手数料のかからないシャンゼリゼ通りの両替屋を教えてくれ、Cambioという看板を目印に行くよう勧めてくれたが、面倒なのでホテルで換金したその直後のことだった。日本セクションの前には最近の「週刊朝日」も何冊か置いてある。
Dr
Rは気さくで、年の頃は同じくらいの耳鼻科が専門のフランス人医師だった。一応の経過を述べたあと、舌を診てもらった。どれどれといった感じで、調べ、ゴム手袋をはめて触診したあと、「なんともありませんね」と言う。しかも「バイオプシーをする必要はありません」とも言う。そして消毒薬のボロスチロールを処方してくれた。ベタジンを使っているのだけれど、というと「それはいい。つづけてください」。しかし、なにもしないで帰るのも来た甲斐がない気がして、べつに害はないなら、バイオプシーをやってもらってもいいと伝えたところ、「傷は治りかけているのに、バイオプシーで傷をつければまた、傷を悪化させますよ」と言う。「明日は国民休祭日で病院も休みだから、あさってもう一度来てください」。この診察には、母親が日本人の日仏ハーフの看護士のFさん、日本人医師のDr
Mも立ち会ってくれた。せっかくバングラデシュからやってきたのだから、できるだけの検査をしてもらえないかと言うと、血液検査(扁平上皮癌マーカーを含む)、糞便検査、尿検査、心電図、そして翌々日の15日にはMRI(核磁気共鳴画像法)をしてもらった。 この病院の優れた点は187床の病院でありながら1000床なみの設備とスタッフを抱えていることである。したがって検査はすべて病院内でただちに実施できるし、結果が早く入手できる。胸部X線撮影は日本出発前にしてもらったから省いた。
この13日はホテルに帰って、近所で見つけて目をつけていた「Y」という定食屋といった風情の日本料理店に出向き、チラシ弁当をたべた。日本人がやっているのではなさそうだったが、旨いので、ここには続けて3回通った。身持ちのいい娘が誘惑に負けて身を持ち崩す過程に似て、毒を食らわば皿までもという勢いで、禁制をかなぐり捨てて寿司も食べたし、大胆に刺身も食べた。もっとも、日本国外で生魚を食べないというのもフランスは例外である。調理法にはうるさい国柄だから。
「Y」から帰ると、ひと瓶飲んだキリンビールが効いてそのまま寝入ってしまった。目が覚めたら、夜中の2時だ。9時から10時のあいだにSに電話をいれることをすっかり忘れていた。なにしろバングラデシュと時差が4時間あり、前の晩は寝ていなかったから、時間感覚がまったく機能していなかった。わびのメールを送って、金曜日昼か夜、日本食のレストランへ招待した。オペラ座界隈のブックオフで買った中古本のガイドブックを調べてニコロ通りの「A」を7時に予約した。
ところが、その当日、時間感覚がない上に土地勘が乏しいことから、レストランにたどり着いたのは8時だった。1時間遅れで、エッフェル塔の見える広場の近くの店に足早に駆けつけ、着いたら、荷物はあるがSがいない。「女性の方はなんども外へ様子を見に出られてましたよ」と店の主人が気の毒気に言う。心が痛んで、20年前のことが思い出された。
その昔、パリで学会があった際、苦労してたどり着いたモタボ通りの日本食レストランで10年ぶりに待ち合わせをしたとき、同じように1時間待ったあげくに再会したのだった。モタボ通りがMt
Talbotというのからしてわかるのに手間取った。そのときはどちらも店にいながら、気づかなかったのである。店の店内をはさんで壁際のむこうとこちらのテーブルに付きながら、他の客は入っては出ていれかわるのに、ふたりだけは食べもせず、座っていた。1時間がすぎたころ、ようやくお互いを意識するようになり、「あなたはもしかしてSか?」ときいたら、「そうです、あなたはヤマゲさんですね」ときれいな日本語で返事が返ってきて、はじめてわかった。識別しにくかったのはSは日本では金髪だったのに、黒髪にしていたためでもあった。あれから、さらに20年である。
この日金曜日は病院で、MRIをはじめて体験した。11時からはじまり頭を固定して円筒形のトンネルのなかに頭の方から入って行くのである。楽しい。そもそも、病気らしいことをしたことがなかった。入院経験もないし、12歳の時にただの風邪を結核の疑いがあるといわれて、自宅療養をしたきりである。それも、ツベルクリン既陽性を擬陽性だと間違って医者に伝えたために誤診されたものだった。2テスラらしい高磁場が、耳栓をしていても聞こえる、1秒間に3回くらいの規則正しい音をたてて頭に照射されるのである。ピップエレキバンが80−130ミリテスラらしいからその約20倍の磁束密度である。なんだか楽しい。気のせいだろうが脳内に温感が感じられた。音に合わせて、両眼瞼がリズミカルに収縮するのが感じられた。数分の後、ガドリニウムという造影剤を右腕に静脈注射し、ふたたび6分ほど照射が行なわれた。終った後で、鏡をみると左眼瞼の下に水ぶくれが出来ていた。右こめかみにも小さな腫れができていた。
着替え室で待っていると車いすに乗ったMRI担当のDr
Mが扉を開けて入ってきて異常は見当たらなかったと伝えた。下瞼の腫れは、造影剤に対する一時的な反応だろうとのことだった。頭の縦断面と横断面の断層撮影の画像と診断書は間もなく、待合室で待っている間に出来上がってきた。診断書を封筒から出してさっと目を通すと、”sans
caractere pathologique”, “petite ulceration”, “sans infiltration musculaire”,
“sans diffusion ganglionnaire”, “sans autre anomalie
visible”という単語といくつもの”normaux(正常)”という単語が目に飛び込んで来た。フランス語”sans”というのは“without(無し)”のことだ。一応アテネフランセに通ってフランス語をかじったことがあるのだ。検定試験だっていちばんやさしい5級と4級を同時に受けたら受かった。12時半にそれらの画像と診断書を見ながらDr
Rと面談をした。「ほらね、わたしの言ったとおりでしょ?」と満足気である。「わたしには経験ってものがありますからね」と。
Sと7時に待ち合わせをしている日本食レストラン「A」はシャイヨ宮のあるトロカデロ駅から歩いて10分ほどのところだった。シャイヨ宮の大理石のテラスからのエッフェル塔の眺めはすばらしかった。暮れなずんで、パリの町を一望できる大理石の広場の眺めに見とれて7時が過ぎていることをすっかり忘れていた。写真を撮ったり、旅行者たちと話したりしているうちにもう8時が近いのに気づいてあわてて「A」を探してたどり着いたのだった。
 |
 |
| ふたり乗りのこのような小型車がしばしば目にとまった。 | |
日本食レストラン「A」に、20年、30年前の面影をのこしたSの馴染み深い顔が扉から入ってきた。1時間遅れてもまだ待っていてくれる女性はいまどき日本でもめずらしくなってきている。家内もふくめ、共通の友人が多かったから、話の種は尽きなかった。大皿一杯の刺身、寿司、すき焼きをたべた。老いた親のことを気遣う年代であることも共通である。 当時、Sは四谷駅向かいの紀尾井町にあるJ大学の日本語学科に通うためにフランスから来日していたが、すでに日本語に堪能で、敬語も流暢に喋るので、たいへん人気があった。多くの男子学生から慕われてもいた。練馬区にあった国際学生寮で同じ屋根の下に住んでいた。
|
国際学生寮と名前はしゃれているが、キリスト教系の団体が慈善で経営する格安の木造二階建てのオンボロ寮だった。そこにはいつもかたまって行動する南米出身の日系二世、三世たちや台湾からの留学生の一群のほかに、ドイツ、フランス、イギリス、ブラジル、アメリカ、オーストラリア、香港などからの留学生たちが台所と娯楽室を共有にして住んでいた。そのなかに少数、わたしのような日本人も世話役を期待されてだろう、混じって入っていた。造りが安普請な建物だったので、廊下を乱暴に走ると、床のきしむ、うぐいす張りのような音とともに寮全体が揺れ、木の板の壁を隔てて、隣のもの音も筒抜けだった。アメリカ人同士のカップルができて、傍若無人に夜中に嬌声をあげるので、となりのまだ高校出たてといった感じの学生が「ヤマゲさん、なんとか言ってやってくださいよお」と泣かんばかりに頼みにきたこともある。そうすると「もう少し、ひとのことも考えて静かにやってくれないか」と苦言を呈しにゆくのがわたしの役回りだった。
女子学生の方はカリフォルニア大学のサンディエゴ校からJ大学に留学していたが、英会話学校の講師に雇われて生活を大いにエンジョイしていた。畳敷の彼女の部屋の中では、ウサギを放し飼いにしていた。台湾からの留学生は、裕福な者は別として、中華料理屋で皿洗いなどをして学資をかせいでいるものもいた。家族で来ていたKさんは歯科医で、よく窓際の勉強机で粘土をつかって実技試験のための指の訓練をしていた。みごと初回で、日本の国家試験に合格すると、東京近郊の無医村にある村営の歯科医院の院長として単身赴任して行った。ブラジルから診療実習のためにN大学病院に留学していた医師のZは自費留学なので、とても切り詰めた生活をしていた。
Sは日本からフランスに帰国後、パリで一時期、日本政府機関で秘書のようなしごとをしていた。いまは健康食品などの販売会社に勤めているらしい。
バングラデシュでは庭先で飼われている放し飼いのニワトリやアヒルが家禽総数の半数を占めており、主婦がその世話をしている。そのほとんどがせいぜい1軒あたり10羽未満の数だが、鳥インフルエンザが起こって死んだり、殺処分されてしまうと一家にとって大きなダメージを与えてしまう。というのは、庭先養鶏のほとんどが田舎で、雇用の機会のない中、卵を売ることが女性にとってほとんど唯一の現金収入の方法であり、かつ卵がこどもたちの貴重な栄養源、たんぱく源になっているからである。小銭であっても、主婦が家計の収入の獲得に参画することにより、女性の家庭内における地位と発言力を維持することができる。「卵がない場合、それに代わるなにかキャッシュに変換できるものはないのかな」というと、「スピルリナはどう?淡水で育ち、たんぱく源にもなる。ハワイやブルキナファッソなどで栽培が行なわれている」という。「バングラデシュのような、標高が低く、川や湖が非常に多いところでは栽培の可能性は大きいかもしれないが、でもそれが売れるのかな」というと、「わたしの会社が買う」という。
たらふく食べて、夜も更けてメトロで帰るとき、途中で下車する間際、真顔になって「あなたのやっていることを尊敬します」と言い残していった。今度、会うのはいつになるのだろう。
このフランスへの突然の予期せぬ旅に先立つ4日前の晩、アパートに40人を招待してパーティをした。2年半勤務したLが契約満了で辞めるにつきその送別会と、それにナショナルのポジションからインターナショナルのポジションに格上げしてコンサルタントとして3ヶ月ネパールに赴任が決まったKの壮行会もかねてである。
バングラデシュに来て、家で開くはじめてのパーティだったから、料理は「A」ホテルに仕出しを頼み、参加者のリクエストに応えてダッカ市内の日本食レストラン「S」から寿司を注文した。安全を考慮して、卵巻き、カッパ、たくあん巻き、それにマグロの巻き寿司にした。アルコール類は免税の店で買った。
物品調達係のSがほとんどの手配をやってくれて、アルコールもどれだけそろえればいいのかのアドヴァイスもしてくれた。ビール120缶(ハイネケン96缶、バロンビール24缶)、ワイン赤3本、白3本、ウィスキー6本、ジン5本、ウォッカ1本、コニャック1本。最初、その半分の量だったが、少ないと後から皆から恨まれるので増やしてくれないかと言って来た。回教国では酒類は入手が困難だが、酒好きなものは本当に好きである。このSはアパートの契約の際、大家との交渉で大いに世話になった。家具付きということだったが、こちらから言わなければほとんどなにもなかったところ、ソファセット、エアコン6台、冷蔵庫、電子レンジ、キッチンテーブルセット、天井のファン8機にカラーテレビを要求してくれた。そして、契約書類のなかの、一年後、家賃を値上げするものとするという条項を削除させるのに成功したのである。
パーティ前にそれらのアルコール類をテーブルに並べて置いておいたら、「危ないので」自分が管理すると言って、台所の開き戸棚に隠し、必要に応じて出すという。パーティは食べ物が豊富だったこともあり、皆大喜びだった。箸でたべる寿司も珍しがられて大好評だった。終わりに近づいた頃、わたしの好きなクバジエを飲もうと皆に言って、出そうとしたらボトルが見つからない。そんなはずはないのだが、と探してもない。おかしいな、開けた記憶もないのに、と首をひねっていると、居並ぶなかでひとりひげ面のSだけが、片目をパチパチとウィンクしている。Kは「あまり深く追求することはやめよう」と言う。その翌日、瓶を数えてみたら、ビールも40缶以上残っていたし、赤、白ワインはいずれも2本手つかず、ジンも3本、ウィスキー2本も残っていて、おおいに盛り上がっていたわりには、意外と飲む量は少ない。しかし、クバジエとジョニーウォカーの黒が瓶ごとなくなっていた。こんどパーティを開くときには残った酒類はあみだくじかなにかをして、希望者に持ち帰りさせることにしよう。(2010年7月23日)
 |
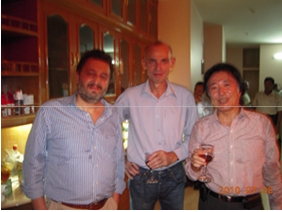 |
| 大好評だった巻き寿司。 |
真ん中は主役のL,左はイタリー人のC |