第1回 東京からダッカへ
 |
|
日本を出発したのが昨年12月15日、寒いさなかだった。 |
東京からダッカへ来て、あと1週間で、はや3ヶ月になろうとしている。そんなときに腹を下した。来て早々から、1ヶ月近く、ホテル住まいであったが、昼食は事務所の仲間と地元の大衆食堂で、現地の食べ物ばかりを食べていたのに、一度も食あたりをしたりしたことはなかった。こちらの食べ物は、たいていカレー味で、チキンやビーフにナンやチャパティ、ライスを付ける。食事のマナーとして、右手の指を使って、すしをつまむような手つきでたべる。ナンやチャパティは問題ないが、ライスとなるとボタボタとテーブルにこぼしてしまう。十日目ころに、毎日カレーを食べることに食傷して、食事量が減った。それでも腹を下した事はなかった。
あるとき、ローマとオーストラリアから客人が来訪したとき、ダッカのSという日本食の店に行こうと1人が言い出した。海外で、生魚を食べることにはとても警戒心があって、滅多に食べない。アメリカでもヨーロッパでもアフリカでも余程のことが無い限り、たとえば大使館で日本人コックさんが寿司や刺身を手ずから握ってくれ調理してくれるような場合以外、敬遠する。それがこのときばかりは、ローマから来たKが、日本食はイタリーでも食べ慣れているから心配要らない、Sという店は、名前は聞いて来たので、ぜひ食べに行こうと積極的だった。刺身が格安で食べられて、しかも旨い。
この国のレストランではアルコールは出ないのが普通である。しかしアメリカンクラブとかダッチクラブ、インターナショナルクラブというような限られた会員制の店なら出るし、外国人客の多いところでは瓶の持ち込みを許すところもある。このSではハイネケンのビールが飲めた。アルコールは日本でも滅多に飲むことはなかったが、バングラデシュに来てからもほとんど飲む事はなかった。おおいにのんで、食べた。翌日、なんの異常も起こらなかった。ところがKが寝込んだ。大切なミッションなのに2日間ホテルで寝込んだ。毎日、旅先でも10キロは走るという若く精悍な男なのに、年とって老いぼれた気分じゃと弱音をはいていた。
そうこうするうちに、先日、朝食を抜いてしまって、しかも昼食時間にミーティングが入って、2時近くになった。ほとんど腹から力が抜け、帰る車の運転手を止め、ファーストフードCの店に駆け込んでピザのテイクアウトとコーラを買って移動中の車の中で食べた。ソーセージの固まりの入っているパンのような、ピザらしくないピザだった。あまりの空腹感だったせいか、食べても妙に満たされる気がしなかった。その夕方ころから腹の具合が悪くなった。元気がなくなり、オフィスのソファで呆然と座すのみだった。夜になって帰宅してから、いっそう悪くなった。今朝、出勤してスタッフに告げると、「ファーストフードってのは気をつけないとあぶないのじゃ」と言っていた。いつも昼食を食べている地元大衆食堂の方が、みすぼらしいながら、安全なのかなあ。
24年間、スイス、アメリカ合衆国、ケニアなどの研究室で過ごしてきたから、ラボのない職場というのははじめてだった。そしてアジアの国々を頻繁に訪れるようになったのもこの職場に来てからだ。それまで、アジアといえば、学生時代に友だちと訪れた韓国と、その後、仲間と旅行で訪れただけの台湾しか知らなかったのが、ベトナム、インドネシア、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ホンコン、中国、ラオス、ミャンマー、タイをどっぷりと浸かるほどに訪れるようになり、国や地域ごとに色が違って面白い。モンゴルでは7月のオオハクチョウの換羽期、キャンプをしながら山階鳥類研究所の人たちの助けをかりて捕獲をした。朝から晩まで、ランドクルーザーで走ってもまだ見渡す限り風景が草原だけというのは得難い体験だった。換羽期は7月の半ばの2週間とかぎられているので、同じく換羽期のオオハクチョウを追って、同じ地域に来ていて、たびたび遠くを走っているのが見られたFAOのグループがいまは仲間なのだから面白い。そのグループの一部が1週間前から、バングラデシュにアメリカやインドから来て、鴨を捕獲しては衛星追跡装置を装着している。今までに世界中で500羽の鳥に衛星追跡装置を装着して渡り鳥の移動をリアルタイムでモニターしている。
FAOへの採用が決まってから、バングラデシュに赴任することになることがわかって驚いた。ベトナムとか東南アジアのよく知っている国を想定していたからだ。バングラデシュをはじめ、南アジアへはどこの国にも行ったことがなかった。したがって、12月15日に日本を出国して、バンコクでブリーフィングを受けた。どんな注意が必要だとか、いろいろアドヴァイスがあった。
 |
 |
| 到着の日、スタッフのうちの主としてインターナショナルの者が歓迎の夕食会を催してくれた。 インターナショナルスタッフの国籍はオランダ、オーストラリア、ミャンマー。インド料理の店で、ワインは持ち込みだった。普段はローマのFAO本部にいる者やオーストラリアの大学で教授をしている者もいる。 到着早々から、ナショナルの新スタッフの採用面接を続けざまにすることからバングラデシュ暮らしは始まった。 |
バンコクの地域事務所にて、副代表のKさんと越境性動物疾病緊急センター(ECTAD)の地域マネージャーのM氏。 |
バングラデシュの観光ガイドがほとんど無いに等しいのにも驚いた。観光化の波にまださらされていないのだと言える。来て住んでみて納得した。ほとんど観光のための体制が出来上がっていない。ベンガルトラのいるダッカ国立動物園も年間三百万人の入園者が訪れる動物園でありながら、外国人は少なく、掲示や表示がバングラデシュ語だけだったりする。上野動物園でさえ、ジャイアントパンダのリンリンが死んで以来、年間三百万人を割ってしまっている。老朽化している設備を新しくし、ベンガルトラをプロモートすれば外国からでも見に来る人はいっぱいいるのにと思う。
元旦の日、年始のお参りのかわりにこの動物園まで、ベンガルトラを見に行って来た。入場料は破格に安く、地元の子連れの家族たちの憩い場所といった感じである。このときの写真を日本の友人たちに送ったら、大変好評だった。なにしろ、ベンガルトラは世界に三千頭しかいない絶滅に瀕している希少種で、その大半がバングラデシュにいて、しかもことしは寅年だ。
出国前には、時間的に間に合いかつ、受けられるワクチンはすべて受けた。すでに受けているHB以外のA型肝炎、日本脳炎、季節性インフルエンザ、新型インフルエンザのワクチンを接種してもらった。又マラリア予防のためドキシサイクリンを365錠貰った。
ダッカに着いたのは、日本と同じくらい寒い12月19日だった。南の常夏の国を想定していたので、外套は脱ぎ捨ててやってきたのだった。とても寒い国だというのが印象深かった。例年にない気温低下だったようである。
最初はスーツだけで過ごしていたが、公用車で送り迎えしてもらい事務所で仕事をする上では問題はないものの、昼食時に近くに出るときがすごく寒かったので、1月の半ばに市場の衣料品店へ外套を買いに行った。概して、こちらの衣料品は品がよく、値が安い。エスキモーがアラスカで着ても喜びそうなのを買った。
値が安く、品がいいのは繊維・ガーメント(縫製品、衣服)産業はこの国の外貨稼ぎの主力で、輸出所得の8割方を占めるため、レベルが高く品が豊富だからだろう。そのせいか、朝、8時前の出勤時には、色とりどりの服をまとった若い女性が集(つど)ってさっそうと勤めにでる姿がいたるところで見られる。日本で言う、お針子さんなのだろうが、こちらでは日本で昔あった紡績工場で過酷な労働を強いられた女工哀史のような悲惨さはまったくない。こちらでは平均的な女性の職業なのだろう。識字率が50パーセントを切るこの国では、女性の職業選択範囲も限られている。与えられた社会的諸条件を疑問もなく受け入れているように見える。英語圏でも長時間低賃金で劣悪な作業場で働くところをSweatshop搾取工場というが、この国では比較的恵まれた職業といえる。
 |
 |
|
家畜局の局長への表敬訪問は着いて4日目に行なった。 こちらの人は話好きで、話しだすと長い。しかし、そんななかでも図抜けて長話を会議でする人がいて、放っておけばいつまでも話しやめないので、はじめは局長が咳払いをしたり、そわそわしたりして暗にシグナルを送るが、それでも止めないでマイクをもぎ取られることもあった。 |
主としてナショナルなスタッフが歓迎のサプライズをしてくれた。 花を抱えているもう1人は、いままでチーム代表の代行をしてくれていたオランダ人獣医師のL。 ナショナルスタッフのなかには現職の大学教授が1人、それに今はもう1人いる。 前の女性は有能な秘書のA. スタッフはとても優秀である。 ウパジラ(バングラデシュの行政単位で村よりは大きいが郡よりは小さい)の獣医師の研修のときなどにはオープニングの挨拶をするのも大切な役割で、”You are at…”と言いかけて、少し言い淀もうものなら”Upazilla”とそばからプロンプトが入る。”a frontline in a battle against avian influenza and other diseases”と言うつもりだったのだが。 “260 Upazilla out of ….“なら、 ”482“と小声で言ってくれる。 |
この局長Dr Rは、面談が昼食時に及ぶと、「昼食をオファーしてもいいかな」とたびたび食事を注文してくれた。手づかみで食べることを覚えたのもこのとき以来である。スタッフにきいたら、食事をだすことは滅多にあることではないということであったから、良くしてもらったと感謝している。
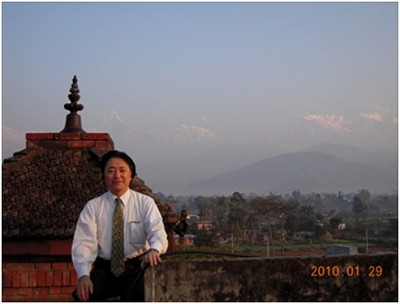 |
|
ネパールのリゾート地、ポカラで会議が開かれたときのもの。 |
ついこの間、この局長が代わり、XXXX部の部長が局長に昇進した。それから間もないある日、同じ部の副部長だったBが、夕方、オフィスへやって来た。新人事が発表されたという。「上がったのか、下がったのか?」と聞くと、上がったと、口の両端を横に目一杯つり上げて嬉しさを顔から発散させていた。頬が競り上がって顔がミッキーマウスに見えた。強面(こわもて)で何となく政治力もありそうな男なのに、無防備に子供のように喜んでいた。おめでとう、と言ってあげたら、まだ名刺もできてなくて、と言って古いDeputy
Directorと肩書きの載った名刺のDeputyのところにペンで線を引いて消して1枚くれた。今度の国際会議には政府代表で出席したいと言っている。その会議には政府から政策と技術の両面からそれぞれ1名ずつ出席できるので、かれが行く上では問題はないだろう。
越境性動物疾病の会議の最中、このポカラでHPAI
H5N1のアウトブレイクが起こった。打ち上げのあったこの日の晩、カリング(殺処分)が実施されるという知らせが入った。緊張した空気が流れた。去年はじめにこの国でははじめてHPAIのアウトブレイクが2度続いておこり、それ以来のものだった。
ポカラのみならず、ネパールでは日本人の評判が全般的にすこぶる良いのには驚いた。カトマンズの空港では、同行者は荷物検査をこまかくやられたのに、わたしの番のときには「日本人か?」とだけ聞かれて、「その通り」と答えたら、「よし」の一言で、検査もされずに通してくれた。しばらく冗談の種にされた。
 |
 |
| めずらしい食べ物を食べさせてくれるというので宿泊のホテルからバスをチャーターして全員で食事をしに行ったのがこのホテル。 巨大な掘り炬燵があってくつろげる。 |
よく日本人が利用するらしく、本棚には日本語書籍がいっぱいあった。学生のころ熱中して読みあさり、後年アフリカから帰国後、目黒区碑文谷のご自宅まで通って教えを受けたなつかしい故川喜田二郎先生の著書 がいくつもあったので、いくらでも出すから売ってくれと頼んだが、日本人の宿泊客のために置いているのでと断られた。 |
 |
 |
| ベンガル湾の夕日を背景にしたもの。 この海岸の陸側にはマングローブの林があり、野生のベンガル虎がいる。一度、野生の虎を見に行きたいなと思っていた矢先、この地方で沿岸環境保全センターの所長をしているR氏と知り合いになった。 しかし、ここまで、ダッカから車でくるのは10時間くらいかかりたいへんだった。しかも3回フェリーで川を渡った。 |
ダッカのタイレストランにて。 FAOバングラデシュにはわたし以外にあと2人のCTA(Chief Technical Advisor/Team Leader)がいる。 1人は食品安全専門のニュージーランド人、もう1人は食品行政専門のイタリー人大学教授。これはローマから来訪したDr Kを歓迎して開かれた夕食会。 |
ベンガル湾に面した町クワカタに来ているとき、2月9日コックスバザールで今年になって8つ目のアウトブレイクが起こった。
Lともう1人を15日にポストアウトブレイク調査に送ったところ、調査のさなかにまた発生が起こった。必要なだけ留まって必要なことをするように指示を出し、18日には自ら現地に赴いた。
 |
 |
| コックスバザールの空港に到着したところ。 折から連休で、リゾート地のコックスバザールは航空券の入手やホテルの手配も容易ではなかったが、予定通り到着できた。機内には裕福そうな子連れのバングラデシュ人親子などが多い20人乗りの双発機だった。 出迎えてくれたのは、コックスバザールの家畜保健所の所長。到着してはじめて、またアウトブレイクが起こって、その晩カリングを実施するということを知らされた。 |
カリングは夜行われるという。 後ろの小屋はその現場の鶏舎。まだ鶏が死につつある。 |
 |
 |
|
これはダッカ市内の家のちかくにある地区での風景。 |
クワカタからの帰路、名物のヨーグルトを買いに立ち寄った町の路地の中で見かけた風景。 |
 |
 |
| コックスバザールのアウトブレイク現場の敷地内にて。 赤いシャツはウパジラ家畜保健所の獣医師。右はダッカのFAOから同行したスタッフのK. とても有能で、今度バリ島での国際会議に出席することになっていたが、同時期にあるワシントンDCでのリーダーシップ養成プログラムという2週間のアメリカ政府の研修の受講者として選ばれたのでそちらの方に行く事にした。 左に黒マスクをしているのは養鶏場のオーナーのこどもだろう。 |
同じくコックスバザールの郊外にある庭先養鶏農家を訪れた時のもの。いくつなんだい?と英語で聞いたら、12歳と英語で答えた。 |
 |
 |
|
ベンガル湾で出会った水牛飼いの少年。 |
ほとんどの家で庭先養鶏が行なわれていた。こどもたちはたいへん人懐っこい。 |
 |
 |
|
コックスバザールの庭先養鶏農家の少年少女たち。なにをしに来たのだろうと興味しんしんで集まってくる。わたしも子供のころは伊勢志摩に育ったから、真珠を買いに世界中から集まってくる中国人やインド人、アメリカ人の商人たちがとても珍しく思えたので気持ちはわかる。 |
これはダッカ市内の繁華街にある生鳥市場Live Bird Marketの風景。 |
おとといの夜から始まった腹の調子はまだ相変わらずだが、元気は回復した。(2010年3月9日)。