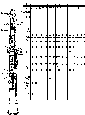 もお見せしよう。オクターブ上のBから上の音は、フランス式は第2オクターブキーを用いているが、ウィーン式はEsなどの12度上の倍音を用いて鳴らす。その方が気柱が長く、良い音がするのである。
もお見せしよう。オクターブ上のBから上の音は、フランス式は第2オクターブキーを用いているが、ウィーン式はEsなどの12度上の倍音を用いて鳴らす。その方が気柱が長く、良い音がするのである。ハンス・ハダモフスキーはアレクサンダー・ヴンデラーの弟子で、ヴンデラーはカラヤンに指揮法を教えたこともある教授であり、作曲家でもあった。
ハダモフスキーは1936年からウィーンフィルのメンバーでオーボエとイングリッシュホルンの奏者であり、彼の伝統に忠実な音色から音楽アカデミーの教授になった。伝統に忠実とは簡単に言えば、ヴィブラートをかけないまっすぐな音であり、フランス式の奏法との混在をおそれたハダモフスキーはその伝統を未来に正しく伝えようと考え、多くの理解者の支援の下に、全10巻から成る教則本を発行することを決意した。
1.基礎技術、2.短い18のエチュード、3.古典様式の曲集(ヘンデルの作品を中心に)、
4.音階と分散和音、5.音程練習、6.新旧のオーボエ音楽(合奏練習用)、
7.オーケストラスタディー、8.リード作り、9.オーボエ設計・歴史・演奏者・文献、
10.記録(自筆譜からオーボエソロの部分、レコード・テープ)
であったが、6、9、10は未完で、8は原稿は完成したが、紛失し、7はオーケストラパートをピアノに書いた伴奏まで付いた超スグレモノだが、鉛筆書きの段階で、ハダモフスキーの家を出ることはなかった。出版された巻は「ウィーンの楽音様式」研究所著著シリーズとして、出回ったようだが、何と実は著者自身が自宅で購入した輪転機で印刷した物である。勿論全て手書きである。ヨーロッパのレストランのメニューを書いた黒板上の文字を思い出していただければ、日本人にとっていかに読みにくい物かは想像できよう。
私はハダモフスキーの愛弟子であった芦野純夫さん、日本人で初めてウィーン式オーボエを持って音楽アカデミーの門をたたいた清水恵士さんから原本をお借りした。自分のために、そしてひょっとしてハダモフスキーへの強い共感をもつ世界中の同志のために、まず第1巻のワープロ入力(独語)、和訳を敢行した。楽譜も楽譜ソフトを用いた。ドイツ語が正確に読みとれているかは、ハダモフスキーの娘婿である音楽アカデミー教授のローレンツさんにチェックしてもらった。全体はページメーカーに入れて独・和対応形式にしてみた。164ページの本巻と付録のピアノ伴奏譜37ページで、オリジナルとほぼ同じページ数に納めることができた。おそらくドイツ語からのヨーロッパ言語への翻訳は自動翻訳も可能であろう(ルデュック社のように)。和訳についてはとりあえず、直訳調で、できるだけ日本語化した英語を用いず、オーストリアへの郷愁を阻害するいっさいの要素を排除した。
多くのフランス式の教則本にはヴィブラートについての説明があるが、ここにはもちろんない。その代わりと言うわけではなかろうが、巻末には循環呼吸法の説明がある。「これができないと演奏できない曲はあるが、ヴィブラートは教える必要がない」とローレンツ先生の弁。
また誰でも辛いロングトーン練習にピアノ伴奏が付き、リズム・音程を常に正しく感じながら練習することと、練習自体が楽しい物であることを初心者に植え付ける目的もある。
ご興味のある方のために、運指表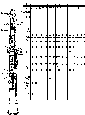 もお見せしよう。オクターブ上のBから上の音は、フランス式は第2オクターブキーを用いているが、ウィーン式はEsなどの12度上の倍音を用いて鳴らす。その方が気柱が長く、良い音がするのである。
もお見せしよう。オクターブ上のBから上の音は、フランス式は第2オクターブキーを用いているが、ウィーン式はEsなどの12度上の倍音を用いて鳴らす。その方が気柱が長く、良い音がするのである。
ただし、この伝統の音を守ろうというハダモフスキーの信念は、芭蕉の俳論の「不易流行」のごとしである。流行とは、3000人収容するホールでベートーヴェンの時代のピアノを鳴らしても響かないから、ベーゼンドルファーを用いたりする、オーケストラの編成を大きくする、奏者の心の琴線の揺動が自然に表われたヴィブラートを認める、などである。不易とは、ウィーンの音楽魂であることは言うまでもない。これを理解できないメンバーや指揮者がいることも事実なので困る。
私のDTPとして作ってみたものの、製本した物が6冊(芦野さん、ローレンツさん、小畑善昭さん、松沢増保さん、ドレミ出版の知人に一冊ずつ)で、ルーズリーフ形式にしたものが1組あるだけです。HDには約10MB占めています。