

| 事故概要・はじめに |
信号機のない丁字路交差点。片側一車線優先道路を進行中の乗用車に、一時停止標識のある左方交差道路から右折侵入してきた軽乗用車が衝突した物損事故で、判例タイムズ・事故類型図【95図】が適用される事故。
加害車両運転者は、右折侵入するにあたり、交差道路左方の安全確認を注視するあまり、進行方向である右方の安全確認を怠り侵入した結果の衝突事故だった。保険会社(東京海上日動)は例によって、判例タイムズを機械的に適用し、基本過失割合10対90をそのまま提示してきた。
被害者は同意することなく、当然のごとく、加害車両・過失加算修正要素である<著しい過失ー前方不注視の著しい場合>の具体的例示としてタイムズに記載されている<脇見運転>の採用を要求した。
事故交渉担当部署となったのは、<横浜損害サービス課>だ。
交代3人目の新たな担当となった男性社員は、事故担当者としてどのような理屈を駆使して<脇見運転>の採用を拒否してきたのか。現実の事故交渉においてよく問題となるテーマだけに、目を通す価値ありと考え公開することにした。
保険会社に対して、<脇見運転>を修正要素として採用することを要求するケースは、交渉実務においてはかなり多い。
そういう意味において、保険屋としての正体を露わにした事故担当者が、どのような理屈をこね回して、採用要求を拒否してくるのか。その実態を知っておくことに損はないと考える。保険屋としての敵の戦略を知る上において貴重な教材を提供したいと思う。
ちなみに、<保険屋>とは、保険会社・事故担当者としての誇りも良心のかけらも失った、目先の利害関係のみの執着に終始する存在に成り下がった担当者のことだ。蔑んで、こう呼ばしてもらっている。
交渉にあたり、横浜損害サービス課・課長代理と名乗る人物は、次のような見解を書面で提示してきた。
はじめに、この書面から紹介することにしよう。
| 課長代理見解書面 |
①脇見運転とは、東京海上日動ホームページに記載されているように、「前方を見ないで運転すること」である。
そして、具体的には、続いて記載説明されている「携帯電話・カーナビを操作しての運転」・「景色・看板などを見ながらの運転」・「助手席・ダッシュボードなどから落ちたものを探したり、拾ったりしながらの運転」等をいう。
②丁字路交差点侵入にあたり、左右の安全確認のため右方を確認した後左前方を注視して、結果として右方の安全確認が疎かになった状態で走行するのは、脇見運転にはあたらない。
交差点侵入に当たり、より注意を要した左方の交通状況の確認のため左方を注視しての走行であるから、前方を見ての走行といえるからである。
◆<コメント> この課長代理なる人物は、電話での対応でこちらが、自身見解の書面提示を要求したが、はじめ、見解の書面提示を拒んできた。交渉は事故担当者がするのであるから、その者と交渉してほしいとの理由からだった。
そこで一計を案じて(笑)、嫌でも書面提示せざるを得なくなる状況に追い込んだ結果、提示されてきた書面が、上記の書面だ。ある意味攻撃材料として今後役に立つ有益な資料になると考えたからだ。
ここから、彼の部下である男性事故担当者との間で、タイムズ修正要素「脇見運転」採用をめぐっての本格的な攻防が始まった。

| 質問書面 |
①前担当者は、左方を注視し「右方向の安全確認が疎かになった状態」での交差点右折侵入は、「脇見運転」ではないと書面回答している。あなたの上司も同見解だ。「脇見運転」ではないとの論理的理由を再度説明願いたし。
②東京海上日動はHPの中で、「脇見運転とは、前方を見ないで運転すること」と説明している。「前方」とはいかなる範囲をいうのか?
| 担当者・回答書面 |
①右方より左方の安全確認がより必要であたため、左方を注視しながら交差点侵入したもの。
安全に車を運転する上での必要な動作を行っていたのであり、「携帯電話・カーナビを操作しての運転」・「景色・看板を見ながらの運転」・「助手席・ダッシュボードなどから落ちたものを探したり、拾ったりしながらの運転」等と同様な脇見運転にはあたらない。
②前方とは、安全に車を運転する上で、安全を確認すべき範囲。
| 質問書面 |
①脇見運転の具体例として、あなたが、「景色・看板を見ながらの運転」を挙げていることから、交差道路左方出入口部分に「進入禁止標識」が設置されていないかどうかを注視しながら右折進入する運転行為は、脇見運転にあたると考えるが、あなたの見解は?
②「前方」の説明はいかなる根拠文献に基づくものか?安全に車を運転する上で、安全を確認すべき範囲には、進行方向右方の安全確認も含まれるのではないのか?
| 担当者・回答書面 |
①本事故とは状況が異なる為、回答致しかねる。
②右方を確認し左方に注視しながら交差点に侵入したものであり、右方の安全確認が疎かになったこと、前方不注視であったことはこれまでの主張同様認めるところであるが、著しい前方不注視にはあたらないことを再度主張する。
| 質問書面 |
①「右方の安全確認が疎かになった」かつ「前方不注視」の状態で交差点に右折侵入した結果、衝突して初めて被害者の車の存在を認識した、と加害者が説明している。この事実から、右方向を注視することなく交差点に右折侵入したことは明らかだ。あなたの見解は?
②再度問う。道交法70条に違反する「脇見運転」とは、具体的にどのような運転行為をいうのか。
③再度質問する。前方とは、安全に車を運転する上で、安全を確認すべき範囲」との説明はいかなる文献に基づくのか?
安全に車を運転する上で、安全を確認すべき範囲の中には、「進行方向である右前方の安全確認も含まれるのか否か?回答されたし。
| 担当者・回答書面 |
①右方より左方の安全確認がより必要であった為、左方を注視しながら交差点侵入したことにより、右方の安全確認が疎かになったことはこれまでの主張通り。
②「携帯電話・カーナビを操作しての運転」・「景色・看板を見ながらの運転」・「助手席・ダッシュボードなどから落ちたものを探したり、拾ったりしながらの運転」等
③右方の安全確認が疎かになったことはこれまでの主張通り。前方の解釈等は本件の過失割合に影響のあるものとは考えていない。
| 質問書面 |
「前方」の説明は、たんなる思いつきによる説明だったということか?
東京海上日動HPが「前方を見ないで運転することが脇見運転だ」と明示している以上、「前方の解釈等は本件の過失割合に影響のあるものとは考えておりません。」などという、根拠文献を提示できないがための、事故担当専門職業人にあるまじき女々しい的外れの弁解は、小学生にも通用しない。
再度問う。あなたが説明した「前方」の内容は、いかなる根拠文献によるのか?
たんなる思いつきの説明ではなかったというのであれば、答えなければならない。
| 担当者・回答書面 |
「前方」の解釈にこだわりがあるようですが、これまでに回答したように右方の安全確認が疎かになったものの、まったく右方を見なかった訳ではない。当方契約者様の主張としては、丁字路交差点進入にあたり右方を確認した後、左前方を注視して交差点に侵入したもの。よって右方も(疎かな状態ではあったが)確認していることから「前方を見ないで運転する」脇見運転にはあたらないと考えるものです。
当方契約者の安全確認動作が「前方不注視」にあたるとしても「著しい前方不注視」や「「脇見運転」に当たらない動作と考えており修正要素にはあたらないと主張するものです。
◆<コメント> 担当者はこのような理屈をこね回す。まさしく、<保険屋>としての屁理屈そのものだ。
右方の安全確認が疎かな状態になった状態で右折進行したから、「前方不注視】の状態で右折進行したことは認める。だが、右方をまったく見なかったわけではなく、疎かな状態ながらも一応右方の安全確認はしている。だから、「前方不注視の著しい場合」に該当する脇見運転にはあたらない。
| 質問書面 |
「前方注視には、進路の前方のみならず、当面の進路の左右に対する注意も含まれる。」<警察時報社刊・自動車事故による業過犯の捜査134頁>
出典根拠となる文献も提示できない思いつきの説明は、事故担当者として、してはいけないということだ。
あなたは、加害車が「右方の安全確認が疎かになった状態」で丁字路交差点に右折侵入した、とさかんにその点を強調しているが、
加害者がどのような「心理状態」で右折侵入したかという、加害者の内面における心理状態は、他人には判断ができないということだ。その判断を強いてしようとすると、あなたが展開している説明のように、自己側に都合の良い勝手な恣意的判断になるという当然の結果を導き出すことになる。
運転者の内面の心理状態は、結局のところ、行為の結果として外部に残された痕跡及び行為者の供述説明等によって推断するほかはないということになる。事実、裁判官も事実認定においてそのような方法をとっている。
「疎かな状態での右方確認は、右方をまったく見ないことではない。だから脇見運転にはあたらない」というあなたの説明は、たんに言葉をもてあそぶ、言葉あそびの域を一歩も出るものではなく、なんの説得力もないということに気づかなければならない。
あなたに質問したい。
①加害車は被害車の存在を認識しないまま右折侵入した結果、衝突した。
この事故状況事実を認めるか否か答えていただきたい。
②加害者は事故現場で「衝突するまで事故相手車両に気づかなかった」ことを認めている。
この事故状況事実を受け入れるかどうか答えていただきたい。
警告として申し上げておくが、あまりにも説得力のない回答をよこすようであれば、あなたには担当者能力なしと判断して、新たな担当者との交代を申し出ることになるという○○氏の伝言を伝えておきたい。
◆<コメント> たんなる事実関係の確認質問書面であるにもかかわらず、1週間経っても回答をよこさない担当者に、直接電話をかけて心理的に揺さぶりをかける作戦に出ることにした。
![]() 「たんなる事実関係確認の質問に何故すぐ回答をよこさないのか?」→「ただいま検討中です。今しばらく待って下さい…。」
「たんなる事実関係確認の質問に何故すぐ回答をよこさないのか?」→「ただいま検討中です。今しばらく待って下さい…。」
![]() 「悪あがきはやめたらどうか…?脇見運転を認めたら、傷口を広げなくてすむのでは…?」→「お断りします。脇見運転を認めることはありません。」
「悪あがきはやめたらどうか…?脇見運転を認めたら、傷口を広げなくてすむのでは…?」→「お断りします。脇見運転を認めることはありません。」
面白いことを言う担当者だ…(笑)。事実確認になんの検討が必要というのか…。意味不明な受け答えだ。
これら①・②の確認事項を互いに肯定した前提のもとにこれまで交渉をしてきたにも関わらず、改めて確認回答を求めると躊躇している。肯定すると脇見運転を認めざるを得なくなると警戒していることがありありと読み取れる。脇見運転否定の主張論理が危うくなったことを、愚かなりにも薄々理解したのだろう。実に姑息な担当者だ(笑)。利害関係に敏感なところだけは、まさしく保険屋そのものだが…(笑)。
「脇見運転を認めることはありません」と言うときの口調だけは、いやにはっきりとしていたことが妙に印象に残った。
★1月29日・回答要求書面FAX提示⇒三度目の催促で、回答書面・2月19日に来る
◆<コメント> 再三の書面回答催促をしたにもかかわらず、いっこうに書面回答をよこしてこない事故担当者。一体どういう神経をしているのか?図太く時間稼ぎをしているつもりなのか…?電話での感触では、とてもそんなふてぶてしい神経を持ち合わせている人物には感じられなかったが…。
膠着状態を打破するため行動を早めることにして、この担当者に最終警告文書を突きつけることにした。
2月13日付けでFAX送信した以下の書面がそれである。
| 通知書面 |
最終警告です。
1月29日付けで、あなたに質問書面をFAX送信提示したにも関わらず、未だ貴殿からの回答書面は未着の状態です。
たんなる事実確認を求めた質問にもかかわらず、未だに回答してこない理由は不明なるも、
2月19日(水曜日)まで
に書面回答なき場合は、あなたが事故交渉担当者としての職務を放棄したものと判断して、あなたとの交渉は打ち切り、新たな行動に出るとの△△氏からの伝言です。
再度、別紙「質問書面」を添付しておきます。
横浜損害サービス二課の事故担当者として、恥ずかしくない行動をとることを、…として切に願うものです。 以上
<別紙・質問書面>
◆質問1
○○車は△△車の存在を認識しないまま右折侵入した結果、衝突した。現場に、スリップ痕跡が一切認められないことが何よりの物的証となる。
この事故状況事実を、交渉初期段階で双方が認めた上での交渉をこれまで進めてきたが、再確認のため改めて質問をしたい。
この事故状況事実を肯定するか否か端的に答えていただきたい。
◆質問2
○○氏は現場で「衝突するまで△△車に気づかなかった」ことを認めていた。
この事故状況事実も、交渉初期段階で双方が認めた上での交渉をこれまで進めてきたが、再確認のため改めて質問をしたい。
この事故状況事実を肯定するか否か端的に答えていただきたい。
◆<コメント> この担当者の神経なら、FAX書面は届いていない、誤送信なのでは…と言い出しかねないことも頭に入れておく必要がある。そこで、下記書面を、事故当事者作成の書面として、「配達証明付き」郵便で担当者に直送することにした。
平成26年2月 日
東京海上日動火災保険株式会社
横浜損害サービス第二課
担当 金崎 和生 殿
通知書
事故交渉担当者として、職務上の義務を果たさないあなたを信頼出来ないがために、このような書面を提示することになりました。
残念なことですが、いたし方ありません。交渉の窓口に立っていただいている谷さんの再三の回答書面提示要求にあなたが未だ回答書面を提示してこないためです。FAX書面送信では、書面は届いていない、誤送信ではないのか、とあなたに反論されたら、こちらとしては、なすすべもありませんから…。
事故交渉担当者としてのプライドを少しでもお持ちなら、職務上の義務を果たしてください。回答期限である、2月19日(水曜日)までに回答書面を提示してこない場合は、あなたとの交渉は打ち切ると同時に、職務上の義務を放棄したあなたの責任を追及することになることをご承知おきください。
もちろん、この事故に当初から関与して、自らの事故見解書面を提示してきたあなたの上司である広田氏の部下に対する管理責任追及も言うまでもないことですから、その旨お伝え下さい。 以上です
◆<コメント> 上記書面は、依頼者である事故当事者のよん所なき他の事情が発生したことにより、回答期限である19日までに書面到着郵送ができなくなったために、金崎担当者に2月18日、直接電話を入れることにした。
![]() 「どういう神経をしているのか…。たんなる事実確認の質問をしたのが1月29日。未だに回答書面が届かないが、明日が書面回答期限だよね…。」→「わかっています…。回答期限は明日19日ですよね。期限までに回答します。」
「どういう神経をしているのか…。たんなる事実確認の質問をしたのが1月29日。未だに回答書面が届かないが、明日が書面回答期限だよね…。」→「わかっています…。回答期限は明日19日ですよね。期限までに回答します。」
◆<コメント> 2月19日、金崎担当者から回答書面がFAXされてきた。予想されたこととはいえ、なんともお粗末な内容の回答書面だった。この人物には、このような内容の書面を提示したら、横浜損害サービス二課の事故担当専門職業人としての自分という人間が、交渉相手にどのように評価されることになるのかという思慮深さがみじんも感じられないということだ。恥というものを知らない人間につける薬はないということか。情けない回答書面を原文のまま公開することにしよう。
| 担当者・回答書面 |
ご回答
拝啓 時下益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。2/13のご質問を下記に回答させて頂きますので、ご確認よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
1.これまでの交渉において齟齬はございません。※「齟齬」(そご)→意見などがくいちがうこと
2.幾度も申し上げました通り、「衝突するまでお相手車に気がつかなかった」ことは認めるところです。しかしながら、右を見て左を注視しての運転が著しい過失にあたるかだけを争点として交渉したいところです。
同様のご質問を繰り返すのであれば○○氏と交渉して参りたいと思います。
◆<コメント> この愚かな担当者は、「脇見運転」論争はやめて「著しい過失」論争に的を絞りたいということなのか…。この書面内容を見る限りそのように読み取れるが…。「前方不注視の著しい場合」が「著しい過失」の一態様であり、「脇見運転」はその具体的例示である。抽象的に「前方不注視の著しい場合」に該当するかどうかを争っても水掛け論になるから、具体的な「脇見運転」に的を絞っての交渉にしたこちらの作戦に乗ると論理的に破綻することになるということを認識した上で、このような回答書面を寄こしてきたということなのか…。
いずれにしても、依頼者と打ち合わせをした結果、この担当者とこれ以上交渉を続けても時間の浪費になるだけだという結論にいたった。
そこで、交渉打ち切り通知書面をこの担当者に送りつけることにした。以下の書面がそれだ。
| 交渉打ち切り通知書面 |
「衝突するまでお相手車に気がつかなかった」。
この事実をもってして、左方注視のみで進行方向である右方を見ることなく右折侵入した何よりの証となる。「右を見た」とは、いかなる根拠にもとづいてそう言っているのか…。なんの裏付けもなくそう言っているのなら、それはたんなる言葉遊びだということに他ならず。進行方向を見ずに運転すれば「脇見運転」であり、これを正視しようとしないあなたは、残念ながら「無能な担当者」と評価せざるをえない。交渉能力のないあなたとこれ以上話し合う気は毛頭ないので、これであなたとの交渉は打ち切りとしたい。これが○○氏からの伝言です。
◆<コメント> 交渉窓口は、本社「お客様相談センター」に移行ということになる。東京海上日動の本社窓口での対応を求めることにした。
以下の書面を送りつけることにした。
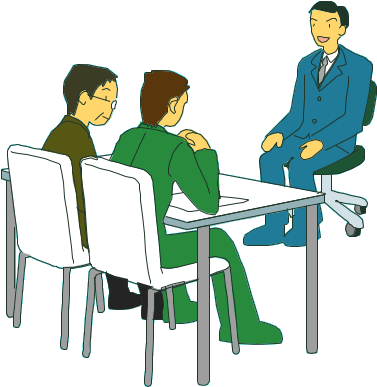
平成26年3月5日
東京海上日動火災保険株式会社
お客様相談センター 御中
○○市○○区○○ ○丁目○-○
△△ ○○○
ご連絡
平成25年◇月◇日◆◆市内で発生した、貴社契約者(△△)との交通物損事故の相手方当事者です。
事故は交通整理の行われていない丁字路交差点内で起きました。貴社契約者が右折進入する際、右方から進行してくる自車の存在に気づかないまま侵入した結果衝突した事故でした。資料A
判例タイムズ・事故類型図「95図」を適用して横浜損害サービス第二課の事故担当者と交渉に入りました。
これまで、書面による交渉を続けてきましたが、担当者は、説得力のない方便的主張をくり返すばかりで、示談交渉の進展が望めなくなりましたので、担当者に交渉打ち切りの通知をして、最後の望みをかけ、このお客様相談センターに連絡をさせていただきました。
発生した事故状況事実を正面から受けとめる事ができる事故担当者との交渉を希望するものですが、残念ながら、横浜損害サービス第二課にそのような人物の存在を期待するのは無理ではないかと悲観的に考えております。
理由は、今回の事故に早い段階から関与してきた横浜損害サービス第二課の課長代理である「広田」氏が、
本件事故に関するご自身の見解を書面提示してきましたが、交渉担当者の主張見解とほぼ同一内容のものであり、事故相手である△△氏が、事故現場で「衝突するまで○○車に気づかなかった」と私に説明した事実を、彼の部下である事故担当者同様に認めた上で、なお貴社契約者の「脇見運転」を否定する見解を示してきているからです。
今回、3人目の担当者である「金崎 和生」氏との間で交渉決裂となったのですが、2人目の担当者であった「須藤 茂」氏は、次のような書面を提示してきました。
◆「○○様は△△様の『右方向の安全確認が疎かになった状態』を『脇見運転』と同視しておりますが、それにつきましては見解の相違がございます。今回の△△様の行動は、安全に交差点に侵入するために左方向を注視していたものであり、漫然とほかの方向を見る脇見運転とは異なることと考えております。確かに進行時右方向の確認方法が不十分であったことは否めませんが、脇見運転ではなく基本割合に含まれる要素と考えております。」資料B
◆「事故態様、△△様の行動についてはご確認の通りで弊社も異論はございません。一方、○○様は△△様の「右方向の安全確認が疎かになった状態」を「脇見運転」と同視しておりますが、それにつきましては見解の相違がございます。今回の△△様の行動は、安全に交差点に進入するために左方向を注視していたものであり、漫然とほかの方向を見る脇見運転とは異なることと考えております。確かに進行時右方向の確認方法が不十分であったことは否めませんが、脇見運転ではなく基本割合に含まれる要素と考えております。資料C
さらに3人目の担当者である「金崎 和生」氏も、次のような書面を提示してきています。
「右方の安全確認が疎かになったものの、まったく右方を見なかったわけではございません。当方契約者様の主張としましては、丁字路交差点進入にあたり右方を確認した後、左前方を注視して交差点に侵入したものです。よって右方も確認していることから『前方を見ないで運転する』脇見運転にはあたらないと考えるものです。」資料D
以上のように、この二人の担当者とも、
進行方向である右方は、左方を注視するあまり疎かな状態にはなったが、疎かなりにも一応右方向は見たのだから、脇見運転にはあたらないという主張であり、この主張は広田課長代理の提示してきた見解とほぼ同一内容であるということです。広田氏の見解は次のとおりです。
①脇見運転とは、東京海上日動ホームページに記載されているように、『前方を見ないで運転すること』である。
そして、具体的には、続いて記載説明されている『携帯電話・カーナビを操作しての運転』・『景色・看板などを見ながらの運転』・『助手席・ダッシュボードなどから落ちたものを探したり、拾ったりしながらの運転』等をいう。
②丁字路交差点侵入にあたり、左右の安全確認のため右方を確認した後左前方を注視して、結果として右方の安全確認が疎かになった状態で走行するのは、脇見運転にはあたらない。交差点進入に当たり、より注意を要した左方の交通状況の確認のため左方を注視しての走行であるから、前方を見ての走行といえるからである。資料E
今回の事故は、事故発生状況に関する事実関係の認識においては、双方ともに争いのない状況下での交渉です。
◆事故発生状況事実関係に関して双方が共有する認識
①△△氏が事故現場で「衝突するまで○○車に気づかなかった」と説明した事実。
②事故現場にスリップ痕がないことから、△△車が進行方向である右方の安全確認を怠り、○○車の存在を認識することなく右折進行した結果衝突したことは、△△氏の①の説明によって裏付けられる事実。
横浜損害サービス第二課は、なんの裏づけも明らかにすることなく、「△△氏は疎かなりにも右方を見た、確認している」と主張しているが、運転者の内的心理状態は、外部に残された事故痕跡や運転者の供述説明によって推断するほかはないという事実認定の基本原則を無視しての主張見解であり、このような説得力のない主張見解は到底受け入れられるものではないということです。
お客様相談センターも、こちら側のメール問い合わせに、次のように明快な回答を寄こしてきています。
「東京海上日動火災保険 お客様相談センター 森田と申します。
この度は、メールをお寄せいただきありがとうございます。
また、ご回答が遅くなりましたことお詫び申し上げます。
ご連絡をいただきました件ですが、「安全運転ほっとNEWS」は、広くお客様にご提供させていただいている読み物ですので、なるべく分かりやすい一般的な言葉を使って「脇見運転とは、前方を見ないで運転すること」と説明しております。
「交差点進入にあたり」ということですので、その後、右左折・直進するパターンが考えられるかと思いますが、仮に交差点に進入して左折する場合であれば、自分の向かう左方を注視して走行するのが通常であり、脇見運転にはあたらないと考えております。
直進・右折する場合では、左方のみを注視している場合には前方を見ないで運転することになりますので、一般的には脇見運転になると考えます。(赤太字・下線は△△)
東京海上日動火災保険株式会社
お客様相談センター 資料E
進行方向を見ることなく走行する危険な運転行為が、「脇見運転」であることは誰もが異論を挟む余地とてないことです。
なんの裏づけもなく疎かなりにも見たのだから「脇見運転」には当たらないとする主張見解は、過失修正を認めたくないがための完全なる「方便」にすぎません。説得力のない屁理屈を駆使して目先の利害関係のみに固執する姿勢は、契約者側が法律上負わなければならない過失賠償責任の範囲を、交渉によって明らかにして保険金を支払うという社会的使命を果たさなければならない保険会社がとるべき本来の姿ではないと思います。
保険会社は、目先の利害関係のみに終始する「保険屋」的レベルの存在に堕ちてはいけないのではないでしょうか。「判例タイムズ」という客観的外部資料を介して話し合いをしている以上、この資料を自己側に都合のいいように理解する恣意的解釈は許されるものではありません。
当の運転者の説明から、右折進行時に右方を見ていなかったという事実が存在するにもかかわらず、なんの裏付けもなく、「右方は侵入時疎かなりにも見た」のだから脇見運転ではないと強弁する担当者に翻弄されつづけいたずらに時間だけを浪費し、その強弁を早期解決のため妥協的に受け入れることは、金銭だけの問題ではなく、心理的に受け入れ難いことだということをご理解いただきたいと思います。
保険会社としての東京海上日動の見識を示してください。
事故状況事実を正面から受けとめることのできる、良識ある事故担当者との交渉を切に望むものです。
ご連絡をお待ちしています。
以上です。
◆<コメント> 保険会社としての東京海上日動の見識を示すことを書面要請した依頼者に対して、東京海上日動の本社窓口である「お客様相談センター」はどのような対応をとってきたのか…。
あろうことか、交渉を打ち切った金崎担当者が再度のこのこと出てきて、「私が引き続き担当することになりました」と直接依頼者に連絡をしてきたのだ。同センターに抗議の電話を入れると、
同センターはただ受理をする窓口にすぎない。このような依頼要請がきたということを担当していた部署に伝えるだけの役割しかもっていない。責任をもって最終処理をするのは、あくまで事故交渉を担当した部署。つまり、担当部署とトラブルになったドライバーとの調整役を担当する窓口部署は組織として持っていないという説明なのだ。
依頼者が交渉能力無しとして引導を渡したこの担当者。自らの主張する見解の非論理性を認めた上での再交渉かと考えたが、「脇見運転」を認めることはなく、あいも変わらずの10対90の基本過失割合主張だ。これが東京海上日動という保険会社の組織としての偽らざる実態だということだ。判例タイムズという客観的資料を介しての交渉において、明らかに非論理的な見解を展開する己の主張には目をつぶり、結論だけを頑なに主張する「保険屋」としての姿であり、今回のように担当部署ぐるみで非論理的強弁を繰り返す組織に一般ドライバーとして対抗する手段は残されていないということになる。保険会社に保険屋として開き直られたら、話し合いレベルの段階では手の打ちようがないということになるのか…。
もっとも、加害者との直接交渉に出るという、保険会社を揺さぶる手段は残されてはいるが…。
直接交渉に出られた加害者は当然のごとく加入保険会社に通報することになる。そうすると保険会社は「弁護士対応」を余儀なくされることになるから、弁護士費用という余計な支払いが増えることになる。保険会社にとっては、10%の過失修正受け入れにこだわった結果、新たな出費を余儀なくされるということになるわけだ。
客観的交渉資料である「判例タイムズ」を恣意的に解釈して、あくまでも基本過失割合に固執し修正要素採用を拒絶する保険屋としての保険会社に対抗する最終的手段として、加害者との直接交渉に難色を示した依頼者に対し、「交通事故紛争処理センター」への示談斡旋申し込みをアドバイスすることにした。同センターは、「被害者救済機関」として設立された経緯があり、ここでの斡旋内容に保険会社は原則として従うことになっており、弁護士が対応してくれるにもかかわらず、費用が一切かからないというメリットがあるからだ。
◆<コメント>依頼者からメールが来た。その中には、金崎事故担当者からのメール文が紹介されていた。底なしの事故担当者…このレベルの担当者が大手を振って保険業界という特殊な世界を闊歩しているということをドライバーは認識しておかなければならないと思う。
判例タイムズという客観的な交渉資料を己側に有利に恣意的解釈して、強弁を張り続ける保険屋担当者に対抗するにはどうしたらいいのか…?その方法は「実利」(具体的な効果・効き目)だ。強弁をくり返して過失修正に応じない保険屋には、それ以上の金銭的支出を余儀なくさせる手法が最も効果のある方法だと現時点では考えている。
加害者との直接交渉に切り替えて弁護士介入を余儀なくさせるのが、その具体的方法の一つだろう。弁護士はタダで動く存在ではないからだ。
右方を確認し左方を注視して走行した。加害車側は「衝突するまで被害車の存在に気づかなかった」と説明する。この事実を認めた上での強弁だけに質(たち)が悪い。進行方向である右方を見ずに走行したから気づかなかったのだ。通常の人間なら誰でもそう判断する。
何の裏付けもなく、右折進入時左右の安全確認をしたと言う。進入時進行方向である右方は確認しているのだから、左方を注視して走行しても「前方」を見ての運転ということになり、脇見運転ではないと強弁する。この強弁がまかり通るとなれば、東京海上日動・横浜損害2課には、「脇見運転」はいつの事故にも存在しないことになる。何の裏付けもないまま、ただ「見た・確認した」と主張説明するだけで脇見運転を否定できることになるからだ。
彼の上司である課長代理もまったく同じ主張をしていることから、横浜損害2課という組織ぐるみの強弁ということができ、その根は深い。このレベルの保険屋事故担当者が日常的に交渉業務に携わっているのが保険実務の実態だということをよく認識しておく必要があるということだ。
依頼者の再度の問いかけに答えた担当者の救いようもないメール文を依頼者の承諾を得て公開しておきたいと思う。
目先の利害関係に執着するあさましい保険屋としての担当者の強弁をじっくりと吟味していただきたい。(H26.3.30)
件名: 東京海上日動火災保険の金崎でございます
○○ ○○ 様
○年○月○日の事故における脇見運転について回答いたします。
弊社お客様相談センターは脇見運転について「直進・右折する場合、左方のみを注視している場合には前方を見ないで運転することになりますので、一般的には脇見運転になると考えます。」と説明しております。一方本件における△△様の運転においては、交差点進入にあたり左右の安全確認のため右方を確認した後、左方を注視して交差点に進入したものです。交差点進入にあたり、より注意を要した左方の交通状況の確認のため、左方を注視しての走行であるので前方を見ての走行と考えております。
