東京体育館
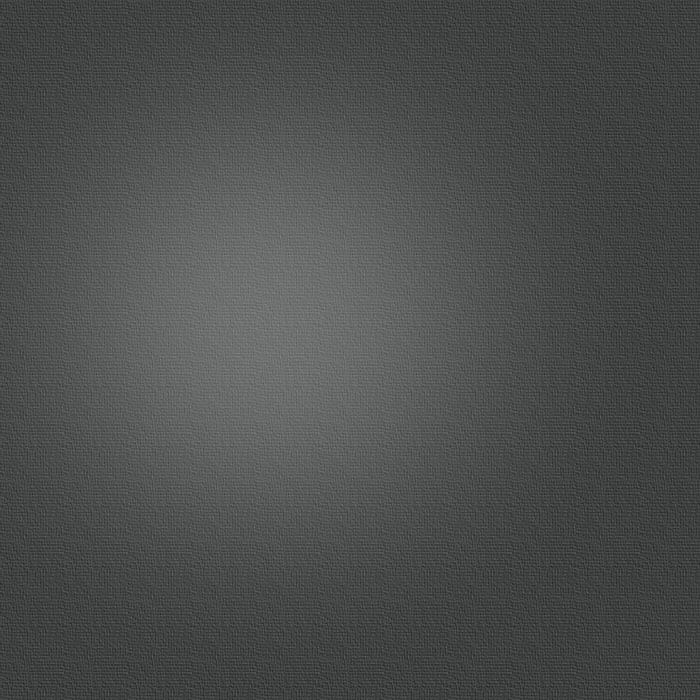


「苦しみがとまらないわ」
彼女は指に挟んだ細長い煙草を震わせていた
表情は髪に隠れて見えない
「少し休みますか?」
彼女は何も応えずに沈黙し、それを契機に
おれたちのテーブルに音の洪水が押しよせた
まるで盲目になったみたいに店内の音が溢れかえる
彼女の肩越しからは換気扇の音が禍々しく吹きすさんでくる
おれは自分の音を見つけるために言葉を継いだ
「無理は良くないですよ、元々役員の方と会う予定でしたし」
彼女は東京体育館の広報だ
おれは記者で彼女に取材している
東京体育館への民間による経営参画の成果についてだ
理事と応接室で面談するはずが突然この広報の女から横槍が入り、
千駄ヶ谷駅前の喫茶店に連れてこられた
「まだ事務所には戻れない、苦しみがとまらないから」
指先が震え続けている
灰が床に落ちても気にする様子はなかった
記事の内容は決まっているようなもので、
こっちは理事からのコメントという体裁がほしいだけだ
広報の相手をしていても時間の無駄だった
「理事は事務所ですよね、会えないのですか?」
「会ってどうするの? 彼はとても忙しい」
「取材のお約束をしたのですが」
「だから格闘技やライブにも貸すようにしたし一般開放枠も増やしたわ」
「そうですよね、そのことも理事からお聞きしたいと…」
「苦しみがとまらないわ」
そう呟くと、彼女は煙草を深く吸い込んで吐いた
煙のカタマリが換気扇の風に乗っておれの顔へと届けられる
その後、彼女は沈黙を続けた
このテーブルは騒々しい店内にぽっかり開いたエアポケットだ
おれの耳には遠い記憶からの声が流れ込んでくる
……誰かがあたしを救わなければならない
「誰かがあたしを救わなければならない」
君はベッドから頭だけをごろりと落とし逆さまな景色を見ていた
おれは寝室の椅子に座り飛び出す絵本を分解しているところだった
「ちょっと待って、もうすぐバネ人間が完成するんだ」
「ああゴミが増える、まだ読んでないのに。ちゃんと捨てといてね」
君の部屋は常に散らかっていて、
おれは手に取ったもので簡単に時間を潰すことができた
床に垂れ下がった君の長い髪には綿埃が付着していた
眼は次第に充血し、喉は透き通るように白かった
君は掠れてしまった声で言った
「苦しいわ、早くなんとかして」
「頭を枕に戻せばいいのかな?」
絵本の世界から解放されたバネ人間がおれの手の中で踊っていた
君にもわかりやすいように逆さまにして見せた
「ねえ顎の下を見て、少し青いでしょ?」
「白いよ、血管が見えているかもしれない」
おれがそう言うと、君は微かに笑みを浮かべて自分で頭を起こした
そのまま身体を反転させベッドに肘を付いて上体を反らせる
表情が髪に隠れて見えなくなった
「あたしの父親なんだけどさ、絞首刑で死んだの」
「すごい話だな、嘘だろ?」
「嘘よ、田舎で元気にしてるわ、でもね母親はいないの」
「何だよそれ」とおれはバネ人間に向き直って吐き捨てた
「母は男と蒸発したの、父と幼いあたしを捨てて。覚えてないけどね」
以来、淋しい町の小さな家で父親と二人で生活してきたと君は語った
「だから君の部屋はいつも賑やかに散らかっているんだね」
「関係ないわ、忙しいだけよ」
身の上話を聞いたからか、おれは急激に君に近づきたくなって隣に潜りこんだ
ベッドの上にも漫画や文庫本やぬいぐるみなどが置かれていて、
おれは何かの角に腰を突かれながら窮屈に身体を寄せた
ついでに、さっきまでのお気に入りだったバネ人間を物の氾濫の中に投棄した
その手で、君の髪を撫でながら囁く
「こうしよう、今日からおれが東京のお父さんだ」
やめてよ気持ち悪いから、と君はおれの手を払いのけた
「父はあなたと違って真面目な人よ、でも真面目すぎて思いつめるというか…」
相変わらず君の表情は髪に隠れたままで、おれはそれが不満だった
おれはもっと君の内側に、心の中にまで入っていきたいと考えていた
「夜、布団に入っているとね、時々父のうなされている声が聞こえたわ」
おれは払われてしまった手をまた君の髪に戻す
すぐに気づかれないように毛先から少しずつ、栗色の光を滑るように
「母の名を叫んで殺してやる殺してやる…って、耳を塞いでも頭の中で響くの」
手のひらが頭頂部に達すると、また元に戻す要領でゆっくり撫で下ろした
今度は拒絶反応を示さなかったが、油断のできない張りつめた空気だった
「そんな夜にね、怖くて眠れなくて、愚かなことに父の様子を見にいったの」
おれは頭を撫でる上下運動を慎重に続けながら、
狭いベッドの中でより身体を密着させていった
「殺してやるって叫ぶ父に、思わず、ごめんなさい許して下さいって謝っちゃった」
このまま心と心が溶け合うように君と同一化したかった
はっきりと言えば、おれは君になりたかったのだ
「その時、あたし、初めて父に首を絞められたわ」
「もういいよ、君は何も悪くない、その苦しみを輸血みたいに全部おれにくれよ」
おれは君の表情を確かめたくなって髪をかき上げようとした
だが、素早くその手をつかまれ制止された
「父は女が憎いのよ、善良そうに見えて女を殺したい変態くんなの」
張りつめていた空気を破るように、君はきりきりとした声で笑った
おれは君の息が切れるまで待つしかなかった
手はつかまれたままだ
「撫でるのはやめて。あたしを救ってほしい、優しく接する以外の方法で」
君は声を引きつらせていて、まるで恥らうような言い方になっていた
「わかった、叱ってほしいんだね、君の弱さを」
「は? 何言ってんの、あたしに説教する奴なんて全員死ねばいい」
突如として、君はつかんだおれの手を自分の首に持っていく
俯く君の首を手のひらで支えるような形になった
「絞めて、ゆっくりよ」
いつの間にか、おれは自分が逃げられない場所にいると気づいた
催眠術をかけられたみたいに、握力を強めていくしか選択肢がなかった
「加減が、わからないな…」
「大丈夫、まだまだいける」
おれはもう一方の手で、君の髪をかき上げて表情を覗いた
眼球が少し飛び出ていた
見たことのない、知らない女がそこにいると思った
徐々に圧迫していくと、君の白い首に青い斑点が浮き上がってきた
それは、君の父親やいろんな男の指の跡のようにも見えた
おれの額から一筋の汗が流れ落ちてくる
「もっといくぞ、知らないからな」
君は声にならない声で呟き続けている
「ごめんなさいごめんなさい、許して…」
ふと見ると、君の手の中でバネ人間が握り潰されていた
「ねえ、聞いてくれる?」
広報の女が突然口を開いた
凍結していた時間が再び流れていく
身体中が汗ばんでいるのがわかる
おれは水を一口飲んで気を取り直そうとした
渇いていた喉がひりひりした
「あの、煙草吸ってもいいですか?」
「いいよ、がんがん吸って」
おれは餌にありつく犬のように慌てて煙草を取り出す
火を点けて一服すると、ようやく現実が鮮明に見えてきた
彼女は前を向いて顔を晒していた
小麦色の肌と、意志の強そうな瞳を持っている
スーツを着ているがカジュアルな服装の方が似合いそうだ
こういうのは記事にならないかもしれないけど、と彼女は言った
「上司が元トレーナーで、机の下にダンベル置いて仕事の合間に持ち上げてるの」
取材先で仕事の愚痴を聞かされることはよくある
おれは理事に会うという使命を思い出しつつ耳を傾けることにした
「彼はいつも、ランチの後にステロイドを飲んでるわ」
彼女が言うには、上司の影響でステロイドが数名の間で流行りだし、
彼女自身も何度か摂取したそうだ
「当たり前のように、みんな笑顔で錠剤を口に放り込んでる」
「それって、身体に良くないわけですよね」
おれから見れば、彼女は面と向かうのが眩しいくらいに健康的で
こっちが身体の心配をするのも滑稽ではあった
しかし、それは薬物によってつくられた外見なのだろうか
「乱用しなければ大丈夫よ、むしろ代謝が良くなったし」
「でも、賛成はできませんね」
「おかげで体脂肪率15%の健康体。…苦しみがとまらないわ」
彼女は深いため息をつき、新しい煙草を口にした
いつの間にか小さな灰皿が吸殻で溢れていた
おれは吸い終わった煙草をその中にねじ込んでいく
「ああ、毎日毎日いろんな人間がジムやプールに汗をかきにくる…」
彼女は絵に描いたようなうんざりした表情を浮かべ、煙を吐き出した
煙の充満する彼女の肺を想像してしまい、痛々しさを感じた
「みんなタイムであり体型であり、きっと理想の自分を追求をしてるのよ」
だから東京体育館は理想と夢と健康に満ちた場所なの、と彼女は初めて笑った
「まるで、広報みたいですね」おれもつられて笑う
知ってるかしら? と彼女はいたずらな表情でおれの顔を覗き込む
「立派な東京体育館はひどい赤字よ、わたしと同じように体質がぼろぼろ…」
彼女はカップを掲げ、もう冷めてしまったであろうコーヒーを口に含んだ
その姿は凛としていたが、立ち昇る煙草の煙のように儚くも見えた
「あの、やめた方がいいですよ、危ないクスリは」
おれは思わず間の抜けたことを言ってしまった
おれの言葉など彼女のつややかな肌に滑り落とされてしまうくらいに、
彼女は晴れやかな顔をしている
それを見て、おれの脳裏に再び君の顔がフラッシュバックした
首を絞め終えた後、君はすっきりした顔で言ったのだ、ああ、お腹がすいたわ…
「あら、そろそろ理事が戻ってくる時間だわ」
「え?」彼女の言葉でまた現実に引き戻される
「彼の所に案内するわ、変なこと聞いたりしないでね、上手に宣伝して」
「ええ、まあ、なんとか…」
とりあえず理事に取材できるようなので、おれはほっとした
ありがとね、と彼女は微笑み煙草を消しながらテーブルの上の伝票をさっと取った
「聞いてほしかった、誰も知らない、わたしの苦しみ」
聞いてほしい、
誰も知らない、
わたしの苦しみ
間が悪く水を注ぎにきたウェイトレスの目も、そう言ってる気がして身震いした
ウェイトレスに断りを入れて、おれたちは席を立ちレジへ向かう
「ところで、あなたすごい汗ね、取材の後にうちのプール寄ってったら?」
「いや、水着持ってませんから」
「裸で入れるお風呂があるの、気持ちいいわよ。入場料600円」
そう言いながら、彼女はレジで二人分のコーヒー代を支払った。