登戸駅-(小田急電鉄)-海老名駅…(5分)…海老名電車基地・見学…(5分)…海老名駅-(小田急電鉄)-厚木駅

今日は、海老名駅電車基地で開催された小田急電鉄のイベント「ファミリー鉄道展2004」を見学しました。

写真は、車海老名電車基地内特設会場にて撮影したロマンスカー20000形、3100形と総合検査車のクヤ31テクノインスペクターです。 左端に写っている車両は、クヤ31「TECHNO-INSPECTOR(テクノインスペクター)」です。2004年3月に小田急電鉄が導入した検測車です。この車両1両で、軌道と架線の測検出来る車両です。日本の鉄道で初め架線と軌道の検測を1両に集約した車両です。製造費用は車両、検測機器類をあわせて約8億円です。

本形式は動力を持たない制御付随車です。電源供給改造された1000形編成が新宿方で牽引または推進するかたちをとります。

写真は、小田急電鉄を走っていたロマンスカー(特急用の車両)3100形です。「NSE(New Super Express)」という愛称です。1963年から1967年にかけて7編成77両が新製され、2000年まで在籍しました。1964年度鉄道友の会第7回ブルーリボン賞を受賞しました。

側面には、「The lastrlunning」のステッカーが貼り付けてありました。

写真は、小田急電鉄を走っている20000形ロマンスカー(特急用の車両)です。「RSE (Resort Super Express)」という愛称です。1991年3月16日に営業運転を開始しました。1992年度鉄道友の会第35回ブルーリボン賞を受賞しました。新宿駅―御殿場駅間の連絡急行「あさぎり」として使用されていた3000形「SSE」の置き換え用として、1990年12月に第1編成が、1991年1月に第2編成が竣工され、7両編成2本計14両が日本車輌製造と川崎重工業で製造されました。

相互乗り入れとなるJR東海との協定に従って、編成の構成、車両の全長、定員、性能や保安機器などを基本的に合わせました。JR東海の371系と仕様を揃えるために、展望席、連接車体や喫茶室など今までのロマンスカーの設定をやめて、20mボギー車の7両編成としました。小田急電鉄の場合、「あさぎり」用の予備編成があることから、運用上箱根特急にも使用することを想定して、箱根登山鉄道の路線の限界にも合わせ7両編成となりました。写真は、車内販売施設です。

7両編成中、3号車と4号車がダブルデッカー車です。その他の5両は、10000形「HiSE」に引き続きハイデッカー車となりました。写真は、ダブルデッカー車の2階車内です。

写真は、小田急3000形です。3000形電車は、小田急電鉄に在籍していた特急形車両ロマンスカーです。1957年に導入された時の塗装です。

正式な愛称は「SE(Super Express)」でしたが、5両編成化後に短編成化にちなんで「SSE(Short Super Express)」とよばれるようになりました。写真は、運転室です。
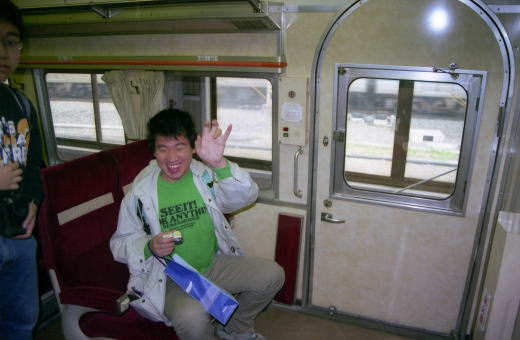
1957年に8両編成3本(24両)、1959年に8両編成1本(8両)の計32両が製造され、1991年まで在籍しました。1958年度鉄道友の会第1回ブルーリボン賞を受賞しました。

写真は、3000形電車の車内・売店設備です。

SSE車は、後に塗装が変更されました。海老名電車基地には、新旧両方の塗装の3000形SSE車両が保存されています。

こちらが、晩年の塗装で保存されている3000形車両です。私が子どもの頃に小田急線を走っていたものです。

海老名電車区に展示されていた車両を撮影した後、架線保守作業車による実演を見学し、鉄道車両部品などを購入しました。そして、ファミリー鉄道展を見学した後私たちは、小田急電車の乗って、厚木操車場にある相模鉄道の旧塗装車両を撮影しに、厚木駅へ向かいました。