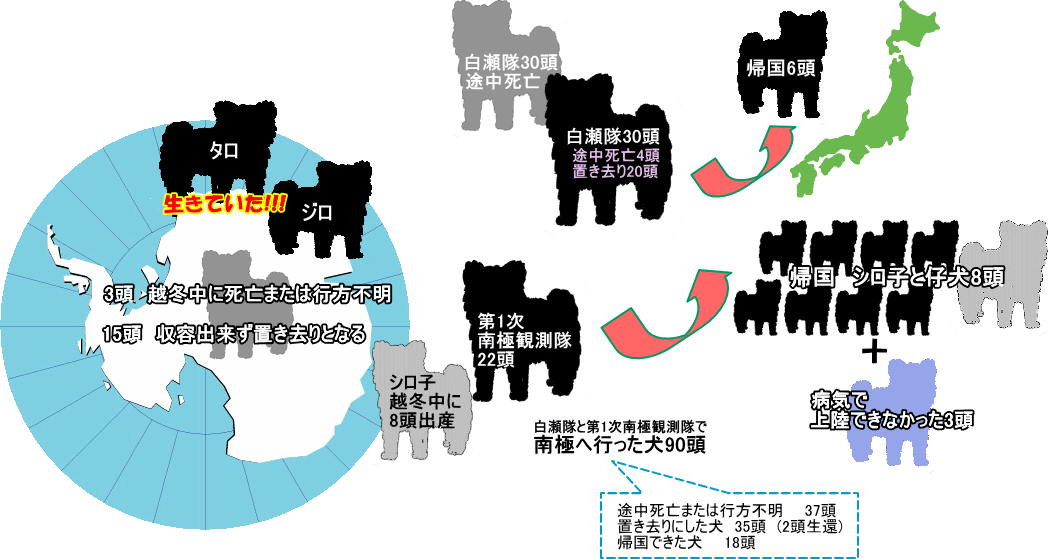「太郎・次郎」と「タロ・ジロ」
1956年 南極観測隊用に樺太犬を集めていた犬飼教授によって名付けられた「タロ・ジロ」
この名は1910年の白瀬隊に同行 南下とともに暑さや寄生虫症により犬が亡くなるなか
最後に残った先導犬の「太郎」と「次郎」から名づけられたものだ
《白瀬隊の犬》
1910年(明治43年) 11月29日 白瀬隊は30頭の犬とともに「開南丸」で芝浦埠頭を出港
南極を目指すが犬たちが数を減らし 夏が終わるということもあって南極圏を目前に上陸を断念
シドニーに留まり 日本からの犬の到着を待って改めて南極を目指した
1912年(明治45年) 1月6日 日本人として初めて南極大陸に上陸
隊長ら5名はそり2台と樺太犬29頭で南極点を目指すが
1月28日 南緯80度地点で食糧不足などのため南極点への到達をあきらめ
この地点を「大和雪原(やまとゆきはら)」と命名し引き返した
後に白瀬中尉はこのときの犬の事を
『犬橇(そり)は29の内23用をなし、1橇10頭の犬を附け、100貫の荷物を載せたるも漸次減じたり。犬はそれより次第に減じ、今は6頭を残すのみ』
とインタビューで語っている
だが 犬橇の担当者は
開南丸へ撤収の際 強風とボートを漕ぐ隙間も無いくらいの流氷で人間が戻るのもやっとだったといい
『この時点で26頭の樺太犬が生き残っていましたが、6頭だけはボートに乗せることができましたが、残りは南極に置き去りにするしかなかったのです』
と語った これを事実とし 最初の樺太犬の置き去り事件 ともいわれている
アイヌの人だったこの担当者は帰国後 犬を大切にするアイヌの掟を破ったとして民族裁判にて有罪になっている
《第1次南極観測隊の犬》
ふたつの探検隊で計90頭の犬が使用され帰国できたのは20頭 置き去りにされたのは35頭
どちらも 文献や資料から かかわった隊員の苦悩の大きさは読み取れるが
今も日本の南極探検の歴史の汚点として人々に記憶されている
せめてもの救いは ジロは越冬中にシロ子と大恋愛?の末 お父さんになり
隊員の懇願によりこのシロ子と子供たちは帰国することができている
「タロ・ジロ」の生還は映画や本になり語りつがれている
樺太犬三兄弟
 タロ・ジロ・サブロ(出発前の訓練中に病死) 写真:名寄市風連歴史民俗資料館
タロ・ジロ・サブロ(出発前の訓練中に病死) 写真:名寄市風連歴史民俗資料館この三兄弟の父親は「風連のクマ」立派な名前だ
 一緒に南極にいっている 写真:名寄市風連歴史民俗資料館
一緒に南極にいっている 写真:名寄市風連歴史民俗資料館生存が確認されたときの 左ジロ/右タロ
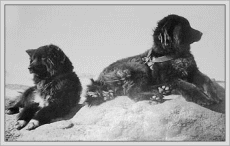
〈参加した90頭の犬〉