虹と音階とスペイン語と
虹と音階とスペイン語の間には、意外と思われるかも知れませんが、実は密接な関係があります。
虹は7色だと教わりました。英語でも Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet です。
このなかで Orange と Indigo はスペイン語起源です。Newton は虹を7色に分けましたが、その
割合はその当時の音階の1種ドリア旋法の振動数に対応して分割しました。
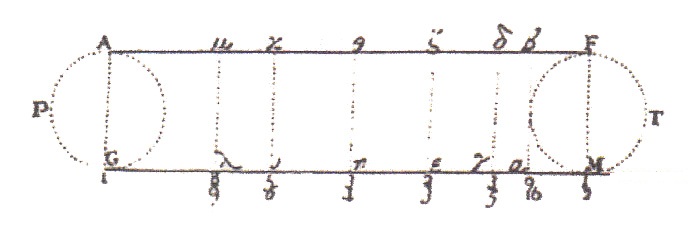 ニュートンは太陽のスペクトルを左図のように分割しました。
ニュートンは太陽のスペクトルを左図のように分割しました。
左端が紫で下の数字は1、右端が赤で下の数字は1/2です。
他の区切り線の数字もいれましょう。
1 8/9 5/6 3/4 2/3 3/5 9/16 1/2......0 →(1)

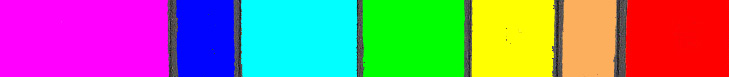
ニュートンの分割に合わせて7色を入れました。 すこし色が濃いようですが。

これは太陽のスペクトルです。
上と色があっていますか。 全然合っていませんね。
そうするとあのニュートンともあろう偉大な学者は、でたらめに虹を分けたのでしょうか。
それを解く鍵が、当時の音階の一種ドリア旋法にあります。
弦の長さと振動数は反比例します。弦の長さが半分になると音の高さは倍になります。
次はドリア旋法の振動の割合です。第2音と第3音が半音、第6音と第7音が半音です。
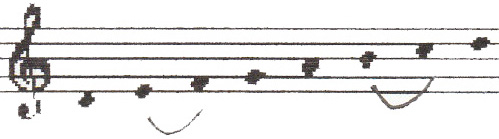
1 9/8 6/5 27/20 3/2 27/16 9/5 2......0 →(2)
(1)と(2)を掛けてみましょう。
1 1 1 81/80 1 81/80 81/80 1 →(3)
(1.01) (1.01) (1.01)
ほぼ一致します。ニュートンが虹を7色に分けたのは、音階の7音に合わせたのです。
このことはイギリスの学者が厳密に証明しました。
そのために当時では新しい語"Indigo"を使いました。スペイン語が元です。
ドリア旋法の振動数に対応させたという指摘も既にあります。
ただしニュートンの分割が正確ではない、恣意的だというのが私の主張です。
もしかしたら、彼は実際には実験などせず、最初から数字を当てはめたかも知れません。
詳しいことは、下記のパワーポイントファイルをダウンして下さい。
ファイルの使用は自由ですが、ご連絡頂ければ幸いです。
連絡先はこちらです。