加藤昇の(新)大豆の話
91. 日本の大豆栽培
私たち日本人にとって大豆は縄文時代の昔から最も身近にある食品の一つでした。そして今は、大豆で作った加工食品を食べない日はないと言えるほどではないでしょうか。これだけ大切な食材でありながら、現在の国産大豆は自給率7%と輸入農産物の代名詞のようになっています。なぜこのような日本大豆の姿となったのか、単純には描けないでしょうが、江戸時代以来、長年にわたり日本の経済が米本位性の政策を続けてきたことが影響しているのではないかと思っています。
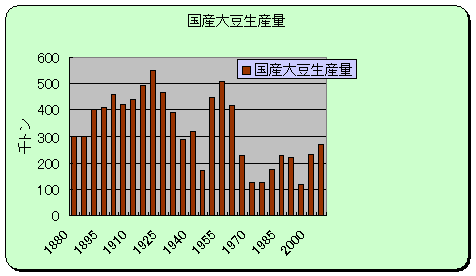 江戸時代には各藩の経済力が米の収穫高で評価されていました。そのためにどうしても米作りに農業生産の力点が置かれてしまいました。米が作れない土地や稲作の周辺の空き地などに大豆や小豆の種をまくようになっていきます。その傾向は戦後のわが国の農政にも受け継がれ、農家は米を作りさえすれば良く、その流通については地域の農協組織が支えてくれており、さらに価格は政府が決めてくれるので農家は何も考えなくても米さえ作っていればよい、との悪しき伝統が近年まで続いていたのではないでしょうか。政府は外国からの輸入米に対して778%という高い関税を課して稲作農家を守ってきました。そして米が余り、大豆が不足している現在に至ってもこの流れは変わることなく、多くの農民は今も米を作り続けているのです。しかし近年になって米の国際価格も高騰してきている一方で、国産の米価格が落ち着いており、内外価格差の縮小から農水省は輸入関税を従来の778%から280%へと表現を変更していますが高関税で米だけを保護している姿には変わりはないのです。
江戸時代には各藩の経済力が米の収穫高で評価されていました。そのためにどうしても米作りに農業生産の力点が置かれてしまいました。米が作れない土地や稲作の周辺の空き地などに大豆や小豆の種をまくようになっていきます。その傾向は戦後のわが国の農政にも受け継がれ、農家は米を作りさえすれば良く、その流通については地域の農協組織が支えてくれており、さらに価格は政府が決めてくれるので農家は何も考えなくても米さえ作っていればよい、との悪しき伝統が近年まで続いていたのではないでしょうか。政府は外国からの輸入米に対して778%という高い関税を課して稲作農家を守ってきました。そして米が余り、大豆が不足している現在に至ってもこの流れは変わることなく、多くの農民は今も米を作り続けているのです。しかし近年になって米の国際価格も高騰してきている一方で、国産の米価格が落ち着いており、内外価格差の縮小から農水省は輸入関税を従来の778%から280%へと表現を変更していますが高関税で米だけを保護している姿には変わりはないのです。
国内で消費されている大豆は年間で約350万トン程度ですが、これに対して国内での大豆生産量は20万トン程度で自給率はたかだか6%程度です。上のグラフにも見られるように国産大豆の生産量は大正12年の55万トンがピークで、その後満州大豆に押されて急速に減少してしまっています。第2次世界大戦後の食料不足で再び増加して50万トンとなりましたが、昭和35年の大豆の輸入自由化で一気に減少し、昭和47年の大豆の輸入関税ゼロでさらに激減をしてしまいました。昭和60年代の米の減反政策で再度増加して27万トンと微増しましたが平成5、6年の冷夏による米不足で農家は一斉に稲作に戻り、大豆の生産量は10万トンにまで落ち込んでしまうという、つまり日本の大豆栽培は稲作との兼ね合いの中で国産大豆の生産量は絶えず振れているのです。やはり、日本の農業は今も米が中心であり、稲作が優遇されていて大豆は農民の意識の中では片隅に追いやられていると言えるでしょう。
しかし、グローバル経済社会の中では稲作に対する鎖国政策を続けることは難しく、多くの国とTPP(環太平洋経済連携協定)を締結することにより米の関税が新たな時代を迎えています。これからは日本の農家も国の内外の状況を判断しながら作物を作っていかなくてはならない時代になっており、個々の農家の作付け戦略が自分の収益に直結することになってくることでしょう。このような動きと関連して従来の米農家から大豆栽培に転換してくる期待も高まっています。2018年での国内の大豆栽培の80%以上が減反休耕田を活用したものと言われています。
もう一つ大豆農家を動かしてきたのは補助金制度でした。日本の大豆栽培は多額の補助金で生産を下支えしてもらっています。しかしそれでも大豆の生産量はいっこうに増大していかないのが実情でした。国内では食糧安保の考え方が繰り返し叫ばれ、政府は2000年度産から「食料・農業・農村基本法」に基づいて、食料自給率の引き上げを目指し、国産大豆の作付面積の拡大を図っていますが、その背景にあるのは「米余り」現象に対応した減反政策と、それを推進する補助金制度であると言えるでしょう。政府は農家の生産意欲を盛り立てるため、大豆生産60キロ当たり約8千円の交付金と、畑作生産機構から千円、担い手支援300円、米から転作した水田には、10アール当たり7万3千円の奨励金を出し、2002年度で247億円、2003年度は231億円の補助金を支給しています。これらによって大豆を生産している農家利益の90%は補助金であるとも言われています。農家は米の生産調整のために大豆への作物転換をしているに過ぎないと言われています。基本的に大豆の生産性は稲作に比べても劣っているし、国際価格に対しても割高なのが実態です。そのため生産意欲を高めるためには交付金による助成が欠かせないとされています。自主流通米での利益が高ければ農家にとって大豆生産に向かう意欲が衰えてきます。結局、現在の国産大豆は私たちの税金を投入して、輸入大豆よりもはるかに高い値段の大豆を作ってもらっていると言えるでしょう。
掲載日 2023.8