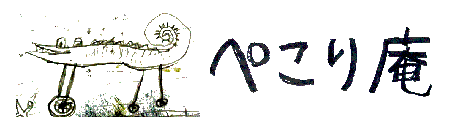■駝鳥舎にて
北原白秋の詩「トラピストの牛(*1)」を白秋自身が朗読したというテープを聞く機会があった。その後しばらくしてから、過去にこれと全く同じ経験をしたことがあるのを思い出した。ぼくの場合は「眼。」が横一列に整列している牛舎ではなく、暴れん坊の住む駝鳥(だちょう)舎だったが。
ぼくが動物園で働いていたころ、一羽の駝鳥が病気で倒れたことがあった。それがかなりの長患いで、ついには二十四時間体制で駝鳥の痰を吸い出すことになり、とうとうある日、ぼくも真夜中に駆り出される羽目になった。与えられた任務は器具を使って定期的にその痰を吸い出すことだけで、あとははただじっと看ていればよいらしいとはいえ、当時ぼくは別の班に所属していてそれまで駝鳥とはかかわったことがなかった。建物内部の迷路のような間取りや特殊な扉の構造もほとんど知らなかったし、備品や道具類の配置ももちろん知らなかった。それがいきなり真夜中に、一人で、しかも重体の駝鳥を看ることになったのである。
駝鳥舎はどこまでも真っ暗で静かだった。患者の安静のためまともな照明もつけられない。唯一の頼みであるはずの懐中電灯は、ぼくと交代した当番が持って帰ってしまったようだ。もう一つくらいその辺に転がっているのかも知れないが、こう真っ暗では探しようもない。力なく横たわった、元来凶暴なはずの駝鳥の首だけが、目の前にかろうじて浮かび上がっているばかりである。ぼくたちの隣、粗末な金網の向こうには若く血気盛んな駝鳥が二、三羽、また廊下の向こう側には縞馬が何頭か、こちらの様子を窺っているか眠っているかしているはずだった。縞馬などは外国から搬入されてきたばかりでまだ環境に慣れていないから、夜中に少しでも驚かすとパニックになって飛び回り壁に激突して死んでしまう、などと、どこまで本当かわからない話を聞かされてもいた。目の不自由な人は視覚以外の感覚が健常者より鋭敏になるといわれるが、このときのぼくはそれを疑似体験しているようなものだった。勝手の分からぬ真っ暗な建物の中で姿の見えぬ巨大な動物たちに囲まれてじっと座っていると、いやでも五感が研ぎ澄まされていく。縞馬の蹄が床を叩くのか、ときどき「トントン」という音が聞こえる。ほかにも、何かが身じろぎするかすかな気配、鼻息。配管の金属部分から反射しているらしいわずかな光。空気の流れが変わるたびに寄せては返すいろいろな臭い。しかしそういうものの前に、この闇の中には音とか臭いとかに分化する以前のもっと濃密で原始的な感覚が充満しているようにぼくには感じられた。だから、白秋がささやくように読んだ「しつ。」「しつ。」「しつ。」は、ぼくにとっては音ではなくまさにそのときの原始的な気配を文字で表したものである。だからこそ「さうした声がするやうで、じつはしませぬ。」なのである。こうした感覚は実際に経験した者にしかわからないかも知れず、白秋が夜の牛舎でぼくと同様の感触を覚えたという想像を楽しんでもそれほど見当違いではないような気もしてくる。
さて、たいしてすることもないぼくは、とりとめのないことを考えているしかなかった。高村光太郎だったか、「何のために駝鳥を飼ふのだ」という有名な詩の一節のうち覚えている部分だけを、目の前で首を投げ出している駝鳥に言って聞かせてやったりした。また、真っ暗で何も見えないということは、逆にどんなものがそこにあるといわれても否定できないということでもある、などとも考えた。この理屈だけからいえば、そこの壁の隅で百鬼夜行絵巻が繰り広げられていても一向に差し支えはないわけである。このことと、実際に充満している野性の気配との相乗効果で、ぼくにはあらゆる不思議なものが眼前に踊っているように思われた。それこそ「甘藍がはらりと一皮はねた」り「雌蘂の花粉が唸っ」たりくらいはしていたに違いない。
周囲の静けさが、また、子どもの頃よく屋根に登って耳を澄ませた真夜中の街の音を思い出させてくれたりもした。真夜中の街はとても静かだったが、それでも少しは動いていて、明かりのついた窓があったり、ずっと遠くで車の音がすることもあった。そしてそのあとは、屋根の上の自分の耳に届くのは、何の音という定義のしようもない、ただ「音」としか名付けようのない不思議な音だけだ。絵の具の色を全部混ぜると変な一つの色になるように、町中のかすかな音を全部拾い集めて混ぜ合わせた、不思議な一つの、始まりも終わりもない、ささやくような音だった。昼間よりもずっと遠くから聞こえてくるその音を聞きながらこれまた遠い星々を眺めているうちに、決まって自分がいま本当に生きているのかどうかもわからなくなって居たたまれなくなった。そして逃げるように家に帰り、家族に気づかれないように布団にもぐり込んだものだった。こうしたことを性懲りもなく繰り返していた時期が、そういえばぼくにもあったのだ。
ふいに廊下の向こうでドアの開く音が、続いて足音がした。懐中電灯を振り回している。交代要員の来る時刻だった。新米獣医も一緒だった。ぼくは二言三言申し送りをして駝鳥舎を後にした。
件の駝鳥が死んだのは、それから二日後くらいだったと思う。
(*1)
北原白秋 『海豹と雲』(昭和四年)より
「トラピストの牛」
月夜であります。
月夜であります。
月夜である。
甘藍がはらりと一皮はねた、
重い羽ばたき、梟だ。
七面鳥は朱に青に、
膨れかへつて焦つてる。
とても明るい山独活だ、
雌蕋の花粉は唸つてる。
バタの香も新鮮だ。
燕麦、漆姑草、青蓬、
裸の子供のにほひもする。
さら、
さら、
さら、さら、さら、さら、唐黍だ。
赤い垂毛は目がさめて、
誰か来ぬかと待つてゐる。
暑い、暑い、暑い、暑い、
へえほう。と
虫も啼いてる、草むらで。
かあん。
と空鳴り、空の鐘。
月夜であります。
月夜であります。
月夜である。
「神父さん。」トントン。
「神父さん。」トントン。
「神父さん。」トントン。
「神父さん。」トントン。
「神父さん。」トントン。
「神父さん。」トントン。
「神父さん。」トントン。
「副院長さん。」トントントン。
「院長さあん。」トン。
「しつ。」
「しつ。」
「しつ。」
「しつ。」
「しつ。」
「しつ。」
「しつ。」
さうした声がするやうで、
じつはしませぬ。牛舎です。
暗さは暗し、静かです。
腐れたにほひ、乳のにほひ、
燦燦ひそむ黄金虫、
ひつそりとうつ尻尾の尖、
草のちり屑、
尿のにほひ、
また食べかけの向日葵の、
花も何処かに燃えてる筈。
眼。
眼。
眼。
眼。
眼。
眼。
眼。
月夜であります。
月夜であります。
月夜である。
「お乳が張つたあ。マリヤさま。」
トン。
「しつしつ。」
「しつ。」
後はひつそり、
牛舎です。