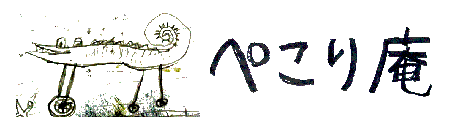■忘れ得ぬ人々
熱にうなされていると思考が後ろ向きになるのか、昔のことがいろいろ思い出されて仕方なかった。そこでこの機会に、昔の忘れ得ぬ人々のことを書き残しておこうと思う。 受験生生活1年目。仕事を辞め、大学に行こうと決心して住み込みの新聞配達を始めた19歳の頃。 ススキノの新聞販売店には社会の最下層のいろんな人が働いていた。窃盗癖のある男やインチキ占い師。売上を持ち逃げして捕まったあげく同じ職場に復帰した男などなど。雇う方も雇われる方も、相手を最低と思いながらもお互いを必要としていたのだ。そこに数人いた「新聞配達奨学生」という名の学生たちは学費を前借りしている弱みから特に劣悪な条件で酷使されていた。夕刊配達は日曜が休みだが、朝刊は年数日の休刊日以外は無休。交代要員なし。労働基準法という言葉すら誰も知らないにちがいなかった。ぼくらは常に空腹だった。一個のおにぎりを前にして、これをいつ食べれば空腹感を最小化できるかをいつも考えていた。栄養不足でいつも口内炎を一個か二個は抱えていた。そしていつも寝不足だった。 ある冬の日にこんなことがあった。奨学生のYという男が配達を終えて寮(という名のボロアパート)に帰る。寒いからストーブをつけようと思った。が、ストーブがない。おかしいな。仕方ないからテレビをつけようと思う。テレビがない。それじゃあまあお湯でも沸かそうか。するとヤカンがない。あらためて周囲を見回すと部屋は空っぽである。空き巣が家財一式を持ち去ったのだ。盗まれて困るような貴重品を持たないぼくらは、部屋に鍵を掛けるという文化もまた持たない。全財産を失った彼は、しかし陽気だった。損害はたかが知れているのだ。しばらくは仲間の部屋で過ごしたりごみ捨て場から家具を拾ったりしてやり繰りした。犯人はすぐにわかった。同じ販売店で直前まで働いていたOという大男だ。彼はぼくらが配達に出ている時間を知っていたし、鍵を掛けないことも知っていた。その時間を狙って空き巣に入り、持ち出せるものはすべて持ち出し、売り払った。数人いる学生のうちYが狙われたのは単なる偶然だった。Oはもちろん捕まったが、後に伝え聞いたところでは彼は刑を終えてまもなく販売店に復帰したらしい。もともと無口で要領の悪いOは、この事件の後も何事もなかったように淡々と働いたようだ。 ぼくらの寮があったのは、繁華街の裏の、札幌で最も貧しい吹き溜まりのようなスラム街だった。路地はビールの空き瓶や紙くずが散乱し、常に酒や嘔吐物の臭いがした。女の住む部屋のドアを蹴りながら叫ぶチンピラの怒鳴り声でしばしば起こされた。玄関もトイレも共同で一つずつしかない貧困者向けアパートがひしめいている中に、全ての窓が厚い鉄板で防護された豪邸の庭をドーベルマンが走り回っていたりした。「高度成長」「一億総中流」などと世間は浮かれていたが、ぼくには何のことかさっぱりわからなかった。 静まり返った午前4時過ぎ。いつものように人気(ひとけ)のないあるアパートの前で自転車を止め、いつもの部数の新聞を持って歩き出す。すると「◯◯!(男の名だったが忘れた)」と女の金切声がする。振り向くとパジャマ姿の女が泣きじゃくっている。ぼくの顔を認めるなり「ちがう〜!」といってまた泣く。どうやら寝ている間に男に逃げ出され、あわてて外に飛び出してぼくの姿を認め、男と勘違いして思わず呼び止めたということのようだ。その日一日、女の泣き声が耳から離れず受験勉強が手に付かなかった。 受験生生活2年目。 深夜にタクシーの洗車をするバイトをしていた。常に一人ぼっちで生きてきたぼくは、極端な礼儀知らずで気の利かない風変わりな若造だったにちがいない。ただ、仕事は一生懸命やった。そんなぼくを気にかけてくれる、Nさんという30歳くらいの男がいた。彼はススキノの風俗店での仕事のあと朝までここで働く苦労人だ。貧乏だったはずだが、真っ赤なおんぼろのクーペを乗りまわしていた。「アイヌの血を引いてるんだ」といって毛深い腕をまくってぼくに見せたりした。彼は、無口なぼくから身の上話を聞き出すのがうまかった。ぼくは、父親がいないこと、アパートの一人暮らしで受験勉強をしていることなどを間もなく白状させられた。そのうちに彼は時々仕事帰りにロイヤルホストで朝食をごちそうしてくれるようになった。「おまえは父親の愛に飢えているんだ」などと言うこともあったから、自分が父親代わりにぼくをかわいがっているつもりらしかった。ぼくはロイヤルホストがレストランだということを知らなかった。のみならず、レストランで注文をする手順、そこでものを食べる作法、支払いまでの流れ、そんな常識もまるで持ち合わせぬこと原始人の如くであった。とまどっているぼくをよそに、いつも彼は慣れた態度で勝手に注文し、適当に食べ、ぼくのアパートまで真っ赤なクーペで送ってくれた。ぼくはそんな彼の好意に対してどう振る舞えばいいのかわからなかった。ぼくはいつもぶっきらぼうだった。やがて受験をし、合格通知がきた。同時にこのバイトは辞めることになった。バイトの最後の日はいつになく作業量が多かった。ぼくはNさんに「合格したよ」と言い、彼は「そうか」と応えたようだった。しかしそのままお互い忙しさに呑まれ、それ以上言葉を交わすことなく帰宅した。ぼくはそれから新生活の準備のことで頭が一杯になった。それきり彼と会うことはなかった。 やがてじわじわと彼のことが思い出されるようになったのはそれから何年もたってからだ。思えば、彼に出会うまでは、ぼくにとって大人とはぼくから何かをむしり取ろうとする捕食者だった。ぼくのために何かをしてくれる大人に初めて出会ったと思った。誰かに感謝したいと初めて思った。 彼に別れの挨拶や感謝の念を伝えられなかった後悔は今でも棘のように胸に引っかかっている。