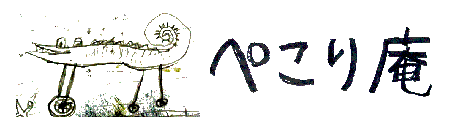■蟹
蟹は、夜の森を歩き続けた。海がどの方角にあるかなど、皆目分からぬ。そもそも海とはどんなものかさえ想像も付かぬ。只、己の血がそこへ向かえと命ずるばかりである。関節の一個一個から溢れ出てくるものが熱なのか体液なのか、そんなことは知らぬ。只、込み上げてくる衝動のために体じゅうがひりひりと熱い。これほど自分に海を渇望させるものは何か。生きるために向かうのか、死ぬためか。自分は昨日まで何処でどうしていたのか。果たして、この世に蟹というものは自分一人だけなのだろうか。そういった疑問の助けになりそうなものは真っ暗な森の中には何も見当たらなかった。鋭い八本の指節で草と泥を掻きむしりながら、蟹は只、夢中で歩いた。先刻からの雨があちこちに水溜まりを作っていた。蟹はその水溜まりの一つに辿り着くと、その真ん中へ飛び込んだ。ここが海か、と己に問うてみる。水。水。水に咽せ返って慌てて外へ転び出る。水ほど不快なものがこの世にあるだろうか。だが、自分はついこの間まで池の底で安穏として沙虫の死骸を漁っていたのではなかったか。そうした記憶が、突然甦ってはまた消える。
蟹が森を抜け畑に出た時、雨はすでに止んでいた。やがて厚い雲の隙間から丸く青い月がのぞく。蟹が叢の下からそれを見上げたとき、蟹の中の何か別の生き物が蟹の内蔵を噛む。蟹の体に白い電流が走る。蟹は弾かれたように歩を早める。自分はここに留まってはならぬ。死ぬためか生きるためかは知らぬ。ここではない、何処かへ。
月。今まで何回となく見上げてきたのではなかったか。どうして今夜の月だけがこうまで自分を駆り立てるのか。月へ向かえば海へ辿り着くのか。海とは、月のことか。巨大な満月は、抗いようのない腕力で蟹を引きずり込む。蟹は、月を目指して息もつかぬほど歩き、やがて行き当たった柱に取り付くと、我知らずそこを垂直に登り始めた。
柱と思っていたものは、着物の女だった。女は蟹を裾からぶら下げたまま、もう一人の女と共に歩き出した。東屋の軒先で二人で雨宿りをしていたのだ。二人の女は提灯を提げ、雨上がりの夜道を村へ向かって歩いた。姿を見せなくなった薬売りの噂、味噌、中新田からの乗合馬車……果てしのない生き物のような会話。やがて小さな川に差し掛かると、女は事もなげにそれを飛び越え、そこで女二人は別れた。蟹は、女が歩いていることにも頓着せず只無心に着物の裾をよじ登り続けた。細かな繊維の間に苦労して足掛かりを探りながら女の体を這い上がり、やがて後ろ髪に足が届くところまで辿り着いた。蟹は、もう目が見えなくなっていた。女の髪の匂い。これが海か、と蟹はまた己に問うた。その時、「きゃああ」という鋭い悲鳴がした。気が付くと蟹は空中に放り上げられていて、次の瞬間、地べたに仰向けに叩き付けられた。男の押し殺した声もどこからか聞こえたようだった。
ぬかるんだ泥の上で、蟹の指節の先が僅かに宙を掻いた。しかしその後は、もう動けなかった。堅い甲羅に女の髪が一本、纏わり付いていた。