
オオクワガタ成虫飼育方法
オオクワガタの特徴
♂35〜78mm
♀34〜50mm
からだは全体的に黒色50mm以下の雄は小歯型が多く55mm以下の雄には中歯型が多い、70mm以上の個体には大歯型多く、なかには湾曲が強いものもある。性格的には雄は優しく臆病であるメスは攻撃的である。メスは強い光沢を持ち比較的他のクワガタと見分けする事は容易い。
生態
成虫は5月〜9月に平地〜低山地に出現する。本州では台場クヌギと呼ばれる太くて背の低いクヌギなどの大木の樹液に集まる。昼間は木の洞に潜っていることが多く、夜にほかの虫とかち合わないように食事をする。大変臆病で光、音に敏感反応し、洞に逃げてしまうことが多い。この習性がオオクワガタを見つかりにくくし、採集をする事が難しかったと思われます。有名な採集地は採集者に荒らされたり、開発で木が切り倒されたりでオオクワガタを激減させている原因で生育地帯を少なくしている。
1.成虫選定
親虫は1ペアで飼育して下さい。メスはオスに比べて攻撃的です。サイズのバランスを考えたペアを選定して下さい。大型のオスほど交尾意欲が強く、交尾を嫌うメスを挟み殺してしまうことがあります。しばらく様子を見て相性の合わないメスとはペアリングをさせないほうがよいでしょう。しかし、もっと恐ろしいのはメスが蛋白質不足でオスを食べてしまうことです。しばらく一緒に居させたらオスを離してあげるといいでしょう。オオクワガタのオスとメスは仲が良く常に一緒に居ることが多いので大変わかりやすいと思います。
オオクワガタの成虫の選び方は、若い親で外傷のない親を選び、羽化後半年以上の成虫を使いましょう。古い個体は体重が軽くなるので若い元気な親を使うほうが産卵数も増えます。古いメスの親にはカブトムシの幼虫か蛹を与えます。(必ず回復し産卵数も増えます)手に入らなかったらバナナにヨーグルトを混ぜて与えて下さい。ヨーグルトはメスのタンパク質不足に効果があります。
近親交配(子供同士、親と子)を避けるために他からの血の入れ替えは必要ですが、あまり神経質になる必要はないと思います。本来、オオクワガタやヒラタクワガタはテリトリーを広く保つ事をしていないので、庭先の一本の木(クヌギ等)に累代して暮らして生きている事が多い。もし、心配な場合は何年か一回に雄、雌のどちらかを入れ替えればいいでしょう。また、雄で後肢の腿節・附節を失ったものや、雌で腿節を除く前足や大顎を欠いたものは使用しないほうが良いでしょう。
できれば天然物を入手できればいいのですが、野外でオオクワガタが採集できることは毎年難しくなっています。もし購入するなら、信用できるペットショップで購入して下さい。産地についてですが、産地で微妙な差が確かにありますので、成虫を見て自分の好みにあったものを購入すると良いでしょう。累代を気にするよりも個体の格好良さを気にすることをお勧めします。自分の目でしっかりと見て決め、好みの形を探す方がいいでしょう。後にその個体が、「佐賀産」であることを知る方が良いオオクワガタを手にすることができるでしょう。「天然採集、佐賀産」と表示があっても、それが本当に「佐賀産」である唯一の判断材料がショップの信用性です。特徴で産地を見分けるようになるまでには多くの個体を手にし、多くのオオクワガタに触れる経験が必要です。最近はそのブリーダーによって形が異なり、Aさんの家で生まれれば、「A血統」となりブランドとして取り引きされています。
メス35mmなら55mm以上でよいが、メス40mmなら65mm以上のオスを選んだ方がよいでしょう。メスの方が凶暴で、メスがオスの足を切ってしまうことやオスの腹を食い破り体液を吸ってしまうことがあります。メスは産卵前はタンパク質不足になり、タンパク質補給のためこのような行動をとることがあります。オスとメスの相性、餌不足には注意をしましょう。
2.産卵木の選定と準備
a.直径12cm以上の椎茸のホダ木を準備して下さい。天然木を使用する場合はいろいろな面で気を付けて下さい。「木に他の虫が混入していること。」「雑菌が多く産卵木としては適さないこと。」水で産卵木を浸けたぐらいでは虫(外敵)や雑菌は除去できません。産卵木にラップをかけ電子レンジでチンして下さい。こんな面倒なことをしなくても今は
市販で販売している産卵木のクヌギかコナラを購入して下さい。木の部分が柔らかく丁度爪で簡単に跡がつく程度がよいでしょう。
b.産卵木を水に一日浸す。木の内部に水分が行き届くようにします。乾燥防止です。
c.産卵木を日陰で乾かします。(半日ぐらい)
d.産卵木の皮を半分ぐらいマイナスドライバー等を使用し、はぎ取ります。産卵しやすいようにするためです。
3.ケースのセット
a.コンテナケースの用意(ケ−ス内の乾燥、虫の脱走などを防止です)
b.ケースの底に厚さ3cmぐらいの発酵マットを堅詰めで敷き、その上に先ほど用意した産卵木を並べて置きその間に発酵マット敷き詰めて下さい。
c.木の皮をその上に置いて下さい。隠れ家
d.餌を入れて下さい。(高蛋白のゼリーを使用して下さい。)
e.成虫をペアで入れて下さい。ペアリングがすんでいない場合はそのままオスとメスを入れたままにして下さい。ペアリングがすんでいる場合はメスのみ入れて下さい。
*後は飼育管理し3ヶ月後に産卵木を取り出し、木を少しずつ剪定ばさみ等で取り幼虫を割り出します。
4.飼育管理
a.ケース内が乾燥しないように気を付けて下さい。虫にとって乾燥は大敵です。
b.餌を切らさないように気を付けて下さい。
c.ケース内が32度以上にならないように注意し、夏場、暑いときはエアコンで温度調節を行って下さい。エアコンがない場合はなるべく涼しいところへ置き扇風機で風を送ってあげて下さい。
d.ダニが虫に多くつくようでしたら歯ブラシ等で軽く吹き、きれいに取り除いて下さい。ショウジョウバエやキノコバエは取り除いても取り除いても発生してきますので餌はこまめに交換して下さい。一番は、蠅取り紙が効果があります。
e.冬場の管理的には温度が下がれば産卵しませんので、冬場産卵するつもりのない人は乾燥だけ気を付けて下さい。加温し冬場も産卵させる方は室温を25度以上にして下さい。
5.繁殖管理


強制的にペアリングする方法と自然にペアリングする方法があります。強制的にペアリングする方法は、小さなケースを用意しその中にオスとメスを一匹づつ入れ軽く息を吹きかけますオスの触覚が動き始めメスに交尾行動をします。自然にペアリングする方法はオスとメスをいっしょにしておき自然に交尾を促す方法です。常に一緒になり、オスとメスがV字型に交尾したら早くて2,3週間で産卵が始まります。
産卵木をメスが坑道をあけてぼろぼろにしていきます。ぼろぼろにした産卵木は回収し、2ヶ月間ぐらいほかの飼育ケースで産卵木を保管します。(湿気を逃がさないようにして下さい) そのまま放置しておくとメスが孵化した幼虫を食べてしまうことがあります。
6.幼虫回収
産卵木を剪定ばさみ等で割り出していきます。1令幼虫、2令幼虫、卵が出てくるはずです。
取り出した幼虫はプリンケースで保管します。卵や一令幼虫の場合は発酵マットで管理し、二令幼虫に成長したら菌糸ビンに移し替えて下さい。
この時の注意としては必ず手を洗いなるべく幼虫を手で触らないようにして下さい。
7.幼虫飼育・管理
菌糸ビン



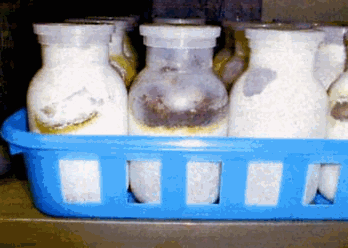

オオヒラタケなどの菌床は、幼虫を大きくするのによい餌です。ビンやプラスティクの容器で市販されています。この方法が現在一番多く用いられている方法です。特徴として、短い期間で大型の個体が作出できることです。ビンの交換時期もわかりやすく初心者でも容易に取り扱うことができます。しかし、夏場はビンの内部が発熱し死んでしまうことがありますので室温管理は必要になります。プラスティクよりビンの方が発熱しにくく取り扱いがしやすいでしょう。
菌糸ビンのサイズは500cc、800cc、1100cc、1400cc、2000ccといろいろありますが最初のビンは500ccか800ccでいいでしょう。キャップを開けてピンセットで皮膜をはがします。(この時ピンセットは必ずエタノールで消毒します)その中に静かに幼虫を入れキャップをします。
菌糸ビンの交換時期は3ヶ月ぐらいすると白いところが1/3になりましたら次の交換時期です。初二令で最初のビンに入れた幼虫は次のビンへ入れ替えるときには三令幼虫になっておりオスなら20g前後、メスなら10g前後に成長しています。次の菌糸ビンはオスは少し大きめ(1100cc〜1400cc)の菌糸ビンへ入れてあげると良いでしょう。メスはそままのサイズの800ccでいいでしょう。オスの場合はもう一回ぐらい交換すると思いますが、そのまま羽化する事もありますので観察をし続けて下さい。
自らで菌糸ビンを作成する場合は、菌糸をビンへ詰める場合はエタノールを用意し、部屋の中に噴霧します。雑菌が抑えることができます。菌糸ブロックを小間かくし、ビンの中に堅く詰めていきます。一週間ぐらいで使用可能になります。
☆注意事項
室温は絶対30度以上にしない。温度差のある場所には置かない。
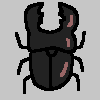

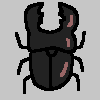
扇風機で風を送りガスの発生を防止する。
直射日光はさけ、なるべく暗い場所を選ぶ。
菌糸ビンの入れ替えは早めに行う。遅れると菌糸ビンの中の菌糸が泥状になり幼虫が病気になることがあります。羽化不全の原因にもなります。
前蛹、蛹の時は動かさない。
発酵マット飼育
前項の菌糸ビン飼育が盛んになる前はこの方法をみんなやっていた。
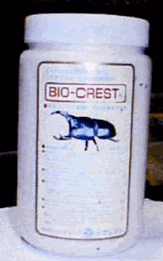

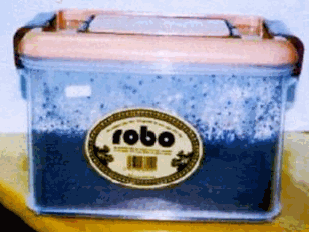
菌糸の代わりに小麦粉添加発酵マットをビンに詰め込み菌糸ビン飼育と同じように餌を交換しながら幼虫を成長させていく方法です。
材飼育
材飼育は小ケースにクヌギやコナラの処理した材を埋め込みマットと一緒にセットします。その後、幼虫を一匹入れ成長させていく方法です。
8.オス、メスの判別
幼虫の判別については、1回目のビン交換の時でいいでしょう。最初はわからないものですが、多くの幼虫を見分けるうちにオス、メスの判別は容易にできます。幼虫の体重を測定することで判別することもできます。1回目のビン交換時に体重が20g前後はオス、10g前後はメスと単純に分けることもできます。メスはこの時期(三令幼虫)には腹部に卵巣が見えてきますので判別できます。
9.クワガタムシ予備知識
クワガタムシは完全変態の形をとり長生きする昆虫で、卵から幼虫・蛹・成虫と、大きく3段階の変態を経て成虫になります。幼虫は卵から孵化したばかりの一令(初令)幼虫から1度目の脱皮で二令(若令)幼虫となり、二度目の脱皮で三令(終令)幼虫となり成長して行きます。三令幼虫から蛹になる前の期間を前蛹期という準備期間があります。
自然界ではオオクワガタは2年の幼虫期間を経て晩夏に成虫となり、そのまま蛹室内で越冬し、翌年初夏に野外に出て活動を行います。自然界で3年の寿命、飼育下では長くて4から5年の寿命と思われます。クワガタのほとんどは1年ぐらいの寿命ですが、環境条件によっては長生きする個体もいます。
幼虫で1年過ごすものを1年型、2年過ごすものを2年型といいます。
クワガタムシは成虫になってからは大きくなりません。幼虫期の生育環境、温度、餌の栄養価水分の関係で大きくなったり、小さくなったりします。太さやクワの大きさ、前胸の大きさは遺伝による影響が大きく形はオスの親に類似し、長さの遺伝はメスの遺伝が強いと思われる。
10.成虫管理
羽化して間もないクワガタムシは餌を食べませんが、しばらくすると16gゼリーを一日で食べてしまいます。餌は多く入れずなくなったときに交換してあげるといいでしょう。
もし、かびが生えたり色が変色した場合は交換して下さい。マットはクヌギ発酵マットでいいのですがショウジョウバエが発生しやすく臭いがしますので、針葉樹マットをお勧めいたします。雑菌がわきにくく臭いもだいぶ抑えられます。
他のクワガタの飼育方法
(ラコダール、ルデキング、ワラストン)

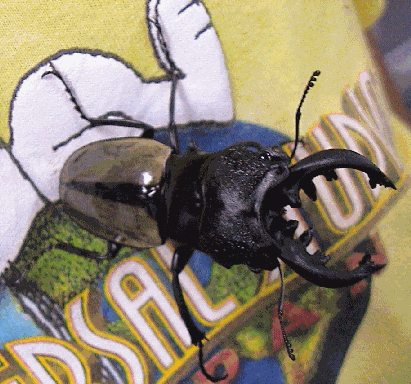
繁殖セットとしては、ケースを用意しその中にアンテマットを軽く「ふあーと」入れていきます。産卵木はいりません。マットは水分が幾分多めの方がいいでしょう。3ヶ月してから幼虫を取りだしてみて下さい。幼虫はアンテマット(発酵マット)で飼育します。古いマットに新しいマットを加えていく方がいいでしょう。菌糸ビンへ入れても死んでしまいますので注意をして下さい。飼育下では短歯型がでやすく大変難しい種類です。
(タランドス・オウゴンオニクワガタ)
繁殖セットは菌床の強い飼育材かカワラタケの菌糸ビンを使用します。菌床の強い飼育材は霊糸材かカワラ材をアンテマットの中に皮を取り埋め込みます。カワラタケの菌糸ビンの方法はアンテマットの上にビンを寝かせておく方法です。この両方のやり方を併用する方がより確かなやり方といえます。タランドスの幼虫は、カワタケの菌糸ビンを使用する方がよく育つと考えられます。タランドスは幼虫期間が短く最短で3ヶ月で羽化してしまうこともあります。
(アンタエウスオオクワガタ)
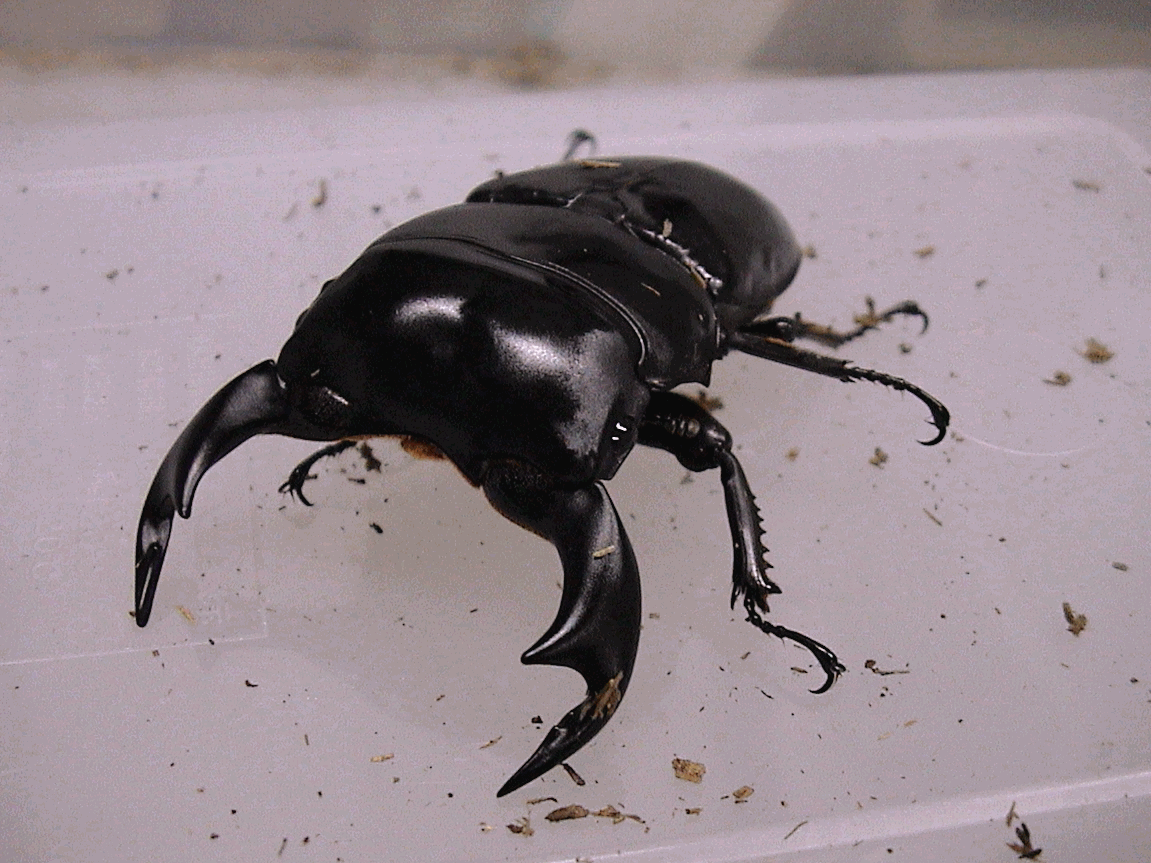
繁殖セットとしては、ケースを用意しその中にアンテマットを5cmぐらい堅く底に詰めます。水分は多めでいいです。その上に隠れ家になる木を置きセットします。強制ペアリング後、メスのみ入れる方が集中して生んでくれるでしょう。幼虫は、菌糸ビンで育てます。オスは大変大きくなりますので2Lぐらいの大きなビンで育てて下さい。
(ニジイロ)
繁殖セットとしては、ケースを用意しその中にアンテマットを5cmぐらい堅く底に詰めます。水分は多めでいいです。その上に隠れ家になる木を置きセットします。オスとメスを一匹づつ入れて下さい。幼虫は菌糸ビンで育ちますが、発酵マットでも十分育ちます。
(ヒラタクワガタ)
おおむねオオクワガタの飼育方法と同じでかまいません。注意しなければならないことは外国産のヒラタの幼虫は体長が大きくなるのでそれなりの大きいビンで飼育して下さい。菌糸ビンでも十分成長し、ある程度は大きくなりますが栄養が多いため成長が早くなり体長が伸びきれない傾向があります。発酵マットで飼育する方が幼虫期が長いので


十分熟成されて、より大きい個体が作出が望まれます。多く産卵しますので計画的に飼育しましょう。
(ミヤマクワガタ)
繁殖セットとしては、ケースを用意しその中にアンテマットを5cmぐらい堅く底に詰めていきます。その上にオオクワガタと同じ処理した産卵木を皮をはいでマットで包み込むようにセットします。マットは水分が幾分多めの方がいいでしょう。3ヶ月してから幼虫を取りだしてみて下さい。幼虫はアンテマット(発酵マット)で飼育する方がいいでしょう。
(ギラファ)

繁殖セットとしては、ケースを用意しその中にアンテマットを5cmぐらい堅く底に詰めていきます。材はオオクワガタと同じ処理した産卵木を皮をはいでその上に置き、産卵木が半分ぐらい隠れるようにマットを敷きます。マットは水分が幾分多めの方がいいでしょう。3ヶ月してから幼虫を取りだしてみて下さい。幼虫はアンテマット(発酵マット)、菌糸ビンでもどちらでも育ちます。注意として多く産卵しますので、後のことを考えて飼育しましょう。
(セアカフタマタ)

繁殖セットとしては、ケースを用意しその中にアンテマットを5cmぐらい堅く底に詰めていきます。材はオオクワガタと同じ処理した産卵木を皮をはいでその上に置き、産卵木が半分ぐらい隠れるようにマットを敷きます。マットは水分が幾分多めの方がいいでしょう。3ヶ月してから幼虫を取りだしてみて下さい。幼虫はアンテマット(発酵マット)、菌糸ビンでもどちらでも育ちます。飼育したものは野外のものより小さいことが多く、80mmを超えれば成功と言えます。