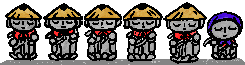山添村のほぼ中央の、平らな円錐形をした神野山(618m)は、かつては火山であったとか、いや、岩石が硬いので浸食に耐えた「残丘」であるなどと言われ、地元の人には「神の山」と言って親しまれている。五月はツツジ、夏はキャンプ、年間を通じて手軽なハイキングコースである。
名張川流域には縄文早期の遺物が数多く出土し、布目ダム建設のときの布目川流域の発掘調査では、縄文及び南北朝時代の遺物や住居跡が発掘されたとか。これらのことが、この村の太古からの長い歴史を物語っている。ダムの湖底に水没しかかった幾つかの遺跡や磨崖仏は、この村の人々の手厚い保護により、今は安全な場所に移されている。
8月2日、大阪の日中の気温が何年ぶりかに38度を越える炎暑。奈良地方もそれに近かったであろう。地図で見ると遠隔の地に見えた奈良県北東端の山添村も、名神高速・近畿自動車道・西名阪・名阪国道をひと走り、1時間30分で神野山登山口に到着した。村の中央を南北に名阪国道が走っているので意外に便利であった。多くの石仏は車道の傍にあるので、この季節しんどい目をして歩くより車が楽である。