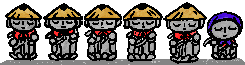山の辺の道の石仏 【桜井・天理】 2000.9.15
- 山の辺の道は、奈良盆地東側の山麓を南北に、桜井から天理まで16kmの緑ゆたかなハイキングコースである。桜井駅から金屋の石仏まで約30分、ここは三輪そうめんの産地でもある。古代大和朝廷のころは交通の要衝。交易の市が立ち、歌垣が催されて多くの男女の出会いと別れがあったとか。そのような歴史の断片を、ところどころの案内掲示板で知る。ここからののどかな山沿いの道は「山の辺の道」という名称がぴったりである。今日のメインは長岳寺と念仏寺付近の石仏。
- 途中、日本最古の神社の一つ、三輪山を御神体とする大神神社を訪れ、そこから間もないところの桧原神社で昼食。長岳寺に着いたのが午後2時前。長岳寺の敷地は広いが目的の石仏をすぐ見付ける事が出来た。念仏寺はここから30分ぐらいのところ。しかし、竜王山を背景にした野に佇む石仏群を見付けることができない。天気予報通り雨が降り出した。探すこと2時間、地元の3~4人のひとに資料写真を見てもらったがわからない。やがて大雨になり石仏はあきらめた。天理まで行くのも断念、バスで桜井駅に戻ったのが午後6時前であった。
-
山の辺の道
-
金屋の石仏
右が釈迦、左が弥勒で凝灰岩に等身大に彫られている。石棺の蓋であったと思われる。重文であるため、収蔵庫の鉄格子ごしにしか拝観できない。時代は平安とも奈良とも云われている。願い事を一つだけ聞いて下さる。欲張ってはだめとか。 -
念仏寺付近の畦道の石仏
-
長岳寺の笠塔婆
塔身上段は地蔵立像(半肉彫り)。 中段は二僧坐像(薄肉彫り)。 元亨2年(1322)の紀年銘がある。 -
長岳寺の弥勒石棺仏
法量は2メートル近い如来形。鎌倉時代。 「弥勒菩薩は今、都卒天で成道をめざして修行しており、56億7千万年後に如来となってこの世に下生して、輪廻転生するわれわれの魂を救済すると云う。」長岳寺パンフレットより。 -
長岳寺の池の畔の石仏