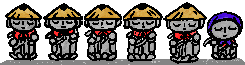柳生街道は春日山の奥深い原始林に囲まれたひなびた山道である。新薬師寺附近から柳生へ通じるこの道は、奈良時代には平城京から東国への近道であったため街道の名が残っているとか。その昔、多くの柳生の剣豪がこの街道を往来したであろう。街道沿いには平安・鎌倉期の磨崖仏、石窟仏が多く点在し「春日山」の名のように極めて清浄な神や仏の世界が古い歴史を語りかける。
JR奈良駅に着いたのが9時、2時間に1本しかない柳生行きのバスは8時半に出たばかり、タクシーで行くには遠すぎるので次のバスを待つことにする。周辺をぶらぶら歩き、10時ごろ近鉄奈良駅バス停へ行って見たら既に多くのハイカーが行列していた。勘をはたらかせてJR
奈良駅のバス停迄戻ったらズバリ的中楽々座ることが出来た。
今日は新薬師寺と柳生の中間点、忍辱山の円成寺までバスで行き新薬師寺へ戻ってくるコースである(約12km)。 忍辱山(にんにくせん)は円成寺の山号で忍辱とはあらゆることに耐え忍ぶという意味で、ここは修行の聖地であったとか。円成寺は春日信仰にかかわり深い古寺で日本最古で最小の国宝建造物である春日造り社殿が在る。ハイキングは円成寺横の東海自然歩道からはじまる。平日はほとんど人と出会うこともなくひたすら奈良へ向かって歩くのである。コースの中間点附近に江戸時代から続く茶店がある「峠の茶屋」である。この辺りから石仏巡りがはじまる。地獄谷石窟仏、春日山石窟仏、首切地蔵、朝日観音、夕日観音と巡り無事デジカメに収めることが出来たが途中ちょっとしたハプニングがあった。
地獄谷石窟仏から春日山石窟仏へ行く途中、道標にしたがっていたつもりだが道に迷ってしまった。丁度山で仕事をしている人(奈良営林署の人と思う)がいたので道を尋ねようと思ったら逆に「なぜこの山に入ってきた」と叱られた。「ここは国有林だから無断で入ってはいけない」という。道を尋ねるどころか逆に追い返されそうになった。私有林だったら仕方ないと思ったが国有林であると聞いて、道に迷っている者に対するその態度に腹が立った。こっちは40数年税金を納めてきたんだぞと言ってやりたかった。50mほど先に道標らしいもの見えたので、そこまで行かせてくれと言ったら「わしが見ていて通す訳にはいかん」と言う。横を向いていたので、ここは穏やかにと思い「済みません、これから気を付けます」といって、ちょっと離れた所に居た家内に合図して素早くその場を通り抜けた。道標は「地獄谷石窟仏はこちら」とあった。もとへ戻っていたのである。1時間ロスってしまった。疲れがドット出てきた。新池近くの道標には注意。
⇩ 剣豪柳生十兵衛の弟子、荒木又右衛門が試し切りに首を切ったという伝説がある が、いくら軟質な凝灰岩とはいえ、刀で切るのは無理であろう。伝説とはそういうものであろうか。
- ⇩ 石材を採掘した凝灰岩の奥壁中央に如来坐像(写真)、両脇に薬師と十一面観音 立像が線刻彫りされている。朱色の彩色は古いものではなく、昭和20年代に誰かが着彩したらしい。
- ⇧ ここの石窟仏は、大仏殿を建てるために石材を取った跡に彫られたもので、石仏は全部で18体あるが、写真はそのうちの東窟に彫られた六地蔵の四体である。誰が彫ったのか明らかでないが、 大乗院の一僧(山伏)が岩窟に起居して彫刻したとか、石材を掘り取ったときに石工が彫刻したとか言われている。
- ⇩ 西向きの岩肌に彫られているので夕日観音と呼ばれている。資料によると会津八一が「その表情笑うが如く、また泣くが如し」と評したとか。朝日観音と同一作者が彫ったといわれている。
- ⇧ 岩壁に彫られた朝日観音は、早朝、高円山の頂から差し昇る朝日に真っ先に照らされることから名付けられたもので、実際は両側に地蔵菩薩を配した弥勒如来である。機会があれば朝日に照らされた瞬間を見てみたい。
- 帰りは街道の渓谷に沿った石畳の滝坂道を下って新薬師寺まで。ここの石畳は江戸中期に奈良町奉行が敷設したとかで周りの原始林と相まって歴史を感じさせる格別の風情がある