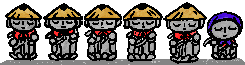当尾の石仏【京都府・加茂】 2001.4.2
- 春真っ盛りの四月二日京都府相楽郡加茂町の当尾(とうの)の里を訪 れた。当尾は今こそ草深い山村であるが、すぐ南は古都奈良に接しその 昔は世俗化した奈良仏教を厭う僧侶の隠遁の地であった。今を去る千二 百年前の聖武天皇が岩船寺、浄瑠璃寺を建立したことから大きく開け鎌 倉時代戦火に焼けるまで地域一帯は九十九の堂塔・伽藍が軒を連ねそ の眺めが「塔の尾根」のようだったことから「当尾」の地名が生まれたと言 われている。 当尾の浄瑠璃寺から岩船寺に至る約7kmのハイキングコースは「石仏の里」を訪ねる「石仏めぐりコース」になっている。山中の散策路には名匠の手による有名石仏の他に、名もない千以上もの同地に住んだ人々の傑作が点在し、その時代の村人の信仰心の豊かさがうかがえる。「草にうもれた大衆芸術」、「信仰心が彫らせた住人の力作」である。
- JR奈良駅からバスで浄瑠璃寺へ、平日とはいえ花のシーズンでもあり 座席はほぼハイキング客で満席。浄瑠璃寺の参道の背の高いコブシは満 開だったが本堂前の桜はまだ10日は早いようであった。寺の入口のみや げ物屋には昔懐かしい駄菓子が並び、生姜入りの芋アメを買った。 岩船寺から約10分ほど山道を下ったところに赤田川へ注ぐ支流が滝を つくり、日の光をさえぎる鬱そうとした所に浄瑠璃寺奥之院の不動明王像 がある。 もとの道へ戻って岩船寺までの石仏の里めぐりは普通に歩けば2時間の 里道山道コースであるが、石仏の見方によっては1日でたりず、何回も出か けることになるのであろう。石仏の表情は四季折々の背景によって、また見 る人のうつろう心によって変化するのであろうなどと考えながら岩船寺に到 着したのが3時過ぎであった。名物のアジサイは6月の中旬が見ごろと寺の 僧が言っていた。そのころには修復中の本堂の覆いもとれるとか。
- 岩船寺地域の民家は、普通の長閑な山村の農家のたたずまいであるが、 かつて浄土信仰の霊地として栄えた歴史的背景を思えば、信仰と深く係る 独特の風土を感じることが出来る。 道端の所々にお茶や椎茸・赤唐辛子・切干大根などを吊るした無人販売 所がある。JR加茂駅行きのバスを待っていたら、売店のおばさんが「こしか けなせぇ」と言ってイスを出してくれた。「最近はUSJに客をとられてさっぱり やで」とこぼしていた。
-
浄瑠璃寺奥之院の不動明王
永仁4年(1296年) 豪快で毅然とした不動明王は奥之院の淨域をじっと見守っている。
-
一願不動明王磨崖仏
弘安10年(1287年) 岩船寺近くの山道をちょっと下ったところの竹薮の木漏れ日に映える不動明王は、この世のありさまをキットにらんでいる。「願いごとがあったら一つだけ叶えてあげるよ」。
-
からすの壷阿弥陀如来坐像
康永2年(1343年) 願主は恒性、舟型光背を持つ定印の阿弥陀仏で、向かって右横の小さな穴は線刻の燈籠で、灯明を供えることができる。
-
からすの壷地蔵菩薩立像
康永2年(1343年) 願主は勝珍、左の阿弥陀如来巨石の向かって左側側壁にこの地蔵さまは彫られている。うっかりしている見過ごしてしまう 。
-
笑い仏
永仁7年(1299年) 願主は岩船寺住僧、大工末行。 向かって右は 観世音菩薩坐像 、 中央は 阿弥陀如来坐像 、 向かって左は 勢至菩薩坐像。当尾の石仏の中で最も知られた阿弥陀三尊像である。中国の名工、伊行末の子孫、末行の作であるとか。
-
眠り地蔵 南北朝時代
像容が素晴らしく、おそらく名匠の作と思われるが、永い年月の間に地盤変動があって埋もれてしまった。今は、「笑い仏」の傍で静かに眠っておられる。いや、眠りたいけど今の世の中の有様を憂えて眠れない日々を過ごしておられるのかも。
-
三体地蔵磨崖仏
鎌倉末期 岩船寺近くの山中の巨石に彫られた三体地蔵は、過去、現在、未来の三界の安寧を祈っておられる。六地蔵信仰が広まる以前の一つの形態で、とても珍しい石仏であるとか。
-
一龕(いちがん)六地蔵石仏
南北朝時代 岩船寺近くの墓地の入口に珍しい六地蔵が あった。何処が珍しいかと言うと、一つの石龕 (石の厨子)に六体の地蔵が彫られているか らである。
-
tono9
-
tono10
-
tono11
-
tono12
-
tono13
-
tono14
-
tono15
-
tono16
- 【当尾の石仏推薦の弁 】 石仏研究家 太田古朴さん 昭和42年6月10日 朝日新聞より ~夢をさそう素朴な姿~ 石仏は、ほとけさまのなかでは安物だといわれるかもしれません。しかし、道ばたに立って、いつも民衆の中にあり、いまでも近所の人の信仰を受けている石仏は、生きたほとけさんといえるでしょう。石仏を見る楽しさは、孤独を味わう楽しさともいえます。風化して、銘も読みにくくなった石仏をじっとながめ「さて、どんな人がつくったのだろう。なにを願ったのだろう」と、夢は過去へと広がります。単純、素朴なものが多いだけに、だれでもが勝手に描ける、楽しい夢です。そんな石仏がかたまっているのが、浄瑠璃寺周辺の当尾でしょう。