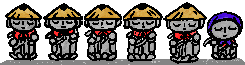- 狛坂磨崖仏(平安前期) たて6メートル、よこ4.5メートル。花崗岩 の北面に半肉彫り。壇上中央が宣字座上の阿弥陀如来坐像。その両側に蓮台付脇侍菩薩立像。 上部には9躯の化仏を配している。 磨崖仏は明治直前に焼失した狛坂寺(金勝寺の別院で今はその跡が残っている)の建立前に狛長者の寄進によって時の名工に命じて造像されたとか。
- 逆さ観音(鎌倉時代) 逆さまに彫ったのではなく、ダム用の石を採掘したときに裏が削られて倒れた。
- 【石仏辞典】日本石仏協会編「石仏巡り入門」より
- 磨崖仏=山間に切り立って露出する岩壁、又は大岩や岩塊に彫られた石像。更には石窟・洞穴・古墳穴などの壁面に刻まれた穴仏も磨崖仏と云っている。石工は岩盤を「生き石」、大岩や岩塊を「死に石」といっているが、「死に石」に刻まれた石仏も磨崖仏に違いはない。その他、岩壁に種子や仏名・名号・題目・戒名など文字を刻んだものを磨崖碑、塔を掘ったものを磨崖塔と別称されている。古代の日本では自然信仰が盛んだった。 特に山岳信仰や山神信仰・巨岩信仰が各地に根付いていた。山がちな国土をなすわが国では、富士山に代表されるように、山岳それ自体に畏怖を感じ、霊力ある神として崇拝されていた。
- 仏教が日本に伝えられてから(6世紀前半?)、古代日本の山岳信仰ないし山神信仰に一つの変化が生じた。かつて山岳それ自体が聖なる存在であったのに対し、仏教伝来後、山岳の一崖に仏像が刻印されるようになると、今度はこの刻印された仏像のほうに聖性ないし神聖が移動したのである。それを端的に象徴し、その証拠を現在に伝えているものが、磨崖仏である。仏教伝来以前の神道では自然物をそのまま神とすることはあっても、彫像の類を神とすることはなかった。神道でも神形の彫像を崇拝するようになったのは、明らかに後代における仏教の影響である。 その意味からしても磨崖仏は古代日本の造形美術史上、画期をなす石仏である。