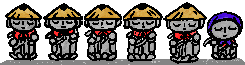- 葛城の道は、奈良盆地の西南端に位置する奈良県御所市の西部にあり、葛城・金剛山系の麓を南北に結ぶ全長約13kmの里道である。葛城山麓は朝日を受ける好立地と、山から流れる清流によって古代から豊かな穀庫地帯を形成してきた。そうした経済を背景に豪族葛城氏が繁栄したのである。又、この地方は古墳文化以前の日本の神々の信仰や、数々の神話のふるさとでもあり、格調高い古社が多い。そのような環境の地において石仏を見つけるのは難しいかなと思いながら調べてみたら、いくつかの石仏があるのを知った。「葛城の道」を紹介するとき必ず出てくる六地蔵と九品寺の千躰石仏、弥勒寺の峯山百体観音霊場石仏である。これ以外にもいくつかの石仏があると思うが見つけたらこのページに追加していきたい。


- [六地蔵] 葛城の道の始発点、猿目橋近くの住宅地のまん中に、巨石に刻まれた六地蔵がある。田畑を潤し、多くの恵みをもたらす葛城山の清流も、ひとたび牙をむくと大自然の脅威を見せつける。灌漑が発達していない古代、中世においてはなおさらである。六地蔵巨石も室町時代に発生した大土石流でこの地に流れ着いたといわれている。人々は度重なる災害や疫病からのがれるため、又、来世の極楽浄土を願う強い信仰心から、この巨石に六体の地蔵を彫ったのであろう。


- [九品寺(くほんじ)の千躰石仏] 九品寺は浄土宗知恩院派の名刹である。この寺を有名にしたのは、寺の裏山の地下から総数1800余体の石仏が発掘された。伝承によると、南北朝時代にこの地を支配していた豪族、楢原氏が南朝方について北朝と戦ったとき死んだ兵士たちの「身代わり地蔵」として奉納されたものといわれている。今は、寺の裏山の段々上に整然と並べられている。高い樹木が覆いかぶさり昼間も薄暗く、霊的な雰囲気が漂う。この場所にしばらく佇んでいると、兵士たちのすすり泣きが聞こえてくるようである。

-
- [峯山百体観音霊場石仏] 峯山観音霊場は葛城の道の終点、東佐味にある。観音様は三十三様に姿を変化して無限の慈悲でこの世の生きとし生けるものの苦難を救うという。平安時代に観音様の三十三化身と女性の厄年の三十三才が一体となり、三十三ヶ所の霊場を巡礼する風習がはじまった。峯山百体観音霊場は、西国、秩父、坂東の三ヶ所の霊場の観音様を祀り、一山を巡ればごりやくが3倍というわけ。

- 峯山百体観音霊場の石仏 (文化五年)1808年 これは、とり小屋でも犬小屋でもない。 この小さな祠の中に観音様がいらっしゃる。 格子越しにしかお顔が拝見できないのが残念。
-
- 【石仏辞典】 日本石仏協会編「石仏巡り入門」参考 六地蔵=寺や墓地の入り口、道端に並んで造立されている六種の地蔵は、来世において六道(衆生が来世に住むところを、前世にした業により地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の6種に分けられている。六界ともいう。)に現れて衆生の苦しみを救済する。像容は1体づつ彫って6体並べたもの、一石に6体彫ったもの、3体づつ二石に彫ったもの、石幢や石柱に彫ったものなどがあり、配列は一定していない。平安時代末期、疫病除けと道祖神信仰が結びつき六道輪廻信仰の主尊となり、庶民信仰の代表的な存在である。