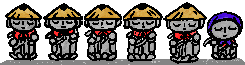円覚寺の百観音(北鎌倉)
JR北鎌倉駅より徒歩2分、ほぼ地続きのところに円覚寺がある。広い境内の樹木や草花を楽しみながら方丈の庭へ。ここに坂東33、秩父34、西国33、合計100の観音石像が整然と並んでいる。さながら美人コンテストのようである。優しい顔、可愛い顔、厳しい顔、悲しそうな顔、艶やかな顔と実に表情豊かに見る人を魅了してくれる。
「およそ700年前の文永・弘安の二度にわたる蒙古軍襲来という空前の国難を迎えた時の執権北条時宗は国を挙げて蒙古の大軍を撃退した。時宗はかねてより深く禅に帰依し、弘安の役のさなかにも、中国から招いた仏光国師を師として、日夜禅に励んでいた。時宗は、文永・弘安両役に殉じた彼此両軍の菩提を弔い、己の精神的支柱となった禅道を広めたいと願い円覚寺を建立しした。」以上、円覚寺パンフレットより。 今は各種の座禅会が開かれ、静かな境致と共に人々に深い心の安らぎを与えている。
- 東慶寺のお地蔵さま(北鎌倉)
- 横須賀線北鎌倉駅から4~5分。東慶寺は明治に至るまで男子禁制の尼寺で、駈込寺、 縁切寺として多くの女人を救済したとか。今 は男僧の寺である。境内の中ほどに身の丈 30~40センチの小さなお地蔵さま。苔むした石垣を背景に愛らしく佇んでいる。訪れる人々の幸せをひたすら願っているようである。
- 北鎌倉には、北条時宗が眠る円覚寺と、時宗夫人が眠る東慶寺が、JR横須賀線を挟んで向かい合わせに立ち、今も仲睦まじい姿を見せている。
- 東慶寺は、時宗の夫人(覚山尼)が弘安8年(1285)に開創した尼寺であった。時宗夫人がどうして尼寺に入ったか定かでないが、戦乱の中、男たちの犠牲になった女を見て、女人救済を思い立ったのであろうか。駆け込み寺として庶民に親しまれた東慶寺には、多くの女たちの物語が秘められている。
- 鎌倉の六地蔵
- 鎌倉駅より南へ、長谷通りを10分ほど行くと 国道134号線と交差するところに、鎌倉に住ん だ人なら誰でも知っているであろう、ふるさとの 思い出でもある六地蔵がある。ここは昔刑場が あった場所と云われ、それにちなんで、六地蔵 の後ろに芭蕉翁の奥の細道の一句「夏草やつ はものどもが夢の跡」の句碑が建てられている。
- 九品寺の六地蔵
- 鎌倉駅からバスで6~7分、由比ヶ浜の 隣の材木座海水浴場の近くに九品寺があ る。この寺は建武3年(1336)新田義貞が 鎌倉を攻め滅ぼした時に建立したとか。こ の寺の有名石仏は薬師如来座像であるが 「現在は鎌倉国宝館に出陣中です」とあっ た。寺からちょっと浜辺の方へ行くと、サー ファーや、サーフボートを積んだ車が往き来 する。いかにも鎌倉らしい風情である。
- 鎌倉市岡本。JR大船駅から西へ約6分柏尾川沿いの路傍に佇む六地蔵。ここは玉縄首塚のあるところ。1526年玉縄城主北条氏時が鎌倉を攻略せんとして攻込んできた南總の武将里見義弘と戦った場所。 今、六地蔵は庶民の日常の生活の無事をひたすら願っているようである。
岡本の六地蔵

- 禅の精神が息づく円覚寺 小学館 週刊「古寺をゆく」 2001/6/19 より
- はじめて円覚寺の門の前に立ったとき、そこに俗世間とは違う気配が漂っているのをはっきりと感じる。北鎌倉駅に降りて円覚寺のうっそうとした森を眺めたとき、すぐそこに『門』の世界が広がっているのだと思うと緊張する。総門をくぐると木立に囲まれた境内は、たしかに黒々と陰っている。円覚寺の静寂には意味があるのだ。そのせいなのか、ここを訪れるものは誰もが寡黙になり、生きる意味について考えたくなる。いかに生きるべきか---。それは今も変わらぬ私たちの不変の問いである。厳しい時代であればあるほど、人は生きることに苦闘し、迷うものかもしれない。道を見うしない、生きにくさを感じたら、この寺を訪ね、心ゆくまで歩き、たたずむのがいい。円覚寺はけっして簡単に答えを与えてはくれまい。しかし、いつの時代も生き悩む人々を厳父のように迎え、励ましてくれるだろう。