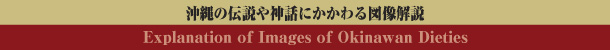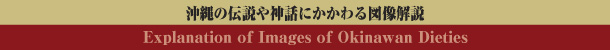|
(ウナイ・ウィーキ像、天孫氏(子)像、家族像、母子像、女神像など)
拝所などに安置されている図像の中には、仏教に由来する図像、道教・儒教に由来する図像、また神道神などの図像とは別に、比較的新しく沖縄で創作されたと推測される図像群がある。その中には、「ウナイ・ウィーキ」と呼ばれている琉装の男女の像(図26)(今帰仁村今泊、湧川屋のもの-図25-、今帰仁村古宇利島兼次さん宅東棟空き家)、天孫氏像(国頭村辺戸、ノロ殿内)、家族像(大宜味村田嘉里、今帰仁村湧川新里屋)(図27、30)母子像(大宜味村田嘉里、国頭村宜名真宜名真神社)、女神像(図33)(今帰仁村湧川新里屋別棟、今帰仁村平敷)などがある。
これらはかなりの腕の日本画家によって絹本に描かれたもの(今帰仁村湧川新里屋の家族像、同別棟の女神像、今帰仁村平敷の女神像)から、劇画風のもの(国頭村辺戸ノロ殿内の天孫氏像)、また木彫(国頭村宜名真宜名真神社)まで多彩である。作者名が記されているのもある。注文によって制作されたと言われているものや、作者がお告げによって制作し奉納したと伝えられるものもある。
今帰仁村湧川新里屋の家族の像や、同所別棟の女神像は、その衣装など日本の古代神話に着想を得ているようである。女神像は手に三つの玉を持っている。新里屋に置かれているその他のいくつかの絹本も含み、これらの作者は、明らかに本格的に日本画の訓練を受けた画家である。これらは首里から来た画家が描いたと言い伝えられており、たとえば様式の上からも柳光観のような画家を考えることができる。柳は京都で日本画を学んだ人物である。
国頭村宜名真宜名真神社の木彫の母子像は、「じしち母神」という名がついており、傷みがはげしく詳細が見て取れなくなっている今帰仁村平敷の女神像は「生母の神 義本王の神」と呼ばれたり、観音と呼ばれたりしているが、それぞれの作例は、それを管理する門中や集落によって異る意味を賦与されているのであろう。いずれにしても、それらは祖先崇拝の中で門中の始祖や、その誕生の物語に関わっているように思われる。家族像の中には男がヘラなどの農具を持っているものがある(図27)。農耕の始まりと始祖の誕生とを結びつけているものかもしれない。ウナイ・ウィーキ像も創世神話を通して、始祖たちを描いたものと思われる。安達義弘氏は、祖先祭祀の中での沖縄人の自己アイデンティティーの獲得の営みが、明治初頭以降に成立した「長浜系図」を下敷きとした天孫氏を始祖とする「祖先由来記」に収斂していったことを述べているが、図像の中には天孫氏を描いたものもある。
たとえば関羽や千手観音の図像などは、現在拝所や個人宅に所蔵されているものの多くが描き直しされたものであるとはいえ、王朝時代から制作されていたのにたいし、おそらくこれらの図像は比較的新しいのではないかと考えられ、あるいは、上述のような始祖同定の希求の中で、各拝所での祖先祭祀に伴って語り継がれる始祖の物語や創世神話などを図解し、権威づけするために作られていったのかもしれない。
安達義弘
『沖縄の祖先崇拝と自己アイデンティティー』九州大学出版会、2001年
『沖縄県姓氏家系大辞典』角川日本姓氏歴史人物大事典47,平成4年
|