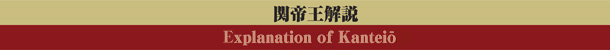|
関帝王とは、三国時代(220〜280年)、蜀の劉備を扶けて功あった名将、関羽(162?〜219年)のこと。字は雲長、河東解県(現山西省臨猗付近)の人である。彼にまつわる逸話・伝説は、正史のみならず雑多かつ広範な メディア、とりわけ芝居や語り物・小説・連環画などを通じて広く受容され、民衆レベルでの圧倒的な人気と尊崇を 博してきた。一般的には「関帝」「関公」の敬称がある。関帝信仰はまた、国家レベルにおいても重要な意味をもつ。その神格化はすでに唐宋代に始まるが、宋代には「武安王」、明代万暦22(1594)年には「協天護国忠義大 帝」に追封され、清代には皇室の守護神となった。その崇拝は儒教・道教・仏教を問わず、山西夫子、伽藍菩薩など の諡が贈られている。関帝廟は全国津々浦々に遍布し、華僑の海外進出に伴い広く海外へも伝播したことは周知の事実である。関帝に付された最も典型的な性格は、「勇武」「忠義」の権化としてのそれである。が、また発財・地獄の神・・・などといった多様な機能も与えられており、概して万能の神といえる。
「関帝王」の呼称は沖縄独自のものである。いっぽう、「ウンチャンチーチン」という呼び名は、道教における「関帝聖君guan-di-sheng-qun」(或いは「文昌帝君wen-zhang-di-qun」か、とも)の音訛である。また俗称として「ウァーサ王」(「ブタの王」の意)の名があるが、その来源は現在のところ不明である。屠殺業者の出自をもつという伝承があるため、という説がある。公的文書の記録には「護国伏魔の神」(『唐栄旧記全集』)「勅封忠義 関聖大帝」(「関帝王祭文」)等の名があり、受容当初には「護国伏魔」「忠義」といった意味付けが、中国とほぼ 同様に認知・受容されていたことを物語る。
関帝像が初めて琉球にもたらされたのは、1691年のことである。1683年に来琉した册封正使、汪楫の求め に応じて王府が福建より請来し、天妃宮の一隅にこれを奉安したのが始まりとされる。このとき請来したのは関帝・ 周倉・関平の三体の神像であった。上天妃宮内の関帝廟での祭祀(6月23日の顕神、8月15日の単刀会)は、久米村の男性により執り行われる決まりで、久米三十六姓や首里・那覇の旧家には関帝の彫像や画を家の守護神としてウドゥングゥワー〈神祠〉に祀ることがあったらしい。近世になると、画像が普及し、床の間にこれを掛ける風習が中流階級へも広まったという(『那覇市史』p.450参照)。
神屋や床の間に関帝王の画を掛ける家は、現在でも少なくない。更に、関帝王のウマリビー(誕生日=5月13日)に一門が集合し、祭祀を執り行う家もある。現存する関帝王の図像や風習から判明することは、関帝王図像が主として士族を中心に流布したこと、そして家や門中といった血縁的紐帯の中で綿々と受け継がれているということである。前者は、関帝王図像が王府の支配機構に組み込まれ、連動したものであったことを示唆する。元来、首里・那覇士族 の家庭に関帝王の画や彫像が入り込んできた契機は、王府から褒美・恩寵として下賜された数多くの書画類すなわち 贈答品にあったと思しい。すなわち、中国の例に見る如く、忠義と勇武の象徴である関帝は、国家機構の維持・強化 という面でも実に有り難い神であり、王府から士族層へ贈られた「関帝」像は、まさに贈り物として理にかなったものであったということができよう。首里城正殿御差床背部に安置されたという数多くの中国由来の扁額同様、士族層 が王府より拝謁したそれらの書画をうやうやしく邸宅内に飾ったであろうことは、想像に難くない。そこにおいて重要 であったのは、関帝そのものが備えている能力・御利益というよりはむしろ、王府から自らの功績の証として賜った、 関係性の象徴としてのそれであったかもしれない。もちろん沖縄における関帝王にも、守護神、商売の神、盗難よけの神などといった有り難い御利益が付与されてはいる。
しかし現在、関帝王図像そのものに盛られた意味がどことなく虚ろであるのは、いっぽうで、人と人をつなぐ関係性の表明(象徴記号)としての画の機能を色濃く示すものに違いない。沖縄の関帝王図像研究には、普及過程における具体例を文献に照らして拾い集めると同時に、現代における受容のあり方を聴き取り等により総合させてゆくアプローチが必要である。それにより、図像そのものの複雑な機能の一端が照らし出されると同時に、沖縄における、図 像を媒介とした政治・親族的な人の関わりの一端が掘り起こされるのではないだろうか。その意味で、沖縄の関帝王 図像は、今後更に研究・考察されるべき、興味深い対象といえよう。
関帝王図像
関帝王図像は、大別して二種に分けられる。すなわち、騎馬像と座像である。まず、騎馬像には馬に颯爽と跨がり、手には長刀をしかと捧げもち、五束の美鬚をなびかせる関帝王の姿(図2)、そしてその背後に旗をかざした従者を描く構図(図3)がひとつの定型である。蛇足のそしりを恐れず敢えて限定するならば、「馬」はすなわち関羽の愛馬「赤兎馬(せきとば)」 であり、「刀」は「青竜偃月刀」、「従者」は「周倉」ということになる。しかし、沖縄の関帝王図像においては、 それらを限定する要素は稀薄であり、概ね意識されていないと思しい。例えば「周倉」にはその図像的特徴(極めて特徴的ないかつい顔と体躯)を踏襲するものと、単なる一従者として描かれるものに分かれるが、前者にしてもその 固有名詞が意識されているとは考えにくい。すなわち、近世の「ヤマト」とは異なり、関帝にまつわる物語ごとの受容はなかっただろうと推測される。あくまでも神としての関帝が受容されたのであろう。関帝王は蛟袍金甲を身につける。立派な鬚は「美鬚公」と呼ばれた関羽の、欠かすべからざる要素である。細部における変容は大きいものの、 構図および人物表現の諸要素においては、忠実に伝えている。単身の騎馬像も時にある。
座像は、蛟袍を身にまとう関帝王(下に鎧がのぞき、武将・勇武の神であることを示す)と、背後の左右に、義子の関平・配下の周倉を配す(図1)。二人はそれぞれ、関平が官印(曹操から拝領の「漢寿亭侯」印)、周倉が青竜偃月刀を護持する姿に描かれ、それぞれ文武の機能を担わされていると思しい。いっぽう、中央に安座する関帝王は、前述の 五束の髯をねじりながら(威風堂々たる偉丈夫に典型的なポーズ。芝居の所作の影響がおそらくある)、泰山の如く鎮座する。時に彼の愛読書といわれる『春秋』を手に、これを拝読するポーズも関帝図像の一典型だ。騎馬像、座像、いずれも中国にその図像ルーツを求めることができるが、前者は歴史英雄としての関羽図像、後者は神様としての関帝図像の系列に位置するといえるだろうか。
沖縄の関帝王図像には、もはやその原形が判別不可能なほど、上から新たな手を入れられたものが比較的多い。その際用いられる画材は概ね、いたって多様で、蛍光色やマジック、水彩、鉛筆、金銀など、鮮明な色彩が特に好まれているようである。また画材についてもあまり頓着しない姿勢が目に付く。紙については、比較的入手しやすい画用紙などを使用し、また額装の際にも、市販の賞状額を使用することが多い。これは管見の及ぶかぎりの現代の状況である。王府の絵師たち、或いは近世の美術家たちが残した関帝王図像というものも、少なからず残っている。概して泥臭さが消臭されているが如く、やや雅でさわやかな関帝王。若き日の日本画家たちが、アルバイトがてら関帝像を描いたというエピソードも少なからずあり、市井の商品として、既成の関帝像が売られていたという話もしばしば耳にする。また地方廻りの旅絵師が村々を廻ったとの話もあり、予想以上に関帝像や床の間飾りの画を掛ける習慣が広く民間へも広まり、需要のあるものであったことが、分かるのである。
(参考文献)
窪徳忠『増訂 沖縄の習俗と信仰:中国との比較硏究』東京大学出版界、1974年
窪徳忠『中国文化と南島』第一書房、南島文化宋書、1981年
外間守善・波照間栄吉編『定本 琉球国由来記』角川書店、1997年
馬書田『中国民間諸神』団結出版社、1990年
『那覇市史』資料編第二巻 7「那覇の民俗」那覇市企画部市史編纂室、1979年
|