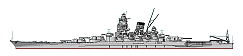[戻る]
アニメンタリー
決断
昭和46年に放映されたアニメーションとドキュメンタリーをかけあわせた造語を冠にした番組でした。
制作は竜の子プロでしたから、人物描写のタッチは「ガッチャマン」などに通ずるものがありました。
検索しても、この番組のことは少ないようなので資料としてまとめてみました。
まずは、オープニング・ナレーションから。
「人生にとって最も貴重な瞬間 それは決断の時である
太平洋戦争は われわれに 平和の尊さを教えたが
また 生きるための教訓を 数多くのこしている」
![]()
|
話数 |
タ イ ト ル |
教 訓 |
補 足 |
| 第 1話 | 真珠湾奇襲 | 真にすぐれた指揮官とは、常に目的を見失わず一瞬の間に正しい決断を下すものだと言われる。逆にその時の状況に左右されて目的を見失う時、成果は不十分なものしか期待できないのである。 | 再攻撃を加えるべきであったかどうかは永遠の論争として残された。ある者は臆病と非難し、ある者は慎重と尊敬する、南雲忠一中将の決断を描く。 |
| 第 2話 | ミッドウェイ海戦 ー前編ー |
常に緻密な計算とその計算が生む決断の時を知る者こそ真の勝利者となれる。 希望的観測にすがって決断の時を見失う者には悲劇は必ず来るのである。 |
赤城、加賀、蒼龍3隻の空母を一瞬のうちに失 う…あと5分敵が来るのが遅かったら、こんなやられ方はしなかった?南雲中将の決断を、米軍の決断と対比して描く。 |
| 第 3話 | ミッドウェイ海戦 ー後編ー |
指揮するものがその任務と目標を見定め断固たる行動を起こす時、部下は困難を恐れず全能力を発揮する。それは勝者と敗者、敵と味方の区別なくたたえる姿だからである。 | この日を境に、太平洋上における攻撃の主導権は日本からアメリカに移された。その敗北の中、奮闘した空母飛龍を率いた山口多聞少将の姿を描く。 |
| 第 4話 | マレー突進作戦 | 戦いとはいかなるものか、その目標は何か、そして決断はいつ、この最も基本的なテーマをはっきり捉えた指揮官と、それをおろそかにした指揮官、それはあまりにも明らかに勝利と敗北を決定づける。 | ”マレーの虎”とうたわれた猛将山下奉文中将と、全く守勢にまわる方策をとったイギリスのパーシバル中将の指揮を描く。 |
| 第 5話 | シンガポール攻略 | 指揮官とは何か。戦いを自分のものとし、自分自身を第一線に置き、部下の行動目標を定め、自ら先に立って勝利へ導く存在である。指揮官が戦いと行政事務を取り違え 、戦うのは部下だけと思う時、その存在の意義を失う。 | 日本の山下中将とイギリスのパーシバル中将、二人の指揮官の両極端な姿を描く。 |
| 第 6話 | 香港攻略 | 部下の勢いに接した時、状況に応じて、その勢いをさらに励まし、全組織に及ぼすことが出来るかどうか、それは常に上級指揮官のすぐれた決断にかかっているのである。 | 司令部の作戦を無視した下級指揮官の独断攻撃の成功から、集団を指揮するものが常に心せねばならぬ問題、戦場における指揮官のあり方を問う。 |
| 第 7話 | マレー沖海戦 | 翌日、プリンス・オブ・ウェールズ、レパルスの沈没現場へ飛んだ日本機はふたつの花束を投下した。マレー沖海戦における日本、イギリス両海軍の戦いは見事であり堂々としたものであった。ひとつの花束はイギリスの戦士に、もうひとつは日本の戦士のために、ひたすら自分の務めを果たすべく戦い続けたその心情にささげられた。しかし日本海軍はその花束が象徴する航空機時代の訪れを十分に見極めず、やがて大きな敗北への道を歩むのである。 | これも唄になったり、円谷英二が特撮で、この海戦の映画 「ハワイ・マレー沖海戦」を戦時中につくったりで話題にも。プリンス・オブ・ウェールズはイギリスが世界に誇った不沈戦艦として有名。ドイツではビスマルク、そして日本の大和、武蔵…ともに運命は… |
| 第 8話 | 珊瑚海々戦 | 味方の損害にとらわれすぎる時、敵の被害は見過ごされ、作戦は停滞する。日本海軍第四艦隊は戦術に勝って 、戦略に負けたのである。 | 世界海戦史上初の空母対空母の決戦を描く。智将 井上成美についての評価が分かれる作戦。 |
| 第 9話 | ジャワ攻略 | ジャワ作戦は太平洋戦争中、心から現地住民の歓迎を受け、思いどおりの結果を得た唯 ひとつの作戦だったと言われる。それは司令官今村中将が飽くまで原住民の保護をはかり、焼き討ち戦術を拒否した愛の決断の成果であった。 | インドネシア民族独立運動があったとはいえ、評価の分かれるところかも? |
| 第10話 | 海軍落下傘部隊 | 我々は、この戦いの中で、指揮官の〜“作戦優先”〜という言葉の意味を、もう一度 、考えてみなければならない。 | 「見よ落下傘、空をゆく…」と唄になるほど称賛されたため、落下傘部隊と陸戦部隊とが強く対立し合ってしまうという悲劇を描く。 |
| 第11話 | バターン・コレヒドール攻略 | 司令官は大本営の命令を守りマニラを攻略した。部下の苦労を思い、武将としての誇りを捨てて増援を求めた。無益な死傷を避けるためバターンの捕虜をコレヒドールから移動させた。だが、司令官が過酷な戦場で示したこの心やさしい決断の数々は、むしろ指揮官としては女々しい欠点と見なされた。 | バターン死の行進、マッカーサーの「I shall return」という言葉なども知られるところ。第14軍司令官 本間中将を描く。 |
| 第12話 | 潜水艦伊‐168 | 絶えず温厚な性格を失わず、部下を励まし、ともに目的を成し遂げた、この潜水艦の艦長は、いかなる時にも沈着、冷静 、かつ大胆であった。信頼される決断、特に、極限状態の中で下される正しい判断は、この“沈着”がなければ生まれない。 | 第2話・3話から続く日本海軍の大敗北となったミッドウェイ海戦において、 山口少将率いる日本空母飛龍からの攻撃で大破したが沈まなかった米空母ヨークタウンを撃沈した潜水艦の活躍を描く。 |
| 第13話 | 第一次ソロモン海戦 | 決断にあたっては目前の勝利や被害に迷うことなく、常に将来を展望し、大局を見失ってはならない。 | 日本海軍の伝統にとらわれ過ぎた三川中将の決断は、やがて訪れるガダルカナルの悲劇の原因のひとつとなる。 |
| 第14話 | 加藤隼戦闘隊 | その不屈の闘志と精神は部下たちの心の中に生きていた… | 唄にもなった加藤隊長の活躍と壮絶な最期を描く。 |
| 第15話 | ラバウル航空隊 | 坂を転がるような趨勢(すうせい)の中にあっては、そのいかなる決断も無益・無力に過ぎぬものなのだろうか…それはただ天のみが知るものなのかもしれない。 | 唄にもなったラバウル…メロディーがむなしく響きます。 |
| 第16話 | キスカ島撤退 | 常に可能性を見つめ、それを成功につなぐべき冷静な決断こそ真に価値を発揮することができる。 | 奇跡の作戦〜警戒厳しい敵中、守備隊全員の救出を指揮したヒゲの木村少将を描く。 |
| 第17話 | 特攻隊誕生 | 決断を下すものは自らを裁く覚悟が必要である。 たとえそれが死であろうとも。 |
特攻隊の発案者大西瀧治郎長官は終戦直後に自決…関大尉をはじめとする最初の特攻隊員たちを描く。 |
| 第18話 | 山本五十六の死 | この悲しむべき一幕は、我々に戦いに勝つためには敵をよく知ることであると教えた。今日においても正確な情報を先につかんだ者が勝利への決断を下せるのである。 | 戦争を極力避けようとしたが、皮肉にも、連合艦隊司令長官として、その戦いの指揮をとらなければならなくたった男の運命の終わり。 |
| 第19話 | ルンガ沖夜戦 | 厳しい訓練から得られた部下の力を信頼し、すべてを安心して任せた作戦とともに、指揮官の人間としての決断を評価。 | 鬼の第二水雷戦隊田中頼三少将の右足左足の“たとえ”とともに駆逐艦高波乗組員の人間ドラマも印象的でした。 |
| 第20話 | マリアナ沖海戦 | 厳しく“決断”を迫られる場におけるヒューマニズムのあり方が、ことの成否を決定的にする。 | サイパン島攻略に結集した米軍と背水の陣をしく日本軍との対決。、ミッチャー中将と小沢提督を対比して描く。 |
| 第21話 | レイテ沖海戦ー前編ー | 被害担当艦となって艦隊全体の損害を少なく食い止めた猪口少将の決断と、上級者の意を汲み、多くの人命を救った菅野大尉の退艦命令という中堅幹部の決断を評価。 | 日本海軍が不沈を誇った戦艦武蔵の最期を、艦長をはじめとした人物像で描く。涙…涙… |
| 第22話 | レイテ沖海戦ー後編ー | 常に重要な決断には正確な情報が必要であり、正しい情報がいかに集められているかどうかが、決断の決定的な要素であること。 | 海戦史上永遠に残る謎〜敵を前にしての栗田健男艦隊の反転を描く。 |
| 第23話 | 硫黄島作戦 | 物心両面より士気を高め、万歳攻撃を許さず自ら先頭に立ち最後まで戦い続け、日本側より米側により多くの損害を与えた指揮官の決断と姿勢。 | いまや敵に勝つのではなく、いかに永く島を守り本土決戦を食い止めるかを熟慮し 、潔さを捨てた栗林中将の作戦を描く。 |
| 第24話 | 連合艦隊の最期 | 見通しのきかなくなった決断がいかに恐ろしいものなのか、そして米側の決断からは決断の後には果敢な実行力がなけれなばならないということを学びとることができる。 | 戦艦大和を沖縄特攻に向かわせた日本側の決断、それを迎え撃つ米側の決断から学ぶ。 |
| 第25話 | 最後の決断 | 本当の決断とは、自分だけの立場にとらわれず、将来の見通しにたつかどうかなのではないか。 そして、あとは勇気… |
 下村情報局総裁を軸に終戦時の、それぞれの命がけの決断を描く。 下村情報局総裁を軸に終戦時の、それぞれの命がけの決断を描く。 |
放映の関係で歴史的には年代順が後先になっている部分がありますが、
幼心にも戦争の一面と太平洋戦争史を学ばされたように思います。
そして、いま改めて見ると、人生論にもなっていることに感銘を受けます。
さらにくわしくストーリーや人物伝を知りたい方には、シュルクーフさんのHPを
ご紹介します。
(私もレコードジャケット画像やその他情報を提供させていただきました、それはそれは充実したサイト、必見です)
下の大和級戦艦の画像(提供:素材集いやぽぽ)をクリックするか「LINK」のページからどうぞ。