


�������
�Z��ŃG�R�|�C���g���x
�T�v
![]()
| ���V�z�Z������r�S�ېӔC���ᐧ�x �@�V�z�Z������r�S�ېӔC10�N�`���Â�������e�Ƃ������r�S�ېӔC���ᐧ�x�́A����12�N4��1��������{����܂����B����ɂ��A�Z����҂ɂ́A�S�Ă̐V�z�Z��̎擾�_��ɂ����āA�Z��̈��̕����ɂ������r�S�ېӔC��10�N�ԕ������Ƃ��`���t�����Ă��܂��B �i1�j���r �@�u���r�v�Ƃ́A�_��̖ړI�����_��ɒ�߂�ꂽ���e�������Ă��邱�Ƃ������܂��B�܂��_����e�����炩�łȂ������ɂ��ẮA�Љ�ʔO��K�v�Ƃ���鐫�\�������Ă��邱�Ƃ����r�ƂȂ�܂��B���́u�Љ�ʔO�v�́A�ŏI�I�ɂ͍ٔ����Ŕ��f����邱�ƂɂȂ�܂����A����ł͎{�H�Ǝ҂ɂ͏��Ȃ��Ƃ����z��@���̑��W�@�߂ɓK������H�����s���`����������̂Ƃ���Ă��܂��B �i2�j���r���ۂ��̔��f �@���r�́A���n���ɏ�q�̂悤�ȏ����ɓK�����镔�������邩�ǂ����Ŕ��f����܂��B�Ⴆ�u�����������x�X���������r�ł���v�Ƃ��A�u������m�ȉ��̑䕗�Ő������s����ۂ����r�ł���v�Ƃ����悤�ɁA���n��ɔ��������s����ۂ��Ƃ炦�Ĉꗥ�ɔ��f�ł���悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B���������āA���r���ۂ��̍ŏI�I�Ȕ��f�́A�l�X�Ȏ����𖾂炩�ɂ�����ŁA�ٔ������s�����ƂɂȂ�܂��B �i3�j�ΏۂƂȂ�_�� �@�@�Z���V�z���鐿���_��ł��B���z�H������z�H�����ΏۂƂȂ�܂���B �@�A�V�z�Z��̔����_��ł��B �i4�j���r�S�ېӔC���ׂ����� �@�Z���V�z���鐿���_��̐����l�ƁA�V�z�Z��̔����_��̔��傪�ӔC���܂��B �i5�j�ΏۂƂȂ镔�� �@�\���ϗ͏��v�ȕ����ƉJ���̐Z����h�~���镔���ɂ��������r�ɂ��āA10�N�����r�S�ېӔC�����ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��A��̓I�ȕ����͈ȉ��̂Ƃ���ł��B �@�@�\���ϗ͏��v�ȕ��� �@�Z��̊�b�A��b�����A�ǁA���A�����g�A�y��A�ށi�����A����A�ΑōށA���̑������ɗނ�����̂������B�j�A���ŁA�����Ŗ��͉��ˍށi���A�����̑������ɗނ�����̂������B�j�ŁA���Y�Z��̎��d�Ⴕ���͐ύډd�A�ϐ�E�����Ⴕ���͒n�k���̑��̐U���Ⴕ���͏Ռ����x���镔���Ƃ���B �@�A�J���̍�����h�~���镔�� �@�E�Z��̉������͊O�� �@�E�Z��̉������͊O�ǂ̊J�����ɐ݂���ˁA�g���̑��̌��� �@�E�J����r�����邽�߂̏Z��ɐ݂���z���ǂ̂����A���Y�Z��̉����Ⴕ���͊O�ǂ̓������͉����ɂ��镔���B |
| ���ؑ��Z��ϐk���C��̕⏕ �i1�j�ΏۂƂȂ錚�z�� �@���a56�N5��31���ȑO�ɒ��H���ꂽ�ؑ��Z��i�ݗ����g�\�@�̌ˌ��A�����A���p�Z��y�ы����Z��ŁA�����E���݂���Ȃ��j�Ŏ��̂����ꂩ�ɊY������Z�� �@�@�s�������{���閳���ϐk�f�f���́i���j���m�����z�Z��Z���^�[������18�N�x�ȍ~�Ɏ��{�����Z��ϐk�f�f�ő������肪1.0�����́u�|��\�����������͓|��\��������v�Ɣ��肳�ꂽ�Z�� �@�A�i���j���m�����z�Z��Z���^�[������17�N�x�܂łɎ��{�����Z��ϐk�f�f�ő����]����80�_�����Ɛf�f���ꂽ�Z�� �i2�j�ΏۂƂȂ�H�� �@�@�w����l0.7�����x���́w�]���l60�_�����x�̏ꍇ �@�Ώی��z���ɂ��āA����l�i��������)��1.0�ȏ�́u�ꉞ�|�Ȃ��v�Ƃ���ϐk���C�H�� �@�A�w����l0.7�ȏ�1.0�����x���́w�]���l60�_�ȏ�80�_�����x�̏ꍇ �@�K�ʕ����ʏ㕔�\���]�_���A����l��0.3�����Z�������l�ȏ�Ƃ���ϐk���C�H�� �i3�j�ΏۂƂȂ�� �@�ŋ����̎x�����A���̑��s���E�����Ƃ��Ă̋`���𗚍s���Ă���� �i4�j�⏕�̋��z �@�ϐk���C�H���̔�p�i�H����A�v�y�ѕ⋭�v��ɗv�����p�j�ɑ��āA1�˂�����60���~�����x�Ƃ���B �i5�j�����ŁE�Œ莑�Y�ł̍T�� �@�s�����Łt �@ �@�s�Œ莑�Y�Łt �@���a57�N1��1���ȑO���珊������Z��̑ϐk���C�H�����s�����ꍇ�A���Y�Z��ɌW��Œ莑�Y�Łi120�u�����܂Łj���ȉ��̂Ƃ��茸�z����B ����18�`21�N�ɑϐk�H�������@�@�@��3�N��1/2�Ɍ��z ����22�`24�N�ɑϐk�H�������@�@�@��2�N��1/2�Ɍ��z ����25�`27�N�ɑϐk�H�������@�@�@��1�N��1/2�Ɍ��z �@�₢���킹��@�@�e�s���̌��z�ہi�ڍׂɂ��Ă͊e�s���ɏ]���Ă��������B�j |
| ����Q������҂̏Z����C������� �@�g�̂ɏd�x�̏�Q������A���Z����������~���ɂ��邽�߂ɏ��K�͂ȏZ����C�i��z�����s�A�g�ǒ��A��������20���~�@��F����30���~�j��K�v�Ƃ���l�ɏZ����C����t����܂��B �i1�j�Ώێ� �@�����܂��͑劲�@�\��Q�i�ڍׂɂ��Ă͊e�s���ɏ]���Ă��������B�j �i2�j�ΏۍH�� �@�@�肷��̎��t���@�A�i���̉����@�B���̍ގ��ύX�@�C�����˓��ւ̔��̎�ւ��@�D�l���֊�ւ̕֊�̎�ւ��@ �@�E���̑� ���Ώێ҂����ɋ��Z����Z��ɂ��čs������̂Ɍ���܂��B �i3�j��p���S �@���т̏����Ŋz�ɉ����Ď��ȕ��S�����K�v�ł��B �@���͕K�����O�ɂ��ĉ������B�܂��A���ی��@�̎{��̑ΏۂƂȂ�ꍇ�͉��ی��{�D��ɂȂ�܂��B �@�₢���킹��@�@�e�s���̕����ہi�ڍׂɂ��Ă͊e�s���ɏ]���Ă��������B�j ���o���A�t���[���C�ɔ����Œ莑�Y�ł̌��z �@����19�N4���P�����畽��22�N3��31���܂ł̊Ԃɍs��ꂽ���C�H���ŁA���̗v���ɓ��Ă͂܂�ꍇ�ɁA���C���s��ꂽ�N�̗��N�x�̉Ɖ���100�u�������܂ł̌Œ莑�Y�Łi�s�s�v��ł͏����j��3����1�����z���܂��B �i1�j���� �@�@�@����19�N1��1���ȑO���珊�݂���Z��i�݉Ƃ������j �@�A�@���Z�҂�65�Έȏ�̎ҁA�v���E�v�x���̔F������Җ��͏�Q�� �@�B�@���C�H���̔�p��30���~�ȏ�i�s�̕⏕������ی����t�������j �@�C�@���y��ʏȍ����ɒ�߂�o���A�t���[���C�ł��邱�� �@�D�@�V�z�Ɖ����z�y�ёϐk���C���z�����ݎĂ��Ȃ����� �i2�j�\���ɕK�v�ȏ��ށi��3�����ȓ��ɐ\�����K�v�ł��B�j �@�@�@�Œ莑�Y�Ō��z�\���� �@�A�@���F��ʒm���A��Q�Ҏ蒠���̎ʂ� �@�B�@���C�H���̎����̎ʂ� �@�C�@���C�H�����i���������j�̎ʂ� �@�D�@���C�H������O�y�ъ�����̎ʐ^�i���t����j�ꎮ �@�E�@���C�H������O�y�ъ�����̌���}�i�Ԏ�̕����镽�ʐ}�j�̎ʂ� �@�₢���킹��@�@�e�s���̐Ŗ��ہi�ڍׂɂ��Ă͊e�s���ɏ]���Ă��������B�j ���Z��̏ȃG�l���C�ɔ����Œ莑�Y�ł̌��z �@����20�N4��1�����畽��22�N3��31���܂ł̊Ԃɍs��ꂽ�ȃG�l���C�H���ŁA���̗v���ɓ��Ă͂܂�ꍇ�A�H�������������N�̗��N�x���Ɍ���A120�u�������܂ł̉Ɖ��̌Œ莑�Y�ł�3����1�����z���܂��B �i1�j���� �@�@����20�N1��1���ȑO���珊�݂���Z��i���ݏZ��������j �@�A���C�H���̔�p��30���~�ȏ� �@�B����1.����4.�܂ł̉��C�H���ɂ��A���ꂼ��̕��ʂ����s�̏ȃG�l��ɐV���ɓK������悤�ɂȂ邱�Ɓi1.���܂ލH���Ł@�@�O�C�Ɛڂ�����̂̍H���Ɍ���j �@�@�@�@�@�@�@�@1.���̉��C�@2.���̒f�M�@3.�V��̒f�M�@4.�ǂ̒f�M |
| �i2�j�\���ɕK�v�ȏ��ށ@�i��3�����ȓ��ɐ\�����K�v�ł��B�j �@�@�Œ莑�Y�Ō��z�\���� �@�A���C�H���ɗv������p�̗̎����̎ʂ� �@�B���C�H���̓��i���������j�̎ʂ� �@�C�M���h�~���C�H���ؖ��� �@�@�i�����z�m�A�w��m�F�����@�֖��͓o�^�Z��\�]���@�ւɂ��ؖ��j �@�₢���킹��@�e�s���@�Ŗ��ہi�ڍׂɂ��Ă͊e�s���ɏ]���Ă��������B�j �������D�ǏZ��i200�N�Z��j�ɌW��Œ莑�Y�ł̌��z �@�����D�ǏZ��̕��y�̑��i�Ɋւ���@���ɋK�肷��F�蒷���D�ǏZ��ɂ����āA����21�N6��4�����畽��22�N3��31���܂ł̊ԂɐV�z���ꂽ�Z��̏ꍇ�A�V�z����5�N�x���i3�K���Ĉȏ�̒����w�ωΏZ��ɂ��Ă�7�N�x���j�A�Œ莑�Y�Ŋz����@2����1�����z���܂��B�i��˂�����120�u�܂ł����x�Ƃ��܂��B�j �i1�j���� �@�@�����D�ǏZ��̕��y�̑��i�Ɋւ���@���ɋK�肷��F�蒷���D�ǏZ�� �@�@�@1.�Z��̍\�����v�ȕ����ɂ��āA���H�A�����y�і����̖h�~�[�u�ɂ��ϋv�����m�ۂ���Ă��邱�� �@�@�@2.�n�k�ɑ��Ă̈��S�����m�ۂ���Ă��邱�� �@�@�@3.���Z�҂̃��C�t�X�^�C���̕ω����ɑ��A�Ԏ�蓙�̍\���y�ѐݔ��̕ύX��e�Ղɂł��邱�� �@�@�@4.�z�ǂ̓_���A���������e�Ղɍs����ȂǁA�ێ��ۑS��e�Ղɍs����\���ł��邱�� �@�@�@5.���̃o���A�t���[���\�A�ȃG�l���M�[���\��L���Ă��邱�� �@�A�l�̋��Z�̗p�ɋ����镔���̖ʐς��Ɖ��̏��ʐς�2����1�ȏ�̂��� �@�B�Z��̏��ʐς�50�u�i��ˌ��ȊO�̒��ݏZ���40�u�j�ȏ�280�u�ȉ��̂��� �@�@�i���ڂ����͍��y��ʏȂ̃z�[���y�[�W�������������B�j �i2�j�\���ɕK�v�ȏ��� �@�V�z���ꂽ������V���ɌŒ莑�Y�ł��ۂ����邱�ƂƂȂ�N�x�̏����̑�����N��1��31���܂ł̊Ԃɒ�o���Ă������� �@�@�@�F�蒷���D�ǏZ��ɑ���Œ莑�Y�ł̌��z�K�p�\���� �@�@�A�s���{���m�����͎s�������ɂ��ؖ��� �@�₢���킹��@�e�s���@�Ŗ��ہi�ڍׂɂ��Ă͊e�s���ɏ]���Ă��������B�j �����̑��⏕���x
���i�ڍׂɂ��Ă͊e�s���ɂ��q�˂��������B�j |
�����c�̃z�[���y�[�W
�Вc�@�l�@���m���z�m��
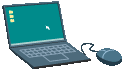
| �d�����e |