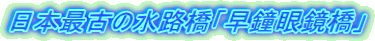
九州、熊本県の通潤橋は「ゆるぬき」などが有名で現在も農業用水として利用され、視察に行ったことがあります。
ところが、その200年も前に長崎県の眼鏡橋と同じ技術で日本最古の水路橋が建設されていました。
10月の九州出張の後に、水資源機構筑後川局に大勢の友人がいたことから、久留米の夜を楽しみながら懇談し、前情報を得てから訪ねてみました。
場所は大牟田市、駅からバスで10数分のところにあり、こじんまりとしていましたがお寺と民家の間に「早鐘眼鏡橋」は現存していました。
1647年に三池藩が干拓した水田への灌漑を目的に大牟田川を水路で立体交差するために建設した石造アーチ型の水路橋で、わが国最古、国の重要文化財に指定されていました。ただ、炭鉱掘削によって水源のため池の底が抜けてしまい現在は水が流れていませんでした。
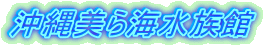
「田舎時間」というのを昔はよく聞くことがあったが、沖縄には未だに「島時間」というものがあるらしい。セミナーが始まっても一割くらいの人が後からノンビリと入ってくる。別に遅れて申し訳けないというような素振りはなく、講師の私にも遠慮なく堂々と着席する。昼食のレストランでも、注文してもなかなか料理が出てこない。周りをみると誰も食べていないし、イライラすることもなく、そのうち出てくるだろうと悠然としている。私にはエレベーターだって、何となく来るのがやたらに遅いと気になってしまう。
タクシーの運転手にそんなことを話しかけると、「沖縄はノンビリしているが、友人や親戚などの人間関係が深くて皆が暖かい、金なんかなくても十分に生きていけるさ〜」とのこと
そんな沖縄気質でも、沖縄はそれなりに発展している印象だった。モノレール(ユイレール)や高速道が出来ていたし、海岸部には巨大リゾート施設が立ち並んでいた。玉泉洞は昔は単なる鍾乳洞しかなかったが観光村になっていた。今回は沖縄にしかない地下ダムを見てみたかったが、構造上見ることは出来ないそうで残念でした。沖縄海洋博覧会の跡地には「美ら海水族館」などが立派に整備されていました。
でも少し違うのかなという印象。沖縄最大の資源はきれいな海や気候的な暖かさではなく、このおおらかな沖縄気質ではないだろうか
![]()


