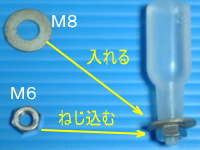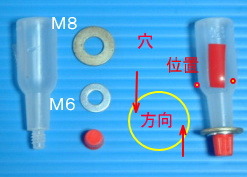| いろいろな浮沈子 |
|
|
|
|
| 浮沈子についてもインターネット上で、いろいろ実験例があるので、それを参考にするとよい。 |
|
|
|
|
| 1 浮沈子をつくる問題 |
|
| |
① |
浮沈子をつくる素材と、それにつけるおもりを何にするか。 |
|
② |
水を入れる容器としてペットボトルは手軽でよいが、口が小さいのと、まわりがやや見にくい。 |
|
|
|
 |
| 2 材料 |
|
タレびん(ペットボトルの口から入る大きさ)
丸形(ビールびん型) |
数個 |
六角ナット(M6)、ワッシャー2種類
(ペットボトルの口の大きさに注意) |
数個 |
| ビーズ(細かいもの) |
少々 |
| 軟質ガラス管 |
少々 |
| フィルムケース |
1 |
| ペットボトル |
数本 |
| コップ |
1 |
| 千枚通し |
|
|
|
|
|
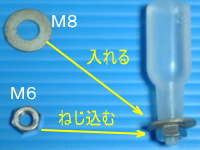 |
| 3 つくり方 |
|
◆ |
丸形のタレびんを使った浮沈子 |
| |
① |
タレびんに、M8ワッシャーとM6サイズナットをねじこむ。
タレびんのふたはしない。 |
|
② |
水を入れて調節する。(使い方参照) |
|
|
|
|
◆ |
回転する浮沈子 |
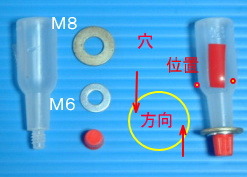 |
|
○ |
タレびんの口に、M8とM6ワッシャー入れ、タレびんのふたをする。 |
|
○ |
千枚通しで、写真のような方向に穴をあける。 |
|
○ |
水を入れて調節する。 |
|
|
|
| 4 使い方 |
|
① |
コップに水を用意する。 |
|
② |
タレびんを押してから、口をコップの水につけ、水を吸い込む。 |
|
③ |
タレびんの水の量を調節して、コップの水につけ、タレびん(浮沈子)の上面が、水面ぎりぎりでうまく浮くようにする。 |
|
④ |
浮沈子の口を上にしてペットボトルに入れる。 |
|
|
⑤ |
ペットボトルを握り、壁がへこむように強く押すと、浮沈子が沈み、握りを弱めると浮沈子が浮き上がる。 |
|
|
※回転浮沈子は、沈んだとき、急に弱めるとよく回る。 |
|
|
|
| 5 ガラス管を使った浮沈子(子供には無理) |
 |
|
|
高度な技術が必要だが、浮沈子への水の出入り、空気の部分の体積の変化がよくわかる。 |
|
○ |
ガスバーナーで、ガラス管の一方を赤くなるまで熱し、ガラス玉を作ってふさぐ。 |
|
○ |
ガラス管の反対側から吹いて、ガラス玉をふくらませる。 |
|
|
|
|
| 6 大型の浮沈子 |
|
|
○ |
フィルムケースと、透明で柔らかく、細長いパイプを使い、大型のものを作ると、ダイナミックでおもしろい。 |