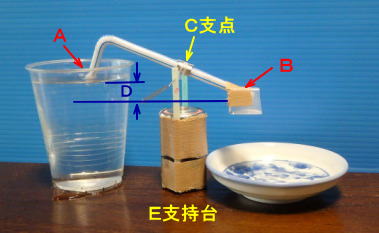| 水飲み鳥(平和鳥、ハッピーバード) これを毛管現象を利用して |
|
 |
|
水飲み鳥は二つのガラスの球を管(鳥の首)で繋いだ形をしている。管は下側の球の底近くに達しているが、上側の球の端までは達していない。内部には一般的に着色された劇薬ジクロロメタン(塩化メチレン)の液体が入っている。空気は抜かれており、内部の空洞は気化したジクロロメタンで満たされている。上側の球には嘴が取り付けられ、頭部はフェルトのような材料で覆われている。多くの場合、目玉とシルクハットと尾羽で飾りつけられている。装置全体は首の回転軸で支えられており、軸のポイントは変えられる。 → 水飲みの動く原理
ここでは、日本ガイシのHPに紹介されている、毛管現象を利用した「水飲み鳥」を参考に、自分なりにつくってみた。(参考HP http://site.ngk.co.jp/lab/no216/exam.html )
|
| 1 課題と工夫 |
|
| |
① |
支点Cを工夫し、シーソー原理(振り子)を敏感にする(感度を上げる)→「ししおどし」を参考にする。 |
| |
② |
Bの水だまりをつくりやすくする。 |
| |
③ |
支持台Aをつくりやすくする。 |
| 2 材料 |
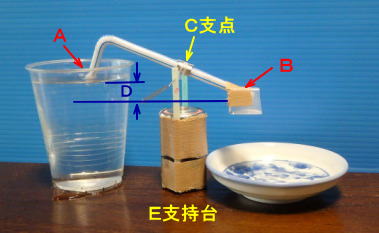 |
|
| まがるストロー 外径6φ |
1 |
| ストロー 6φ |
2 |
| スペ-サー 内径6φ、長さ10mm |
1 |
| 濡れテッシュペーパ |
1 |
| 一口醤油びん |
1 |
| 糸、ガムテープ、ゼムクリップ |
|
| 単1乾電池(水飲み鳥の台) |
1 |
|
| 3 つくり方 |
|
◆ |
本体のつくりかた |
|
① |
まがるストローにテッシュペーパを丸めてつめる。 |
| |
|
※細い針金か竹串に巻き付けてからつめるとやりやすい。 |
|
② |
支点の金具をはめ込む。 |
|
| |
③ |
B側に一口醤油びんを取り付ける。(この角度がむずかしい、工夫をしてください) |
| |
◆ |
支点の金具をつくって本体を通す。 |
| |
④ |
右の写真のように、内径6φのスペ-サーを利用してつくる。 |
| |
⑤ |
上の③に本体を通す。 |
|
| |
◆ |
支持台をつくる |
|
|
⑥ |
ストロー2本をガムテープで、乾電池に貼り付け、立てる。 |
|
⑦ |
立てたストローに穴をあけ、ゼムクリップをのばした針金を使って、支点の金具を通す。 |
|
⑧ |
Aを水につけ、Bに水がたまったらバランスを調節する。 |
| 4 動作の原理 |
| |
① |
頭部Aから、水が毛管現象でストロー内にしみこんでいく。 |
| |
② |
Bに水がたまり、その重さでB側がさがり、下がりすぎると、やがてたまった水が落ちる。 |
|
③ |
水が落ちると、B側が軽くなり、Aが再び、コップの水の中に入る。これが繰り返される。 |
| |
④ |
約1分~2分で繰り返される。 |
| |
⑤ |
うまくいかないときは、支点Cの位置を調節する。(少しやっかいである) |