| 磁界の観察(鉄粉のまき方など) | |||
|---|---|---|---|
| 鉄粉をガラス板やプラスチック板に一様にまくには、ちょっとしたコツが必要で、子供たちには意外とむずかしいらしい。 そこで、教科書などに出てくる方法などを検討し、子供たちがやりやすい方法を工夫してみた。 | |||
| 1 鉄粉の種類と粒の大きさ | |||
| 市販され、学校で用意できるものとしては、普通の鉄粉(化学用鉄粉)と還元鉄であろう。 ※化学用鉄粉をあらかじめ100メッシュ(0.149mm目)のふるいでふるっておくとよい。 |
|||
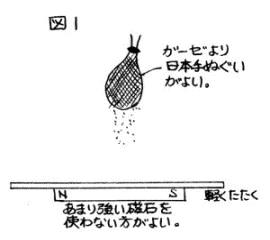 |
|||
| 2 鉄粉のまき方 | |||
| ① ガーゼで包む | |||
| 右の図のように、ガーゼで鉄粉を包み、指で軽くたたくようにする方法である。 ガーゼの網目はあらく、0.5mm目ぐらいなので、鉄粉が一様に出にくい。二重にすることも考えられる。 ※ガーゼの代わりに、日本てぬぐい(0.25mm目)(60~100メッシュ)を使うとよい。 |
|||
| ② 茶こし、ふるいを利用する | |||
| 図2のように、茶こしを使う方法もあるが、①とあまり変わらず、その上、茶こしを購入しなくてはならない。茶こしの代わりに、図3のように、円筒のもの(例えば、紙筒、塩ビ管の切れはし、円筒なくてもよい)に、前述の日本手ぬぐいをはっておけば、安くでき、子供一人一人にゆきわたる。 |
|||
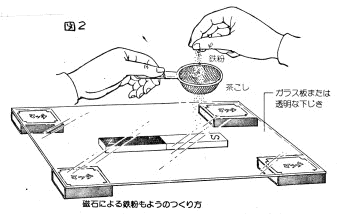 |
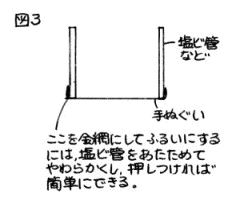 |
||
| ③ フイルムケースを利用する | 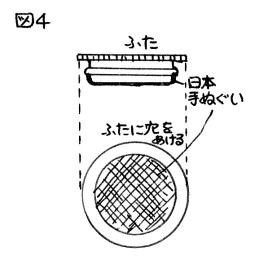 |
||
| 右の図4のように、フィルムケースのふにの一部を切って穴をあけ、そこにガーゼや日本手ぬぐいの布をはりつけ、ケースに鉄粉を入れて、ふたをする。 使うときは、ご飯にふりかけをかけるような要領でやればよい。子供一人一人に鉄粉をわける手間も毎時間しなくてもよい。 |
|||
| ④ 中ぶたのある空びんを利用する | 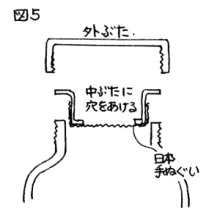 |
||
| この方法が最もよい | |||
| ③のフィルムケースの湯合、布のついたふたを通して鉄粉が空気とふれているので、そのままでは長期に保存できない。更にふたがほしいところである。 都合のよいことに、薬びんなどに中ぶたがあるものがあり、その中ぶたに穴をあけ、布をはればよい。 こうしておけば、鉄粉を使わないときは、外ぶたをしておけば、密閉でき、鉄粉がさびない。 |
|||
| 3 鉄粉の回収 | |||
| 子供たちは、どんなに注意しても、鉄粉をちらばしてしまうもので、ある程度やむを得ないと思う。 机より大きめの紙を引くぐらいで、あとは、床にこぼれたものは、子供に回収方法を考えさせてやらせればよい。 鉄粉をちらばさないものとして、磁界観察板があるが、最初からそれを使うことは感心しない。子供たちの工夫する力を奪わないようにしたい。 |
|||
| 4 磁界の観察 ………… 一度、心ゆくまで やらせてみたら | |||
| 磁界の様子を知るのに、鉄粉を用いて磁力線図をつくる方法は、古くから行われているが、案外、簡単に終らせてしまっているのではないだろうか。磁場といういう「場」の概念を、実験を通してつかませる大事な実験であり、きれいな模様ができたときの子供たちの喜びも大きい実験である。 ぜひ一度、子供たちに心ゆくまでやらせたいものである。 きれいな磁界の模様をつくるこつは、 ○細かい鉄粉を用いる。 ○弱い磁力の磁石を用いる。 あとは、磁石の上に紙をひき、鉄粉を上からまいて、紙のはしを軽くたたけばよい。 (鉄粉をまいてから磁石の上に紙をおいてもよい) また、茜石がたくさんないときは、コンクリート釘を付磁器で磁化させて使えば、子供一人一 人に心ゆくまで楽しませることができる。 以下に,いろいろな磁石の置き方によっで、鉄粉の模様がどのようにできるかを調べる。 その置き方の例をあげておく。 |
|||
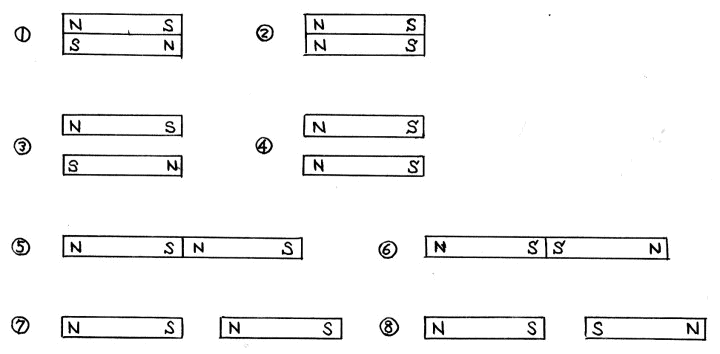 |
|||
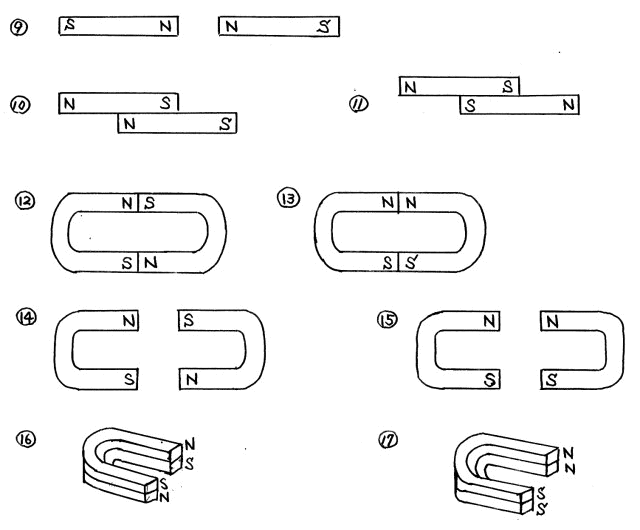 |
|||