2.使用方法
2.8 3点式内径内径測定マイクロメータ
この三点式内径測定器は内径の測定に使います。
内径測定には、2点式のシリンダーゲージが広く使われていますが、点接触になるので被測定物表面に食い込み傷が入る場合があります。この3点式マイクロメータは線接触なので傷が入ることはまずありません。
丸孔又は三角の倍数穴専用で、測定面が120度間隔で3箇所あります。3つの直線で円の内側に接触し求心作用がありますので取り扱いに熟練を要しないと一応教科書等で説明がありますが、ある程度の熟練が必要になるかと思います。
※新しい場合はそれほど神経と使わなくてもよろしいかとも思います。
ここでは使い込んでいるということでの説明になります。
1)構造
一度分解した事がありますので大雑把に説明します。
 |
スピンドルに繋がっている円錐状のコーンが押されると3箇所の測定子が押し出され、穴の内側にあたります。 コーンが下がるとトーションバネで測定子が引き込まれ、常にコーン先端円錐部に接触するようになっています。 |
2)寸法の分かっているリングゲージと比較する。
3点マイクロメータは構造的に測定面全面で図りますが、穴深さ等の関係で測定面の半分又は端だけで測る場合も多々あります。
測定時の深さにあわせてリングゲージで0合わせ(誤差の確認)をします。
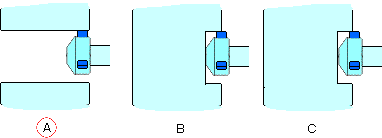 |
※使い込んでくると測定子の摺動部が磨耗してガタがでて測定時測定子に倒れがでます。
| |
浅孔用には左図のようなピンつきもあります。 |
3)測定
シンブル又はラチェット等の動かし方は外測マイクロメータと変わりませんが、内径測定であるがゆえにコツもあります。
測定しようとする孔に入れてシンブル又はラチェットで測定子を広げていくと自動的に求心され、その時の数値が測定値として読み取れます。ただ求心されて安定はしますが、測定面と穴内面には摩擦がありますからその摩擦で測定子が途中で止まってしまう場合がありますので、下アニメのようにシンブル近辺をわずかすりこぎするように回しながら尚且つ上下させて安定させたほうが測定値の信頼性が上ります。
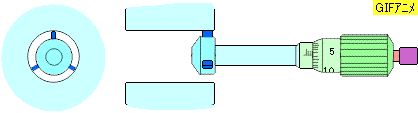 |
※シンブルの数値は外測マイクロメータと反対向きになりますので注意。
4)大径の場合
小径用と大径用では下図のような違いがあります。
| |
小径の場合、測定面の長さと測定面とマイクロメータ中心迄の距離比が小さいです(ここでは2倍程度)。 本体の重量も軽量ですから扱い易い。 |
| |
大径の場合は測定面の長さと測定面とマイクロメータ中心迄の距離比が大きい(ここでは6倍程度)。 本体の重量もかなりあります。 例えが少々違いますが、障子を滑らかした時に止まるのと同じで傾いたまま安定(測定子が動かなくなる)する場合があります。 |
孔測定する場合はとりあえず測定面に合わせ、マイクロメータの測定面部を中心にシンブルを軽くスリコギ状態に小さく回しながら尚且つシンブル又はラチェットを回し、さらにラジアル方向にわずか動かし安定した状態で読み取るようにします。この作業を複数回(2~3回程度)行い、その複数回の数値の誤差が最小なら、その値を測定値にしてよいと思います(下アニメ参照)
※多少オーバーに表現しています。
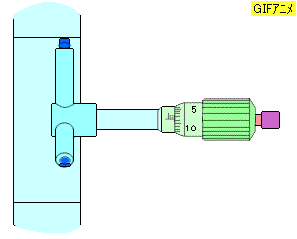 |
5)高精度で測定するには
測定しようとする孔径と同じリングゲージで0点合わせ(誤差の確認)を行い、ラチェットのカチカチ音が同じになるように(音の高さとその間隔等)被測定物の孔を測ります。
慣れれば誤差±1ミクロン程度で測れます。
 |
左記のマークは、外部へのリンク部等を除き、このページの全ての著作物に付けられたものです。 著者:なつお natuo.com |
| 前へ | 次へ |
トップ→測定工具の使い方→2.使用方法→●2.8 3点式内径測定マイクロメータ
© 2000 natuo