幾何公差
6.-1/6 幾何公差Q&A
1.図面に幾何公差の設定は必要でしょうか。
図面は設計者の意図を正しく現場に伝える最も重要な技術情報ですので、情報の欠落、解釈の一義性を確保するために必要な方
法です。 例えば普通公差の累積や公差域の解釈の違い、基準となる形体の指定の不明瞭等から技術会議又は設計者への問い合
わせを減らす効果があります。
2.幾何公差はいつ制定されたのですか。
1957年前後にJIS独自として、平面度・真直度・直角度・真円度・円筒度・平行度・同心度がありましたが、ISO方式に改正する事になり、規格名称も幾何公差とし、JIS B 0021:1972で上記の7つが制定された。続けてJISB0021:1974で、線の輪郭度・面の輪郭度・傾斜度・位置度・対称度・振れが加わりました。
3.データムで使用されるアルファベットの記号の使い方の注意点がありますか。
A~Zまで順番に使い、不足した場合はAA、AB、ACというようになります。
ただし、読み間違いやすいI、O、Qは使用しないようにしたほうがいいと思います(ASMEで規定あり)。
4.データム指示の三角記号を付ける場合の注意点がありますか。
分かり易いように黒色で描き、数が多い場合はデータムの位置情報として一覧を設ければ親切な図面になります。また記号の位置
は寸法線の延長線上にあるのかどうかはっきりさせるように描く事が大事かと思います。
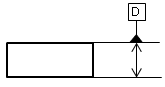 |
黒色なのではっきりデータムであることがわかります。 寸法線の延長線上にあることもわかります。 |
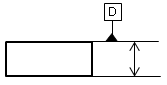 |
同じく黒なのでデータムの位置がわかりやすいですし、寸法線の延長線上ともはっきり分かれていることがわかります。 |
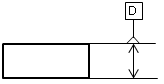 |
白色なので少々分かり難いですね。 |
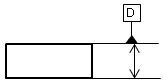 |
寸法線の延長線なのかどうか分かり難ですね。 ※寸法線の延長線上にある場合と、を延長線上にない場 合ではデータムの意味合いが違うので注意して下さい。 |
5.データム平面にうねりが予想される場合(鋳物等)、データム設定の方法で何か良い方法がありますか。
| 右図例のようにデータムターゲットを用いると安定します。 これはあくまで三点で一平面をデータムにしますから、うねり が許容範囲を超えないように平面度の指定も追加したほう がよいかと思います。 |
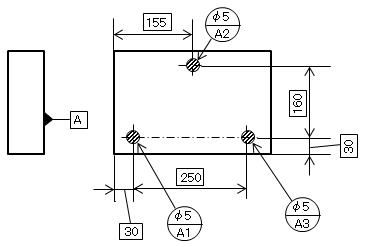 |
6.長方形の枠に囲まれていない寸法数字に位置度の幾何公差があります。この場合許容差の大きい普通公差を適応してもよろしいでしょうか。
規格公差の位置度を規制する場合、寸法数字に普通公差を与えないが代わりに幾何公差の位置度で許容差を指定する事になっています。
たぶん寸法数字に長方形の枠を忘れただけだと思いますので、普通公差より公差の厳しい幾何公差の位置度を優先したほうがいいと思います。
下図参照
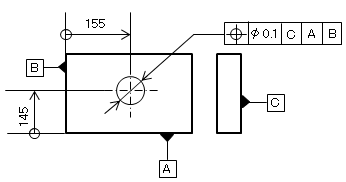 |
※ 何がしかの理由で複数の許容差ある場合は、公差の小 さい方を優先して管理するのがいいでしょう。 参考 ここでは、寸法数字の145及び155に長方形の枠を入れるのが正しいです(下記参照)。 |
|
| |
|
|
7.三次元測定器で測定評価する場合、プローブを当てた以外の所はどう考えたらいいでしょうか。
点当たりで評価する場合、当てていない所のデータがありませんので、その部位が許容差内なのか否かはわかりません。多くの場合、測定値を信頼し、以外の個所も測定値と同等或いはより良いと判断していると思います。
※お互いの信頼関係を壊さないことが重要になります。
8.二方向の指示のはずなのに公差値にφがついています。こういう使い方もありでしょうか。
単純に記入ミスだと思います。方向を定めた指示なのか(φは付かない)、方向を定めない指示なのか(φが付きます)設計者に確
認したほうがいいと思います。
※φの方が同じ公差値でも公差域が小さいので、φた付いたものとして円筒柱を公差域としてもよいかと思います(下表参照)。
| φがついている公差域 | 二方向の公差域 |
φ有り無しの公差領域の差 |
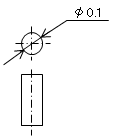 |
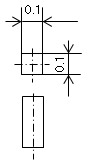 |
|
| ※同じ公差値なら二方向の方が広い(斜線部) |
| 前へ | 次へ |
トップ→幾何公差→●6.-1/6 幾何公差Q&A
© 2000 natuo