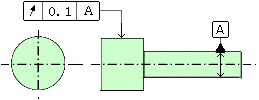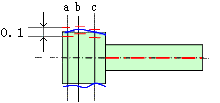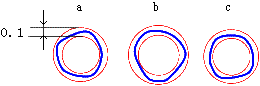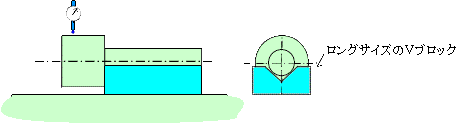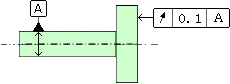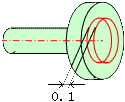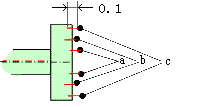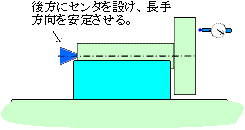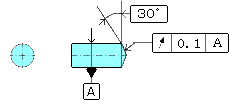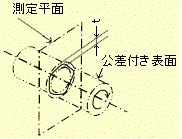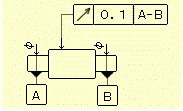| 幾何公差 3.13 円周振れ(右側定義と解釈参照) 1)図示例
公差域 データム軸Aを回転させた時、任意の位置の横断面の振れが0.1迄許容されます。
測定方法例 下図のように基準軸A全長が乗るVブロック上で回して任意の位置の振れ、最大と最小を測定し、その差をその断面の振れ量とします。
2)図示例2
公差域 データムAで回転した時、任意の位置で各々0.1以内の振れなら許容されます。
※ここでは軸心からの任意半径a・b・c各々が0.1に入っていればよい事になります。 測定方法例 端面の測定ですから長手方向にぶれがあると測定結果が安定しません。 お尻側にセンターを固定し、軽く抑えながら回します。
2)備考 この円周振れ公差はカムなどに使われると思います。 現実の測定方法は三次元測定器になろうかと思います。 3)備考2 円錐表面へ円周振れを指示する場合。 図示例と解釈
|
公差域の定義 公差域は、半径が t だけ離れ、データム軸直線に一致する同軸の二つの円の軸線に直角な任意の横断面内に規制される。
図示例と解釈 指示線の矢で示す任意の箇所にインジケータを当て、データム軸線に関して、対象物を1回転させたとき、インジケータの読みの最大値が0.1㎜の間に入っていなければならない。
|
| 前へ | 次へ |
トップ→幾何公差→●3.13 円周振れ
© 2000 natuo