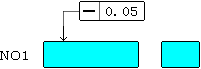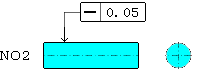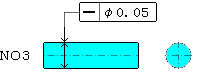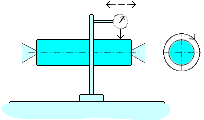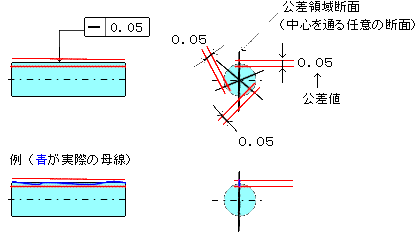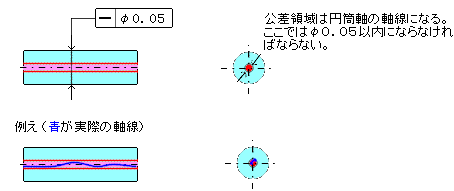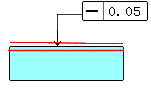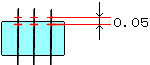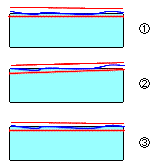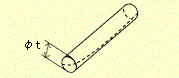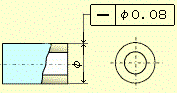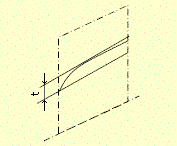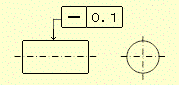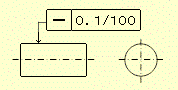| 幾何公差 3.1 真直度(右側定義と解釈参照) 1)図示例と検証方法例
2)図示例と公差領域例 公差値にφが無い場合
角材の場合
3)備考 4.1の1)にあるNO1とNO2は指示線の方向のみ規制され、NO3は公差値にφがあると同時に指示線が寸法線と一致しているので軸線の真直度を意味します。 指示線と寸法線が一致しているのか、していないかで意味も変わってきますので注意して下さい。 |
定義 公差域が示す数値の前に、記号φがついている場合には、この公差域は直径 t の円筒の中の領域である。
図示例と解釈 円筒の直径を示す寸法に公差記入枠が結ばれている場合には、その円筒の軸線は、直径0.08mmの円筒内になければならない。
定義 特に軸対象物の形体については、その軸線を含む平面上におけるものである。
図示例と解釈1 指示線の矢で示す円筒上の任意の母線、その円筒の軸線を含む平面内において、0.1㎜だけ離れた二つの平行な直線の間になければいけない。
図示例と解釈2 指示線の矢で示す円筒面の任意の母線上で、任意に選んだ100㎜の部分は、軸線を含む平面内において、0.1㎜だけ離れた二つの平行な直線の間になければならない。
|
|||||||||||||||||||||||||
| 前へ | 次へ |
トップ→幾何公差→●3.1真直度
© 2000 natuo