6.-1/10 JIS B 0001:2019 10 図形の表し方
10 図形の表し方
10.1 投影図の表し方
10.1.1 一般事項
一般事項は、次による。
a) 対象物の情報を最も明瞭に示す投影図を、主投影図又は正面図とする。
b) 他の投影図(断面図を含む。)が必要な場合には、曖昧さがないように、完全に対象物を規定するのに十分な投影図及び断面図の数とする。
c) できる限り、かくれ線(隠れた外形線及びエッジ)を表す必要のない投影図を選ぶ。
d) 不必要な細微の繰り返しを避ける。
10.1.2 主投影図
主投影図は、次による。
a) 主投影図として、対象物の形状・機能を最も明瞭に表す投影図を描く。
なお、対象物を図示する状態は、図面の目的に応じて、次のいずれかによる。
1) 組立図など、主として機能を表す図面では、対象物を使用する状態。
2) 部品図など、加工のための図面では、加工に当たって図面を最も多く利用する工程で、対象物を置いた状態(図19及び図20参照)。
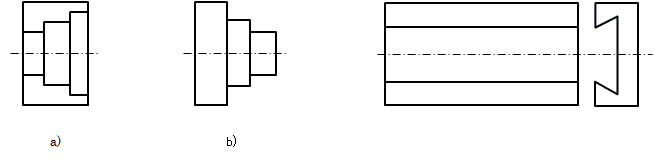 |
|
| 図19-旋盤加工の場合の例 | 図20-フライス加工の場合の例 |
3) 特別の理由がない場合には、対象物を横長に置いた状態。
b) 主投影図を補足する他の投影図は、できる限り少なくし、主投影図だけで表せるものに対しては、他の投影図は描かない(図21参照)。
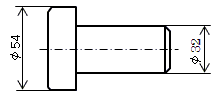 |
| 図21-主投影図だけの例 |
c) 互いに関連する図の配置は、なるべくかくれ線を用いなくてもよいように示す(図22参照)。ただし、比較対照することが不便になる場合には、この限りではない(図23参照)。
図22及び図23入る。
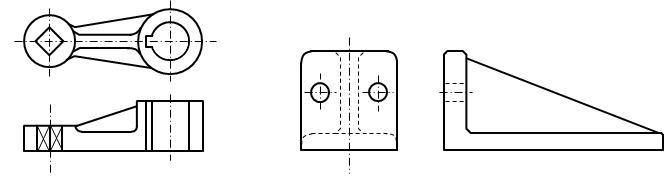 |
|
| 図22-かくれ線を用いない工夫の例 | 図23-比較対照する穴の例 |
10.1.3 部分投影図
図の一部を示せば理解できる場合には、その必要な部分だけを部分投影図として表す。この場合には、省いた部分との境界を破断線で示す(図24参照)。ただし、明確な場合には破断線を省略してもよい。
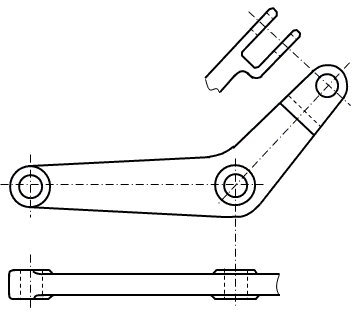 |
| 図24-部分投影図の例 |
| 前へ | 次へ |
トップ→機械製図(JIS B 0001:2019)→●6.-1/10 JIS B 0001:2019 10 図形の表し方
©2000 natuo