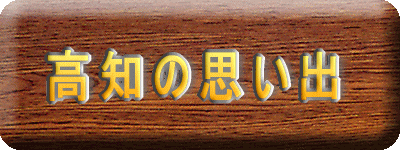
![]()
第53回:よさこい祭




土佐の高知のはりやま橋で、坊さん かんざし買うを見た・・・「よさこい よさこい」
美しい鳴子の音に合わせて、調和のとれた約100〜150名のチームが、楽しく踊る
リズム行進に感動したのは、私が、高知勤務を命ぜられた昭和46年でした。
以来2回目の勤務:昭和51年〜昭和53年、3回目の勤務:平成7年・8年に見学し
ました。そして平成18年の見学:静から動へと豪快な踊りの変遷に、更に感動し
ております。
高知市では、毎年8月9日から12日までの4日間、よさこい祭りが豪快に躍動感、
リズム感をもって、情熱的な夏祭りとして開催されます。
衣装は、見事な法被着物から、現代的、活動的な南国情緒豊かな衣服等々に加え、
現在では、その美しさにロック調、サンバ調、クラブ調、演歌調等々各チームが創意
工夫したさまざまな楽曲と振り付けが目前に広がります。
「鳴子」「衣装」「楽曲」「振り付け」「地方車」各チームの特色ある踊りに、ついつい引き
込まれて行きます。
よさこい祭りの歴史は、第二次世界大戦後の不況を打破しようと高知市の商工会議所
が企画したのが始まりです。
「徳島県の阿波踊り」に追いつけ、追い越せを目標に発足、まずは踊りの振り付けを日本
舞踊「花柳:若柳:藤間:坂東:山村の日舞:5流派」に依頼、踊りのための作詞と作曲
「よさこい鳴子踊り」を高知市在住だった武政英策氏に依頼する。
このときの武政英策氏の提案で、「徳島阿波踊りの素手に対抗して、高知は鳴子を使う
との意見と実践が、よさこい祭の基本アイテムの一つになっています。
第1回よさこい祭りは、昭和29年(1954)8月に開催されました。
よさこい祭のルール
(1) 参加人員は、1チーム 150人以下であること。
人員の極端に少ないチームは、エントリーを断られる場合がある。
(2) 振り付けは、鳴子を持って前進する踊りであること。
(3) 曲は、自由にアレンジすることはできますが、必ず「よさこい鳴子踊り」をどこかに
入れること。
(4) 地方車(トラック)は、1チーム1台であること。
車両の大きさには、制限がある。
参加優秀チームには、よさこい大賞ほか数々の賞が贈られることになっている。








以上有料桟敷席


高知中央公園:無料演舞場

![]()




高知市の中央に立つ典型的な平山城:慶長6(1601)年 土佐に入国した山内一豊
が大高坂山に築城工事を開始:慶長8(1603)年入城した。
以来16代 山内豊範(とよのり)「明治2年6月まで継続」した。
天守閣は、三層六階で、追手門など15の建物とともに国の重要文化財に指定されて
いる。


激動の戦国時代に信長・秀吉・家康と主君を代えながら生き抜いた一豊そして卓越
した政治感覚で夫を陰ながら支え続けた千代の像です。
千代の像は、城内に 一豊の像は、城外の設置されている。なぜ?・・・理由?
山内一豊は、天文14(1545)年、尾張国葉栗郡黒田に生まれる。
一豊は、流浪の末にいくつかの主君に仕えた後、織田信長の家臣である秀吉に使え
信長の越前朝倉攻めの武功で400石を与えられる。
本能寺の変で信長が死亡し、秀吉の天下になると、そのもとで数々の功績を重ね、
天正13(1585)年、近江長浜2万石、天正18(1590)年遠州掛川5万石を与えられた。
慶長5(1600)の関ヶ原で徳川方に味方し、土佐一国を与えられた。


旧山内家 下屋敷 長屋


長屋 瓦 山内神社

日曜市の開始は、約300年前、本町:帯屋町を
経て追手筋で開市されている。
今では、各地で曜日○○市が開催されている。

記録写真集へ
![]()