
![]()
1 東北四大祭
2 三陸:陸中の旅
![]()
![]()
長かった冬季から、一気に開放されたような熱気溢れる東北地方の夏祭りに感動する。


1 青森ねぶた
ねぶた祭りは、七夕様の灯籠流しの変形であるといわれています。七夕祭りは、7月7日
の夜に穢れを川や海に流す禊の行事ですが、ねぶた祭りも7日目には、ねぶた人形を川
や海へ流す慣わしがあります。
七夕祭りが、全国各地でいろいろと型を変え、その土地独特の祭りになった。
それらの中でも日本海側にねぶた祭りに似た祭りが多いそうです。その源流は、京都祇園
祭りで、京の文化は、日本海を伝わって津軽へ運ばれたとも言われています。
京都祇園祭りの宵山は、山、鉾に提灯を飾るもので、琉州の「キリコ」、魚津の「たてもん」
に似ている。
また提灯の配列は、秋田の「竿灯」の下げ方と同じ。北上するにつれて、祇園祭の飾り山
が簡略化されている。しかし、その運行方法は、囃し方、曳き方、車方など同様である。


1−2 弘前:ねぷた・・・ねぷ(PU)た 青森ではねぶ(BU)た と呼ぶそうです。


弘前ねぷたは、丸みをしたもの、何故か青森と趣を異にしています。
2 秋田竿燈
天の川のように煌く星座の如く、、提灯の明りにより見事に装飾された光が、大通りを埋め尽く
し、そして行進する。
米俵を模った提灯は、先端に厄払いの御幣を付け、稲穂に見立てた竿燈を、代表担ぎ手が、自
由に操る。
肩に、腰に、額に、軽々と差し上げる。その技は、観衆を熱狂させる。真夏を彩る競演です。素
晴らしい感動のお祭りの一つです。
竿燈祭りは、真夏の病魔や邪気を払う。ねぶり流し行事として、宝暦年間には、その原型となる
ものが出来ていたといいます。
寛政元年(1789)陰暦7月6日のねぶりながしに、長い竿を十文字に構え、それに灯火を数多く
付けて、太鼓を打ちながら、町内を練り歩き、その灯火は、2丁・3丁にも及ぶといった竿燈の原
型が、津村淙庵の紀行文「雪の降る道」で紹介されている。
元々、藩政以前から秋田市周辺に伝えられているねぶり流しは、笹竹や合歓木に願い事を書い
た短冊を飾り、町を練り歩き、最後に川に流すものであったそうです。
それが、宝暦年間の蝋燭の普及、お盆には、門前に掲げていた高灯籠などが組合されて、独自
の行事として発展したものと言われています。
ねぶり流しは、五穀豊穣や技芸上達を願って、翼7月7日に行われる七夕とともに陰暦7月15日
のお盆を迎えるための一連の行事でもあり、厄除け、みそぎ(禊)、五穀豊穣などを願う現在の
竿燈の形が徐々に出来上がったといいます。


厄除け、五穀豊穣等を祈願してのお祭り 稲穂(提灯46個)の重さ
と竿の長さ(12m)等を保持するバランスが重要とのことです。
2−2竿燈妙技大会





流し 平手 額 肩 腰
竿燈の規格(4種類)
長さ(m) 重さ(kg) 提灯の大きさ(cm) 提灯の数 大若 12 50 64×45 46 中若 9 30 48×36 46 小若 7 15 48×36 24 幼若 5 5 30×21 24
年齢別等(技量の程度を含む)に区分した競技:競演は、幼少時から伝統を
育成すことになり、この発案者と実践された方々に敬意を表したいと思います。
50kgの提灯を肩に、おでこに、腰等とバランス感覚が素晴らしい。
思い出の一つとして、心に残っています。
3 山形花笠まつり
「花笠踊り」で歌われる「花笠音頭」は、別名「花笠踊り唄」とも呼ばれ、明治・大正の頃、山形県
村山地方で歌われていた「土突き唄」が元唄とのことです。
現在のように、にぎやかな伴奏を入れて民謡化したのは、昭和初期のことです。
昭和38年、日本舞踊的な新振り付けの「正調:花笠踊り〜薫風最上川〜」が誕生、平成11年に
は、男性的な踊りの「正調 花笠踊り〜蔵王山暁光」が誕生しています。
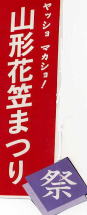

山形出身の北見恭子さんが応援



にぎやかなお囃子にのって踊る雰囲気は、最高です。
4 仙台七夕
仙台藩祖 伊達政宗公は、元和4年(1618)「まれにあふ こよいはいかに 七夕の そらさえ
はるる あまの川かぜ」以下、七夕に因んだ歌を8首を詠んでいるとのことです。
昭和2年 不景気を吹き飛ばそうと商家の有志が、仙台商人の心意気とばかりに、華やかな
七夕飾りを復活させたところ、仙台っ子達は、喝采し、飾りを一目見ようとする人で街は、溢れ
たそうです。
戦争で七夕祭りは、街から消えていましたが、終戦の翌21年 焼け跡に52本の竹飾りが立て
られ、以後除々に復活し、現在の猛況に至っているそうです。







記録写真集へ
![]()
![]()


唐桑半島:巨釜半造






歌手 千昌夫(陸中高田の出身)が建築


青森:三八五観光バス やさしいガイドさん 碁石海岸;碁石岬








浄土か浜


浄土カ浜 北山崎案内図




古牧温泉グランドホテル第1〜第4まであり、地下で繋がっている。 池が凍っている。


渋沢邸の裏側 渋沢公園


渋沢邸の全景 控え室


居間 残雪
明治の実業家:渋沢栄一氏の邸宅で、平成3年 約12億円かけて東京:三田から移築
保存されいる。
この建物は、明治9年 清水建設の創始者:清水喜助氏による建築である。
* 渋沢栄一氏 (天保112年〜昭和6年 1840〜1931)
日本初の第一国立銀行を創立した。この銀行を足場に500を超える
企業を設立、指導援助に当たった。
日本資本主義を築いた実業家である。
* 渋沢敬三氏 (明治29年〜昭和38年 1896〜1963)
祖父が、渋沢栄一、戦時中は日銀総裁、戦後は大蔵大臣として活躍
した経済人である。
* 杉本行雄氏 昭和4年、16歳のときに、渋沢栄一氏の書生となり、戦中・戦後は、
秘書執事として、渋沢敬三氏に仕えた人である。
昭和21年、財閥解体の命令で、渋沢農場を整理するため、青森へ
行き住み付いた。
その後、三沢市で温泉を掘り当てて大観光施設を経営
古牧温泉は、全国温泉地:上位10選:連続1位とのことです。

記録写真集目次へ
![]()