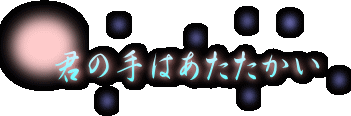師走も半ばに入り、時折雪がちらつくようになった京の都。 今日も今日とて、いや、今夜も今夜とてと言うべきか。 希代の陰陽師・安倍晴明の末孫であり、彼の後継者、と殿上人たちに期待されているがその辺の自覚はなしの少年・安倍昌浩は、今夜も今夜とて邸を抜け出し夜警と称し、夜の都を歩いた。 途中、恒例の『一日一潰れ』が行われ逃げ出す術もなく潰されたりもしたが、それ以外には特に不穏な気配もなく、とりあえず今日、いや今夜のところはということで、昌浩と物の怪は邸に帰宅した。 子の刻を一時ほど過ぎた頃だろうか。 近頃は昼間もそれなりに寒いが、今夜はそれを上回り一層冷え込んでいる。 昌浩は、最近もはや習慣となってきた物の怪の襟巻きで首周りを、手を直衣の袂にしまい交差させて手の寒さを凌いでいた。 ふと頬に冷たいものを感じて空を仰ぐと、術で夜目の聞いた昌浩の眼に、空から鳥の羽根のようにひらひらと舞い落ちる粉雪が映った。 「――雪だ…」 つられて物の怪も顔を空に向けた。夕焼け色の瞳に白い雪が映る。 「どうりで今夜はいつもより寒いわけだな」 「うん」 ふわふわと舞う小さな落下物に、思わず昌浩は足を止めた。 吐く息が白い。 雪はそれよりももっと真白い。 「積もるかな」 「さあな。それより早く邸に戻ろうぜ」 「うん…」 「風邪ひくなよ、晴明の孫」 「孫言うな、物の怪のもっくん」 「もっくん言うな孫」 なおも禁句を言い募る物の怪の頭をぺしんとはたいて、昌浩は先程より速めの速度で、再び歩き出した。 「…まさか今夜も部屋で待ってたりしてないよな」 ぽつりと呟いて、自室があるあたりの、安倍邸を囲む築地塀をよいせとよじり登る。ちなみに物の怪は一足先に塀の上だ。 やはり塀というのは登るよりも降りるほうがいい。降りるためには登るしかないのだが。 築地塀からひらりと庭に飛び降り、たたっと助走をつけて廊下に飛び乗る。 飛び乗ったときに必然的にしゃがみ込むかたちになり、その膝のばねで立ち上がり、自室の妻戸を開けた。 部屋には明りが灯っていた。 「………………」 やはりというか、なんと言うか。 予想はしていた。 していたのだが、それはやはり予想であり、現実を目の当たりにするまでそれは推察に過ぎなかった。 ――予想が現実になったとき、自分はどういう反応をすべきなのだろうか。 一瞬ちらりと昌浩の頭にその思いがよぎったが、すぐにそれは消え去った。 「あ、おかえりなさい、昌浩。それにもっくんも」 「…ただいま」 「おう」 明りを灯し、文机に向かっていたその存在は、気配に気づくと振り向き、花のように微笑んだ。その笑顔に昌浩の動悸が少し速くなる。 昌浩の足元にいた物の怪が、とてとてとその存在――彰子の傍に近づくと、その手元を覗き込んだ。 「お、ちゃんと勉強してるな。偉い偉い」 「ありがとう、もっくん。でもね、ちょっと読めない漢字があって」 「あぁ、そうか。どれどれ、どれが判らないんだ?」 「あのね……」 部屋の主を差し置いて、彰子と物の怪は和気藹々と書を読み始める。 面白くない。 なんだか面白くない。 何がどう面白くないのかは判らないが、とにかく面白くない。 それに何よりも。 「彰子」 「なぁに、昌浩。……あ、そうだった、今夜はどうだったの? 今日も潰されちゃったの?」 「何でそれを彰子が知って―――て、そうじゃなくて」 なあに、と彰子がにこにこと微笑みながら昌浩を見る。 彰子の笑顔が見られるのは嬉しい。嬉しい、けど。 「…あのな、彰子。なんかいつも言ってる気がするけど、こうやって待ってくれなくていいからさ」 「あら、なんで?」 「……なんでって」 すぐさま問い返されて、言葉に詰まる。 何故、と訊かれても、すぐには応えが出てこない。 「あら? 昌浩、直衣がちょっと濡れてるわ。どうかしたの?」 「あ、それは、雪が降ってたから」 「雪? 雪が降っているの?」 「うん」 昌浩が頷くと、彰子は慌てて立ち上がり、妻戸を開けた。 妻戸の向こうでは、白く冷たい雪が、絶え間なく地上に舞い降りていた。 「わぁ……!」 廊下に身を出した彰子の瞳に、冬の景色が映る。 白い、真白い雪。 小さな落下物。 先ほどまで、昌浩と物の怪が邸の外にいたときは、まだちらついている、という表現が一番合っていたものだが、今はもう勢いが増して、絶え間なく、という表現が正しいように思える。 築地塀には、少しずつだが雪が積もり始めている。 舞い降りて、舞い降りて 地上の一部と化す 自身の吐くその白い吐息よりも、更に白い。 「きれい……」 その景色を目にし、無意識に感嘆の言葉が彰子の口から滑り出る。 立ち上がった昌浩が、彰子の斜め後ろ、妻戸に出る。 物の怪は、文机の隣でおすわりをして、二人の様子を見守っている。 「……あのね、昌浩」 「…うん」 しばらく二人の間を沈黙が支配した後、瞳を未だ雪に向けたまま、彰子が口を開いた。 廊下の上には屋根があって、雪は彰子の方には舞い降りてこない。 風に流された雪が、たまに彰子に寄ってくるだけだ。 それが少し、…物悲しい。 「……安倍のお邸に来る前、東三条のお邸にいたときはね。――雪なんて、触らせてもらえなかったわ」 ふと、雪が一粒、彰子のほうに舞い降りてきた。 彰子はそれに手を伸ばし、手に掴む。 ――掴んだ雪は、彰子の手の体温に触れて、その形を無くし、水滴となった。 「雪が降っても、私は邸の奥から見ているだけ。小さい頃に触らせてもらったことはあったけれど、それきりだったわ」 邸の外、妻戸の向こうから見える、その冬という名の季節は、遠いものだった。 「それが、今は」 ――お風邪でも召しては悪うございます。 ――貴女様は藤原の姫なのですから。 ――姫様に何かあったら、殿に何と申し上げればよいのでしょう。 「今は……こんなにも近い」 息がしろい。 雪が舞い落ちる。 こんなにも近い。 東三条の邸にいるのが嫌な訳ではなかった。 あの邸があの時の彰子の唯一の居場所だった。 不満だった訳ではない。 彰子はあの邸しか知らなかったのだから。 ただ。 寒い寒い冬の日。 ひらひらと舞い落ちる雪に。 近づいて、触りたかった。 「…彰子」 戸惑った昌浩の声。 安倍の邸はあたたかい。 東三条の邸も華やかであたたかかったが、それとは別に、気持ちがあたたまる。 晴明がいて、吉昌がいて、露樹がいて。物の怪がいて、――昌浩がいて。 ここにいられるのが嬉しい。 昌浩の傍にこうしていられるのが嬉しい。 「――私ね、嬉しいの。こうやって、雪に触れられるのも、昌浩と一緒にいられるのも。 ――昌浩の部屋で、書を読みながら、昌浩を待っていられるのも」 彰子が振り返る。 妻戸のところに立ちすくんでいた昌浩に笑いかける。 「こうやって、昌浩にお帰りなさいが言えるのが、嬉しいの」 「…彰子」 「待ってあげているんじゃないわ。私が待ちたくて待ってるの」 「でも」 「………駄目?」 上目遣いに見つめられ、う、と昌浩が小さく唸る。 真摯な視線に耐えられない。 「……遅くなるって判ってる時は、言うから。その時は、待ってないで寝ろよ。――約束、してくれるなら」 彰子の表情が明るくなる。 「もちろん、守るわ。約束ね。――約束、二つ目ね?」 「うん」 彰子が小指を差し出す。昌浩も小指を差し出して、彰子の小指に絡めた。 二回目の、指きり。 ゆーびきーりげんまん、と彰子が歌う。 歌にあわせて、小指を絡めたまま手を揺らす。 「昌浩、手が冷たいわ」 「え。そう? ごめん」 指切りをし終わって、彰子が言った。 彰子は今まで邸の中にいたのでそんなに冷たくはないが、ずっと夜の外を歩いていた昌浩の手は冷たかった。 「ううん、いいけど……」 呟いて、彰子は頭を振る。 そして、思わぬ行動に出た。 「え、ぁあ彰子っ?」 昌浩の手を掴み、片手で妻戸を閉めて、部屋の中に入って、そして一緒に座った。 これには今まで温かく二人を見守っていた物の怪も、目を丸く…いや、目を見開いた。 彰子は二人して座り込むと、昌浩の両手を合わせて、自分の手で覆うようにした。そして、 はーっ 「ぅえ、彰子っ!?」 彰子が強引に昌浩を邸の中に引っ張ったこと事態驚きだったが、更にこれにも驚いた。 息を吹きかけて、覆った手をこする。 それを、何度も何度も、繰り返す。 「あ、ああああぁぁあ彰子、ちょっと」 予想もしなかったこの出来事に、昌浩はうろたえる。言葉が上手く紡げない。 「少しは温かくなるでしょう?」 彰子がにっこり笑う。笑顔が見られるのは嬉しい。嬉しい、だが、これはちょっと! 「……熱いねぇ」 その様子を見ていた物の怪が、ポツリと呟く。二人の周りだけ、別の意味で熱そうだ。 しかしそんな物の怪の呟きも、うろたえまくっている昌浩の耳には届かない。 そんな昌浩と物の怪の様子など気にした風もなく、息を吹きかけてはこすっている。 「――〜〜〜〜っ、彰子!」 とうとう耐え切れなくなり、昌浩が小さく叫ぶ。 「なぁに?」 きょとん、と彰子が首をかしげる。ちなみに表情は笑顔だ。 「あ、あのだから、…だ、大丈夫だからその」 「でも、まだ冷たいわ」 あたためようとしてくれているのは判る。嬉しい。だがちょっと精神的にいただけない。 先ほどから昌浩の心臓は爆走中で、平常に戻りそうもない。 「昌浩、…嫌?」 青天の霹靂。 本当にこの姫には驚かされてばかりだ、と昌浩は思う。 「いや、そ、そういう訳じゃ決してないけど」 「なら、なんで?」 ぷう、と彰子が頬を膨らませる。 なんで、と言われても。 言葉に詰まる。 嬉しい。自分のことを思っての行動だというのは判る。判るのだが、なんだか恥ずかしい。 ――、でも。 この手は、あたたかい。 あたたかいぬくもり。 少し前までは感じることさえ出来なかった。 苦しくて、痛くて。死んだほうがましだと、思う事もあった。 でもその苦しみ、痛みは。――彰子が生きているという、確かな証拠だった。 触れる事も、言葉を交わすことも。――姿を見ることさえできなくなる。けれど。 生きていてくれるのならば。 ――その、ぬくもりが。 今、ここに在る。 「…じゃあ、――その」 「なぁに?」 一つしか年は違わない。けれど自分より小さな手。 昌浩をあたためようと、覆う手。 「その、息。息は…いいから」 ――その手を離さないで 君の手はあたたかい。 「…わかった」 彰子はにっこり笑うと、手の位置を変えた。 「――――仲のよろしいことで」 物の怪はポツリと呟くと、袿を数枚引きずって、二人にかけた。 壁に寄り掛かった二人は、仲良く手を繋いだまま、静かな寝息を立てている。 冬の夜は、静かに過ぎていった。 終わってみましょう。
|
||||
|
||||