〒110-0004 東京都台東区下谷1-8-20
浄土宗長松寺のページCONTACT US
きっと会いましょう

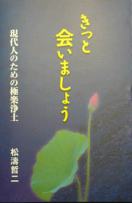
全文をテキストデータで載せました。ダウンロードして電子ブックで読んでください。
- 第四章
第四章 大乗仏教の登場
前章で、最初のお経の成立の様子と、多くの部派に分裂した仏教の歴史をたどってみました。仏教の理解というのは本当に大変です。時間の長さは言うまでもありませんが、内容の複雑さが我々の理解を妨げているのです。泣き言を言っても始まりません。さて、お釈迦様が亡くなってから四百年から五百年ぐらいたって、(お釈迦様の生きた時代がはっきりと確定できないため、三百年から四百年という説もあります。)大乗仏教が登場してきます。その中に、般若経、法華経、浄土経、少し後の時期になりますが密教が含まれています。日本に伝わった仏教はこの大乗仏教です。日本の仏教宗派は、この大乗仏教の流れになります。その大乗仏教ですが、実はどのように登場してきたのかこれがまた学問的には難しい問題ではっきりとしていないのです。どんな人達が中心となって、どの辺の地域でできあがっていったのか、たくさんに分かれた部派との関係はどうなのかなど、ある程度解明されていますが、今も研究が続けられている状況です。まあ、思想的に徐々にできあがっていったと言えば間違いはないのですが、それでは、今浄土の理解ということには役立たなくなってしまいます。なんとか、みなさんに解りやすくお話しなければなりません。その登場の様子を考えていくことが、浄土への距離をちぢめることになるかもしれません。どんな理由で大乗仏教が登場したのか。どんな理由で浄土教が登場したのか。何か浄土に結びつくものがあるかも知れません。ただ、繰り返し言いますが、これらの大乗仏教の経典が一朝一夕にできたものではないことははっきりしています。つまり誰か一人の作者がいて、あっというまに書き上げたと言うことはありません。法華経などは実際に何回か後から書き加えられた部分があるというのが常識となっています。徐々にできあがった証拠です。多くの人が参加して議論されてできあがっていったのです。その他のお経についても同様のことが言えます。大乗仏教の話をするときには、このことが大前提となります。その他にも注意しなければならない点がいろいろ大乗仏教の登場にはあったのですが、そのすべてをここで取り上げるというわけにはいきません。浄土の理解をするというのが、この本の目的ですから、その目的にあった見方をしていこうと思います。とは言うものの、学術的にも、なるべく正確を期して行きたいとは思っています。さてそこで、ある有名な王様の話からスタートして大乗仏教の登場を考えていきましょう。
みなさんは、アショーカ(阿育)王という名前を聞いた事がありますか。仏教にとっては非常に大切な王様です。お釈迦様が亡くなって百年ほどしてマウリヤ王朝という国にアショーカ王という王様がでました。この時代のインドの国々は勢力争いから、戦を繰り返すという状況でした。この王様がある戦争をした時のことです。その様子はあまりに悲惨で残酷でありました。それを見て、アショーカ王は、自らの起こした戦争を非常に悔いて反省しました。こんなことはもうやめようと思いました。そして心機一転人々の和合を説く仏教に帰依して、友好共存政策に転換したのです。そして全インドを支配する王国を築きました。それからというもの一生懸命仏教の修行に励み仏教を保護し広めていきました。伝道師と呼ばれる人々を海外に派遣するなど、仏教が広まったのは、この王様の功績が大きいのです。また王様は仏教の遺跡の整備をしたり、たくさんの仏塔を建立しました。最初仏塔というのはお釈迦様の舎利(遺骨)をまつるためのものでしたが、アショーカ王の王国がインド全土を支配するに及んでその支配地域に広くたくさん建立されていったのです。王様の建てた塔が大乗仏教とどのような関係があるのかと思われるでしょうが、もう少し時代の経過を見てください。
お釈迦様の亡き後、遺骨を八カ国に分けて仏塔をつくりそこに安置したという話は有名ですが、アショーカ王の建てた仏塔も、お釈迦様を慕う人たちが崇拝して信仰のよすがとしたのです。それと、仏教の聖地として、誕生の地ルンビニー、成道の地ブッダガヤー、初転法輪の地サールナート、涅槃の地クシナーラーというお釈迦様ゆかりの地が信仰の対象となりました。これらの地の整備をするなど、仏教を広める努力を熱心にしました。そのアショーカ王が全国にたてた仏塔は、その地域の人々にとって信仰の中心的存在になっていきました。いわゆる仏塔信仰の始まりです。そしてその塔を中心として建物が建造され、人々がそこに集まり新しい仏教集団ができあがっていきました。その集団は、建物などの財産管理ということがあったようなので、在家と呼ばれる人(お坊さんでない人)が、その管理に当たりました。一方その当時の仏教教団の中心的な存在は、どういう人達だったかというと、僧院を中心にして出家者が、お経を研究して、師僧から弟子に教えを伝えると言う形態の仏教専門家集団となっていました。前述しましたが、こうした集団にはパトロンがついて、お坊さん達は専ら、教義的哲学的な研究に没頭することができたようです。そのため、民衆とは非常にかけ離れたものとなってしまったようです。それに対して、この新しいグループは、こうした仏教専門家とは別の活動をするようになったのです。そしてその集団の中で、遺跡を訪れる人々に向かって教えを説く役目の人などが登場して新しい思想が仏教の中に生まれていきました。基本的にはお釈迦様を讃える話を巡拝にきた人に話していたものと考えられています(讃仏思想)。ところがこれが、徐々にエスカレートして、お釈迦様を讃えるあまり神格化する方向へと向かっていきました。話の筋を想像してみると、おそらく最初は、お釈迦様はすばらしい人でした。お釈迦様の教えはすばらしい。と言うことを伝えていたのでしょうが、そのすばらしさを強調するあまり、並大抵の教えではないと神格化する方向に進んでゆきました。人間釈迦が神様のような存在になって行きました。そう言う存在になるためには、並大抵の修行ではたりないから、前世から、お釈迦様は長い間修行していたのだと言うことになり、数々の奇跡が創作され、お釈迦様物語が成立しました。今大乗仏教の大きな流れを記述してゆきますが、このあたりから大乗仏教の世界に入ってきます。続けてそのあらすじを追ってみましょう。神というのはスーパーな存在ですから、神格化が進んだと言うことにともなって、スーパーな仏様が仏教の中に登場するようになります。代表選手は、毘廬舎那仏(びるしゃなぶつ)でして、奈良の大仏さんがそれです。その他にも阿弥陀様、観音様、弥勒菩薩といったスーパーな仏様たちが登場しました。
そんなにすばらしい教えであるならば、お釈迦様のようにこのことに気がついた人が過去にもいたはずだということになり過去仏が説かれるようになります。(過去七仏思想)次には、未来にもきっと現れるはずだということで、弥勒菩薩のような未来仏が説かれるようになります。最終的にはそれほどすばらしい教えならば、現在も多くの悟りをひらいた仏が仏様の国(仏国土)にいるということになりました。これが現在仏です。この現在仏という世界に踏み込むというのは思想的には大きな飛躍となります。現在と言うことになれば実体験するという可能性が生じるわけですが、現実的には不可能です。そこをあえて踏み込むというのは大きな飛躍です。この中で一番人気があるのが、手前味噌になりますが、極楽浄土の阿弥陀様ということになります。
又、この当時には、仏教がかつて批判したバラモン教が先住民族の信仰と習合してヒンズー教ができあがり、インドの代表的な宗教となってきたのです。このヒンズー教の影響も見逃すことのできない要因です。仏教が民衆とは、離れた存在となっていたのは前述しました。ヒンズー教は非常に民衆に近く救済主義的であったので、大乗仏教に救済主義的要素が取り入れられました。
本来仏教は自己の修行を専らとするものでしたが、利他行(他人の幸福を考える)に邁進するという看板を掲げるるようになった。このように、大乗仏教では、もっぱら他人の救済を第一にするという菩薩(ボーディサットバ)という理想像が打ち出されました。また、ヒンズー教の影響かどうかわかりませんが、呪術的要素を取り入れた密教が後半成立しました。呪術的なものが人間にどのような安心を与えるのかというのも非常に興味のある問題ですがこの本ではテーマが違いますので先に進みます。
次のような考えも登場します。その教えがそんなにすばらしいものならば、今この世の中にも充ち満ちているはずだ、我々は今その中に浸っているはずだ。我々の中にもその種があるはずだということで、誰でもが仏になれるという思想(如来蔵、仏性)を登場させました。「一切衆生悉有仏性」(一切の衆生は悉く仏性を有す)という難しい言葉で表現されます。どんな人も悟りを開くことができるという考えです。自己の完成を目指すという初期の仏教から見ると、隔絶の感があります。しかし、一般民衆にとっては、これは非常にありがたい考えです。
このように、様々の要因がからみあって大乗仏教は登場しました。その大まかな姿をお話ししましたが、在家(宗教専門家でない人)仏教運動が大乗仏教の基本になっている事は疑いのない事と言えます。そして今、この本のテーマに関して、一番重要なのは、この新しく登場した大乗仏教が、いろいろ新しい主張をするために新しい教典、大乗教典を作っていったのです。こうして登場した大乗仏教の中に、そう、般若経、法華経、華厳経、阿弥陀経、最後の方になりますが密教と言ったお経が存在しています。ようやくここに浄土教が登場しました。お釈迦様が亡くなった後、四百年から五百年たった時代に、新しく創作されていったのです。この点をよく覚えていてください。
さて、大乗仏教が登場してきた概要ですが、ご理解いただけましたか。お釈迦様を讃えるところから出発して、まったく新しい仏教を創り出していったのです。歴史の流れですから、事実として受け止めなくてはなりません。こうした認識を欠いては、仏教に値打ちが出てきません。こうしたことを前提としても浄土教はすばらしいと思っています。どうかここは私を信じて先に進んでください。しかし、なぜ仏教がこのように変化してしまったのでしょう。お釈迦様を讃えるあまり、何となくできあがってしまったと言うことではありません。そこには何か人間的な要求があったと思われるのです。これが非常に重要なことはみなさんもおわかりだと思います。お釈迦様の説いたことで十分ではなかったのでしょうか。何か変えないといけないものがあったのでしょうか。私はお釈迦様の教えに何か人を寄せ付けないような厳しさがあったのではないだろうかと考えているのです。この辺のことは理解が難しいですね。こういう問題は研究している先生が大勢いらっしゃるのでそちらにおまかせすることにして、とりあえず、お釈迦様の仏教の基本姿勢にさかのぼってこのことを考えてみようと思います。みなさん第二章で、お釈迦様とヴァッチャの会話を紹介しましたが、それを思い出して下さい。重要ですから、繁をいとわず再掲しましょう。
「ヴァッチャよ、なんじがまったく解らなくなったというのは、当然であろう。ヴァッチャよ、この教法は、はなはだ深く、知りがたく、すぐれて微妙であって、智慧ある者のみが知りうるところのものである。他の見解にしたがっている者や、他の行を修している者には、とうてい知られ難いものであろう。だが、ヴァッチャよ、わたしはさらに、なんじのために説こう。いまわたしが、なんじに問うから、思いのままに答えるがよい。ヴァッチャよ、もしなんじの前に、火が燃えているとしたならば、なんじは、火が燃えていると知ることができるか。」
「むろんである。」
「では、ヴァッチャよ、この火は何によって燃えるのであるかと問われたならば、なんじは何と答えるか。」
「それは、この火は、薪があるから燃えるのだと、わたしは答える」
「では、もしなんじの前で、その火が消えたならば、なんじは、火は消えた、と知ることができるか。」
「むろんである。」
「では、ヴァッチャよ、かの火はどこに行ってしまったのかと問われたならば、なんじはいかに答えるか。」
「世尊よ、それは問いが適当ではない。かの火は、薪があったから燃えたのであり、薪が尽きたから消えたのである。」
そこで、世尊は、うなずいて、さて説いて言った。
「ヴァッチャよ、まったくその通りである。そしてそれと同じように、かの色をもって人を示す者には、色が捨てられ、その根は断たれる時、その人はすでになく、また生ぜさるものとなるであろう。その時、ヴァッチャよ、人は色より解脱したのである。それは甚深無量にして底なき大海のごとくであって、赴きて生ずるというも、赴きて生ぜずというも、 当たらないであろう。そして、ヴァッチャよ、受についても、想についても、行についても 識についてもまた同じである。」
かように世尊が説かれるのを聞いて、ヴァッチャは豁然(かつぜん)としてさとることができた。」
ここでちょっと仏教教室ですが、色、受、想、行、識というのは、五蘊(ごうん)といって、人間の構成要素、つまり、この五つの要素によって人間ができていると考えられていたわけですが、そのどれをもって、その人の存在を示しても、それが捨てられ、根が断たれるとき、薪がつきて火が消えるのと同じ理屈で、その人は存在しなくなると言っています。解脱するのだと言うのです。解放されるのだというのです。思いのままに答えてたどりつく道理ですが、説かれたところは非常に厳しい内容です。要するに、人間のある要素を持ってその存在を示しても、死後の存在を証明する根拠とはなり得ないと炎の例えをもちいて経験的に言っているのです。だから、それ以後の議論はしてはいけないと続けて教えます。どうですか。これを聞いて親しみを感じる人はまずいないと思います。言われてしまえば肯かざるを得ませんが、そこには人間的なものが何か欠けているように思うのです。もっとも、お釈迦様は人間的なことを、克服しようとしていたのかもしれません。
また、次のようなお話があります。
お釈迦様が亡くなる少し前次のような会話がアーナンダとの間にありました。それは最後の旅の時の事です。お釈迦様は旅の途中非常に重い病気にかかりました。年老いた身でありながら、生きるか死ぬかという病を一時克服したのです。その時、アーナンダはお釈迦様に、もしお釈迦様がいなくなったら誰を指導者として誰を頼りとしてやっていけばいいのでしょうかと尋ねたのです。心細くなったのでしょう。それに対してのお釈迦様の答えは、
「アーナンダよ、まことに、今においてもまた我が亡きのちにおいても、みずからを洲とし、みずからを依所(えしょ)として、他人を依所とすることなく、また法を洲とし、法を依所として、他を依所とすることなくして修行せんとするものは、アーナンダよ、かかるものは、我が比丘衆のなかにおいて、最高の地位にあるものである。」と答えたのです。大変有名な言葉です。法帰依、自帰依(ほうきえ、じきえ)と仏教的には言います。教えに従い、自らをよりどころとしなさいと言う教えです。お釈迦様は、なによりもまず自己の知恵を持って、お釈迦様の説いた教えに従って自己修行を続けて行きなさいと言う孤高の道を示したのです。智恵を持って人間の持つ苦に打ち勝とうとする事を基本姿勢としたのです。一般の人々にとっては、どちらかというと近寄りがたい教えでした。出家者の道だったのです。
又次のような話もあります。
ある村の長がお釈迦様が人々に教えを説く様子を見ていて、ある人には詳しく説きある人にはそれほど詳しく説かないという事に気がつきました。そのことをお釈迦様に尋ねると次のような答えが返ってきたのです。
「部落の長よ、なんじは、このような場合をいかに思うであろうか。ここに一人の農夫があって、かれに三つの田があるとするがよい。その一つの田はすぐれた美田であり、もうひとつの田は中等の田であり、さらに、今ひとつの田は悪質の砂地であって、塩分をふくんでいるとする。それらの田に、いま農夫は種子をまこうとする。そのとき、かれはまず、いずれの田よりはじめるであろう」
このように反対に質問するような形で答えが返ってきたのです。もちろん農夫は美田より種をまき始め、次に中等の田そして最後に悪質の田ということになります。そのように人に教えを説く場合も優秀な人から説き始めるのが当たり前と答えました。お釈迦様がまず教えを伝えたのは知識優秀なものたちだったのです。お釈迦様の教えが基本的には理解の難しい教えであったということです。私自身も、こういった仕事にかかわって何年も仏教に取り組んできました。しかし、正直なところお釈迦様の教えを理解しきれないでいます。それは、後世人の手が加わったと言うこともありますが、一つの哲学としてもそれは非常に難しいものです。お釈迦様の教えは、思うままに答えていってたどり着くことができますが、ものごとの本質をついていて、普段我々がウッカリしてしまっていることを教えてくれるような一つの哲学だと私は理解しています。そしてそれは、まったく正しいものなのですが、それを身につける事は、なかなか難しいことなのです。今述べてきたように、お釈迦様の教えには何か人を寄せ付けないところがあった。このことは、仏教の理解が思うようにできない人々を創り出しました。又、仏教教団の中に階層をかたちづくる原因となりました。お釈迦様の教えがどうも解らない近づきがたいという人たちを作り出しました。こうした階層性を打ち破りすべての人が理解し実践してゆく仏教にしようという要求が、お釈迦様の仏教には最初から課題としてあったといえるのです。こうした基本的な要因に、前述したアショーカ王の建造した仏塔にはじまる仏塔信仰の盛り上がりの中で、その仏塔を訪れる不特定多数の人たちに向かって、仏教を説くという作業は、ちょうどマッチしていたのです。つまり仏教をすべての人に開かれたものにしようと言うことになりました。これが大乗仏教の基本です。そして、当時勢力を延ばしてきたヒンズー教の救済主義的な性格は、非常に仏教にとっては魅力的なものであったのです。仏教的な民衆救済という考えが、こうした背景の中長い長い年月をかけて生み出されていったのです。
大乗仏教と根本仏教あるいは原始仏教と呼ばれる教えを比較するときこのような見方をするとよく理解できます。同じお釈迦様が説いたのだろうかという、仏教のお経どうしの矛盾はこんな事情から生じたものです。ちょっと難しくなってしまいました。大乗仏教の登場、お解りいただけましたか、古い古いインドの国のお話です。学問的にもまだはっきりとしたものがなく理解が非常に難しいのです、がしかし、その基本的性格を一言で言えば大衆化したのです。良い意味でも悪い意味でも大衆化したのです。我々のようなできの悪いもののために仏教が近づいてきてくれたとも言えます。優しく温かく解りやすくなったとも言えます。
さて、ここまで讃仏運動に端を発した大乗仏教への変化の様子を大まかに見てみました。せっかくですから、もう少し大乗仏教の特徴を見てみましょう。根本仏教といわれる初期の仏教(お釈迦様の教え)は、自己の知恵でもって、苦の原因を見極め実践をもって苦に打ち勝とうとする教えであって、とにかく自己の内面的な修行の完成が第一とされます。後に大乗仏教の側から批判されますが、ちょっと利己的と見られるこの初期仏教の目指す理想像は阿羅漢(あらかん)というものだったのです。これに対して大乗仏教が目指した理想像は、他人を救う誓いを立て、その誓いを実現することで原動力を得て仏になろうという菩薩というものに変わっていきました。浄土宗では、誓願が実現されて法蔵菩薩という人が、阿弥陀様という仏様になったということになっています。誓いが実現することが原動力になるというメカニズムが見て取れます。よく考えてみるとこれは何か不思議な仕組みです。何故そうした誓いを実現することがそのような力を持つことになるのかその根拠は明らかではありません。普通に考えても、約束を実現することが何か特別な力を生み出すと言うことにはならない。しかし、お経では、そのようになっているのです。これも専門的な話でした。元に戻りましょう。自己の修行ということになると、つまり阿羅漢を目指すと言うことになると、人それぞれ能力の違いが問題となりますが、他の人を救済するという誓いを立てる、つまり菩薩という理想像をめざすことは、誰にでも出来ることだったわけです。これは非常に大きな転換でした。難行から易行への転換です。
又、大乗仏教では八宗の祖と言われる龍樹(りゅうじゅ)という人がでて、「空」という思想を完成させました。初期仏教では、知恵の目で物事を分析してゆくと言うスタイルが中心で、お釈迦様の説いた有名な十二因縁という因果関係も深い知恵の目によって洞察されたものです。「これあるによりかれあり」という存在の基本にのっとって物事の関係を解明していったのです。物事が移り変わり変化してゆくこと(無常)を、知恵の目で見据え人間の苦の原因を発見してその滅し方を発見したのです。あくまでも、人間自身の知恵がその基本となっていました。それに対して、大乗仏教では、物事が関係性の中で変化を続け、常住不変のものが存在しないと言う有様を「空」という非常に直感的な思想で把握してしまったのです。経験的な分析と言うことから、感覚的な直感へと移行したと言うことです。それは、やはりより大衆的なものへと変化していったことを表しています。
さてこの辺で、まえにのべました法然上人の教判についてふれてみましょう。法然上人は仏教全体をどう理解したかというと、聖道門(しょうどうもん)と浄土門(じょうどもん)という風に仏教全体を二つに分けることにしたのです。何ともおおざっぱな感じがします。しかし、今まで仏教の歴史を見てきたとおり、仏教はお釈迦様一人の教えではありません。だから、こんな風にある一つの基準をもとに二つに分けるというのはまったく正しい方法と言うことになります。さらに、この聖道門と浄土門を難行と易行に対応させて、聖者の道、難行道、浄土の道、易行道と分けました。何ともわかりやすいではありませんか。そして、何の矛盾も生じません。もちろん、我々のような凡夫、つまりできの悪い者には易行の浄土門がすぐれているということです。私はこの理屈が結構気に入っているんです。
まあ、大乗仏教についてはそれこそ、このテーマだけで一冊の本ができてしまうくらいですから、これで良いという事はありません。しかし、この本のテーマは「浄土」です。大乗仏教の中にその浄土が位置していることは解りましたが、大乗仏教の成立の背景の中にはこれと言って浄土に関係したことはないようです。より具体的な検討が必要なのでしょう。ですから、これくらいにして先へ進みましょう。
さてこのように、大乗仏教は成立していったのです。もうご理解していらっしゃると思いますが、大乗仏教のお経は新しく創られたものなのです。誰かによって書かれたのです。具体的な名前は解りませんが仏教教団の中で作り出された物語なのです。お釈迦様が説いたものではありません。「大乗非仏説」といって、大乗仏教はお釈迦様の教えではないという主張が昔からされています。我が国でも江戸時代頃には、その研究がされるようになってきました。その後の研究によってもこれは間違いのない事実でした。最初にこのことを知ったとき、一瞬ガッカリしたものです。つまり、浄土経にしても法華経にしても密教のお経にしても、大乗仏教はすべて、お釈迦様の説いたものでないのだということだったわけです。我々の仲間にも、この大乗非仏説ということを非常に悲観的に考えている人が多くてなるべく触れないようにしている向きがないわけではありません。仏教の教祖が説いていないというのが、何か正当性を欠いているという思いがあるようです。しかし、私の場合、そう思った次の瞬間ホッとしたのです。浄土教に関してだけ、いや私だけかもしれませんが、何故かというと、お釈迦様は人間の死後のことを説かなかった。これは事実のようです。しかし、あるともないとも言っていないのです。だから、もしお釈迦様が浄土のことを説いたらば、今のお経よりもっとすばらしい浄土を説いたかもしれない。とちょっとのんきな考えが浮かんだのです。だから、大乗仏教が非仏説であったのは、私にとってはそれほどのこともなく受け止めることができたのです。なんて勝手な解釈を言うのかと思われるでしょう。もっともです。そして今、年を重ね五十となって、仮にお釈迦様が説いたとしても今と同じ浄土のお経ができあがったように思うようになりました。重ねて勝手で申し訳ありません。でも本当にそう思うのです。何と言ったら良いか、人間は最後の最後にここにやってくるように思う。浄土とはそんな風に実に不思議な存在です。とにかく、現在残る浄土教はお釈迦様以外の人達が作ったものだと言うことははっきりと認めなくてはなりません。しかし誰が作った話かなどというのは、まったく問題にならないと言うこともぜひみなさんに理解してもらいたいと思います。無理矢理にこうしたことを隠して話をする必要はありません。こうしたことを明白に示してゆかないと、いつまでたっても問題が解決しません。ありのままに事実を見つめるところから本当の解決が生まれると思うのです。
それでは、それらのお経は何のために創られたのでしょう。誰かが暇つぶしに考えたのでしょうか?まさかそんなことはありません。多くの人をこれはお釈迦様の教えだと言ってだましておもしろがっていたのでしょうか?そんなこともありません。お経が書かれるには何かその必要があったと考えるのが自然です。お経という文章がながい年月をかけてできあがっていったというのはそのお経が必要であったからです。前述したように、その基本的な背景として、仏教をすべての人に開かれた仏教にしようという時代の流れがありました。しかし、個々のお経には全体の流れから独立したそのお経自体の理由があるのです。
皆さんには、お経が次のようにはじまることはお話ししました。「如是我聞・・」「我かくのごとく聞けり・・・」という風にはじまるのです。アーナンダの言葉を借りて始まります。つまり、お釈迦様が以下のようにお説きになるのを、私は聞きました。といって始まるのです。しかし、もうお解りでしょうが大乗仏教をお釈迦様は説いていません。そうした文学形式を借りて新しい思想を広く人々に伝えるためにお経を創作していったのです。ですから制作者にどんな意図や意志があったのかと言うことが重要になります。ところがその当時の議論の詳細な内容は議事録などないので今解りません。だから、それは何らかの方法で推測するよりないのです。そのためにはまず、まっすぐにそのお経に取り組んでみると言うのが有効です。そのお経に何が書かれているのかをよく読んで理解し、そのお経が何に応えようとして作られたものかを理解していけばある程度解るはずです。そのお経のお話が答えとなるような質問を想定してみるとそこに、意図や意志が現れてくると言うことになります。そこに、そのお経が創られた理由があるはずです。いよいよ近づいてきたかも知れません。
その作業の題材としてまず「法華経」をとる上げてみようと思います。法華経は日本で一番読まれているお経かも知れません。ですからその内容を少し知っておくと言うことはさまざまな場面で有用なことです。いましばらくこのお経を例にとってこの問題を考えてゆきましょう。お経が何のために作られたかと言うことです。まず、あらすじをたどっていきましょう。そしてその後でこのお経が何に答えようとしているか考えてみましょう。そこに「法華経」の存在理由があるはずです。
まず法華経の最初の場面がどのように始まるかという事から始めましょう。お釈迦様があらゆる教えを説いた後、法華経という最後のそして最高の教えをこれから説きます。このお経はめったに説かれない最高のお経です。という出だしで話が始まります。もちろんこうした設定をすることで、このお経のすばらしさを伝えようとするものです。ですから実際にこんな事があったなんて勘違いしてはいけません。さて次にこのお経の前半の方は、数々の有名な示唆的なたとえ話を通して、いままでにお釈迦様の説いた教えは方便(よりすばらしい教えに導くために仮に説かれたとする。)で説かれたもので、すべての教えは今からこの法華経が説く一乗(一つの教え)にまとめられていくと説くのです。法華経以前に説かれた教え、つまり方便により示された教えは、教義的には三乗というのですが、ここでまた、ちょっと仏教教室です。悟りに至る道に三つの異なる道があります。その三乗とは、声聞(しょうもん・仏の教えを聞いて修行し悟りを開く)、縁覚(えんがく・自分で縁起の心理を悟る)、菩薩(ぼさつ・利他行を実践して悟りに至る)の三つの道です。声聞と縁覚は小乗(自己完成をめざす道)、菩薩は大乗(利他行を旨とする道)で全く違うもの、対立するものとされていたたのです。しかし、法華経ではそのような区別は理解の悪い我々のような人々のための方便として説かれたもので、そうした立場を超越して、最終的にはすべての人が法華経の説く唯一究極の真理へと到達すると説きます。これがまず「法華経」の一つの柱です。法華一乗(ほっけいちじょう)と呼びます。すべての道は法華経の説く一乗の道に集約されていくとするのです。
そしてこれからその法華経をお釈迦様が説きますという風に、話が展開していきます。とてもおもしろいのですが、いま読んでいるのは確か法華経であったはずなのに、その法華経の中で法華経をこれから説くこれから説くというふうに言うのです。じゃあどこからが法華経なのだろうかという事になるのですが、やはり今読んでいるところを含めた全体が法華経なのです。不思議な筋の話になっています。
さて、物語の展開としては、法華経以前の教えが方便であったという事から、法華経までの修行法にしたがって修行してきた人の立場がどうなってしまうのかという疑問が提出されます。今までの修行が無駄になってしまわないかと言うことです。舎利仏や目連、大迦葉と言うお釈迦様在世時代の人たちの名前が出てきます。これも名前を借りているわけです。そこで、お釈迦様はそうした人たちの成仏(修行の完成)を約束します。心配しなくても良いということです。そして、このお経の中心部分がやってきます。悟りをひらくということは、そんな簡単にできることではない。お釈迦様も前世からの長い長い時を経て仏となった。そのことは未来についても同じである。となると、今現在もいるに違いない。そうなると、常に永遠に仏様が存在していると言うことになるではないか。お釈迦様と言う究極の悟りをひらいた存在は久遠仏としてあらゆる時代にいつも存在してたし、これからも存在するのだと説きます。これが法華経の久遠仏と言うもう一つの柱です。ですから、人間の姿をしたお釈迦様がこの世で亡くなったのは、人々を導くための方便で亡くなったとするのです。最初に久遠仏であることが解ると人々は安心してしまって精進努力しなくなってしまうというのです。はじめから永遠にいると説くと人々はそのありがたさが分からなくなってしまうから、お釈迦様はまず死んで見せたということになるのです。何か、インドの人の理屈っぽさがこんな所にも現れているように思いますが、そういう理屈も成り立つわけで、なるほどということになります。そして、真の仏は五百千万億那由他阿僧祗劫というはるか昔に悟りを開いて永遠に我々に語りかけていると説きます。久遠に存在しているのですから、いつでもどこでも、すべての人がその教えに従って成仏できますと言う事になります。これが法華経の一番大事な主張です。いつでも、どこでも、すべての人がというのが法華経のすごいところです。このような宣言は自分の能力の限界を感じている人、自分には仏教は無理だとあきらめがちになってしまう人、仏教の外に自分はいると思っている人にとってはとてもありがたいことでした。いつでもどこでもだれでもというのですから、人々を励ますものでした。万人に開かれた仏教というのはこんな点に現れています。すべての人をこの法華経で救い取ろうという意志が働いています。すべての人だけでなく草も木も(一木一草)すべて、理想の状態に到達できると言う考えにつながっています。仏教学的には本覚思想という難しいことになりますが、この思想によると、人間が努力して修行をして悟りを目指すという道をとるのでなく、もともと人間は悟るための素質を自分の中に持っているのだということになります。ガラス玉がくもっているように現れないだけであるから、それを磨いてあがれば大丈夫というような考えです。この二つの考え方の対立は日本の思想を考える上で非常に重要なものです。始覚思想と本覚思想と言いますが、この視点がないと理解の難しいことが昔の日本にはたくさんあります。そして続いて、このお経を信じて読んだり人に伝えたりする事が我々のとるべき道であり、非常に功徳がある事が説かれ、また、このお経を広めていく事は非常な困難と迫害を受けるだろうということが預言されています。最後の預言は、日蓮さんがその迫害に耐えて強い信仰を持ち続けたきっかけとなった部分です。自らの受けた迫害をこの法華経の預言通りと考えたのです。簡単にあらすじを追うとこんな話になっています。このほかにも法華経には、いろいろな思想が盛り込まれていますが、今これだけのことからも解ってくることがあります。このお話を素直に読むと、この法華経がどんな意志を持って作られたものか、わかってきます。
大乗仏教は、お釈迦様の説いた原始仏教とか根本仏教と呼ばれる仏教とは違う主張をしましたので、さまざまな矛盾が仏教の中に生じました。先に述べたように、大乗仏教の打ち出した菩薩と、根本仏教の阿羅漢という理想像の違いは非常にわかりやすい矛盾です。それは、個人主義的というか利己的なものと利他的なものとの対照と言えるかも知れません。また、「空」という直感的な思考法もやはり対立の一つとしてあげられます。法華経の前にはこのような混乱があったものと思われます。大乗仏教の内部でこの矛盾をなんとか解決したいということが大きな課題となりました。この矛盾を超越した新しい思想を打ち出そうとする意志がはたらいているのがわかります。これが一乗思想というものです。このように法華経というのは、非常に教義的な意図の強いお経だということが解ります。その一乗思想の裏付けとして打ち出されているのが久遠仏の思想です。新しい器に新しい思想が注ぎ込まれてゆきます。
ここでまた、ちょっと仏教教室です。久遠仏の思想というのは、ちょっと段階がありまして、まずお釈迦様の悟った教えを法と呼びますが、この教えは本当にすばらしいものだから、この法を過去にも悟った仏があるはずだという考えがでまして、これを過去仏と言います。となると、未来にもでるだろうとなり、これが未来仏です。この辺までは常識的な考えなのですが、それならば現在も存在するはずだと言うことで、現在仏というのが登場するようになったのです。今現在多くの仏国土が世界中に存在していて、そこに仏様がそれぞれいらっしゃるとなってきたのです。過去現在未来となれば永遠に仏が存在する久遠仏の登場となってきます。この久遠仏の段階になりますと前の段階の仏様とは趣を異にしまして、非常に抽象的な仏様となりました。法そのものが仏の本体であるという非人格的な考え方になってきました。法身仏なんて言うんです。そうなるとそうした法はこの世の中に充ち満ちているはずだから、我々人間の中にそうした法身仏と同質のもの、仏様となる素質があるんだとなりこれが「仏性」と呼ばれるようになりました。となるとすべて人や物が仏性を持っていてそのままで救われている。悟りを開けると言う考えとなっていったのです。よく考えたというか。すばらしい筋だと思いますが、お坊さんとして取り組んでいるからそう思うのであって、今、みなさんの顔が思い浮かんで、血の気が引くのが解りました。こうしたお話どんな意味があるのと言われそうです。しかし、今は法華経の意図を探ろうと言うことですから、お付き合いください。とにかく久遠仏という考えによって仏教を総合的に再構築しようという意志が法華経には働いています。これが法華経のできた理由です。素直に読んでいくとこのような話です。素直に読むというのは、建物の外に出て建物を見るようにと言うことです。中にいて建物を見ていてもその本当の姿が見えません。ですから仏教の外に出てごく素直に読むとこうした理解となります。
このように法華経は、初期仏教から大乗仏教まで移行してくる間に生じた大きな矛盾を何とかしようとしたお経なのです。何とかしようというのは余りよい表現ではありませんが、法華経の制作者達は正直そう思っていたと思います。お釈迦様以来仏教が歩んできた道を何とか矛盾なく筋道の通ったものにすると言う課題がそこには横たわっていました。ですから新しく打ち出された理想像の菩薩という道と初期仏教で説かれた自己完成の道との矛盾に代表されるような様々な疑問混乱を超越してゆこうという形でこの法華経というお経が制作されたと考えるのが自然です。そのような必要もなくただこのような物語が出来たと考えるのはかえって不自然です。様々な思想を総合的にまとめて筋道をつけようとする意思がこのお経には働いています。法華経が昔から諸経の王と呼ばれてきた理由には、このような意思が働いていたからに他なりません。すべてを統一的に総合しようという意思が働いていたのですから当然といえば当然かもしれません。法華経についてこんな理解が可能です。私はこんな風に理解しています。
今、法華経について制作者の意図を探る作業をしました。同じ事を浄土教でしてみるとそこに大切な意味が現れてくるのではないかと言うことになってきました。ではいよいよ、浄土のお経は、どんなお話になっているかということになります。第二章で浄土の記述の一部を見ましたが、浄土のお話は法華経ほど難しくありません。全体のお話は次のようなものです。法蔵菩薩という人が非常に長い間修行をして、四十八の誓願を立て、その誓願が成就して、成就した事によって原動力を得て、極楽浄土という理想世界が建立され、悟りを開いて阿弥陀仏となり、今現在、その極楽世界にいて、その阿弥陀様の名を称えた人を、その命終わるときに、ご浄土に迎えてくれるというお話になっています。死んだ後は楽しみばかりの世界があなたを待っていますというとても素朴な物語です。その素朴なお話を素朴にごく自然に素直に読んで、このお話が答えとなるような問いを考えてみるとどうなるでしょう?この答えに対する質問を考えてみると、人は死ぬとどうなるのだろうか?どこへ行くのだろうか?と言う問いが浮かんできます。自分は、この世でろくによい行いを積んだとはいえないが、無事に来世良いところへゆけるだろうか。昔、インドでは輪廻の思想が強かったですから、このような問いが考えられるわけです。「浄土へ往く」が答えとなるような問いを考えれば、このような問いが考えられるわけです。そして、その背後には我々の願望や興味と言ったものがあるというのが解ります。おやおやと思った方もいらっしゃるでしょう。スタートラインへ戻ってしまったようです。お釈迦様に対してなされたマールンクヤやヴァッチャの問いがそのまま、ここにも登場しています。お釈迦様は無記という態度で答えなかったのですが、四五百年後に、そのお釈迦様が答えなかった問いに対してこうした素朴な物語が創り出されたわけです。阿弥陀様の名を称えた者は浄土に迎えとられるというのです。進歩してきたはずの仏教が後戻りしてしまったよううにさえ見えます。大切なのは、なぜこうした物語が作られたかと言うことですが、実に唐突な物語がいきなり書かれていると言わざるを得ません。その中間というか、これこれこういう訳でと言う部分がどうもない。これが浄土の教えの特徴です。このために大きな誤解を受けているのです。せっかくここまで来て肝心のことが書かれていない。人間は死ぬとどうなってどこへ行くのかという疑問は、人間であれば誰もが抱くもっとも根元的な疑問です。しかしそこからこれこれの理由でと言う部分がなく、こうした夢物語となっているのです。第一部で述べたように誰もあの世から戻って来て話をしてくれる人がいないのですからいつまでたっても、人間が存在する限り、人間の死後に関する興味は尽きないということは解ります。しかし、だからと言ってどういうつもりでと言う点がまったく表されない形では誤解を受けるのももっともです。
最初に人間の思想の中で、来世信仰が最後の最後まで残るという勝手な予想をしたのは、人間にとってもっとも根元的であるからです。このように何度も何度もテーマとして登場してきます。そして永遠に解決されない問題のように思われます。人間がこの世にいる限り登場してきます。
お釈迦様は、この問題には取り組んではいけないとしたのですが、それにしても、人間のそのような疑問に浄土のお経は何を訴えているのでしょうか。お釈迦様が取り組んではいけないと言った問題にあえて、大乗仏教の運動家たちは取り組み、あのような物語を創出したのです。いったい何を我々に訴えたかったのか、これが大問題です。これがこの本のテーマです。実際に後の時代の人々の中にはこのお経を読んでありがたいと本当に感じてその信仰の中に一生を閉じるという人たちがいました。今もいます。しかし逆に、この夢物語のような記述に幻滅して浄土の教えを低い教えであると見なす人の多いことも事実です。「こういう話を信じている人はごく単純な人だ」と決めつけている人々です。今この本を読んでいるみなさんもそうではありませんか。実際法然上人に至るまでは、浄土教を傍らに信仰するという傾向が強く、どちらかというと仏教の中でさえこのように見なされていたとも言えます。しかし、違うんです。浄土教の値打ちはちゃんとあるんです。法華経と浄土のお経とを通してそれがどのように成立したか、その理由を探ってみましたが、背景がご理解いただけたとおもいます。浄土教に関しては、さらなる疑問が登場したようで、「なんだ」と言わないでください。本論はまだまだ先です。これからです。
それにしても、人間のそのような疑問要望に応えるために創作られたと理解するとしても浄土のお経に表現されているご浄土は、よくもまあこんな勝手に夢のような世界を考え出したものだと言うことになります。皆さんからそんな指摘を受けそうですし、実際そうした指摘を受けているのです。どうして、これほど誇張した表現になったのだろうかと思います。こんなにまですごくなくても私なんぞはもう充分ですけれど、浄土は人間の想像を超えた存在です。讃仏思想によりスーパーなものになったと言うことだけでなく、超越的なものなのです。人間の欲望に安易に応える形で歯止めがきかなくなったものではありません。実際大乗仏教が人間の欲望に迎合するような形で成立していっているという指摘は、ある程度正しいものなのでしょう。小乗仏教の側から大乗仏教は仏説にあらずと批判される一つの重要な点です。万人に開かれた仏教を目ざしたところに生じた弊害といえるかもしれません。しかし、浄土の教えが人間の欲望への単なる迎合であったならば、もうとっくの昔に浄土教は消えてなくなっていたでしょう。大昔にこんなお経がありました。といって誰も顧みないものとなっていたでしょう。しかし、浄土信仰は今も生きています。なぜでしょう。人間の素朴な願いとして、死後浄土のような理想的な場所に行けたらとを考えるのは当然のことでしょう。しかし、それだけではないんです。もっと大切なことがあるのです。ご浄土の問題は、この物語の奥にあるものを理解しないとならないのです。やはり建物を出た理解が必要のようです。お経を離れた理解、仏教を飛び出した理解が今度は必要だと言うことが解ってきたよようです。仏教の中だけで、それを理解しようすると、浄土があると信じるか信じないかという、最初の一歩の問題に戻ってしまいます。それでいいんだという人もいますが、浄土の教えはそんなに平板なものではありません。もっともっと深い場所にあります。とにかく仏教の枠を飛び出してこの問題を考えてみる必要があります。そちらの方へ話を進めていきましょう。
バナースペース
スタジオ阿弥陀
〒110-0004
東京都台東区下谷1-8-20
TEL 03-3844-5949
FAX 03-3847-9301