〒110-0004 東京都台東区下谷1-8-20
浄土宗長松寺のページCONTACT US
きっと会いましょう

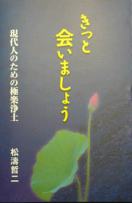
全文をテキストデータで載せました。ダウンロードして電子ブックで読んでください。
- 第二章
第二章 浄土のお経の問題点
第一章では臨死体験という問題について一つの体験談をもとに考えてみました。そのことを通して人間の経験の限界がよく理解できたと思います。人間が行って戻ってくると言うことには自ずと限界があるわけです。そのままあちらの世界に行ってしまえば、今度は後の人に伝えることができない。当たり前です。まあとにかく、人間の脳が非常に重要な役割を演じているということがわかったのは、一つの成果です。しかし、とてもではありませんが疑い深いみなさんを説得するというものではありません。かえって疑いが深まったなんて人もいるかもしれません。しかし、そう思う人でも向かい合って二人きりでお酒でも飲みながら真剣にこうした話をされたら、「へぇー」ときっと肯いてしまうのかもしれません。そんな風に実に不思議なものです。だから、その昔人々が、死後話と勘違いしたのも当然といわねばなりません。とは言うものの、そのような勘違いを考慮に入れたとしても、臨死体験の話は、浄土への旅路の入り口までも行きつくことはできません。そこでこの章ではちょっと違った方面から考えてみましょう。
「あの世」という時日本人の多くの人の共通のイメージは、やはり仏教のお経に書かれている「浄土」ではないでしょうか。そこでこの章では、あの世の代表として浄土、詳しくは西方極楽浄土というのですが、そのお経に書かれた「浄土」を検討してみましょう。それがこの本の主題を考える上で不可欠であると考えるからです。それではさっそく読んでいきましょう。
その西方極楽浄土ですが、「阿弥陀経」というお経に詳しく書かれています。皆さんは読んだことありませんよね。よっぽど熱心なお檀家さんでも、これを読むと言うことはまずない。今しばらくお経の記述に従ってそこに現れる浄土の姿を見てゆきましょう。解りにくいのでとりあえず、書き下し文を使って読んでゆきましょう。
「これより西方に十万億の仏土を過ぎて世界あり、名付けて極楽という。」
西の方角、十万億仏土を過ぎたというのはどのような距離でしょうか、仏様の国を十万億個過ぎたところです。一つの仏国土がどれくらいの大きさか広さか解りませんが、とにかく遠くの方にあるということになります。仏教では東西南北上下に様々な仏国土、仏さんの国があることになっています。その中の西の方角、つまりお日様の沈む方角に極楽浄土があります。
「その土にほとけましまし、阿弥陀と号したてまつる。いま現にましまして説法したまえり。」
その極楽浄土に阿弥陀様がいます。それも今いらっしゃいます。時代が変わっても常に今いらっしゃいます。そして、説法をしています。そんなバカなと言わないでください。このあたりからすでに皆さんの首をひねった姿が思い浮かびます。
「舎利弗、かの土を何が故に名付けて極楽となす。その国の衆生にもろもろの苦あることなく、ただもろもろの楽のみを受く。故に極楽と名づく。」
苦のないと言うことが極楽浄土の一番の特徴です。だから極楽というのです。楽なことだけがあるのです。
この後の記述については、多少解りにくいので書き下し文も止めて、和訳で示しましょう。
「また舎利弗よ、極楽世界には七重の欄干が廻らされ、七重の宝石網で覆われ、七重の宝樹の並木が立ちならんでいる。これらはみな金、銀、瑠璃(るり)玻璃(はり)の四宝でできている。到る所にこれらのものがめぐりめぐらされていて実に美しい。こうしたわけでこのほとけの世界を極楽というのである。」
「また舎利弗よ、極楽世界には七宝の池があるが、中には八つの功徳をもつ水がみちみちていて、池の底には金の砂が敷きつめられている。池の四方に階段があって、金、銀、瑠璃(るり)、玻璃(はり)の四宝によってできている。池の岸に楼閣があるが、金、銀、瑠璃(るり)、玻璃(はり)、槍直(しゃこ)、赤珠(しゃくしゅ)、瑪瑙(めのう)の七宝によってできていて、この七宝によって美しく飾られている。池の中には蓮華が咲き、蓮華の大きさは車輪のように大きく、青蓮華からは青色の光りが放たれ、黄蓮華からは黄色の光りが放たれ、赤蓮華からは赤色の光りが放たれ、白蓮華からは白色の光りが放たれ、同時にそれぞれの蓮華から微妙な芳しい香りがただよっている。舎利弗よ、極楽世界にはこのように功徳の多い荘厳が成就されている。」
全文を読もうというのではないのですが、どのような内容なのか一般の人はほとんど知らないと思います。ですから、その雰囲気だけでも理解していただければと思い引用しています。ちょっと長い引用ですが、少しがんばって読んでいただけるとありがたいです。
「また舎利弗よ、極楽世界にはいつも天楽が奏でられている。極楽の大地は黄金によってつくられ、その大地の上には昼夜六回にわたって芳香を放つ美しい天の妙華が降り散ってくる。極楽世界の人々は毎朝早く花篭にこの妙華を盛って、他の世界にいる数限りなく多い仏たちを巡り、仏に花を捧げて供養する。このように諸仏を供養してから人々は極楽に戻ってきて朝食をとる。食事を終って宝樹の間を逍遥する。舎利弗よ、極楽世界にはこのように功徳の多い荘厳が成就されている。」
大地が黄金というのはちょっと、痛そうですが、砂金のようなもので出来ているのかな、なんて想像しますけど、とにかくまぶしいのじゃないかと思います。その他にも数々の荘厳がまだまだ続きます。続けて読んでいただけるか心配ですが、もう少しがんばって進んでください。
「また次に舎利弗よ、極楽世界には羽色の違った美しい鳥がいる。これらの鳥は白鵠(びゃっこく)、孔雀(くじゃく)、鸚鵡(おうむ)、舎利(しゃり)、迦陵頻伽(かりょうびんが)、共命(ぐみょう)という鳥であって、昼夜六回にわたって柔和な優雅な声で鳴く。鳥の声は人々の耳には法を説く声として聞かれる。たとえば悟りを得るための信、精進、念、定、慧という五根について説き、五根の働きによって得られた破悪の力である五力を説き、修行をするのに真偽と善悪を区別して正しく修行できる方法としての七菩提分について説き、道理を正しくみる八つの方法である八正道を説いている。人々は鳥が法を説く声を聞くと、誰もが仏の威徳を念じ、法の勝れていることを念じ、和合教団の功徳を念ずるようになる。」
少し話が仏教の教義の方へ進んでいっているのがおわかりになると思います。ちょっと理解が難しくなってきました。このように内容が変化しているのも、一つのヒントとなるのですが、今ここでは触れないで続けます。もう少しがんばってください。
「舎利弗よ、極楽世界にいる美しく勝れた鳥は罪の報いによって鳥の世界に生れてきたものであると考えてはならない。そのわけは極楽世界に地獄、餓鬼、畜生の世界がないからである。舎利弗よ、極楽は地獄、餓鬼、畜生という悪世界の名すら聞かれない世界であるから、烏が住む世界はないのである。まして実際に鳥類がいるわけがない。このような鳥は鳥の形こそしているが、実は阿弥陀仏が正法を宜べさせるために変化して現わし給うた霊鳥なのである。」
この部分はどうも言い訳をしているように私には思えるのですけれど、皆さんどう思いますか。後ほどこのことには、ちょっと触れてみたいと思います。いずれにしても、法を説く霊鳥がいて、その声を聞くうちに自然と人々は仏教のすばらしさを理解してゆき、仏教を志す仲間と集うすばらしさを理解するようになると言うのです。引用はあと少しですから、がんばってください。
「舎利弗よ、極楽世界に微風が吹きわたり、風が宝樹と宝網をゆり動かし、微妙な音を出している。たとえば百千種類もの音楽を同時に一緒に演奏してだす音のように美しく、妙なる音調をもっている。人々がこの風の音を聞くと、誰でも自然に仏を念じ、法を念じ、和合憎を念ずる心をおこす。舎利弗よ、極楽世界にはこのように功徳の多い荘厳が成就されている。」
音を奏でる微風の記述が続きました。お経はまだまだ続くのですが、このあたりまでくると、なるほどこのようなお経かと内容が少し解ってもらえたと思います。さて、法を説く霊鳥の話がありましたが、そこの部分でちょっとおもしろいなと思ったことがあります。ちょっと脇道にそれますがお許しください。まず鳥が登場します。ところが極楽に動物(畜生)がいてはいけないというのでしょうか、まるで言い訳をしているような部分がありました。悪い行いが積み重なったために鳥となってしまう。インドの輪廻思想に従えばありえることですが、鳥がいては具合が悪いじゃないか、という指摘でもあったのでしょうか。あるいは、そのような質問を想定してそれにに対して、前もって理屈をこねるような文章になっているのです。このお経が制作された当時の何かそのような現実の議論を想像させるような文章になっています。私などは鳥が出てきてもいっこうにかまわないし、気にもしません、こんな説明があるものだから、そうか鳥がいちゃいけないのかなんて思ったりしているわけです。まあ我々のそんな疑問を前もって解っていて、説いておいてくれたと考えれば、なんて親切なんだろうと言うことになる訳です。この箇所などは気にかけなければ、ごく普通に説明がちょっと合間にはさまれただけだと読めないこともないわけです。何故こんなことを言い出したかというと、後の章で明らかになりますが、お経がどのように成立していったかと言うことと関係があります。今ここでは詳しくは述べませんが、ちょっと触れてみると、お経が相談しながら創られていったということになると、こうした部分は、ちょうどその返の事情をよく表していたりするわけです。お経というのも一つの文章として残っているものですから見方によってずいぶん印象が変わってきます。意外とこんな些細なところから、見方が変わったりと言うことがあるんです。こんな議論が現実に、本当にあったのかななんて考えてみると急に今までとは違った文章に見えてきたりします。ちょっと横道にそれましたが、話を元に戻すと、この後もまだまだ極楽の荘厳な姿の記述が続きます。
極楽浄土はこのように人間にとって理想的で夢のようなところです。誰でもこんなところなら行ってみたいと思う、そんな場所です。ただ一つ死なずに済めばということではあります。
さて、阿弥陀経の最初の部分を引用してみました。どうですか?みなさん、何を感じましたか。このように次から次へ楽なこと、極楽ですから楽なことのオンパレードとなります。もう十分と思わず言ってしまいます。ここまでそろってなくても、例えばこの十分の一ぐらいでも私だったら大変結構という気がします。さて、事はそんなのんきな話ではありません。この文章に向かい合っているみなさんの中には、ことによるとほんのさわりだけでしたが今はじめて阿弥陀経の中身に触れた人もたくさんいると思います。その皆さんの顔を思い浮かべると、これはもう「あかん」と言う感じです。ここまで読み進んでくれた人は相当に我慢強いと言えるかもしれません(笑)。とてもではないですが、この続きを最後まで読んでくださいとはなかなか言えません。しかしこの本を読み終える頃には読んでみようかななんて思ってくれればいいなと思います。とにかく、これをこのまま、みなさんに読んで聞かせてこの文章への理解を求めるのは難しいことでしょう。我々浄土宗のお坊さんの苦労はこの点にあります。
第一章の臨死体験の話からみるとずいぶんかけ離れたものだなと言う感じがすると思います。臨死体験と浄土のお経をならべて比較してみても、結びつくような点はほとんどありません。もちろんいい加減な話は除いてと言うことです。つまりこうした浄土の内容が先にも指摘しましたが臨死体験の話を元にした記述ではないと言うことです。臨死体験のお話はその人の経験や知識がベースとなっています。だからせいぜい死という一点を超えて少し進んだところのお話です。お花畑やまばゆい光を見たというような話はあります。しかし、浄土のお経に書かれているような、豪華で詳細にわたる話はありません。つまり、浄土の内容は、人間の経験や知識などとは無縁のものなのです。せめて、浄土のお経も臨死体験の話などが元になっていて、似たような話がいっぱいあるとか言うことになれば、これはずいぶん心強いのですが、実際にはそうではありません。人間の経験が裏付ける所はありません。いきなり、こういった内容ですから初めてごらんになったみなさんは、一体これは何なのかと思うのは当然です。似たような古くからある伝承物語などを思い浮かべてくれる人は非常に好意的な人々で、ほとんどの人は、空想・夢物語ということがすぐに頭に浮かびます。そして、いったい何のためにこうした物語が存在しているのかと言うことを考えてみると、さっぱりその意味を見いだせないということになります。
さてそのみなさんのしそうな、ちょっと科学的な指摘をしてみると、極楽は西の方向にあるというのですが、西へ西へと進んでいけば地球はまるいのですから、一周して元の場所にもどるじゃないかということになります。方向を変えて空の方、つまり宇宙の方に方向をとれば、無数の星がありますがその果ては未だに解明されない暗闇があります。宇宙の研究はその全体から見ればごく一部が解明されたとしか言えませんが、かといってその暗闇に浄土の存在を求めるには無理があるでしょう。こういった現代科学の世界でこの問題を眺めると、極楽浄土の存在はきわめて危ういということになります。しかし、ここからが大切です。こういったことをすべてふまえた上で浄土を考えてみたいというのがこの本の趣旨です。こういった指摘を前に自らの仲間内の世界へ後戻りして、信じるか信じないかと言う単純な問題にすべての問題解決の鍵を預けてしまうという態度を我々は取りつづけてきたと言えます。というより、ほとんど我々僧侶は本能的にそうした態度を取ってしまいます。しかし、私は、浄土の教えはそんな浅いものだと思っていないのです。ここから前進してこそ本当の浄土が姿を現すと固く信じているのです。そこで一つ、みなさんに考えてもらいたいことがあります。科学の進歩していなかった時代の人たち、昔の人たちはこのお話を単純に信じていたのでしょうか。それほど単純だったのでしょうか。科学的に無知で単純だったから、昔の人の中に浄土の教えが成立していたと言う指摘が実際になされます。私は簡単にそう言って片付けられないものを感じています。昔の人も今の我々とそう違わないのじゃないかと思っているのです。同じ人間じゃないかと思うのです。同じ人間だと。だから、そこにはこうした浄土の話を支えているものがきっと何かある。必ずあると思うのです。浄土教の心とも言うべきものがきっと何かあると思うのです。そうしたものが全くないまま、いきなりあの物語であるならばとっくの昔に浄土の教えは消えてなくなっていたと思います。自然科学の進歩とともに消え去っていたでしょう。しかし、浄土はしぶとくと言うか、信仰としてしっかり残っています。そこにはなにかがあるのです。それを捕まえることが大切です。そうすればみなさんになるほどと言ってもらえるわけです。
さてご浄土(あの世)を考えるのにはいくつかの鍵があると最初に言いました。第一の鍵はまだ誰も観たことがないということでした。それなのにどうしてお経の中にその姿が書かれているのだろうか。ということになります。普通見たことのないものの話をすると、「見てきたような・・を言い」ということになって、これは困ったな(笑)ということなのですが、これが理解の難しいところです。しかし、この誰も見たことのない浄土の記述がどうして存在しているのかと言う疑問を理解しないことには、浄土にたどり着くことはできません。これからしばらく、この問題に取り組まねばなりません。仏教の専門的な話なども含めて、少し仏教の勉強をしないとなりません。なるべく解りやすく進めてゆきますのでがんばってついてきてください。まああわてずに何ごとも一歩一歩進んでいきましょう。さて、そろそろお釈迦様に登場してもらいましょう。仏教というのは、お釈迦様の教えです。ということになっています。だから、お釈迦さまのことを勉強してゆくのはとても大事なことです。お釈迦様はどんなことを言っていたのでしょう。これを学んで行くことがとても重要なヒントを提供してくれます。浄土を考える上で不可欠のものということになります。
さて、そのお釈迦様ですが、どこから取り組んだらいいか、とても難しい。お釈迦様ほどその真の姿が分からなくなってしまった人もいません。仏教教団の中で神格化されたためその人間的な面が覆い隠されてしまったのです。まあいろいろ考えたのですが、この本のテーマに一番関係していると思われる次のお経からスタートしましょう。そのお釈迦様、この問題に関係して、こんなことを言っているのです。「毒箭(どくや)の譬喩(たとえ)」というお話です。それを読んでみましょう。
南伝 中部経典 六、三 摩羅迦小経
漢訳 中阿含経 二二一 筋喩経
「かようにわたしは聞いた。ある時、世尊は、サーヴァッティー(舎衛城)の祇園精舎にあられた。その時、ひとり離れて冥想静坐していたマールンクヤ(摩羅迦)比丘は、心の中でかように思った。「世尊は、このような問題については説かず、捨ておきて、問えば答えることを拒む。すなわち、世界は常住であるか、無常であるか。世界は辺際があるか、辺際がないか。霊魂と身体とは同じであるか、別であるか。人は死後も存するか、存せぬか。このような問題について、世尊は、なにごとも説いて下さらぬ。わたしはそれが不満であって、堪えられない。そうだ、わたしはいま世尊のもとに行き、その解釈を問おう。もし世尊がいぜんとして説かれないならば、わたしは修学の業をすてて、世俗に還ろう。」
そうです。この問題です。これが肝心の問題です。これに答えてもらわなくては仕方がないと、マールンクヤという人が、お釈迦様に今日こそは、答えてもらおうと決心します。答えのない時はもう仏教の修行をやめてしまおうという決意をしました。
そこで彼は沈黙冥想の坐をたってお釈迦様のもとにゆき、世尊を拝して言いました。
「世尊よ、わたしはひとり遠きに離れ坐しているとき、心の中でかように思った。世尊は、世界の常・無常、世界の有辺・無辺等の問題については、何ごとも説かれず、問えば答えを拒まれる。わたしはそれが不満であって、 堪えられない。いまわたしは、重ねて問い申す。それでも答えられぬならば、わたしは修学をすてて、世俗に還るのほかはない。世尊よ、もし世界は常住なりと知らば、かく説かれよ。もし世界は無常なりと知らば、かく説かれよ。もしまた、世界は常住とも無常とも知らぬならば、予は知らぬと説かれるのが正当である。」
さあさあ応えてください。と迫りました。三者択一の答えしかないのだから、何とか言うのが当たり前ですと迫りました。お釈迦様が応えます。
世尊は言った。
「マールンクヤよ、わたしはかつて、なんじに、かような問題について説いてやるから、わたしのもとに来って清浄行を修するがよいと言ったことがあろうか。」
彼は答えて言った。
「世尊は、そのようには申されなかった。」
そこでお釈迦様は、彼のために、このように説かれた。
「では、マールンクヤよ、なんじは誰であって、誰に対して不満を述べようとするのであるか。マールンクヤよ、ここに人あって、かような問題について、わたしが語るまでは、わたしのもとで清浄の行を修しないと言ったとするがよい。そのとき、もしわたしがそれについて語らなかったならば、彼はついに清浄の行を修する機会なくして命終わるであろう。」
人間の一生は短いのです。興味に従って行動していたのでは、肝心なことを実行する機会を失ってしまうと言っています。
「マールンクヤよ、さらに、人あって、毒箭をもって射られたとするがよい。彼の親友たちは、彼のために医者を迎えるであろう。だが彼は、わたしを射た人はどのような人であるか。わたしを射た弓はいかなる弓であるか。わたしを傷つけた箭は、そのやがらはいかに、その羽はいかに、その尖端はどのような形をしているか。それらのことが知られぬうちは、この箭を抜いてはならぬ、と言ったとするがよい。マールンクヤよ、もしそうすると、彼はそれらのことを知ることを得ずして、命終わるであろう。」
ものごとには順序があります。自らの興味に従っていては、肝心なことが完成されません。それでは何もなりません。まず、矢を抜いて毒を吸いだし傷の手当てをしなくてはなりません。
「マールンクヤよ、世界は常住であるとか、または無常であるとかの見解があっても、清浄の行が成る道理はない。むしろ、それらの見解があるところには、いぜんとして、生老病死、愁悲苦悩がとどまり存するであろう。わたしは、この現在の生存において、それらを征服することを教えるのである。」
あなたが今質問していることは、的はずれです。今現在の苦を克服するために役立たない議論ですと言っています。
「その故に、マールンクヤよ、わたしの説かないことは、説かれぬままに受持せねばならぬ。わたしの説いたことは、説かれたままに受持せねばならぬ。」
だから私の言ったとおりにしなさいと言う理屈です。
「マールンクヤよ、世界の常・無常、有辺・無辺などのことは、わたしはこれを説かない。なにゆえに説かないのであるか。実にそれは、道理の把握に役立たず、正道の実践に役立たず、厭離、離欲、滅尽、寂静、智通、正覚、涅槃に役立たぬからである。その故に、 わたしは説かないのである。」
苦を克服して人間が幸福になるために役立たないことは、私は説かないと言います。そして、私は苦の克服に必要なことはすべて伝えているとします。
「 マールンクヤよ、それでは、わたしの説いたものとは何であるか。『これは苦である』とわたしは説いた。『これは苦の集起である』とわたしは説いた。『これは苦の滅である』とわたしは説いた。 また『これは苦の滅にいたる道である』とわたしは説いた。」
これが有名な四諦と言う教えです。苦集滅道と言いますが、人間の存在は苦である(苦)、その苦は何によって起こるか(集)、そして、その苦はどうすればなくなるか(滅)、そのためにはどうしたらよいか(道)、このようにお釈迦様は説いたのです。これで十分です。よけいなことは考えてはいけません。
「ではなにゆえにわたしは、それらのことを説いたのであろうか。実にそれは、道理の把握をもたらし、正道の実践に基礎をあたえ、厭離、離欲、滅尽・寂静、智通、正覚、涅槃に役立つからである。マールンクヤよ、その故に、わたしの説かないことは、説かれぬままに受持するがよい。わたしの説いたことは、説かれたままに受持するがよい。」
世尊はかく説かれた。マールンクヤは歓喜して、世尊の教えを信受した。」
だから、私の説かなかったことは説かれないまま、説いたことは説いたままに実践しなさいと言ってます。こんな、お話(お経)です。なんだ応えてないじゃないか。と言われそうです。一番聞きたいところについて答えてないのです。しかし、お釈迦様はとても大切なことを言っています。何故、お釈迦様は、そのような問題には答えないと言うのでしょうか。その理由を理解することがとても重要です。浄土を理解する上で重要です。「世界は有限か無限か」「人は死後も存するか、存せぬか」と言った問いは、お釈迦様の在世当時流行していた問いのようです。と言うより、現代においても関心がなくなったと言うことはありません。人間の一番の関心事といえます。しかし、お釈迦様はそれは的外れな人間の興味にすぎないと説きます。的はずれと言われようが我々の関心はその点にあります。それに答えてもらわないとどうも落ち着かない気がします。しかし、それはただ我々の興味を満たすだけのことで、人間の苦の克服という一番大切なテーマから見ると、それは的がはずれているというのです。もっともっと大切なことがあり、まず、苦を克服するための清浄の行を実践することが大切なのです。
「この現在の生存において、それら(愁悲苦悩)を征服することを教えるのである。」 という言葉がこのことをよく表現しています。そして、これがお釈迦様の一番基本的な姿勢と言うことになります。
人間の頭の中の興味を満足させてやることよりも、現実の苦の克服を目指すのです。ちょっと考えてみてください。人間は勘違いをしているのです。死後人間が存するとしても、やはり今この世の苦しみが消えてなくなることはありません。あの世や極楽があったとしても、それはあくまで死後のことで、現在の生存における苦、生老病死に代表される四苦八苦はそのことによって克服されることはないのです。我々は何かそのことが解るとすべて解決するような錯覚をしています。人間の一生は短いので、的はずれなことをしていてはいたずらに時間を浪費することになります。そんな時間の余裕は我々にはないのです。まずその苦を克服することを念頭に置かなければならないのです。そのために、道理の把握に役立つことだけを考え、役立たないことは捨て置く。その道をお釈迦様は示しました。その実践を積んでゆくことが大切であるというのです。人は死後も存在するかという人間の頭の中だけの問いは、ちょうどこの毒箭の譬えでは、どんな毒使って、どんな弓でもって、どんな矢を使い、その羽はどんなものであるか。それは毒矢で射られた者にとっては興味の尽きない問題であるかもしれません。しかし、まず毒矢を抜いて、毒を吸い出すことから始めなくては人間は助からないのです。マールンクヤのした質問について、お釈迦様は永久にその興味が満たされないこと、その問題が永久に解決しないことを見抜いていたのです。そして我々に近づくなと言っているのです。我々は人間が死後も存在すると言ってくれれば人間の苦が解決に向かうような勘違いをしているのです。百歩譲って我々が決して見ることができないと言うより経験できないといった方が良いかもしれませんが、死後の生があり、死後の世界があったとしても、我々の回りで実際に起こる多くの死、我々が見ることのできる、経験しなければならない「死」という苦はなくなりません。ちょっと難しくなりますが、「人は死後も存在するか」「世界は有限か無限か」といった問いは、経験に基づかない形而上学的議論というふうにいわれます。それは、人間の尽きぬ興味の対象ではあります。しかし、お釈迦様は、その問題は、永久に解決されない問題、つまり永久にみずかけ論になってしまう問題であると宣言したのです。経験できないのですから、結局水掛け論になります。それは臨死体験の話の時に指摘したとおりと言うことです。従って、私の説かなかったことは説かれなかったまま、説いたことは説いたまま実践を積み重ねなさいと言うのです。その実際的方法としてお釈迦様はあの有名な八正道という実践の道を示したのです。人間の苦を滅する実際的な道を示したのです。ここに仏教の一番基本的な姿勢が打ち出されています。
皆さんも八正道はご存じですね。いや意外と知らないかもしれません。お釈迦様のように悟りを開くために取るべき八つの実践の道です。正しく観察し正しい見解を持つ正見。正しく考える正思。正見や正思に基づき正しい言葉を使う正語。正しく行動する正業。正しい生活方法をとる正命。正しく努力する正精進。正しく教えを思念する正念。正しく瞑想しこころを一つに集中する正定。この八つの道です。これを実践して苦を克服しようと我々に、お釈迦様は語りかけているのです。想像するに八正道をまじめに実践して行くととても立派な人間になるのは間違いないでしょう。しかし、立派な人間になること、人間が完成されていくことと人間の苦が克服されるという関係がよく解らない。そのメカニズムがよく理解できない。とっても素晴らしい人格が完成して行くとそうした苦が解決されるのかなあなんて、何となく想像するのが精一杯というところです。もっともこの点については輪廻という思想が大きく関係しているようです。人間は行いによって輪廻を続けていると言う思想です。とりあえずこの本のテーマとはちょっと距離がありますので先に進みましょう。とにかく私自身が八正道を実践できてない証拠だなんて言われると身も蓋もないので、先を急ぎます。
こんなお経を前にすると、さて困りました。みなさんに「それ見たことか」と言われそうです。お釈迦様はあの世について何も応えてないじゃないかと言われそうですし、かえってそういったことに取り組むなといっているじゃないかと言われそうです。そしてその弊害さえも指摘しています。さて、この他に、この問題について、お釈迦様は何か言っていなかったのでしょうか。もう一つ有名なお話(お経)を読んでみましょう。
南伝中部経典 七二 婆蹉衡嘩多人喩経
漢訳 雑阿含径 三四、二四 見
火は消えたり
かようにわたしは聞いた。
ある時、世尊(お釈迦様)は、サーヴァッティー(舎衛城)の祇園精舎にあられた。その時、ヴァッチャ(婆磋)という外道の行者が、世尊を訪ねてきた。二人は友誼にみち礼譲ある挨拶を交わしてから、さて彼は世尊に問うて言った。
「世尊よ、あなたは、世界は常住であると思われるか。これのみが真であって、他は虚妄であると思われるか。」
「ヴァッチャよ、わたしは、そうは思わない。」
「では、世尊は、世界は常住でないという意見であるか。」
「そうではない。」
「しからば世尊よ、あなたは、世界には辺際があると思われるか。」
「わたしは、そうは思わない。」 「では、世尊は、世界は辺際がないという意見であろうか。」
「そうでもない。」
さらにヴァツチャは、霊魂と身体は同一であるか別であるか、人は死後にもなお存するか存しないか等のことについて、お釈迦様がいずれの意見であるかを聞いた。だが、お釈迦様は、そのいずれの意見をもとらない旨を答えた。
(マールンクヤと同じ質問をした人がいたのです。)
かくて、ヴァッチヤは、さらに問うて言った。
「いったい、世尊は、いかなるわざわいを見るが故に、かように一切の見解をしりぞけられるのであるか。」
すると世尊は、かように教えて言った。
「ヴァッチャよ、世界は常住であるというのは、それは独断に陥っているものであり、見惑(思想的観念的な迷い)の叢林に迷いこみ、見取(低劣な誤った見解などに執着して、それをすぐれた真実の見解であると考えること)の結縛にとらわれているのである。それは、苦をともない、悩みをともない、破滅をともない、厭離、離欲、滅尽、寂静・智通、正覚、涅槃に役立たない。世界は常住でないといっても、あるいは、世界は辺際があるといっても、辺際がないといっても、あるいは、霊魂と身体とは同じであるといっても、別であるといっても、あるいはまた、人は死後にもなお存すといっても、存せぬといっても、また同じことである。」
マールンクヤの時と同じですね。役立たない議論ですと言っています。むしろ人間に災いをもたらすと言っています。「ある」とか「ない」とか言ってもそれは、果てしのないみずかけ論になってしまうことをお釈迦様は知っていたのです。そして、議論をやめなさいとヴァッチャにいっているのです。
ヴァッチャは、そこでまた問うて言った。
「しからば、世尊よ、あなたは見惑に陥るということが、まったくないであろうか。」
世尊は、それに答えて、こう言った。
「ヴァッチャよ、わたし自身においては、見惑、見取に陥るということはない。わたしは、実に、このように考えるのである。・・・・ かようにして色があり、かようにして色の因があり、かようにして色の滅がある。また、かようにして受があり、かようにして受の因があり、かようにして受の滅がある。そして、想についても、行についても、識についてもまた同じである。かように考えるが故に、わたしは一切の幻想をすて、一切の迷妄を断ち、一切の我見を離れて、執著することもなく、解脱したというのである。」
経験的な事実にもとずいて、物事をありのままに見ようというのがお釈迦様の教えです。そしてここでも四諦の教えが説かれます。苦集滅道の道理に従って迷いを断ちましょうと説いています。
ヴァッチャは、さらにまた問うて言った。
「世尊よ、では、かくのごとくにして心解脱せる者は、いずこに赴きて生ずるのであろうか。」
「ヴァッチャよ、赴き生ずるというのは、適当ではない。」
「では、どこにも赴き生ぜぬというのであろうか。」
「ヴァッチャよ、赴き生ぜぬというのも、適当ではない。」
「世尊よ、それでは、わたしはまったく解らなくなってしまった。以前に世尊と対座問答することによって、わたしの得た深い確信すらも、すっかり消え失せてしまった。」
ヴァッチャでなくとも、赴き生ずるでもなく、赴き生ぜないでもないというのは、我々には理解が難しいことです。お釈迦様は何を言っているのでしょう。
すると世尊は、彼のために、このように説明せられた。
「ヴァッチャよ、なんじがまったく解らなくなったというのは、当然であろう。ヴァッチャよ、この教法は、はなはだ深く、知りがたく、すぐれて微妙であって、智慧ある者のみが知りうるところのものである。他の見解にしたがっている者や、他の行を修している者には、とうてい知られ難いものであろう。だが、ヴァッチャよ、わたしはさらに、なんじのために説こう。いまわたしが、なんじに問うから、思いのままに答えるがよい。ヴァッチャよ、もしなんじの前に、火が燃えているとしたならば、なんじは、火が燃えていると知ることができるか。」
「むろんである。」
「では、ヴァッチャよ、この火は何によって燃えるのであるかと問われたならば、なんじは何と答えるか。」
「それは、この火は、薪があるから燃えるのだと、わたしは答える」
「では、もしなんじの前で、その火が消えたならば、なんじは、火は消えた、と知ることができるか。」
「むろんである。」
「では、ヴァッチャよ、かの火はどこに行ってしまったのかと問われたならば、なんじはいかに答えるか。」
「世尊よ、それは問いが適当ではない。かの火は、薪があったから燃えたのであり、薪が尽きたから消えたのである。」
そこで、世尊は、うなずいて、さて説いて言った。
「ヴァッチャよ、まったくその通りである。そしてそれと同じように、かの色をもって人を示す者には、色が捨てられ、その根は断たれる時、その人はすでになく、また生ぜさるものとなるであろう。その時、ヴァッチャよ、人は色より解脱したのである。それは甚深無量にして底なき大海のごとくであって、赴きて生ずるというも、赴きて生ぜずというも、 当たらないであろう。そして、ヴァッチャよ、受についても、想についても、行についても 識についてもまた同じである。」
かように世尊が説かれるのを聞いて、ヴァッチャは豁然(かつぜん)としてさとることができた。そして、世尊に白して言った。
「世尊よ、まことに、大なる沙羅の樹が、葉おち、枝おち、樹皮も脱落し、膚材も脱落して、ただ心材のみが残って立っているかのように、世尊の説かれるところは、一切を脱落して、ただ心材においてのみ確立している。偉大なるかな世尊、あたかも倒れたるを起こすがごとく、覆われたるを現すがごとく、迷える者に道を教えるがごとく、あるいはまた、闇の中に燈火をもたらして、眼ある者は見よというがごとく、世尊はさまざまな方便をもって、わたしに法を示したもうた。わたしはここに、世尊に帰依したてまつり、世尊の教法に帰依したてまつり、世尊の比丘僧伽に帰依したてまつる。願わくは、世尊よ、今日よりはじめて、わたしの命終わるまで、わたしを在家の信者として容れたまわんことを。」
終わりの部分は他のお経の最後にも現れる決まり文句で、みんなで合唱する時の決まりみたいなもので、他の場所でもたびたび出てきます。後に述べることと関係するので参考に引用しました。ちょっと長くなりましたが、これが大変有名なお経でして、お釈迦様を語る場合避けて通ることはできません。どうですか、みなさんは豁然と悟られましたか。とても難しいですね。お釈迦様は何をいっているのでしょう。どうも我々人間と薪が燃えるときの炎とが同じであると言っています。我々人間もただ存在するものであるといっているのです。ただそこにあるものだと言っているのです。燃える炎のようにただそこにあるものだと言っています。ただこれだけのことならば、なるほど言われてみればそうだなと思います。炎と同じであることが何故豁然と悟ると言うことになるのか、これだけではよくわかりませんね。我々人間は時間の中に存在し、時間の経過を意識しながら生活しています。時間的経過の中で異なった状態に移行していく経験を一瞬一瞬積んでいます。異なった状態に移行するというのはあるところからあるところに移ると言うことです。同じ場所にいたとしても時間が経過すればそれは違った場所でやはりそこへ行くという気がする。我々の感覚ではどこかへ行くんです。それが普通の人間の感覚です。ところがお釈迦様の認識した事実は人間はただ存在するものだと言うことです。縁があってただ存在するのです。燃える炎が強くなったり弱くなったりします。ちょうど我々が違った状態に移行すると言うことに当たります。炎の場合、それが消えても我々はそれがどこに行ったのかとは思いません。人間だけが違っていると勘違いしているのです。炎というのはマキがあるから生じる現象です。マキが燃え尽きれば存在しないものなのです。我々を人間たらしめているものが尽きれば、我々は存在しないのです。もっと端的にマキを肉体に置き換えてみればよく理解できます。
人間は亡くなると、甚深無量にして底なき大海のごとくなものに帰すと言う的確な言葉でまとめています。言われてみればそうだなと思います。どこかに行ったり来たりするという問い自体が正しくないということです。ヴァッチャの心の中はこうした確信だったのです。それでは普段の我々の勘違いはどうして起こるのでしょうか。それはやはり時間の経過と言うことではないでしょうか。異なった状態に移ると言うというのは、時間的経過を含んでいます。この時間の経過というもがとてもくせ者です。このくせ者のために我々は勘違いをしてしまっています。AからBへ変化したとき、我々は両方を頭の中に置き,AからBへ行くと言う認識をしています。しかし、Aがある時にはBはなく、Bが生じるときにはAは存在しないのです。同時に存在しないことは自明のことですが、Aにある時はBは未来の予見として、Bにある時はAは過去の記憶として我々の中にあります。だからどこかに行くという認識をします。しかしこれが勘違いなのです。人間存在のすべてはただ存在するのです。どこかに行ったり来たりするものではないのです。解りやすく言えば、人間、亡くなるとすべて腐り果てることはちょっと考えれば解ります。ただ存在すると言うことは、そういったことを意味しています。しかし、その時に魂というか、この「私」という存在がどうなってしまうのかというのが人間の最大の関心事です。この「自分」だけはその例外であるように思う。いや思いたい。この思いたいという気持ちが前章の臨死体験で登場した霊魂というようなものを生み出しているのかも知れないし、浄土に関するその他のいろいろな議論はこの気持ちがもとになっているのは間違いありません。ただそうした勘違いは、人間に本来的に備わっているもののように思う。そうした勘違いをするように人間はできているのです。そして、もう一つさらに重要なことはその勘違いに気がつく能力を持っていると言うことです。勘違いしたまま人生を終えると言うことであれば、浄土の問題は全く違ったものになっていました。人生の中でいろいろな場面でそうした勘違いの事実を突きつけられる場面に出会い、そしてはっとするのです。やはりこの「自分」も存在しなくなるものなのじゃないか。どうもお釈迦様はそんな風に言っているように思う。少なくとも前述のお経からはそう言っているように聞こえる。何かとても厳しいことを言ってるようだ。
何かとても難しくなってきました。我々の普段の感覚とひどくかけ離れているように感じます。我々は時間の経過の中でいろいろな体験をしていますので、物事が連続しているという感覚を持っています。時間的には連続していますが、次のものが生ずるときには前のものはなく、その時その場所にそのものがある。という表現になるのでしょうかどうも表現に困ります。ところが、これが、そんなに縁のないものではないのです。意外に身近なものなのです。と言うより人間は忘れてしまったのです。時間の経過を人間が理解するようになるには脳の発達が必要なのですが、三歳ぐらいになってようやく理解し始めるのだそうです。完全に理解するには十歳ぐらいにならないとだめなのだそうです。一昨日とかあさってと言うことを理解するというのは、意外に大変なことなのだそうです。前のことを覚えていて今との連続を理解できるようにならないと時間の理解はできません。つまり「そこへ行く」と言うことはAからBへという距離的考えも含みますが、今からその時までと言う時間の経過の要素が含まれているわけです。ところが、時間の理解がないと、それは、「そこへ歩く」という何というか収まりの悪い表現になります。ただ人間の動作を表現しただけのものとなります。だから、人によっても違いますが三歳ぐらいまでの人間は、ただ存在するという感覚で生活しているんです。行き当たりばったりと言うことでしょうか。我々はそれを忘れてしまったのです。決して人間にとって縁のない感覚ではないのです。夢中で遊んでいる子供にとっては、そのときそのときの自分があるだけで、それ以外に自分はない。前後の自分なんてことは考えてない。何か意外なところに意外なものがあったようです。小さな子がスヤスヤ眠っている姿を見ると幸せそうだなと思います。人間の幸せっていがいとこんな身近にあるのかななんて思います。
人間が成長するにつれて時間や距離とかいう知識を身につけてゆくのは、よりよく生きるためです。難しくいうと生存確率が一番高くなるように人間は行動します。これは本能的なものです。そのために必要な知識を身につけるということです。生きるために身につけた知識なのですが、時間や距離の認識はそれを身につけた人間を苦しめます。これは仕方がないことです。知識を身につけなくては生きてはゆけませんから。しかし、死と言うことに関しては、生きるために身につけた知識は役に立ちません。そうした知識をもとに考えると、人間は存在しなくなるということはつらいことです。つらいという言葉では表現しきれません。今の自分の前後は存在しないのですが、人間はその前後を記憶し予想して、そして畏れるのです。恐怖するのです。とても厳しいことになってきました。我々の感覚とは非常にかけ離れたことをいっているようです。いずれ人間はすべての人や物と別れなければならなりません。こんな風に思っています。こうした見方が、人間の苦の本源です。我々が身につけた知識をもとに見ればとても辛いことなのです。けれども、このことから目を背けてはいけないのです。とてもつらくて思わず目を背けてします。当然です。しかし、いつかはこの事実と向き合わなければなりません。
出来れば死後、ご浄土のような安楽な世界に行くことが出来ればという願いは誰でもが理解できます。ところがお釈迦様はそのようには説かなかった。死後の世界があるとかないとか一切説かなかった。「無記」「捨置答」と仏教では言いますが、回答不能ということでしょうか。前の章で述べましたが、人間の経験の限界をはっきり認識すればこの問いが回答不能であることはすぐにも解ります。それに答えが出たとしても、人間の本源的な苦は解決されないからです。一瞬、解決されるような気がするのです。ところが、死後の世界があったとしても、それはあくまで死後のことです。この世の苦しみは消えてなくなることはありません。お釈迦様はなにより今この世での苦の克服を目指したのです。この世において、この世の苦しみを克服しようとしたのです。
またみなさんに「それ見たことかお釈迦様はいいことを言っているじゃないか」と言われてしまいそうです。どうもピンチの連続です。でも最後に逆転を期して少しずつ話を進めましょう。
ところで、その極楽浄土ですが、お釈迦様が説いたのではなかったのでしょうか。浄土教も仏教です。仏の教えというのですからお釈迦様の教えということなんです。どうも何か変だぞということになる。「なんだお釈迦様も矛盾しているじゃないか」と言うことです。そう言われるのはもっともなことです。どうも同じ仏教の中に矛盾したものが一緒に存在している。夢のような浄土のお話しに対して、一方そのような問題に取り組んではいけないというお話と、矛盾したものが仏教の中に存在しているのです。これが重要な事実です。長い仏教の歴史的な営みの中に生じた矛盾といえます。しかし、この矛盾の中に問題の本質があります。この問題を考えていくことが、浄土に近づいていくことになると思います。次の章では、仏教のお経というものがどんなものなのかみていきましょう。
バナースペース
スタジオ阿弥陀
〒110-0004
東京都台東区下谷1-8-20
TEL 03-3844-5949
FAX 03-3847-9301