<教師力:1> 変わる子と親 対応に苦悩 揺らぐ自信
この春、5人の教師が定年を待たず、東京のある公立小学校を去った。いずれも40〜50代のベテランだった。
その一人が振り返る。
授業に工夫をこらし、30代半ばで「出世コース」といわれる都の教育研究員に選ばれた。指導は厳しかった。それでも子どもたちはついてきたとの自負がある。
歯車が狂いだしたのは数年前だ。 子どもに注意したことをきっかけに関係がこじれ、親からの苦情が相次いだ。校長室に連日呼ばれた。「どんな指導をしているのか」と責められた。教育委員会の指導主事が授業の視察に来た。精神的に追い込まれ休職、そのまま退職した。「もう、復帰できる自信がわいてこなかった」
5人の事情は少しずつ違うが、周辺の教師らは、共通の悩みもあったとみる。「手のかかる子や、主張するばかりの親が増えた。参ってしまう先生は多い」「特に年配の先生は、若い親との感覚の違いに悩む」
やめていくベテラン教師たち。東京都の公立小中学校では昨年度、50代の教師約500人が早期退職制度で去った。同年代の約4%にあたる。
大阪府でも同様の制度で00年度、小中の約1000人がやめた。予想以上の数で先生が不足、01年度は急きょ、前年度の倍の約1500人の講師を採用した。50代で退職した元中学教師は「助けてくれる生徒や親が減った。疲れ切った」と言った。
■ ■
「教師を支える会」は99年から、教師の悩みをメールや電話で聞いてきたボランティア団体だ。教師や学者ら約200人が相談を受けている。相談総数は、少なくとも年1000件はあるという。
相談員の大竹直子さん(33)は年20件ほど受ける。半数が「やめたい、休みたい」という訴えだ。「自殺したい」という声もある。「年々、深刻化している」と感じる。
代表の諸富祥彦・千葉大助教授(教育臨床学)は話す。「かつてない教師受難の時代。責めるばかりでは、委縮し、やる気をなくしてしまう。しわ寄せは子どもたちにいく。日本の教育にとって大きなマイナスだ」
「やめたいと考えたことがある」。最近の複数の調査では、いずれも半数前後の教師が、そう答えている。直接の理由は「多忙」が多い。そこから「忙しくて子どもと向き合えない」ことにつながっていく。
■ ■
埼玉県の朝霞市立朝霞第二小の増田修治先生(45)は、子どもが面白いと感じた体験などを自由に書かせる「ユーモア詩」の取り組みで知られる。教室には笑いが絶えず、親にも好評だ。3月末には、テレビ番組「徹子の部屋」に出演した。
その増田先生でも10年ほど前、「やめたい」と考えたことがある。
授業に集中せず、居眠りや塾の宿題をする。掃除や係活動に協力しない。半数の子どもがそんな状況に陥った。注意すると、親から自宅にまで苦情が来た。「もう、わからなくなり、自信もプライドも砕かれた」
悩むなか、思いついたのがユーモア詩だった。
〈だれだって、おならは出る。/でも、それぞれ音はちがう。/大きい音のおならを出す人もいれば/小さい音のおならを出す人もいる。/なぜ、音の大きさが違うのだろう。/きっとおしりの穴の大きさが違うんだ〉
こんな詩から、子どもの感覚をつかみ、自信を取り戻すことができた。
しかし、増田先生の周囲では、「熱心だった」といわれる先生が学校を去っている。埼玉県でも01年度までの3年間で小中の約900人が早期退職制度でやめた。全体の約3%だ。
埼玉県教職員組合は最近、小冊子を作った。退職を思いとどまった教師の手記を載せている。
増田先生も編集に加わった小冊子には、異例のタイトルがついた。〈だから先生やめないで〉
◇
教師は学校教育の「要」だ。子どもや親の意識が変わり、競争を促す制度が導入されるなか、これからの教師を考える。
(2003/4/21)
朝日新聞
この記事がのった文庫が発行されました。
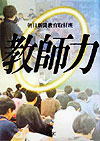
| 標題 |
『教師力』(朝日文庫)朝日新聞教育取材班著 |
| 朝日新聞社 04.7.30 | |
| 279p 15cm(A6) 560(税別) | |
| 要旨 |
子どもや保護者の意識が大きく変化し、その質がかつてないほど厳しく問われ始めた“学校教育の要"教師−本書では苦悶する教師たちの実情を軸に、教育産業の今、変わりゆく入試事情、国家と教育のあり方を取り上げる。朝日新聞で連載された大型企画「転機の教育シリーズ」文庫化最終巻。 |