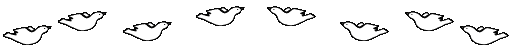
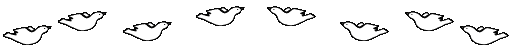
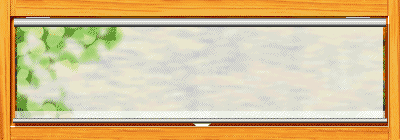
「長崎佐世保小六女児殺害事件に思うこと」
現代の子どもたちの抱えるコミュニケーション不足症候群
1、長崎佐世保小六女児殺害事件に思うこと
今年の6月1日に起きた「佐世保・小6殺害事件」は、教育関係者のみならず、すべての大人たちを驚愕させました。小学校四年生のクラス32人に、事件のあった翌日に「どの程度事件について知っているか」「チャットや掲示板について知っているか」などを調査したところ、次のようでした。
①6月2日の朝に、この事件を知っていたひとは…28人
②お父さんやお母さんと、この事件について話し合った…16人
③インターネットを家でやったことがある…16人
④自分の家の人がホームページを作っている…4人
⑤ニュースで「チャット」のことを知った…15人
⑥「チャット」って、どういうものかを知っている…0人
⑦「けいじ板」について、はじめから知っていた…10人
これを見ると、小学校四年生であってもかなり事件に興味・関心を持つと同時に、ショックを受けていることがわかります。四年生のある男の子が、
「先生、女の子もすごいね。やるときゃやるんだねー。」
との言葉を思わず発していました。
今回の佐世保の事件では、チャットや掲示板などが原因であるようにマスコミ等で取り上げられていますが、そうした見方だけで良いのでしょうか? 私の今回の事件における一番の疑問は、「被害者と加害者が単学級でいつも顔をあわせていたのですから、掲示板やチャットで悪口を書いたことがトラブルの原因であったとしても、学校で『あなたが掲示板に悪口を書いたのでしょう!』とか『悪口書くのをやめてよね!』と言えなかったのはなぜか?」ということです。もしそうした形で声に出せていたら、きっとこの殺害事件は起きなかったし、違った形になったと思うのです。
被害者と加害者の関係が、どうしてそうした対面型のコミュニケーションに発展していかなったのでしょうか。私は、そこに現代の子どもたちの抱えるコミュニケーション不足症候群をみるのです。対面型コミュニケーションは、会話をしている人が主体になっているように思えますが、実は聞き手が主体者であり、会話をリードしているのです。教育心理学に、ヒィドウンカリキュラム(ヒィドウンメッセージ)という考え方があります。ヒィドウンとは隠れたという意味です。例えば、クラスにおいて「A子ちゃんは作文が上手だね」とほめたとすると、それはそのほめ言葉の裏側に「他の子は作文がへただね」というメッセージが隠れているのです。そのことは、兄弟関係に顕著に見られます。「お兄ちゃんはすごいね!」と言うと、たいてい「ぼくはどう?」と弟が出てきます。それは、無意識的に言葉の裏側のヒィドウンメッセージを受け止めているのです。
では、対面型コミュニケーションを考えた時に、会話をしている人は聞き手の表情やしぐさ・うなずき方などのメッセージを受け止めながら会話を進めているのです。そう考えると、対話型コミュニケーションの主体は、聞き手であるとも言えるのです。
それに対して、掲示板やチャットは、相手の反応や表情を気にせずに話し手が主体となって会話をリードできるのです。実は、現代の子どもたちにとって、「相手の反応を気にせずに思ったことを書ける」というのはとても気楽な作業なのです。小学校高学年ともなると、友だちに対して「こんなことを言ったら、嫌われてしまうのではないか?」といった気遣いをしています。その気遣いは、現代の子どもたちにとって非常に苦痛を伴う作業です。
対面型コミュニケーションが、相手から発信される様々な情報を処理する能力が要求されるのに比べて、チャットや掲示板の方が「情報処理能力」を要求されないし、よけいな「気遣い」をしなくてすむのです。最近、チャットや掲示板にはまるのが、男の子より女の子の方が多くなっているのは、女の子の中に「情報処理能力」や「相手に気遣いをしながら会話していく力」が衰退していっているからではないでしょうか。
つまり、今回の事件の悲惨さの陰で、現代の子どものコミュニケーション能力不足が指摘できるのはないかと思うのです。そう考えると、現代の教育の課題が「コミュニケーション能力の向上」と「自己を表現する力」にあるように思えるのです。
そうした課題に早急にこたえることが、今の学校教育に求められているのではないでしょうか。
2、コミュニケーション能力の向上が不可欠!
日本の社会だけでなく、世界全体が「強者の論理」に飲み込まれようとしているなか、やっぱり大切なのはコミュニケーション能力だと思います。暴力ではなく、相手の民族性や考え、宗教の違いを理解した上で、合意点を創り出していく能力こそが、今を生きる子どもたちに必要なのではないでしょうか。
そして、地域や学校や家庭で、表現の自由が保障されたコミュニケーション空間をいたるところに創りだしていくことが大切なのではないでしょうか。コミュニケーション能力の向上は、子どもたちを「強者の論理」から「合意の論理」へと育てていくのに必要不可欠なものです。
まずは、身近なところから子どもたちの表現の自由を保障しましょう。それこそが、今の現状を変えていく大きな力になるはずです。私が『ユーモア詩』を通して子どもの表現を保障していく取り組みをしているのも、そうした理由によるところが大きいのです。
朝霞市立朝霞第二小学校
増田 修治


(注意)このページはMIDIを使用しています。