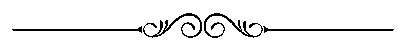近代性へのこだわりからの自由
unlearnに関しては、私自身の経験も書いておきたいと思います。「あ、もういいや」という感じで私から剥がれ落ちていった非常に大きなものは、「近代」というイメージ、いや、たんにイメージというのではなく、強い規範的な観念でした。つまり、われわれは「近代」に生きている、という事実のイメージではなく、われわれは「近代的であるべきだ」という、言わばオブセッション、強迫観念です。
「近代的であるべきだ」という強迫観念は、私に特有の個人的なことではなく、明治から昭和にかけての人々、とりわけ日本社会の古い体質に批判的な人々に顕著なものでした。若い世代の人々にはピンとこなくて、理解するのに歴史的想像力が必要になってきているかもしれません。しかし、グローバル化対応の人材養成が論じられるときや、パワハラのような縦型の人間関係から生じる問題に対処しようとするとき、あるいは、自己決定や自己責任が過度に強調されるときなどに、この観念は形を変えて姿を現わすこともありそうですから、今日でも実践的な意味を持つ問題であるように思います。
日本と日本人の精神は西欧近代に遅れている、変革しなければならない、という思いは、明治期、第二次大戦の敗戦後、そして、近年のグローバル化状況の中で、繰り返し日本人に取り憑いてきました。時期ごとに少しずつ内容は違っていたとしても、ともかく、日本にある既存のものの多くが過去のしがらみとして否定的に評価され、そこからの脱却が差し迫った課題とされました。この課題については、政治の世界で多くが語られましたし、文学でもおなじみのテーマでした。西欧風に近代化する必要性は、日本人の生活のほとんどの分野で語られ続けていたのでした。
政治学の分野では、私の学生時代は、啓蒙された自立し自律性のある個人が作為的に形成する民主的政治秩序、というのが実践面での主要な課題として強調されていました。さらに、こうした政治秩序と、平等や公平な社会システムとをセットにした何らかの形の社会主義という志向が重なる傾向も強かったように思います。もちろん、より具体的なゴールやその到達方法をめぐってはさまざまな見解があり、相互に厳しく対立することもありましたが、議論の基軸というかパラダイムは、西欧的近代化の推進ということでした。国粋主義や土着主義にしても、西欧的近代化への反発の産物という意味では、このパラダイムの存在が前提にありました。こういう前提を受け容れること自体を自覚的に拒否する立場は、たとえあったとしても、私を含め一般にはほとんど伝わっていませんでした。私の学生時代、依然として強大な影響力を持っていた丸山真男さんの諸著作や、福田歓一さんの『近代政治原理成立史序説』などに代表される政治思想史研究は、この近代化パラダイムに沿ったものと受け止められていたと思います。こういう受け止め方の前提には、民主主義を定着させ守るとともに、実態としては不徹底なところがあるので改革を進めよう、という姿勢がありました。
【補注】半澤先生の「回想の「ケンブリッジ学派」」では、このパラダイムの呪縛力について、はるかに明晰に論じられています(半澤孝麿『回想のケンブリッジ』、みすず書房、2019年所収)。しかし、ここではやはり、私自身の経験を私なりの言葉で記しておきたいと思います。なお、半澤先生は、「丸山・福田パラダイム」は団塊世代まで支配したと書いておられますが(半澤孝麿「回想の「ケンブリッジ学派」」、20頁)、団塊世代に後続する私の世代でもまだ強力なものだった点は補足しておくべきでしょう。
この姿勢それ自体は、今でも十分に妥当で立派なものだと思います。しかし、その立場を正当化するために訴えられた政治や社会の「近代化」や、それにふさわしい人間精神の「近代化」の議論に関して言えば、大きな問題がありました。つまり、民主主義を正当化しようとして現在の理解枠組で過去の出来事や思想を取り上げたために、歴史的事実の理解という点で視野が狭くなり歪みが生じてしまったのです。それは、民主主義そのものの理解やそれを支え動かしていく市民のあり方の理解にまで影響することになりました。歴史的理解における問題の一例が、ジョン・ロックの扱いです。近代政治原理の発展という見方に沿った政治思想史の教科書では、この原理の確立に貢献した政治思想家の一人として、ロックが必ず言及されていました。ロックの社会契約説やそれにもとづいた抵抗権論や革命権論は、「市民革命」の思想であり、作為による近代的で民主的な政治秩序形成の理論的先駆だ、と評価されていたのです。
しかし、こうした評価をひとまず措いて、ロック本人の議論の立て方に注目すると、異なったロック理解の視界が開けてきます。その一つの例は、ジョン・ダンが明らかにしたように、ロックの宗教的コミットメントの重要性であり、近代化=世俗化(宗教からの離脱)という理解枠組に収まらないロックの姿です。この姿が視野の外にあったために、世俗統治を意味するcivil governmentに「市民政府」という無理のある訳語があてられたのでした。
もう一つの重要な例としては、ロックの家族論が歴史的文脈の中で持っていた意味をあげることができるでしょう。ロックが自説を展開するにあたって論駁の標的としたのは、よく知られているように、フィルマーの家父長権論でした。神は、人類が登場した最初の段階で家長としてのアダムに家族を支配する権利を与え、これが君主の支配権として代々伝わってきたのであり、したがって、君主の支配権は神から与えられたものだから、これに逆らってはならない、という王権神授説です。現代の観点からすると途方もない議論のように見えますが、しかし、フィルマーの実際の論述に当たってみると、巧妙な議論が各所に見られ、家長の強大な権力を自明視していた社会であれば、聖書の権威も相まって、ななかなか手強い議論だっただろうと想像できます。
ロックはフィルマーのこの議論を論駁するために、家族における家長の権力の絶対性を否定し、家族が夫婦の結びつき(conjugal society)を出発点としていることを強調します。これは、核家族と言いかえてよいものです。独立した対等な男女が合意によって結びつき、子どもを産み育てる。子どもの養育の趣旨は、独立した自由人を育てることだから、親の子に対する支配権はあくまでもこの趣旨に即したものでしかない。また、その趣旨からすれば、父権は正確には両親の権力である。たとえ、成人後に子どもが家族の一員として残留したとしても、成人した子どもは独立した人間として扱うべきであり、親がそうした子どもに対して専制的な支配権を持つといったフィルマーの議論は成り立たないのだ、というわけです。これを前提に、自由人相互を律する権力のあり方へと議論が展開していくことになります。
個人主義と核家族が自明視されている今日であれば、ロックの議論は非常に説得力のあるものに見えるでしょう。しかし、問題は、こういう家族論が当時のイングランドで説得力を持てたのかどうかです。ロックは説得力があると確信していた、と私は思います。なぜなら、家父長が絶大な権威を持つ大家族は、旧約聖書の世界であればともかくも、当時のイングランド社会では上層の一部に限られていたからです。そのセクターでフィルマーの議論が説得力を持てたとしても、実のところ、イングランド全体としては核家族的世帯が主流でした。
日本の場合、今日では個人主義と核家族が自明視されていると言いましたが、そうなってからあまり時間は経っていないように思います。印象としてしか言えませんが、1980年代以降ではないでしょうか。女性は嫁いで生家を離れ、男性は長男であれば結婚しても親と同居し、家業があればそれを継ぎ、のちのちは親の葬式や法事を仕切るというのが、まだ、少なくとも建前論として私も含めて1970年代までの若者の多くに共有されていましたし、また、建前論としてでも成り立つ程度の実態はあったように思います。
こういう社会で、ロック流の近代政治原理が説かれると、家族関係と政治権力のあり方の両方について、非常に要求度の高い議論になります。この場合、ロックが読者として想定した人々からは実情に即したものとして有力な支持が期待できた議論は、現実から離れた観念的抽象的な理想論として浮き上がってしまいます。自立・自律・主体性、それに加えて私が高校生の頃によく使われた言葉としては「自己否定」というのは、まずは政治以前に、現実の具体的な家族関係とぶつかってしまうのです。ここが近代日本の急進的な学生・青年運動の本音レベルでの弱点を衝く急所だったわけで、い わゆる「転向」の問題にも連動する話です。
イングランドやそこから移り住んだピューリタンたちの北アメリカ【補注参照】は、政治革命によって自由で民主的な政治体制を確立したあとに、革命的な思想や観念によって個人主義と核家族を受け容れたわけではありません。因果関係は、むしろ逆です。だから、ロックは核家族における両親の権威と、政治的権威との本質的な違いを説得的に論じることができたのでした。理論的には、アリストテレスのプラトン批判をなぞった議論ではありますが、人々に訴える力の源泉はあくまでもイングランドの実態にあったわけです。
【補注】ただし、アメリカでも南部は、家父長制的な傾向が強かったと考えられます。アメリカ南部やインドには、フィルマーと同郷(ケント州)の出身者が多かったようです。
家族のあり方と政治のあり方の両方を同時に、イデオロギーとしてはともかくも制度的実態として、家父長的なものから、自由で平等なものに一挙に変えることは非常に困難でしょう。いや、おそらく不可能だと思います。だとすると、残された道は二つ考えられます。一つは、日常生活上の人間関係や権威の見方を建前と本音で使い分け、この領域での自由平等は建前論にとどめ、政治における自由平等を訴えることです。もう一つは、日常生活上の人間関係や権威のこういう本音レベルでのあり方に関しても、実現の可否はともかくも、徹底した変革を訴えることです。1960年代から70年代にかけては、私の印象では、第一の選択肢を年長世代の中のリベラルな部分が選び、第二の選択肢を団塊世代の中の急進的な部分が選んでいたように思います。実は、あくまでも仮想的な抽象論としてですが、さらにもう一つの選択肢もありえます。ルソーの『社会契約論』に出てくるような立法者に頼るという選択肢です。ルソーの立法者は、結果を原因に変換する装置です。社会契約を人々が行なう段階では、人々には社会経験がないので、自由で平等な政治制度の具体的なあり方を判断し選択できるような知見や心構えが欠けています。そこで、立法者が、人々が経験によってそうした知見や心構えを得ることができるような教育効果のある政治制度を設計し、絶大な権威で人々に受け容れさせます。そして、そういう政治制度が存続した結果として、人々は自分たちが身につけた知見や心構えでその政治制度を運用していくということになるわけです。
しかし、そんな立法者は神話としてならともかく、実際には存在しません。人民の側にしても、過去のしがらみが身についていて、社会経験のない白紙状態というわけではありません。自由で平等な政治制度の存続に必要な知見や心構えは、生活実感として権威主義的な支配はごめんだという想いが世代を超えて引き継がれる一方で、何世代にもわたって自由で平等な人間関係の経験(特に失敗の経験)を積み重ねることによってしか得られません。それは、永久革命という勇ましい話ではなく、生活上の実利が絡んだ地味でスローペースな企てです。このプロセスを性急に達成しようとすると、それを人間革命と呼ぼうが市民教育と呼ぼうが、社会や政治や仕組の中での実地経験の成果として待っていられなくなります。つまり、社会的因果性の問題とみなせなくなり、精神主義の問題になってしまいます。神のような超人的立法者の代わりに、みんなが超人的にならなければならないわけです。ともかく頑張ってそれぞれ自分を変える、そうすれば世の中も変わる、ということです。近代日本の知識人にかなりアピールしたように思えるカントの自律論も、そんな読み方がされていたようにも思えますし、日本では戦前戦後を問わず、因果性を無視した精神主義を好む風潮もありました。単発の旧式銃でも気合いで突撃すれば機関銃に勝てるからひるむなとか、共産主義の闘士なら革命成就まで恋愛するなとか、スポーツ中に水を飲むなとか、地位や思想的立場に関係なく、枚挙にいとまのないぐらいです。主体性とか「作為する精神」という言葉は、もっと垢抜けしたものの言い方だったかもしれませんが、それでもやはり無から有は作れないとなると、はた迷惑なド根性路線になってしまいます。私が高校生時代に耳にした「自己否定」という言葉にも、そうしたものを感じざるをえませんでした。
このようにして、無理がある、不自然だという思いとともに、「近代」という観念をめぐる私のunlearnはくり返され進んで行きました。だんだんと気づいてきたことは、自己変革とか人間革命と言っても、政治的関心から語られる場合は、目的はあくまでも望ましい政治秩序に向けられていたという点です。政治のために、個人に過剰の負荷をかけているのではないか。政治は、そうまでして個人が追求すべき唯一至上の目的なのだろうか。宗教を退ける世俗的啓蒙的精神が、近代政治や近代政治思想の特徴と言われるけれども、政治そのものが道徳主義的に再定義され宗教的なオブセッションのようにして個人の精神にのしかかっているのではないか。
【補注】ただし、少なくとも敗戦からしばらくのちまでの時期に関しては、政治が戦争を抑止するどころか戦争を助長したという悔恨が、こういう政治重視の見方に反映していた面があったことは斟酌すべきでしょう。
他方、近代性の自信満々な自己確信に反発するポストやアンチというリアクションもありましたが、そこに漂うシニシズムや相対主義自体、近代の確実性の観念に縛られながらそれに反発しているのであって、その意味では同じ土俵に立っているように思えました。こう見ると、問題の根は政治だけにあるのでもなく、また、日本に特有の事情だけではなく、西欧自身にもありそうだという気もしてきました。私が最終的にたどり着いたのは、これらの言説の根底にある自我というものの捉え方の狭さというか浅さに問題がある、という理解でした。これは、日本に限られているわけはなく、西欧にも共通する普遍的な傾向だと思います。日本の場合には、そうした狭さや浅さに劣等感が絡んでいて、さらに事態が複雑困難になっています。欧米にくらべて社会や政治の近代性が不徹底だ、そうした社会や政治を変えるような個人の自立性や主体性が足りない、という主張は、さまざまな立場から繰り返されていました。
「自分を変える」という考え方が全部だめだ、というのではありません。本当に変わることが必要であれば、変わってよいし、変わらざるをえないとも言えるでしょう。人間は切実な必要性に対してはかなり柔軟性があるように思います。でも、劣等感や自己嫌悪という動機ではろくなことになりません。劣等感や自己嫌悪には、何らかのルサンチマンがともなっています。それはコンプレックス=複合的心情であって、他に優越して肯定されたいという承認欲求が背後にあります。アドラー流に強い言い方をすれば、それは権力志向の一つのあり方です。自己の尊厳の感覚と取り違えられがちなので、厄介な代物です。残念ながらどんな人間にもある心の影の部分であり、自覚して上手に飼い慣らすしかありません。しかし、こういうことが自覚されないままの心の習慣ができてしまうと、当座の劣等感の解消では終わらず、自分の劣等感を生じさせるような自他の差を強迫的に次々と探し求めることになってしまいます。
こうした劣等感とは別に、近代の自律性の捉え方そのものにも問題があります。これは普遍的な問題で、日本に限らず西欧にも当てはまります。他者による支配から脱却し自らを支配することが自律だ、という見方に不足しているのは、自律を語るときには「支配」の観念そのものも考え直す必要があるという点での自覚です。自律はautnomyであり、つまり、規律(nomos)=法を自分に課すことを意味しています。気まぐれの支配でなく法の支配として自己支配を考えているわけで、これは非常に結構なことです。現代の自己決定論者にもぜひ念頭に置いてらいたい点です。しかし、問題は、ルールに従うときの従い方、従うときの動機のあり方です。実践理性から感性的契機を排除すると、理論的には恣意性のないすっきりしたものになるかのように見えますが、そういう恣意的な感性は理性の指示にどうやって従うのでしょう。恣意のレベルの感性は、同レベルのもの、つまり、権力行使によって与えられる直接の苦痛か、あるいは少なくともそうした苦痛を予期することによる恐怖感にしか反応できないでしょう。
実践理性を高く祭り上げれば上げるほど、それによって支配されるべき感性は低レベルになっていきます。低レベルの被治者に必要なのは、他律的支配ではなく個々の事例ごとの命令であり、つまり、奴隷を扱うような専制的支配です。一元論を前提にした善悪の二項対立という発想だと、こうなってしまうのです。善が極致に達すると悪も極致に達します。実践理性は根源悪と切っても切れないペアになるのです。
劣等感を持つ自我と、劣悪な感性を専制的に支配しようとする自我観は、抑圧的で強迫観念的な自我観として合流します。理性から神や宗教は放逐されたのかもしれませんが、その代わりに、上位のすぐれた自我や理性的自我が神格化されるのです。これが自分とのつきあい方にとどまらずに、政治に持ち込まれるとどんなことになるかは、バーリンが積極的自由概念への批判の中ですでに明らかにしてます。しかし、だからといって、消極的自由概念であればすべてよし、ということにもならないように思います。バーリンもそう主張していたわけではありません。
【補注】とはいえ、バーリンは一元主義的世界観を強く批判しながら、それと不可分に結びついている二項対立的発想を、自由概念をめぐる議論の中で図らずも助長してしまった観があります。冷戦期のイデオロギー対立に巻き込まれた結果だと言えるでしょう。
それでは、自我をどう捉え、それとどうつきあっていけばよいのでしょうか。笑われることを覚悟の上で、私はあえて、愛という視点を持つことを提唱したいと思います。今の若い世代で知っている人はあまりいないでしょうが、80年代のポップスで、ビリー・ジョエルのI Love You Just the Way You Areという曲がありました。メロディーもいいのですが、このタイトルと歌詞も魅力的です。誰かを今と全然違う別の姿であって欲しいと思いながら、その人を愛することはできないという真理を衝いていて、最高の口説き文句になっていると思います。愛の試金石は、あるがままの相手を受け容れ許せるかどうかだ、ということです。
自分に向かい合うときも、同じだと思います。伸びやかな気持ちで変わり向上していくのはよいとしても、今の自分をとことん見下げるような根性自体が、そうした向上心を濁らせてしまうように思えます。まず変わる必要があるのは、この根性の方でしょう。既存の自己を嫌悪し否定しようとしている自己とは何か、 という問いが不可欠なわけです。この問いを省い てしまうと、思考は平板化して停止に至り、「自我イデオロギー」とでも言えるようなもの取り憑かれてしまいます。イデオロギーは経験的現実を無視しようとします。でも、経験的現実以外のところで確実なものを実感することは難しいので、結局、際限のない「自分探し」のようなことが生じてくるのです。「自分探し」をしている「自分」は何なのか、なぜそんなことをしているのか、という問いが出てくる必要がある、ということです。
自分に向かい合うときの愛という点で参考になる思想家は、西欧の文脈であれば、アウグスティヌスだと思います。アウグスティヌスは、自己を含めた 地上にあるものの不完全さや悪に向かい合いつつも神が創造したものとして自己を含めた地上のものを愛する姿勢を示しているからです。
キリスト教徒でない私自身の場合は、特に仏教と縁があるわけではないので すが、日本に長く暮らす中で年をとり、自分の生命の有限性への現実感が高まってくるにつれて、生命あるもの全般への愛、というのが少し実感できるようになってきました。若い頃は可愛いというよりもちょっとこわい感じすらした牛や馬のような大きな動物も、とても愛おしく感じられるようになってきました。そうした愛の対象としての生命全般に自分も含めてやろうじゃないか、と思うようにもなりました。自我に執着する自己愛とは違います。むしろ、自分の存在の所与性を認め、自分は自分の排他的所有物ではないと認めることなのです。思い付き程度のものでしかない自分の抽象論のために、自分を酷使したりいじり回してはいけない。それは、生命に対する忘恩のきわみではないか。命あるものとして愛おしみ大事にしてやる、なおかつ、それを前提に、必要とあれば変わり向上 していく努力もする、それでできることもいろいろあるし、それ以上は、望んでも無理だし無意味だと思うようになりました。
もちろん、命あるものは「対立物の結合」ですから、よいことばかりではありません。物理的に醜く見えることもあるだろうし、さらに人間の場合は 心の中にいつも恐るべき影がつきまとっている。それをないことにするのはよくありません。知的にも道徳的にも割り切れないことがたくさんあるけれども、だからといって、ないことしようとしても、実際にはなくなってくれません。むしろ、割り切ろうとする態度を反省の対象にする必要があります。「近代的」であろうとする知識人の自我や自己意識の捉え方も、無理を抱え込んだ割り切り方の一つとして相対化する必要があります。その結果として、そうした捉え方において軽視されてきたもの――家族生活、無意識、身体、庶民の習俗や宗教的信仰――に向き合うことにもなります。これは土着主義への開き直りではありません。向かい合うことと無条件の肯定とは違います。
「知識人」という他人事のような言い方をしましたけれども、これは思想と論理を扱う仕事を本業にしようと力んでいた、若い頃の私自身に他なりません。そういう自分を、再度力んで変えようと思ったのではありません。窮屈なのでやめることにしただけです。割り切れない現実に直面するのは楽ではないけれど、抑圧的で強迫的な自我意識はもっとつらいし、周囲にも大迷惑だ、とわかったということです。これが私のunlearnの現時点での到達点です。