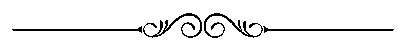LearnとUnlearn
二項対立を考察したエッセイの中で、カオスと完全な静止状態とのあいだにあって自己組織化していくプロセスを取り上げましたが、ここでは、外からではなく内からはこのプロセスがどう見えるのかを考えてみたいと思います。内から見ることができる自己組織化体、つまり人間は、自分の進化をどう感じ意識するのか、ということです。
いろいろな例があるでしょうが、私自身は、ミルがその点に言及していたのがずっと印象に残っています。ミルは20歳代後半にカーライル宛の手紙の中で、自分の「成長しつつあるという感じ(the feeling of growth)」を伝えていました。さらに、『自伝』の冒頭にも注目される記述があります。原文でないと伝わりにくいところがあるので、原文を引くことにします。
|
It has also seemed to me that in an age of transition in opinions, there may be somewhat both of interest and of benefit in noting the successive phases of any mind which was always pressing forward, equally ready to learn and to unlearn either from its own thoughts or from those of others. (John Stuart Mill, Autobiography, The Collected Works of John Stuart Mill, University of Toronto Press, vol.1, p.5.) |
ここで注目したいのは、unlearnという言葉です。ミルの専門研究者だった山下重一さんは、「学ばない」と訳していました。これは、残念ながら誤訳と言わざるをえません。岩波文庫版(朱牟田夏雄訳)では、「反省の資とする」という訳語が当てられています。これはunlearnの意味を理解した上での苦心の訳語だと思われますが、いったんは学び身につけたものを捨てるというニュアンスが十分には伝わってこない感じです。ただし、「反省の資とする」という表現は、捨て去った後に残るものを上手に示唆していると思います。さきほと私が使った「捨て去る」という訳語だと、その点が伝わりません。
よい訳語はないものかと思いあぐねていたところ、しばらく前のことですが、unlearnという語について鶴見俊輔さんが言及した10年ほど前の新聞記事があるのを知りました。unlearnに「まなびほぐす」という訳語を当てていて、さすがだと思いました。
| 戦前、私はニューヨークでヘレン・ケラーに会った。私が大学生であると知ると、「私は大学でたくさんのことをまなんだが、そのあとたくさん、まなびほぐさなければならなかった」といった。まなび(ラーン)、後にまなびほぐす(アンラーン)。「アンラーン」ということばは初めて聞いたが、意味はわかった。型通りにセーターを編み、ほどいて元の毛糸に戻して自分の体に合わせて編みなおすという情景が想像された。大学でまなぶ知識はむろん必要だ。しかし覚えただけでは役に立たない。それをまなびほぐしたものが血となり肉となる。(2006年12月27日朝日新聞(朝刊)13面「鶴見俊輔さんと語る生き死に学びほぐす」) |
ミル『自伝』のこの部分は、ミルについて私が本腰を入れて研究を始めてからしばらく後の20歳代後半、自分の精神的な変化にもぴったりな気がして、お気に入りになったのですが、ただ、若かったその当時は、unlearnにかなり力みがあったように思います。年をとってもう少し落ち着いてくると、「つねに前進」と力を入れて意識的に何かを捨てるというよりも、「あ、もういいや」という感じで何かが脱落していきます。未練や喪失感はまったくありません。むしろ、かさぶたが剥がれ落ちていくような解放感があって、すっきりします。もちろん、かさぶたの痕は残りますけれども、それはそれで精神的資産の一部になってくれます。unlearn がこうなってくると、その後は、learn も同じように力みがなくなります。世阿弥の「守・破・離」という見方からすれば、unlearnには「破」と「離」の二種類がある、ということでしょうか。
なぜ、力みが抜けたのかと考えてみると、うまくやりおおせて他人から褒めてもらおう、といった浅いレベルの自我の欲求が、だんたん、どうでもよいものになってきたからだと思います。生身の人間ですから、完全になくなるなどということはありえませんが、年を取ってくると結構疲れる欲求であることはたしかです。おかげで、多少なりとも平衡感覚がついたようです。自転車に乗るのに慣れてハンドル操作がスムースになり、ぐらつかなくなるのに似ている感じがします。ただ、生きている以上は、力まなくても前進は続けるわけで、そうでなければ動的な平衡にはなりませんから、ペダルをこぎつつける脚力は必要です。つまり、前進のためには何よりも積極的な好奇心が必要ですし、好奇心を支える心身の力を維持するためには、日々のささやかな努力が年齢を重ねればそれだけいっそう必要なようです。